仕事でも趣味でも、あることを初めて始める時、こんな風に言います。
「一からの出発」
でもこんな風にも言いますね。
「ゼロからの出発」
まあ、ゼロからでも一からでも、最初から始めるというニュアンスはあるから大差ないのでは…、とも思います。
が、実はこの言葉の奥に、ちょっと深い「背景」があるように思えてなりません。
「ゼロ」
これは英語です。
日本語では「零」と訳します。
それなら「零からの出発」と言ってもよいようですが、この表現はほとんど聞いたことがありません。
日本語にすると、なぜか「一からの出発」なのです。
広辞苑で「零」を調べてみると、整数としての「ゼロ」の意味以外にも様々な意味があります。
「雨のしずく。こぼれ落ちること」
「きわめて小さいこと」
「はした。あまり」
「零細」という言葉もあるとおり、わずかながら存在している様子をも表す言葉で、厳密にいえばゼロと少し違う単語なのです。
何もないことを示す言葉として、日本語には「無」という言葉もあります。
しかし、「無からの出発」とも言いません。
「無」は単に「有」ではないことを示すだけでなく、仏教の世界では、西洋の「神」の存在にも似た、絶対的で根源的な概念として考えられてきました。
3、2、1と数を減らしていくと、1の次が0です。
しかし「無」という概念は、東洋ではそんな狭義の「0」とは違うものなのです。
こう考えていくと、英語のzeroにぴったりと相当する言葉の概念は、実は昔の日本語にはなかったと言っても過言ではありません。
今「ワン」「ツー」は誰もが英語として考えるのに対し、「ゼロ」が半ば日本語として認識されていることが何よりの証拠です。
だから日本では、初心者のことを表すのに「一からの出発」と表現した方がしっくりきていたのでしょう。
そして、英語の「ゼロ」という言葉が輸入されて初めて「ゼロからの出発」という表現を使い始めたのだと思います。
「無」に対する、東洋と西洋の考え方の違いが、「ゼロからの出発」か「一からの出発」かの違いになったのではないでしょうか。
外は雨。
零、雨のしずくの音に耳を傾けながら、プチ哲学してみました。
http://blog.goo.ne.jp/syusakuhikaru/e/ad6a7be6f0265fa11c88b0e61cc358bc
「一からの出発」
でもこんな風にも言いますね。
「ゼロからの出発」
まあ、ゼロからでも一からでも、最初から始めるというニュアンスはあるから大差ないのでは…、とも思います。
が、実はこの言葉の奥に、ちょっと深い「背景」があるように思えてなりません。
「ゼロ」
これは英語です。
日本語では「零」と訳します。
それなら「零からの出発」と言ってもよいようですが、この表現はほとんど聞いたことがありません。
日本語にすると、なぜか「一からの出発」なのです。
広辞苑で「零」を調べてみると、整数としての「ゼロ」の意味以外にも様々な意味があります。
「雨のしずく。こぼれ落ちること」
「きわめて小さいこと」
「はした。あまり」
「零細」という言葉もあるとおり、わずかながら存在している様子をも表す言葉で、厳密にいえばゼロと少し違う単語なのです。
何もないことを示す言葉として、日本語には「無」という言葉もあります。
しかし、「無からの出発」とも言いません。
「無」は単に「有」ではないことを示すだけでなく、仏教の世界では、西洋の「神」の存在にも似た、絶対的で根源的な概念として考えられてきました。
3、2、1と数を減らしていくと、1の次が0です。
しかし「無」という概念は、東洋ではそんな狭義の「0」とは違うものなのです。
こう考えていくと、英語のzeroにぴったりと相当する言葉の概念は、実は昔の日本語にはなかったと言っても過言ではありません。
今「ワン」「ツー」は誰もが英語として考えるのに対し、「ゼロ」が半ば日本語として認識されていることが何よりの証拠です。
だから日本では、初心者のことを表すのに「一からの出発」と表現した方がしっくりきていたのでしょう。
そして、英語の「ゼロ」という言葉が輸入されて初めて「ゼロからの出発」という表現を使い始めたのだと思います。
「無」に対する、東洋と西洋の考え方の違いが、「ゼロからの出発」か「一からの出発」かの違いになったのではないでしょうか。
外は雨。
零、雨のしずくの音に耳を傾けながら、プチ哲学してみました。
http://blog.goo.ne.jp/syusakuhikaru/e/ad6a7be6f0265fa11c88b0e61cc358bc










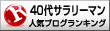
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます