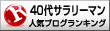フランスのカンヌに行きました。
季節もよく、天候にも恵まれ、快適な旅でした。
その帰り道、パリのシャルル・ドゴール空港で、東京へのフライトを待っている間に、ちょっと不思議な体験をしました。
同僚や家族に土産物を買おうと免税店を回っていた時のことです。
リカーショップに入り、お気に入りのサンテミリオンの赤ワインがとても安く売られていたので、一本買うことに決め、レジに並びました。
私の前に並んでいたのは、東洋人の客。
彼が支払いを済ませると、レジ係のイタリア人らしき若い男性が「シェイシェイ」と、声をかけています。
それに応えて、その東洋人が「シェイシェイ」と言葉を返したので、彼が中国人なのだと分かりました。
近年中国人は世界中を旅行するようになり、ヨーロッパでも日本人よりはるかに数多く中国人を見かけます。
なるほど、ヨーロッパの人たちは、今では東洋人の観光客といえば中国人だと思うものなのかな、と考えながら、私は黙って赤ワインをレジに出しました。
すると、そのレジ係の男性は、私に釣銭を渡しながら「ドモ、アリガト」と言ったのです。
私は、彼とひとことも言葉を交わしていません。
先ほどの中国人も、見かけだけでは中国人なのか韓国人なのか日本人なのか、よく分からないくらいでした。
なぜ言葉を交わさずとも、彼が中国人で、私が日本人だと分かったのか、不思議でした。
その次に訪れたチョコレート屋さんでも同じようなことがありました。
フランス人の女性が私にボーディングチケットを見せるように要求したのですが、私が勘違いしてパスポートを見せたところ、隣の中国人らしき店員が「トージョーケン…キップ」とつたない日本語で話したのです。
彼が搭乗券や切符という日本語を知っていたことは、驚くに足らぬことですが、ほとんどまだ会話を交わしていないのに、少なくとも日本語はひとことも発していないのに、彼は瞬時に私を日本人だと悟っていたのです。
私は、人の顔の区別をつけるのが苦手で、ヨーロッパに行くと、その人がどこの国の人かは、主に聞こえてくる言葉で判別します。
たとえ英語を話していても、フランス語なまり、イタリア語なまりの英語なら、フランス人、イタリア人だと分かります。
しかし顔や身なりだけではなかなか判別がつきません。
そんな私にとって、この空港での体験は新鮮な驚きでした。
フランスのシャルル・ドゴール空港は、世界中の国々の人たちが行き交う場所です。
そこで働く人たちは、毎日実に多くの人種を相手に商売をしています。
彼らが、訪れる客に対して「シェイシェイ」と声をかけるのか、「アリガト」とかけるのか。商売のプロとしては重要なことなのでしょう。
佇まい、物腰、服装や装飾品、あるいは髪型や化粧の仕方…。
言葉を耳にしなくても、その人の出身国や人種を判別する手段はたくさんあります。
考えてみれば、人間がまだ言葉を持たなかった時代にも、目の前にいる相手が敵なのか味方なのか、同一人種なのか違うのかを見分けることは、生きるために必要な能力だったはずです。
これだけ近代化が進み、言葉が発達した時代にも、そうした本能的な識別能力は、脳のどこかに残されているのでしょう。
フランスワインのおつりを受け取りながら、私は日本語で「アリガト」と言ってきたイタリア人のレジ係に「Thank you.」と英語で返して、東京行きのフライトのゲートに向かったのでした。
季節もよく、天候にも恵まれ、快適な旅でした。
その帰り道、パリのシャルル・ドゴール空港で、東京へのフライトを待っている間に、ちょっと不思議な体験をしました。
同僚や家族に土産物を買おうと免税店を回っていた時のことです。
リカーショップに入り、お気に入りのサンテミリオンの赤ワインがとても安く売られていたので、一本買うことに決め、レジに並びました。
私の前に並んでいたのは、東洋人の客。
彼が支払いを済ませると、レジ係のイタリア人らしき若い男性が「シェイシェイ」と、声をかけています。
それに応えて、その東洋人が「シェイシェイ」と言葉を返したので、彼が中国人なのだと分かりました。
近年中国人は世界中を旅行するようになり、ヨーロッパでも日本人よりはるかに数多く中国人を見かけます。
なるほど、ヨーロッパの人たちは、今では東洋人の観光客といえば中国人だと思うものなのかな、と考えながら、私は黙って赤ワインをレジに出しました。
すると、そのレジ係の男性は、私に釣銭を渡しながら「ドモ、アリガト」と言ったのです。
私は、彼とひとことも言葉を交わしていません。
先ほどの中国人も、見かけだけでは中国人なのか韓国人なのか日本人なのか、よく分からないくらいでした。
なぜ言葉を交わさずとも、彼が中国人で、私が日本人だと分かったのか、不思議でした。
その次に訪れたチョコレート屋さんでも同じようなことがありました。
フランス人の女性が私にボーディングチケットを見せるように要求したのですが、私が勘違いしてパスポートを見せたところ、隣の中国人らしき店員が「トージョーケン…キップ」とつたない日本語で話したのです。
彼が搭乗券や切符という日本語を知っていたことは、驚くに足らぬことですが、ほとんどまだ会話を交わしていないのに、少なくとも日本語はひとことも発していないのに、彼は瞬時に私を日本人だと悟っていたのです。
私は、人の顔の区別をつけるのが苦手で、ヨーロッパに行くと、その人がどこの国の人かは、主に聞こえてくる言葉で判別します。
たとえ英語を話していても、フランス語なまり、イタリア語なまりの英語なら、フランス人、イタリア人だと分かります。
しかし顔や身なりだけではなかなか判別がつきません。
そんな私にとって、この空港での体験は新鮮な驚きでした。
フランスのシャルル・ドゴール空港は、世界中の国々の人たちが行き交う場所です。
そこで働く人たちは、毎日実に多くの人種を相手に商売をしています。
彼らが、訪れる客に対して「シェイシェイ」と声をかけるのか、「アリガト」とかけるのか。商売のプロとしては重要なことなのでしょう。
佇まい、物腰、服装や装飾品、あるいは髪型や化粧の仕方…。
言葉を耳にしなくても、その人の出身国や人種を判別する手段はたくさんあります。
考えてみれば、人間がまだ言葉を持たなかった時代にも、目の前にいる相手が敵なのか味方なのか、同一人種なのか違うのかを見分けることは、生きるために必要な能力だったはずです。
これだけ近代化が進み、言葉が発達した時代にも、そうした本能的な識別能力は、脳のどこかに残されているのでしょう。
フランスワインのおつりを受け取りながら、私は日本語で「アリガト」と言ってきたイタリア人のレジ係に「Thank you.」と英語で返して、東京行きのフライトのゲートに向かったのでした。