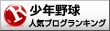卓球の選手時代に自分の打っている姿をビデオで見て驚いた。自分ではほぼ水平に振っているつもりだったが、実際はかなり下から上に振っていた。かように自分の「感覚」と、「実際の見え方」には、かなりのズレがある。
バッティングにおいても、レベルに振っているつもりでもアッパーになっている場合がある。これを修正するための練習は「片寄った」「変な」練習になる。同様に、矯正を目的にしたアドバイスも、「毒を以て毒を制す」的な言い回しになる。
王貞治は巨人入団当時、かなりのアッパースイングだったそうである。荒川コーチが提案した、ダウンスイング素振りや、吊るした短冊を真剣で切る練習が奏功し、きれいなレベルスイングになったという。イチローの打席入り前の素振りもズレを意識した振り方になっているように思う。
コーチングにおいて「理論」と「感覚のズレ」を合わせて説明するべき技術は多い。理論で「どうしてか」を語り、実践で「どうするか」を説明する、それができて「本質」が伝わる。