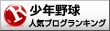小指方向に手首が曲がるとヘッドが下がる
グリップが高い位置にある状態で構えて、そのまま振り下ろす
と、ほとんどは
手首が小指方向に折れて
バット・手首・肘がまっすぐ並び
ヘッドが下がった状態になる
そもそも手首そのものは思うほど動かない
「手のひら・手の甲」方向はせいぜい180度。親指・小指方向は30度くらい
スクリューパンチ方向には270度くらい回るが、手首が回っているわけではない
「スクリュー動作」は手首と肘をつなぐ2本の筋肉が、お互いの位置を入れ替えるように回転し、パワーが生まれる
その時、手首は一切曲げずに固定すべきで、曲がった時点でロスが生じる
「手首が強い人」は、2本の筋肉が太い人
あるいは、効率的に「スクリュー動作」ができる人
さて、「ヘッドが下がっている」とは?
「スクリュー動作が上手くできない状態だ」ということを警告するための表現だ
癖でそうなる選手もいるが、小学生場合はバットの重さをさばけないまま手首が折れてしまうケースがほとんどである
先が重いバットをさばくのは難しい→どうしても手先で操作したくなる→本来「支点」であるべき手首が「力点」も兼ねることになる→支点が動くから、作用点である「ヘッド」をうまくコントロールできない
→なかなか芯を食わない
「力点」と「支点」の距離が、「支点」と「作用点」の距離より短いと、「てこの原理」の恩恵を受けられない
→芯を食っても飛ばない
百害あって一利もない