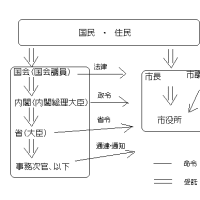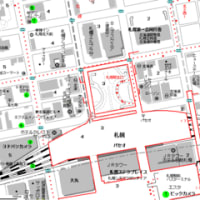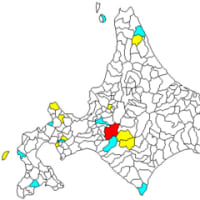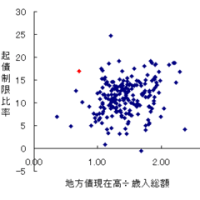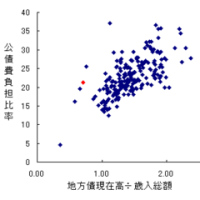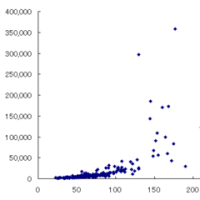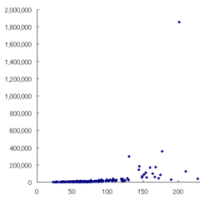(職務に専念する義務)
第三十五条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
★勤務時間中に勤務条件に関する措置の要求を人事委員会に対して行う場合でも、法律又は条例に特別の定めが無い限り、法的には職務専念義務に抵触する(行政実例昭和27年2月29日)
★法律に定めがある場合とは、休職、停職、職員団体と当局との勤務時間内の交渉、労働基準法に基づく休暇がある。
●地方公務員法---------------------------
(交渉)
第五十五条
8 本条に規定する適法な交渉は、勤務時間中においても行なうことができる。
---------------------------
★当局と適法な交渉を行うため職員団体から指名された職員も、職務専念義務の免除について任命権者から承認を得なければならない(行政実例昭和41年6月21日)
★条例に定めがある場合とは、休日・休暇に関する条例に基づく休日・休暇(行政実例昭和26年12月12日地自公発549号)、勤務時間に関する条例に基づく休息時間、職務専念義務の免除に関する条例に定めるものがある。
●札幌市の休日を定める条例---------------------------
(本市の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、本市の休日とし、本市の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
●札幌市職員の勤務条件に関する条例---------------------------
(休息時間)
第7条 任命権者は、所定の勤務時間のうちに休息時間を置くことができる。
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
●札幌市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例---------------------------
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き、職員の職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ、任命権者又は、その委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生福利に関する事業に参加する場合
(3) 職員団体の業務に従事する場合
(4) 前3号に規定する場合を除くほか、人事委員会規則で定める場合。ただし、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員については、任命権者が定める場合
●札幌市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則---------------------------
昭和47年3月24日人事委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第6号)第2条第4号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第2条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定による勤務条件の措置の要求に関する審理に措置要求者として出席する場合
(2) 地方公務員法第49条の2第1項の規定による不利益処分についての不服申立てに関する審理に不服申立人として出席する場合
(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づく審査請求及び再審査請求の審理に審査請求人及び再審査請求人として出席する場合
(4) 札幌市職員の苦情相談に関する規則(平成17年人事委員会規則第7号)第4条の規定による人事委員会の事情聴取等に応ずる場合
(5) 国又は地方公共団体が法令又は条例等に基づき設置した委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員として、その事務を行う場合
(6) 本市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役員又は職員としての地位を兼ね、その事務を行う場合
(7) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合
(8) 国、他の地方公共団体又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に掲げる学校その他本市行政の運営上関係のある団体等から委嘱を受け、市政又は学術に関し講演、講義等を行う場合
(9) 職務遂行上必要な国、道又は本市の実施する試験を受ける場合
(10) 国又は地方公共団体が主催、共催又は後援する行事に役員又は構成員として参加する場合
(11) 学校教育法第52条の2の規定による大学通信教育の面接授業(年を通じて行われるもの及び夜間に行われるものを除く。)に出席する場合
(12) 前各号に掲げるもののほか、人事委員会が特に認める場合
---------------------------
★職務専念義務が免除された勤務時間に対して、給与が支払われる場合もあれば、そうでない場合もある。札幌市の場合は、組合専従になるとき以外は支払われる。
●札幌市職員給与条例---------------------------
(給与の減額)
第8条 職員が勤務しないときは、休日等(勤務条件条例第9条第1項に規定する祝日法による休日(勤務条件条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)及び勤務条件条例第9条第1項に規定する年末年始の休日(勤務条件条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)をいう。以下同じ。)である場合、勤務条件条例第11条に規定する休暇による場合その他その勤務しないことにつき正当な権限を有する者の承認があつた場合を除き、その勤務しない時間につき、第31条の2に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に当該勤務しない時間の数を人事委員会規則で定めるところにより乗じて得た額を減額して給与を支給する。
●札幌市職員給与条例施行規則
(勤務しないことにつき承認があつた場合)
第4条 条例第8条に規定する勤務をしないことにつき正当な権限を有する者の承認があつた場合とは、札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号)第6条又は職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第34号)第2条の適用がある場合を除くほか、次の各号に掲げる条例及び規則の規定又は人事委員会が特に必要と認めて定めた基準に基づき、勤務しないことにつき正当な権限を有する者が承認を与えた場合とする。
(1) 札幌市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第6号。以下「職務専念義務特例条例」という。)第2条第1号及び第2号
(2) 札幌市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和47年人事委員会規則第6号)第2条
---------------------------
★国家公務員法が原則として官職を兼ねることを禁止しているのに対して、地方公務員法の場合同一地方公共団体内において他の職を兼ねることをは禁止されていない。
●国家公務員法---------------------------
(職務に専念する義務)
第百一条 職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。
---------------------------
★県費負担教職員の、職務専念義務の免除は、服務に関する事項なので市町村教育委員会が行う。
●地方教育行政の組織及び運営に関する法律---------------------------
(服務の監督)
第四十三条 市町村委員会は、県費負担教職員の服務を監督する。
---------------------------
★勤務時間中に、リボン等を着用する組合活動が職務専念義務違反の問題として争われることがあるが、判例が固まっていない(そのため、知識として問われたのを見たことは無い)。
★公益法人等へは公務員の身分を有したままの派遣、営利法人等へは復職をはじめ処遇に配慮した上での退職派遣となる。
●公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律---------------------------
(職員の派遣)
第二条 任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる団体(以下この項及び第三項において「公益法人等」という。)のうち、その業務の全部又は一部が当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、当該地方公共団体がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるものとして条例で定めるものとの間の取決めに基づき、当該公益法人等の業務にその役職員として専ら従事させるため、条例で定めるところにより、職員(条例で定める職員を除く。)を派遣することができる。
一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人
二 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十五条に規定する一般地方独立行政法人
三 特別の法律により設立された法人(前号に掲げるもの及び営利を目的とするものを除く。)で政令で定めるもの
四 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項に規定する連合組織で同項の規定による届出をしたもの
2 任命権者は、前項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)の実施に当たっては、あらかじめ、当該職員に同項の取決めの内容を明示し、その同意を得なければならない。
3 第一項の取決めにおいては、当該職員派遣に係る職員の職員派遣を受ける公益法人等(以下「派遣先団体」という。)における報酬その他の勤務条件及び当該派遣先団体において従事すべき業務、当該職員の職員派遣の期間、当該職員の職務への復帰に関する事項その他職員派遣に当たって合意しておくべきものとして条例で定める事項を定めるものとする。
4 前項の規定により第一項の取決めで定める職員派遣に係る職員の派遣先団体において従事すべき業務は、当該派遣先団体の主たる業務が地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有すると認められる業務である場合を除き、地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有すると認められる業務を主たる内容とするものでなければならない。
(特定法人の業務に従事するために退職した者の採用)
第十条 任命権者と特定法人(当該地方公共団体が出資している株式会社のうち、その業務の全部又は一部が地域の振興、住民の生活の向上その他公益の増進に寄与するとともに当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、当該地方公共団体がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるものとして条例で定めるものをいう。以下同じ。)との間で締結された取決めに定められた内容に従って当該特定法人の業務に従事するよう求める任命権者の要請に応じて職員(条例で定める職員を除く。)が退職し、引き続き当該特定法人の役職員として在職した後、当該取決めで定める当該特定法人において業務に従事すべき期間が満了した場合又はその者が当該特定法人の役職員の地位を失った場合その他の条例で定める場合には、地方公務員法第十六条各号(第三号を除く。)の一に該当する場合(同条の条例で定める場合を除く。)その他条例で定める場合を除き、その者が退職した時就いていた職又はこれに相当する職に係る任命権者は、当該特定法人の役職員としての在職に引き続き、その者を職員として採用するものとする。
2 前項の取決めにおいては、同項の要請に応じて退職し引き続き当該特定法人に在職する者(以下「退職派遣者」という。)の当該特定法人における報酬その他の勤務条件並びに当該特定法人において従事すべき業務及び業務に従事すべき期間、同項の規定による当該退職派遣者の採用に関する事項その他当該退職派遣者が当該特定法人の業務に従事するに当たって合意しておくべきものとして条例で定める事項を定めるものとする。
3 前項の規定により第一項の取決めで定める退職派遣者の特定法人において従事すべき業務は、当該特定法人の主たる業務が地域の振興、住民の生活の向上その他公益の増進に寄与し、かつ、地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有すると認められる業務(以下この項において「公益寄与業務」という。)である場合を除き、公益寄与業務を主たる内容とするものでなければならない。
4 第二項の規定により第一項の取決めで定める退職派遣者の特定法人において業務に従事すべき期間は、同項の要請に応じて退職をする日の翌日から起算して三年を超えない範囲内で定めるものとする。
5 第一項の規定による採用については、地方公務員法第二十二条第一項の規定は、適用しない。
---------------------------
第三十五条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
★勤務時間中に勤務条件に関する措置の要求を人事委員会に対して行う場合でも、法律又は条例に特別の定めが無い限り、法的には職務専念義務に抵触する(行政実例昭和27年2月29日)
★法律に定めがある場合とは、休職、停職、職員団体と当局との勤務時間内の交渉、労働基準法に基づく休暇がある。
●地方公務員法---------------------------
(交渉)
第五十五条
8 本条に規定する適法な交渉は、勤務時間中においても行なうことができる。
---------------------------
★当局と適法な交渉を行うため職員団体から指名された職員も、職務専念義務の免除について任命権者から承認を得なければならない(行政実例昭和41年6月21日)
★条例に定めがある場合とは、休日・休暇に関する条例に基づく休日・休暇(行政実例昭和26年12月12日地自公発549号)、勤務時間に関する条例に基づく休息時間、職務専念義務の免除に関する条例に定めるものがある。
●札幌市の休日を定める条例---------------------------
(本市の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、本市の休日とし、本市の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
●札幌市職員の勤務条件に関する条例---------------------------
(休息時間)
第7条 任命権者は、所定の勤務時間のうちに休息時間を置くことができる。
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
●札幌市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例---------------------------
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き、職員の職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ、任命権者又は、その委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生福利に関する事業に参加する場合
(3) 職員団体の業務に従事する場合
(4) 前3号に規定する場合を除くほか、人事委員会規則で定める場合。ただし、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員については、任命権者が定める場合
●札幌市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則---------------------------
昭和47年3月24日人事委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第6号)第2条第4号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第2条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定による勤務条件の措置の要求に関する審理に措置要求者として出席する場合
(2) 地方公務員法第49条の2第1項の規定による不利益処分についての不服申立てに関する審理に不服申立人として出席する場合
(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づく審査請求及び再審査請求の審理に審査請求人及び再審査請求人として出席する場合
(4) 札幌市職員の苦情相談に関する規則(平成17年人事委員会規則第7号)第4条の規定による人事委員会の事情聴取等に応ずる場合
(5) 国又は地方公共団体が法令又は条例等に基づき設置した委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員として、その事務を行う場合
(6) 本市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役員又は職員としての地位を兼ね、その事務を行う場合
(7) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合
(8) 国、他の地方公共団体又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に掲げる学校その他本市行政の運営上関係のある団体等から委嘱を受け、市政又は学術に関し講演、講義等を行う場合
(9) 職務遂行上必要な国、道又は本市の実施する試験を受ける場合
(10) 国又は地方公共団体が主催、共催又は後援する行事に役員又は構成員として参加する場合
(11) 学校教育法第52条の2の規定による大学通信教育の面接授業(年を通じて行われるもの及び夜間に行われるものを除く。)に出席する場合
(12) 前各号に掲げるもののほか、人事委員会が特に認める場合
---------------------------
★職務専念義務が免除された勤務時間に対して、給与が支払われる場合もあれば、そうでない場合もある。札幌市の場合は、組合専従になるとき以外は支払われる。
●札幌市職員給与条例---------------------------
(給与の減額)
第8条 職員が勤務しないときは、休日等(勤務条件条例第9条第1項に規定する祝日法による休日(勤務条件条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)及び勤務条件条例第9条第1項に規定する年末年始の休日(勤務条件条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)をいう。以下同じ。)である場合、勤務条件条例第11条に規定する休暇による場合その他その勤務しないことにつき正当な権限を有する者の承認があつた場合を除き、その勤務しない時間につき、第31条の2に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に当該勤務しない時間の数を人事委員会規則で定めるところにより乗じて得た額を減額して給与を支給する。
●札幌市職員給与条例施行規則
(勤務しないことにつき承認があつた場合)
第4条 条例第8条に規定する勤務をしないことにつき正当な権限を有する者の承認があつた場合とは、札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号)第6条又は職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第34号)第2条の適用がある場合を除くほか、次の各号に掲げる条例及び規則の規定又は人事委員会が特に必要と認めて定めた基準に基づき、勤務しないことにつき正当な権限を有する者が承認を与えた場合とする。
(1) 札幌市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第6号。以下「職務専念義務特例条例」という。)第2条第1号及び第2号
(2) 札幌市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和47年人事委員会規則第6号)第2条
---------------------------
★国家公務員法が原則として官職を兼ねることを禁止しているのに対して、地方公務員法の場合同一地方公共団体内において他の職を兼ねることをは禁止されていない。
●国家公務員法---------------------------
(職務に専念する義務)
第百一条 職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。
---------------------------
★県費負担教職員の、職務専念義務の免除は、服務に関する事項なので市町村教育委員会が行う。
●地方教育行政の組織及び運営に関する法律---------------------------
(服務の監督)
第四十三条 市町村委員会は、県費負担教職員の服務を監督する。
---------------------------
★勤務時間中に、リボン等を着用する組合活動が職務専念義務違反の問題として争われることがあるが、判例が固まっていない(そのため、知識として問われたのを見たことは無い)。
★公益法人等へは公務員の身分を有したままの派遣、営利法人等へは復職をはじめ処遇に配慮した上での退職派遣となる。
●公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律---------------------------
(職員の派遣)
第二条 任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる団体(以下この項及び第三項において「公益法人等」という。)のうち、その業務の全部又は一部が当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、当該地方公共団体がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるものとして条例で定めるものとの間の取決めに基づき、当該公益法人等の業務にその役職員として専ら従事させるため、条例で定めるところにより、職員(条例で定める職員を除く。)を派遣することができる。
一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人
二 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十五条に規定する一般地方独立行政法人
三 特別の法律により設立された法人(前号に掲げるもの及び営利を目的とするものを除く。)で政令で定めるもの
四 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項に規定する連合組織で同項の規定による届出をしたもの
2 任命権者は、前項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)の実施に当たっては、あらかじめ、当該職員に同項の取決めの内容を明示し、その同意を得なければならない。
3 第一項の取決めにおいては、当該職員派遣に係る職員の職員派遣を受ける公益法人等(以下「派遣先団体」という。)における報酬その他の勤務条件及び当該派遣先団体において従事すべき業務、当該職員の職員派遣の期間、当該職員の職務への復帰に関する事項その他職員派遣に当たって合意しておくべきものとして条例で定める事項を定めるものとする。
4 前項の規定により第一項の取決めで定める職員派遣に係る職員の派遣先団体において従事すべき業務は、当該派遣先団体の主たる業務が地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有すると認められる業務である場合を除き、地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有すると認められる業務を主たる内容とするものでなければならない。
(特定法人の業務に従事するために退職した者の採用)
第十条 任命権者と特定法人(当該地方公共団体が出資している株式会社のうち、その業務の全部又は一部が地域の振興、住民の生活の向上その他公益の増進に寄与するとともに当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、当該地方公共団体がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるものとして条例で定めるものをいう。以下同じ。)との間で締結された取決めに定められた内容に従って当該特定法人の業務に従事するよう求める任命権者の要請に応じて職員(条例で定める職員を除く。)が退職し、引き続き当該特定法人の役職員として在職した後、当該取決めで定める当該特定法人において業務に従事すべき期間が満了した場合又はその者が当該特定法人の役職員の地位を失った場合その他の条例で定める場合には、地方公務員法第十六条各号(第三号を除く。)の一に該当する場合(同条の条例で定める場合を除く。)その他条例で定める場合を除き、その者が退職した時就いていた職又はこれに相当する職に係る任命権者は、当該特定法人の役職員としての在職に引き続き、その者を職員として採用するものとする。
2 前項の取決めにおいては、同項の要請に応じて退職し引き続き当該特定法人に在職する者(以下「退職派遣者」という。)の当該特定法人における報酬その他の勤務条件並びに当該特定法人において従事すべき業務及び業務に従事すべき期間、同項の規定による当該退職派遣者の採用に関する事項その他当該退職派遣者が当該特定法人の業務に従事するに当たって合意しておくべきものとして条例で定める事項を定めるものとする。
3 前項の規定により第一項の取決めで定める退職派遣者の特定法人において従事すべき業務は、当該特定法人の主たる業務が地域の振興、住民の生活の向上その他公益の増進に寄与し、かつ、地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有すると認められる業務(以下この項において「公益寄与業務」という。)である場合を除き、公益寄与業務を主たる内容とするものでなければならない。
4 第二項の規定により第一項の取決めで定める退職派遣者の特定法人において業務に従事すべき期間は、同項の要請に応じて退職をする日の翌日から起算して三年を超えない範囲内で定めるものとする。
5 第一項の規定による採用については、地方公務員法第二十二条第一項の規定は、適用しない。
---------------------------