いつだったか東京に遊びにいったとき、山﨑修平さんに誘われて詩の朗読イベントに参加したことがある。
下北沢だったか荻窪だったか、そのあたりのカフェが会場だったはずだ。不慣れな都市の雑踏を乗り越え、日のすっかり落ちた路地を抜けてたどり着くと、店内にはすでに30名ほどの人がいた。参加料と引き換えにジンジャーエールを受け取ってしばらく待つ。主催者からの簡単な挨拶のあと、さっそくイベントは始まった。
興味深い場だった。朗読といいつつも、一般に「朗読」と言われて思い浮かべるようなシンプルに作品を読み上げるスタイルだけではなく、楽器や踊り、身振り手振りなどを駆使して身体的に表現を行うスタイルの朗読もあった。私にとっては、前者のスタイルの方がより好感が持てるようで、後者のスタイルに近いものは、これが東京の自意識かあ、という捻くれた感想の方が強かった。なんとなくだが、後者のスタイルの「私が表現をしているのだ」ということを殊更に目の前に提示する感じが、どこかで自身が特別であるということを誇示しなければ雑踏の不特定多数に飲み込まれてしまうのではないか、という都市的な恐怖に由来するオーバーな表現に見えたのだ。この都市ではそうでなければだめだったのだろう、と分かった風にしておいているうち、ジンジャーエールがなくなった。
会場からの受けが良いのは後者のスタイルのようだった。もっとも、受けていることがわかりやすかっただけかもしれないが。これが東京の自意識かあ、とまた仮想敵を大きく取りながら追加でジンジャーエールを頼んでいると、山﨑さんの朗読の番になった。最初から朗読者として参加登録していたらしく、しっかり自身の作品を複数印刷して持ってきていた。
率直にいって、山﨑さんの朗読はあまり受けなかった。
山﨑さんの朗読が、前者のシンプルな朗読のスタイルであったためだろうか。それとも、大きな反応として見えていなかっただけで、静かに会場には浸透していたのだろうか。私にとってはかなり好みの朗読だったが。とりあえず、会場にあまり受けてなかった風であったのが、むしろ私にはとても面白かった。そして私の席の方に戻ってきた山﨑さんはひとこと、「今日はよくなかったね」とばつの悪そうな顔で言った。
*
私が東京という都市やその意識、そこに生まれる表現に対して(おそらくは羨望の裏返しであろう)偏見や捻くれた態度を持っていることは、上述の意地の悪い文章から明確であろうが、一方で東京という都市のエッセンスや空気を多分に取り込んだ山﨑修平作品は、なぜか私にとって素直に心地よい。
どうしてもこうなっていたと思うんだよね古い写真立てに写真は飾られていない
たとえば未完成の高層ビルディングを描く一人の男の話だ
貝のなまえ、海のなまえ、海岸のなまえを尋ねてあなたは贈り物を受けとる
自転車で知らないところへ近づいて
はじめてまっすぐな道路は続いて
もう一度ハナミズキを見に行こう声は細くしなやかに都市をほどいてゆく
17時5分、紀伊國屋書店新宿本店2階の窓から
切手の大きさの一点を観る夢を咥えてたくましいひかりばかりで
ほんとうはここでしょここのここでないところ
すると、するするとほどけてゆく
「情けないね、ほんとうに聴きたい音楽は」たよりない語尾と、所在なげな笑みを浮かべて
「パブロ・ピカソは長生きだったってこと?」たぶん晴れてきているのに雨傘しかもきれいな
近刊の第二詩集『ダンスする食う寝る』より1編を全文引用してみる。
ここでは、「未完成の高層ビルディング」のような抽象的な都会的なイメージから、より具体的な「紀伊國屋書店新宿本店2階」[2]にまで足を踏み入れる。「未完成の高層ビルディング」の時点で都市はあくまで抽象的な都市であるが、「紀伊國屋書店新宿本店2階」まで行が進んだとき、その都市は東京に確定される。一方、「紀伊國屋書店新宿本店2階」以外の表現は非常に抽象度が高いままに提示されている。写真が飾られていない「古い写真立て」は誰の像も結ばずにただ写真立てというどこにでもありそうな事物を指し示すし、「一人の男の話」の具体的な内容は明かされない。「なまえ」は多いが、どれもここでは具体名では呼ばれない。「ハナミズキ」や「パブロ・ピカソ」はより具体的だが、「ハナミズキを見に行こう」「パブロ・ピカソは長生きだった」と語法に組み込まれて詩に置かれた途端、それらが何を指し示そうとしていたのかは流れるようにぼやかされる。
山﨑作品の基本的な特徴はこのように、都市という都市を東京という具体的な都市へ収斂させながら、それ以外の事物を言葉の流れのなかであくまでも単なる流れであるかのように抽象化して見せる手法にあると私は思う。
(……)
ちょうど炭酸が切れたころにやってくる
レコードを荻窪で買っておかしな服を着て
初対面の抽象的な絵画あるいは人の列、解釈不能なすべて
そのどれもが僕らにとって幸福な時間だった
(……)
「乾季のみ客を受け入れる街の隅に置かれた毛布はひとつの哲学」[3]
今度は第一詩集からの引用だが、ここでも同様の事象が起こっているように思われる。「炭酸」「レコード」「絵画」など単語は様々あるが、それらが結ぶのはいずれも抽象度の高い像である。その抽象の流れにおいて、「荻窪」という単語だけが現実の世界との接点として錨をおろしている。裏を返せば、「荻窪」があるからこそ私はこの一連を、どこか地続きのものとして素直に受け入れられるのだとも思う。
すべての都市を東京に収斂させる。そのような目で眺めるとするなら、山﨑修平とは圧倒的に東京という風土の詩人である。その風土にはしかし、意地の悪い叙述で私が「東京の自意識」と乱暴に呼称していたような、あの都市的な恐怖の姿は見当たらない。
(……)
水蒸気に乱反射する彼らの仲間が俺の大切なドンペリニヨンを明け透けに語るというから君が壊した万引き自慰メンのことを三日月がガサツだからと呼ぶことにしたこれは博打だねと言うから樹々の樹皮を液の垂れるところまで放っておいたこのようにして堕落していくことまで親愛なる江戸城が俺に勇気をくれたけれどもう一度川を背にして数えた日のことを教えて欲しい今はこんなになってしまって俺はそこに加担している今もそうだだから口笛のなかに小鳥が奏でるまでそして加わりワクワクするまで泣くのをやめるなんてことはよしてぶっ倒しに行くまでしずかにゆっくりと右に行った方が近道なんだ僕の家はダンスする食う寝るダンスする食う寝るそしてあなたが光らせた花のしおれてゆくまでの日々のことを(……)
「自意識」というキーワードで詩を見るなら、たとえば一般には「俺」という一人称の登場がその放出なのだと思うこともできるかもしれない。しかし、やはりここでも私は、この一連にそれほど強い「東京の自意識」や都市的な恐怖というものを感じない。なぜかと考えてみればたぶん、もうここでは「雑踏の不特定多数に飲み込まれて」いることが前提に「俺」という存在があるからではないだろうかと思う。
私が意地悪く「東京の自意識」と呼んでいたものが、どのような自意識なのかと問うなら、それは自身が特別な存在である/特別な存在になりうると信じることに依ってその存在意義を見出す自意識であったのではないか。対して、山﨑作品で見出される「俺」——自意識は、東京という風土のなかで常に流され続けることを前提に、決して特別ではない自分自身を肯定するという意識なのではないか。山﨑作品に特徴的な、言葉をフローティングさせて次々につなぎ合わせていく手法のなかにおいて、「俺」に代表される一人称、「君」という二人称、「彼ら」という三人称のいずれもが、常に流されていく宿命を背負っている。流れのなかに特別な存在として立ち上がるための錨は、誰の手にもない。風土たる東京のみ、いままさに流れを内包している都市の存在のみが、この詩歌の空間にとっては錨なのである。ここにおいては、どのような「俺」も特別ではなく、抽象的な流れにすべてを委ねざるを得ない存在である。そして、その一点のみ前提として受け入れてしまえば、「俺」にはもう何も恐怖することはない。誰も特別にはなれないのだから、誰も——「俺」も特別でなくともよいのである。
特別でなくともよいということ。それは私たちにできる最大限の自身の肯定ではないだろうか。私が山﨑作品に感じる心地よさは、そうした反転した自己の肯定にあるのかもしれない。
*
イベントが終わって、よくわからないままにいろんな人に挨拶してから、私は山﨑さんとカフェから出た。山﨑さんはまだ少し不服そうだった。東京って感じがしますね、と私がいうと、「今日は良くなかったね」と山﨑さんは再び言った。思いっきり凹んで拗ねているのがとても面白かった。その一帯にありがちな、深夜まで煌々としている小さな書店やレコード店を見て回りながら駅へと向かう。東京って感じがするなあと思った。
誰もがきっと、何らかの形で特別でありたいと願うだろう。その願いは、叶ったり叶わなかったりするのだろう。でも、願うことを揶揄してはいけないのだ。そして、たとえ特別でなかったとしても、それこそが特別であることだって、きっとあるのだ。てのひらに錨がなくとも、私たちは風の流れと土の確かさに、夜の都市を歩くことができる。
【註】
[1]山﨑修平『ダンスする食う寝る』(思潮社、2020年)
[2]実際にある店舗で、紀伊國屋書店新宿本店の2階の窓の近くには詩歌句のコーナーがある。足を運ぶと、だいたい詩歌句の知り合いに会える。
[3]山﨑修平『ロックンロールは死んだらしいよ』(思潮社、2016年)
[4]前掲書[1]
下北沢だったか荻窪だったか、そのあたりのカフェが会場だったはずだ。不慣れな都市の雑踏を乗り越え、日のすっかり落ちた路地を抜けてたどり着くと、店内にはすでに30名ほどの人がいた。参加料と引き換えにジンジャーエールを受け取ってしばらく待つ。主催者からの簡単な挨拶のあと、さっそくイベントは始まった。
興味深い場だった。朗読といいつつも、一般に「朗読」と言われて思い浮かべるようなシンプルに作品を読み上げるスタイルだけではなく、楽器や踊り、身振り手振りなどを駆使して身体的に表現を行うスタイルの朗読もあった。私にとっては、前者のスタイルの方がより好感が持てるようで、後者のスタイルに近いものは、これが東京の自意識かあ、という捻くれた感想の方が強かった。なんとなくだが、後者のスタイルの「私が表現をしているのだ」ということを殊更に目の前に提示する感じが、どこかで自身が特別であるということを誇示しなければ雑踏の不特定多数に飲み込まれてしまうのではないか、という都市的な恐怖に由来するオーバーな表現に見えたのだ。この都市ではそうでなければだめだったのだろう、と分かった風にしておいているうち、ジンジャーエールがなくなった。
会場からの受けが良いのは後者のスタイルのようだった。もっとも、受けていることがわかりやすかっただけかもしれないが。これが東京の自意識かあ、とまた仮想敵を大きく取りながら追加でジンジャーエールを頼んでいると、山﨑さんの朗読の番になった。最初から朗読者として参加登録していたらしく、しっかり自身の作品を複数印刷して持ってきていた。
率直にいって、山﨑さんの朗読はあまり受けなかった。
山﨑さんの朗読が、前者のシンプルな朗読のスタイルであったためだろうか。それとも、大きな反応として見えていなかっただけで、静かに会場には浸透していたのだろうか。私にとってはかなり好みの朗読だったが。とりあえず、会場にあまり受けてなかった風であったのが、むしろ私にはとても面白かった。そして私の席の方に戻ってきた山﨑さんはひとこと、「今日はよくなかったね」とばつの悪そうな顔で言った。
*
私が東京という都市やその意識、そこに生まれる表現に対して(おそらくは羨望の裏返しであろう)偏見や捻くれた態度を持っていることは、上述の意地の悪い文章から明確であろうが、一方で東京という都市のエッセンスや空気を多分に取り込んだ山﨑修平作品は、なぜか私にとって素直に心地よい。
どうしてもこうなっていたと思うんだよね古い写真立てに写真は飾られていない
たとえば未完成の高層ビルディングを描く一人の男の話だ
貝のなまえ、海のなまえ、海岸のなまえを尋ねてあなたは贈り物を受けとる
自転車で知らないところへ近づいて
はじめてまっすぐな道路は続いて
もう一度ハナミズキを見に行こう声は細くしなやかに都市をほどいてゆく
17時5分、紀伊國屋書店新宿本店2階の窓から
切手の大きさの一点を観る夢を咥えてたくましいひかりばかりで
ほんとうはここでしょここのここでないところ
すると、するするとほどけてゆく
「情けないね、ほんとうに聴きたい音楽は」たよりない語尾と、所在なげな笑みを浮かべて
「パブロ・ピカソは長生きだったってこと?」たぶん晴れてきているのに雨傘しかもきれいな
「開かれた窓」[1]
近刊の第二詩集『ダンスする食う寝る』より1編を全文引用してみる。
ここでは、「未完成の高層ビルディング」のような抽象的な都会的なイメージから、より具体的な「紀伊國屋書店新宿本店2階」[2]にまで足を踏み入れる。「未完成の高層ビルディング」の時点で都市はあくまで抽象的な都市であるが、「紀伊國屋書店新宿本店2階」まで行が進んだとき、その都市は東京に確定される。一方、「紀伊國屋書店新宿本店2階」以外の表現は非常に抽象度が高いままに提示されている。写真が飾られていない「古い写真立て」は誰の像も結ばずにただ写真立てというどこにでもありそうな事物を指し示すし、「一人の男の話」の具体的な内容は明かされない。「なまえ」は多いが、どれもここでは具体名では呼ばれない。「ハナミズキ」や「パブロ・ピカソ」はより具体的だが、「ハナミズキを見に行こう」「パブロ・ピカソは長生きだった」と語法に組み込まれて詩に置かれた途端、それらが何を指し示そうとしていたのかは流れるようにぼやかされる。
山﨑作品の基本的な特徴はこのように、都市という都市を東京という具体的な都市へ収斂させながら、それ以外の事物を言葉の流れのなかであくまでも単なる流れであるかのように抽象化して見せる手法にあると私は思う。
(……)
ちょうど炭酸が切れたころにやってくる
レコードを荻窪で買っておかしな服を着て
初対面の抽象的な絵画あるいは人の列、解釈不能なすべて
そのどれもが僕らにとって幸福な時間だった
(……)
「乾季のみ客を受け入れる街の隅に置かれた毛布はひとつの哲学」[3]
今度は第一詩集からの引用だが、ここでも同様の事象が起こっているように思われる。「炭酸」「レコード」「絵画」など単語は様々あるが、それらが結ぶのはいずれも抽象度の高い像である。その抽象の流れにおいて、「荻窪」という単語だけが現実の世界との接点として錨をおろしている。裏を返せば、「荻窪」があるからこそ私はこの一連を、どこか地続きのものとして素直に受け入れられるのだとも思う。
すべての都市を東京に収斂させる。そのような目で眺めるとするなら、山﨑修平とは圧倒的に東京という風土の詩人である。その風土にはしかし、意地の悪い叙述で私が「東京の自意識」と乱暴に呼称していたような、あの都市的な恐怖の姿は見当たらない。
(……)
水蒸気に乱反射する彼らの仲間が俺の大切なドンペリニヨンを明け透けに語るというから君が壊した万引き自慰メンのことを三日月がガサツだからと呼ぶことにしたこれは博打だねと言うから樹々の樹皮を液の垂れるところまで放っておいたこのようにして堕落していくことまで親愛なる江戸城が俺に勇気をくれたけれどもう一度川を背にして数えた日のことを教えて欲しい今はこんなになってしまって俺はそこに加担している今もそうだだから口笛のなかに小鳥が奏でるまでそして加わりワクワクするまで泣くのをやめるなんてことはよしてぶっ倒しに行くまでしずかにゆっくりと右に行った方が近道なんだ僕の家はダンスする食う寝るダンスする食う寝るそしてあなたが光らせた花のしおれてゆくまでの日々のことを(……)
「ダンスする食う寝る」[4]
「自意識」というキーワードで詩を見るなら、たとえば一般には「俺」という一人称の登場がその放出なのだと思うこともできるかもしれない。しかし、やはりここでも私は、この一連にそれほど強い「東京の自意識」や都市的な恐怖というものを感じない。なぜかと考えてみればたぶん、もうここでは「雑踏の不特定多数に飲み込まれて」いることが前提に「俺」という存在があるからではないだろうかと思う。
私が意地悪く「東京の自意識」と呼んでいたものが、どのような自意識なのかと問うなら、それは自身が特別な存在である/特別な存在になりうると信じることに依ってその存在意義を見出す自意識であったのではないか。対して、山﨑作品で見出される「俺」——自意識は、東京という風土のなかで常に流され続けることを前提に、決して特別ではない自分自身を肯定するという意識なのではないか。山﨑作品に特徴的な、言葉をフローティングさせて次々につなぎ合わせていく手法のなかにおいて、「俺」に代表される一人称、「君」という二人称、「彼ら」という三人称のいずれもが、常に流されていく宿命を背負っている。流れのなかに特別な存在として立ち上がるための錨は、誰の手にもない。風土たる東京のみ、いままさに流れを内包している都市の存在のみが、この詩歌の空間にとっては錨なのである。ここにおいては、どのような「俺」も特別ではなく、抽象的な流れにすべてを委ねざるを得ない存在である。そして、その一点のみ前提として受け入れてしまえば、「俺」にはもう何も恐怖することはない。誰も特別にはなれないのだから、誰も——「俺」も特別でなくともよいのである。
特別でなくともよいということ。それは私たちにできる最大限の自身の肯定ではないだろうか。私が山﨑作品に感じる心地よさは、そうした反転した自己の肯定にあるのかもしれない。
*
イベントが終わって、よくわからないままにいろんな人に挨拶してから、私は山﨑さんとカフェから出た。山﨑さんはまだ少し不服そうだった。東京って感じがしますね、と私がいうと、「今日は良くなかったね」と山﨑さんは再び言った。思いっきり凹んで拗ねているのがとても面白かった。その一帯にありがちな、深夜まで煌々としている小さな書店やレコード店を見て回りながら駅へと向かう。東京って感じがするなあと思った。
誰もがきっと、何らかの形で特別でありたいと願うだろう。その願いは、叶ったり叶わなかったりするのだろう。でも、願うことを揶揄してはいけないのだ。そして、たとえ特別でなかったとしても、それこそが特別であることだって、きっとあるのだ。てのひらに錨がなくとも、私たちは風の流れと土の確かさに、夜の都市を歩くことができる。
【註】
[1]山﨑修平『ダンスする食う寝る』(思潮社、2020年)
[2]実際にある店舗で、紀伊國屋書店新宿本店の2階の窓の近くには詩歌句のコーナーがある。足を運ぶと、だいたい詩歌句の知り合いに会える。
[3]山﨑修平『ロックンロールは死んだらしいよ』(思潮社、2016年)
[4]前掲書[1]











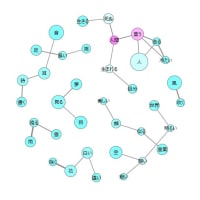


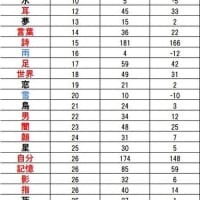
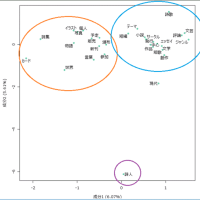
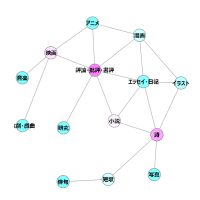
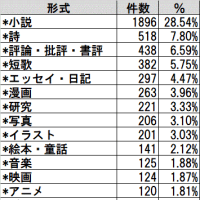
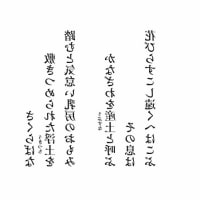
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます