なにも覚えてはいないのに、今この胸に過る切ない痛みは何だろう。どこからかそんな声が聞こえてきてはいつのまにか萎んでいる。またあるときは川のせせらぎに連れ出されて、……川面に浮き上がる鮎の背中が見えてくる。なにかに怯えながらそのなにかを想い出さないよう、キミの頭のなかの誰かが交通整理でもしてくれている、のだろうか……。そうキミはぼんやりすることが好きなくせにどこかぼんやりすることに躊躇いもあって、わけもなくなにかに辿りつきたくなくて(ほんとうのほんとうはたどりついてほっとしたいことだ)//ふっと過られる盛りの光沢が、じつは鮎の背中であったり、そのとたん暗くなってしまう川水の奥行きの、ほんとうに暗い記憶の、襞で、奥に凝り固まってしまった闇の誘惑へ沈んで連れられていく。そんなキミの脈診の震えがボクに伝わってくるようだ。
ときには魚が跳ねて水の土煙が暗い水の底を隠してくれる。そのかわりキミの瞳は少しずつ濁っていくのだ。もう怖がることなんてない恥ずかしい年になって、つい鮎の背中を追って掴もうとする。じっさいはツルンと逃げられたくせに、詩の中では「片っ端から掴んで」「しなやかに暴れる細い腹が/どこか喜んでいる」などと前向きに夢見てもいる。発話する主体とオブジェとしてのコトバとの同化が一瞬かいま見れるように。
冒頭詩「供火拾い」はたんたんと言葉を掃き出しているのにどこか憂いを帯びている。ここで発話者の経験の有無を詮索し解釈する意図はボクにはない。というより詮索するにはかなりの勇気がいるだろうし、なにより高嶋のコトバに反応するボクの脳髄が勝手にしゃべりだしてしまうから、それに誰かを傷つけてしまいそうで……、と言わせそうな繊細なコンテクストとともに柔軟な詩的構成を基軸にコトバという城壁で詩は囲われている。その城壁に潜り込むためには少しの無謀さと無知と、一番大事なことは自分の心を溶解させながらその言葉の壁に話しかけなくてはならないことだと、ボクには思えてくる。
言葉は心の結晶として掃き出されるが、その掃き出す詩人にとって、詩作そのものが現実と絡み合った深い意識の底からふつふつと湧き上がってくる記憶・想いで・現実意識との葛藤に苦しみながら格闘する理性と感情との漆黒を諫めているのだ。詩中での発話者の一人でもある詩人主体をも癒すために、排出され眺められるオブジェとしての結晶であるコトバは、産み落とされたのだから。……言葉は詩人の排泄物でもあるのだ。卵だと言い表した方がきれいで夢を見させてくれるだろうか。そういう言い方もあるかもしれないが、葛藤の末掃き出された結晶物は汚い話ではなくまた汚物でもなく実際もだえ苦しんで精神を食って養分化した後出る、どこか臭い痕跡でもあるのだ。ほんとうにそうなのだ。不安に陥った時のリアルなじぶんの心中で呟かれる内言を振り返ってみればよい。ただこんな言い方にはなかなか賛同は得られないのかもしれない。
けれど栄養を摂取した身体が排泄物を掃き出すように心の割り切れなさや葛藤によってすり減らされ危うく言葉というある固定的な書記に、そのどっちにもつけない心の蟠りを、封じ込めてしまうことによってしか心の安定は訪れないのだ。というパラドクスとともにボクたちは生を享受させていただいている。だから書記であろうと発声であろうと繰り返しその結晶物である言葉に立ち戻っていかないことには心の安定を保てない、人間はそういう言語的存在であり言語依存者なのだ。だからこそ詩の言葉は錯綜するのだ、と言えばまたキミは振り向いてくれるだろうか……。
高嶋の詩の構成は原理的にそのように成り立っているのではないか。冒頭詩「供火拾い」にこだわりすぎて申し訳ないところだが。
あれを追いかけていれば
追いかけ続ければいつか
おとうとが見つかるのだと
信じるように両の足は
少しずつ汚れていった
しし、
しし、
しし、
……
強い臭いだ
これが詩人高嶋樹壱の、どこか苦しげに排出されたコトバの身振りでもあり、一方では詩人主体が嗜好的に筆を執る絵画的詩作法でもある。脳裏に浮かぶ記憶印象を、色彩的というよりコトバの踏み出しに強弱を込めることで濃淡をつけ、また筆を走らせるスピードと跳ねの飛躍。あるいはコノテーションの多性と筆の圧力を奥行きとして。くぼみの深さを暗示させるために。下段に組まれた「しし、/しし、/しし、/……」は虫の音かもしれないが、それがコトバを鼓舞する小さなものたちの生の振動のようにも聞こえ、御呪いのような効果を得るのだ。
「おとうと」とひらがな書きされたオブジェには厚み感が付加されている。もちろん素直に弟として解釈もできるのだけれど、ひらがな書きによって、たとえば「おと・うと」などのように分節可能性が開かれているのだ。非意味化を被った「おと・うと」はたとえば「お」と「う」とが見つかるのだとという統辞可能性とまたは「しし、……」(椿象?)とイメージと音連関を持ちはじめ、響きあったりもする、謎の時空を開き始めるのだ。さらにその複数的連結可能性を「強い臭いだ」という述部を置くことで聯全体を入れ子状に結び、なにやら辛気臭いメランコリーを予兆させもするのだ。
他者や他物を生きる不可能性を前提としながらなお近寄りその境を超えんがため爪をたてる。物質的な回路が欠落しているため、己の物質内であたかも不在の肉体をなぞるように黙劇するのだ。その文脈で詩句の跨ぎを感じられる文字の生きた証として受容すれば、次なる詩篇「旅の子ノオト」も「ノオト」をメタファーとしてではなく固有名詞として受け入れられるようになるだろう。きっとノオトは、幼少時からの無二の親友であり子でありかけがえのないヒトであるのだ。
さらに続く「てっちゃん」ではノオトが複数化し様々な名称に変じ詩人の記憶と感情の襞を揺らし始める。「おばさんの鋏」「五百円玉」「黒いクレヨン」「紙人形」などは一見詩劇を構成する駒のひとつにも読める詩語であるが、詩人にとっては長年親しい存在者たちなのだ。もう少し他の書き手たちとの共有可能性を示唆するために抽象的に言い換えてみようか。
コトバが分岐するとは、言ってみれば詩人身体から煮え切らず、行く先を見失ったリビドーに押し出され身体から剝離された語へと変幻していく、それぞれの身体的欠片が、生と死の狭間でリビドーの宙吊りされた行き場のない彷徨いとして排出され外部に分散される、ということだ。つまり、身体の記憶は、視覚的・聴覚的・触覚的・臭覚的身体の対称的存在者であり、互いに記憶しあう間柄であるということでもある。このようにその詩人身体から受け継がれ語によって受け取られた情念のような痕跡がコトバとしての自存性を得、自律的に詩のコンテクストの中で振舞えるようになるのだ。
ボクが考える発話者の複数性とはこのことを指している。だから一般的に詩人の思念や感情はいくらコトバとして外部化されたとしても、それだけではコトバの他者化は成し遂げられず、さらに詩作行為によって真に表現が他者に開かれているのはほんの一時にすぎない。これまでのコトバの他者化は読み手の存在が担保されているという前提があったとボクには思える。他者に読まれるべき言葉として。だが昔と違って難しく感じられる詩の読者は日を追うごとに減っているのか増えているのかわからないが、いずれにせよ詩のコトバたちは孤立化せざるを得ず、よくもわるくも先の他者化される機会をさえ失っていくのだ。だから高嶋の詩が自己自身から他者化されていく過程を詩作において実践するのは可読性としての開かれと詩人主体が言葉を経験していくプロセスを文脈化し、たとえ読み手がいなくとも、言葉に変幻した情念や思念の痕跡が自己へ還ってくるという言葉の他者的存在性を詩人主体のために担保するためだと、ボクには思えてならないのだ。よって高嶋の詩の可読性は、そのような言葉への執念ともいえる全身全霊を賭した労力が産んだ柔らかな感覚質を読み手に与えるのだ。そして続く詩篇「国境」からは飛翔の翼を用意する他者存在と共に、境界線を乗り越え区別を消散させる旅へと歩みはじめる自由への祈念が胚胎されていくのだ。「「帰れる国がどこにもないって本当か」」という気づきとともに、身体に指標されたルートを無化し、たとえ蟠りがまだ頭の隅に残っていたとしても、心たちだけが通じ合う融解された詩的空間へと赴いていく。
「paper gravity」という詩篇について高嶋は『一千暦のよもやま話(ブログ-blog.livedoor.jp)http://blog.livedoor.jp/keynote1/』の中で、タイトル負けして四苦八苦した詩作事情を吐露しているのだが、翼を胚胎しながらもなかなかすんなりと飛び立つための「滑走路」に位置どれない胸のつかえがあるのかそれとも単なる躊躇いなのかはわからない。なにか割り切れないそのなにかを言外に抱え込んでいるのだろうか。
地平から去った淡い余白の、向こう側だけがどこまでも見えた
想像で駆ける素足ができた
にもかかわらず、
夢中になって刷り上げていく読み手のいないひとつの頁だ
なぜ自信が持てないのか、と声をかけたくなるほど、
くずくずになった新聞紙たちが転がっていく、くずくずの日付
現実の日々をなのかそれとも文字を排出した己の分身である詩句たちをいまだに「引き剝がされて間もない影」としてしか見れない発話主体の謙遜なのか、はたまた経験の消化不足なのか。ただ気持ちだけが高く、/高くありたいのだろうか。むしろアドレセンスの混沌としつつ無暗に不安な心境をとうに忘れてしまった自身にボクが気づかされたのか。
「色狩師見聞・拾遺」は読む経験に戻り心もちを宥めるように、この他者的テクストの襞に紛れながら、翼の意欲を言葉へと取り戻すために小譚が紡がれていく。それも自身が息を殺し飛び立つ間際をうかがうように「気が立っていたような思いであった。」かのように。そして他者化した「少年」と重なり「秋が終わるんだね、うるさい落ち葉も、もう聞こえないもの」は二重奏のように自身へ反響し「今日も白い帳面を開いてはまた熱心に綴りだすのだった。」。だが、詩はなかなか訪れないのだ。しかも「大蝦蟇」に「さっさと狩り終えぬから温うて冬眠もできぬと、」咎められる始末で、ただ言葉が紡いだ風景に和みながら「北風が、鋭くないた。」と仮構の扉を閉じるのだ。引きこもった手の使いに誰かが心寄せてくる。「―あなた、これからどうするつもり?/泊るところがちゃんとあるの?」他人事のように呟く僕は「絵の中の僕が向ける視線は/どの背後よりもずっと遠い」と嘯いては「その眼を埋めた」のだ。どの背後とは明らかに他者の闇であり、その昏さを凌ぐ僕の似顔絵はその誰とも似ていないと言うのだろうか。そんな問いを誰かに発してもらいたくて自信なさげな素振を見せる「foreign evening」を通過し、落下していく先で受け取られた「新しい友達」の記憶と恩師との思い出に支えられようやく飛翔の契機を得ていくのではないか。
きちんと向き合えていれば言葉はもっと整然と語られたのではないか。自己愛が織りなす詩的文彩の向こうに、キミが語りかける人はほんとうにそこにいるのだろうか、「先生」であろうと「タオ」であろうと、読み手には死者にしか見えてこない。心の中の生者であり死者でもある、自己変容と共に置き去りにした他者的存在は自己と離反している、がために詩句は文彩の襞を濃くなぞっていくようだ。この詩的レトリックが放った詩的仮構線が紡ぐコトバの網にかかってくる獲物は、いったい何だろう、という問いがふと浮かんでくる。胸苦しさを読み手に与えながら読み手の意識はどこに居場所を求めればよいのだろうか。そんな息苦しさの蟠りに悶えながらボクは「飛行士たち」へ向かって行った。
そして「飛行士たち」ではいよいよ離陸の準備に向けた詩的段取りが組まれていく。「空はほんのりと明るんでいた」。顔を仰向け憑かれたように飛翔の欲望が静かに燻ぶりから日常の一進一退を振りほどいていく仕草のようにか。「超えてはならない高さをも超え/粉々に滑り落ちていく夢」と、「何度も、翼の幻を見る。」のだ。
鏡像を覗き込むように他者たちのイメージは想像的な自己自身のようにも見えていた。
つまり発話者によってイメージの主体を変転させ、真の自分に触らんがための仮構線で編んだ言葉の網を、現実という大海原に放ち現実の欠片だけでも把持したい詩の衝動に駆られるから。だが無情にもリアルは網目から零れ落ちてしまう。自己からであれ他者からであれ主体全般の思惑は常に裏切られる。それは事後的な過去であればあるほどその鮮度が降下し変様を遂げているからだ。それ故自己でもある他者との享楽を志向し粘り強くその大海原(大空)に向き合う高嶋の健気なその態度に感動させられるのだ。果たして諦めず超越的に上昇していくのか、それともリアルと出会い損ねた仮想的な忘我郷へか
翼はそこで消えることなく
上昇を続けていった











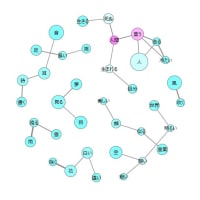


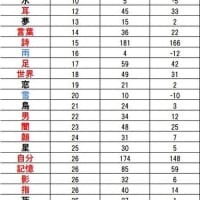
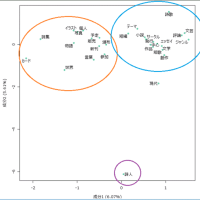
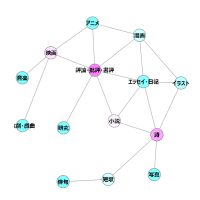
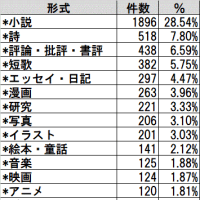
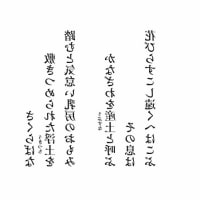
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます