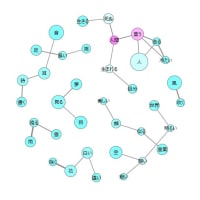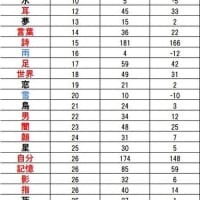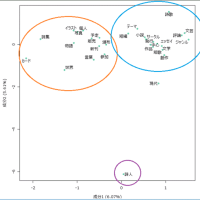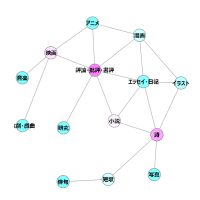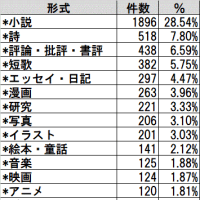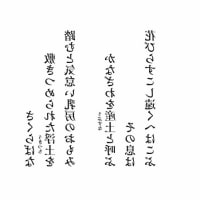全体に紗をかけたようなやわらかくあたたかい闇の中で静かに燃え続ける蠟燭の焔。蠟燭に重なるように刻まれた白い「木村孝夫詩集」の文字と、焔の先に抑えた赤で浮遊するように固定された赤い文字の表題を見つめる。木村孝夫が、自らの躰を蠟のように溶かしながら燃やしているなにか。カバーをめくると死者の隊列のように焔影が並んでいる。
目次は大きめの文字、手書きのような書体。全体は一部と二部に分かれている。本文の印字は濃い目、大きめ。文字の存在感が際立つ配置だ。
鼻から入ってくる臭いに
吐きそうになりながら
その臭いに向かって
海岸線を広範囲に捜索した
視覚で捉えたものは
視覚からこぼれ落ちていったから
烏の嗅覚と、そこにある臭いは
捜索には欠かせなかった
東北大震災の被災地にボランティアに入った童話屋の田中さんが、帰京後に重い口を開いたとき、その第一声が「臭いがね……」だったことを思い出す。「そこに住んでいる人たちに、毎日あの臭いが押し寄せるんですよ、それがね、なんとも……」テレビやラジオの報道では伝わらない、現地に身を置いた者だけが知る、生理的に刻印される記憶。ボランティアは一時的に関わっても、いずれ立ち去る旅人だ。そこに生まれ、育った人たち、住んでいた人たちに押し寄せ続ける臭いを、木村は〈呼んでいる声のような臭いだ〉と記す。
ときどき、子どもの死体と
遭遇するときがあった
捜索隊員の子どもと同じ年齢だ
親もとへやっと帰すことができるが
喜びはない
その臭いに
泣いては何度も吐いた
かつて命のあったもの、かつて形のあったものが汚泥や瓦礫と混ざりあって日が経つにつれて腐臭を強めていく、その臭いが……かえりたい、あいたい、みつけて、たすけて、そう呼びかける声となって木村に重く届いていたのだと思う。思う、としか書けない。真実を知る者ゆえの飾りのない言葉、感情を力づくで押し戻して、溢れるのをこらえるような抑制された木村の筆致に、体験していない者は「思う」としか応えることができない。
木村が聴いた、生理的に全身を刺すような〈声〉は、なぜ、どうして、とは問わなかったろうか。生き残った者、生き延びた者は命を絶たれた者たちの声を聴き、自らの身を持って語り伝える媒介者となる、ならざるを得ないのかもしれない。「海を背負う」で木村が背負っているのは、海に連れ去られた者達の寄せてくる思いだ。
背中から
すうっと入ってくるものがある
今は、無色の時間だ
言葉を探しているが見つからない
防潮堤の一番下で
骨になる臭いがしている
自らを無にして透明にして、寄せてくるものを負い、とらえ、それを言葉に変換していこうとする、ふさわしい言葉を探索しようとする。見つからない、その過程を身近で普段から使い慣れた確かな言葉で記していく。おそらく心の中では、この言葉ではない、もっと違う何かだ、とせめぎ合うものがあるのだろう。「海を背負う」の詩篇の中の言葉を借りれば、〈その海の背後で浮遊しているもの〉〈手からこぼれ落ちてくる〉もの、それが(生の存在〉であることを言い当てる言葉を探し続けながら、使い慣れない技巧的な言葉を“詩的に”当てはめることをせずに、体が実際に用いて“伝わる”ことを確かに知っている言葉で何とか言い表そうとする。その不能性を誠実に更新し続けているのが、木村孝夫の詩なのだ、と言えるかもしれない。
第二部には震災から八年が経ち、その間に見聞きし体験しなければならなかった人の心の切なさ、哀しさ、人災としか言いようのない原発事故へのやり場のない怒り、忘れてはならない、語り伝えなければ、という静かな使命感に裏打ちされた諸々の想いが記されている。
あなたはこの大地の上で
子どもを
裸足で歩かせることができますか?
まだ、帰還困難区域の大地と
和解は済んでいないのです
放射能を測定する高さは
心のある場所から少し離れていますが
大地に直接問いかけて
測定したものではありません
さりげない言葉が選択されているが、大地を踏んで生きるという人としての自然な営みを奪われた怒り、子どもたちに信頼できる未来を手渡せない悲しみ、人の〈心〉の在り処とはまるでかけ離れたところで進められる、便宜的な“和解”や“保障”への憤りが秘められた言葉。ここには、確たる“思想”がある。人が人として生きるための、その芯に必要なもの。
この記憶を消して欲しいと
その人はいう
一人の夜は寂しく不安でたまらない
頷きながら
ただ、黙って聴く
死者の声を“聴く”木村は、生者の真の声を聴く者でもあるようだ。原発避難者が遭遇した苦難の日々、人が暮らしていくときに生じる綺麗ごとでは済まない〈あつれき〉……誰もが心に余裕を有しているわけではない。避難者を苦しめてしまった住人の心から寛容や許容、思いやりの住まう場所であった余裕を奪ったのもまた、震災、そして人災である原発事故ではないのか。
まだ怒りや悔しさがいっぱいあるが
少しずつその思いを
手放していければいい
記憶の芯を取り換えて欲しい
誰にもわからないように、そっと
できるなら記憶も消して欲しい
話すだけ話をして、一巡すると
またここに戻ってくる
二人の間には
アドバイスを置く余白は全くない
本人に非はないし
その切実さには隙がない
頷き
ただ聴くだけだ
真の意味で、誰かの声を聴くことができる人なのだと思う。木村は否定するかもしれないが。
義母への眼差しに、この詩人はこのように“人を見る”のか、と納得させられる、温かなフレーズがあった。
骨は拾えても
知恵を拾うことはできなかった
九十歳の義母の知恵だから
カマに入る前に少なくなっていた筈だ
困っている人を見ると
すぐに自分の知恵を差し上げる人だった
丁寧な言葉を添えて
その人の知恵のまわりに自分の知恵を
そっと置いて来たのだろう
それを誰にも言わない人だったから
いつの間にか
自分の中の知恵が少なくなってしまった
気が付いたのは
同じことを繰り返すようになってからだ
自分のことも
思い出せない日が多くなった
それでも、あの丁寧な言葉で
亡くなった義理の父のことを心配するのだ
「どうしたのでしょうね
そう言えばしばらくみませんわね」
いつか、人はこのように
幼子のような知恵になっていくのだろう
それもまた人間の味だと思うべきなのだ
骨を拾うとき
その幼子のような知恵は拾うことはできなかった
火葬場では、骨は拾えても
知恵を拾うことはできないのだ
「火葬場で」という詩の全行を引いた。「義母の台所」という別の詩によれば、義母の“童がえり”もまた、原発事故による一時避難、そのストレスも要因であるらしい。〈思うべきなのだ〉と自らに言い聞かせるように語る言葉に、悔しさもにじむ。拾えなかった、と繰り返すリフレインに、木村は自責の念も抱いているのかもしれない。しかしこのように記憶に残り、言葉で蘇った姿が、静かに詩の中に生きて居る。木村の義母が身に着け、惜しげなく周りの人々に分け与えた知恵もまた、目に見えぬ形で木村の詩行の間から静かにこぼれ続けている。確かな言葉の枠組みの中に、そうした目に見えぬものが滲み出し、こぼれだす隙間を残しているのが、木村孝夫の詩なのかもしれない。
目次は大きめの文字、手書きのような書体。全体は一部と二部に分かれている。本文の印字は濃い目、大きめ。文字の存在感が際立つ配置だ。
鼻から入ってくる臭いに
吐きそうになりながら
その臭いに向かって
海岸線を広範囲に捜索した
視覚で捉えたものは
視覚からこぼれ落ちていったから
烏の嗅覚と、そこにある臭いは
捜索には欠かせなかった
(「泣いて吐く」1連、4連)
東北大震災の被災地にボランティアに入った童話屋の田中さんが、帰京後に重い口を開いたとき、その第一声が「臭いがね……」だったことを思い出す。「そこに住んでいる人たちに、毎日あの臭いが押し寄せるんですよ、それがね、なんとも……」テレビやラジオの報道では伝わらない、現地に身を置いた者だけが知る、生理的に刻印される記憶。ボランティアは一時的に関わっても、いずれ立ち去る旅人だ。そこに生まれ、育った人たち、住んでいた人たちに押し寄せ続ける臭いを、木村は〈呼んでいる声のような臭いだ〉と記す。
ときどき、子どもの死体と
遭遇するときがあった
捜索隊員の子どもと同じ年齢だ
親もとへやっと帰すことができるが
喜びはない
その臭いに
泣いては何度も吐いた
(「泣いて吐く」8連~終連)
かつて命のあったもの、かつて形のあったものが汚泥や瓦礫と混ざりあって日が経つにつれて腐臭を強めていく、その臭いが……かえりたい、あいたい、みつけて、たすけて、そう呼びかける声となって木村に重く届いていたのだと思う。思う、としか書けない。真実を知る者ゆえの飾りのない言葉、感情を力づくで押し戻して、溢れるのをこらえるような抑制された木村の筆致に、体験していない者は「思う」としか応えることができない。
木村が聴いた、生理的に全身を刺すような〈声〉は、なぜ、どうして、とは問わなかったろうか。生き残った者、生き延びた者は命を絶たれた者たちの声を聴き、自らの身を持って語り伝える媒介者となる、ならざるを得ないのかもしれない。「海を背負う」で木村が背負っているのは、海に連れ去られた者達の寄せてくる思いだ。
背中から
すうっと入ってくるものがある
今は、無色の時間だ
言葉を探しているが見つからない
防潮堤の一番下で
骨になる臭いがしている
(「海を背負う」1連~3連)
自らを無にして透明にして、寄せてくるものを負い、とらえ、それを言葉に変換していこうとする、ふさわしい言葉を探索しようとする。見つからない、その過程を身近で普段から使い慣れた確かな言葉で記していく。おそらく心の中では、この言葉ではない、もっと違う何かだ、とせめぎ合うものがあるのだろう。「海を背負う」の詩篇の中の言葉を借りれば、〈その海の背後で浮遊しているもの〉〈手からこぼれ落ちてくる〉もの、それが(生の存在〉であることを言い当てる言葉を探し続けながら、使い慣れない技巧的な言葉を“詩的に”当てはめることをせずに、体が実際に用いて“伝わる”ことを確かに知っている言葉で何とか言い表そうとする。その不能性を誠実に更新し続けているのが、木村孝夫の詩なのだ、と言えるかもしれない。
第二部には震災から八年が経ち、その間に見聞きし体験しなければならなかった人の心の切なさ、哀しさ、人災としか言いようのない原発事故へのやり場のない怒り、忘れてはならない、語り伝えなければ、という静かな使命感に裏打ちされた諸々の想いが記されている。
あなたはこの大地の上で
子どもを
裸足で歩かせることができますか?
まだ、帰還困難区域の大地と
和解は済んでいないのです
放射能を測定する高さは
心のある場所から少し離れていますが
大地に直接問いかけて
測定したものではありません
(「裸足」1連、2連)
さりげない言葉が選択されているが、大地を踏んで生きるという人としての自然な営みを奪われた怒り、子どもたちに信頼できる未来を手渡せない悲しみ、人の〈心〉の在り処とはまるでかけ離れたところで進められる、便宜的な“和解”や“保障”への憤りが秘められた言葉。ここには、確たる“思想”がある。人が人として生きるための、その芯に必要なもの。
この記憶を消して欲しいと
その人はいう
一人の夜は寂しく不安でたまらない
頷きながら
ただ、黙って聴く
(「傾聴」1連、2連)
死者の声を“聴く”木村は、生者の真の声を聴く者でもあるようだ。原発避難者が遭遇した苦難の日々、人が暮らしていくときに生じる綺麗ごとでは済まない〈あつれき〉……誰もが心に余裕を有しているわけではない。避難者を苦しめてしまった住人の心から寛容や許容、思いやりの住まう場所であった余裕を奪ったのもまた、震災、そして人災である原発事故ではないのか。
まだ怒りや悔しさがいっぱいあるが
少しずつその思いを
手放していければいい
(「傾聴」6連)
記憶の芯を取り換えて欲しい
誰にもわからないように、そっと
できるなら記憶も消して欲しい
話すだけ話をして、一巡すると
またここに戻ってくる
二人の間には
アドバイスを置く余白は全くない
本人に非はないし
その切実さには隙がない
頷き
ただ聴くだけだ
(「傾聴」8連~終連)
真の意味で、誰かの声を聴くことができる人なのだと思う。木村は否定するかもしれないが。
義母への眼差しに、この詩人はこのように“人を見る”のか、と納得させられる、温かなフレーズがあった。
骨は拾えても
知恵を拾うことはできなかった
九十歳の義母の知恵だから
カマに入る前に少なくなっていた筈だ
困っている人を見ると
すぐに自分の知恵を差し上げる人だった
丁寧な言葉を添えて
その人の知恵のまわりに自分の知恵を
そっと置いて来たのだろう
それを誰にも言わない人だったから
いつの間にか
自分の中の知恵が少なくなってしまった
気が付いたのは
同じことを繰り返すようになってからだ
自分のことも
思い出せない日が多くなった
それでも、あの丁寧な言葉で
亡くなった義理の父のことを心配するのだ
「どうしたのでしょうね
そう言えばしばらくみませんわね」
いつか、人はこのように
幼子のような知恵になっていくのだろう
それもまた人間の味だと思うべきなのだ
骨を拾うとき
その幼子のような知恵は拾うことはできなかった
火葬場では、骨は拾えても
知恵を拾うことはできないのだ
(2016年2月死去 90歳)
「火葬場で」という詩の全行を引いた。「義母の台所」という別の詩によれば、義母の“童がえり”もまた、原発事故による一時避難、そのストレスも要因であるらしい。〈思うべきなのだ〉と自らに言い聞かせるように語る言葉に、悔しさもにじむ。拾えなかった、と繰り返すリフレインに、木村は自責の念も抱いているのかもしれない。しかしこのように記憶に残り、言葉で蘇った姿が、静かに詩の中に生きて居る。木村の義母が身に着け、惜しげなく周りの人々に分け与えた知恵もまた、目に見えぬ形で木村の詩行の間から静かにこぼれ続けている。確かな言葉の枠組みの中に、そうした目に見えぬものが滲み出し、こぼれだす隙間を残しているのが、木村孝夫の詩なのかもしれない。