「これは…」。
「そう、今朝の読売さ。今の話は全てこれに書かれてるよ」。
(だったら何だって最初にそう言わないんだ。それよりもさっき渡した銭を返せ)。
お紺は怒りに拳が震えた。そんな様子さえ面白そうにおすがは細い目を吊り上げてほくそ笑んでいる。
「ちょっと待って。これじゃあ、合惚れの二人に悋気したお信さんひとりが悪者じゃないか」。
人三化七のお信が、桜花を追いすがり、その桜花をかばいながら肩を抱いて逃げる男の挿絵が描かれ、まるでお信の狂言のように文が書かれていた。
「おすがさんの話とは真逆じゃないですか」。
「そうかい。あたしは字が読めないからねえ」。
挿絵を見て、大凡の見当をつけていたらしい。
「だからさ、あんたの読売にゃあ本当のことを書いて欲しいのさ」。
事実を書いたとしても今更である。これだけ美談に書かれていたら、如何に事実だろうと勝ち目はないだろう。
「どうしてあの女衒以下の男が、ここまで持ち上げられているか分かるかい」。
(分かる筈もない)。
「男の妹ってえのが、読売に大枚叩いて書かせたからさ。そうそう、あんた知っているかい。ちょいと前にお店もんと茶汲み娘が相対死したことをさ。その死んじまったお店もんってえのが、桜花の間夫の兄さんさ」。
お紺の脳裏に、ひとりの芸者の姿が過る。
「確か、柳橋の…」。
「おや、知っているじゃないか。中井の芸者で梅華ってんだけど、一度に兄さん二人が大変なことになっちまったんだ。生き残った方は助けたかったんじゃないかい」。
(そうと分かればこうしちゃいられない。梅華に会わなくては)。
「おすがさん。最後にひとつだけ教えてくださいな。胡蝶のお女郎さんは皆、証文を返されて自由の身になったって聞いてますけど、どうして…」。
「どうしてまた女郎をやってるかってえんだろう。あたしもさ、真底好いた男がいたのさ。所帯を持つ約束をしてね。だけど、所帯を持つ為に店を出したいって言うんだ。その為に銭が必要だろう。だから一年だけ、一年だけ辛抱して欲しいって言ってね」。
お紺は目を白黒させていた。
ランキングに参加しています。ご協力お願いします。
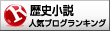
 にほんブログ村
にほんブログ村
「そう、今朝の読売さ。今の話は全てこれに書かれてるよ」。
(だったら何だって最初にそう言わないんだ。それよりもさっき渡した銭を返せ)。
お紺は怒りに拳が震えた。そんな様子さえ面白そうにおすがは細い目を吊り上げてほくそ笑んでいる。
「ちょっと待って。これじゃあ、合惚れの二人に悋気したお信さんひとりが悪者じゃないか」。
人三化七のお信が、桜花を追いすがり、その桜花をかばいながら肩を抱いて逃げる男の挿絵が描かれ、まるでお信の狂言のように文が書かれていた。
「おすがさんの話とは真逆じゃないですか」。
「そうかい。あたしは字が読めないからねえ」。
挿絵を見て、大凡の見当をつけていたらしい。
「だからさ、あんたの読売にゃあ本当のことを書いて欲しいのさ」。
事実を書いたとしても今更である。これだけ美談に書かれていたら、如何に事実だろうと勝ち目はないだろう。
「どうしてあの女衒以下の男が、ここまで持ち上げられているか分かるかい」。
(分かる筈もない)。
「男の妹ってえのが、読売に大枚叩いて書かせたからさ。そうそう、あんた知っているかい。ちょいと前にお店もんと茶汲み娘が相対死したことをさ。その死んじまったお店もんってえのが、桜花の間夫の兄さんさ」。
お紺の脳裏に、ひとりの芸者の姿が過る。
「確か、柳橋の…」。
「おや、知っているじゃないか。中井の芸者で梅華ってんだけど、一度に兄さん二人が大変なことになっちまったんだ。生き残った方は助けたかったんじゃないかい」。
(そうと分かればこうしちゃいられない。梅華に会わなくては)。
「おすがさん。最後にひとつだけ教えてくださいな。胡蝶のお女郎さんは皆、証文を返されて自由の身になったって聞いてますけど、どうして…」。
「どうしてまた女郎をやってるかってえんだろう。あたしもさ、真底好いた男がいたのさ。所帯を持つ約束をしてね。だけど、所帯を持つ為に店を出したいって言うんだ。その為に銭が必要だろう。だから一年だけ、一年だけ辛抱して欲しいって言ってね」。
お紺は目を白黒させていた。
ランキングに参加しています。ご協力お願いします。









