川崎尚之助と柴太一郎は、この手形を取り戻すため、訴訟を起こし、裁判の行われる東京に居住を移すのだが、逆に大豆取引が成立しなかった事を詐欺として訴えられという二重の訴訟となってしまうのだった。
逃走中であった米座省三が東京で逮捕され、手形は尚之助の手に戻るも、既に米は古米となり、相場も下落。取引相手に大損害を与える結果となり、ここでも訴訟が発生する。
詐欺罪として立件された米座は拘禁。尚之助と柴は保護観察状態に置かれるが、身元引受人の元での暮らしは困窮を極め、満足に食べる事も適わなかった程だったという。
後に尚之助は、己の独断だったと供述し、明治7(1874)年に函館へ連行される途中に重病に陥り、東京へと戻され、慢性肺炎の為、明治8(1875)年3月20日、東京医学校病院にて永眠する(享年39歳)。 裁判の判決は下されていなかったが、相続人無しということで、裁判は未決のまま終了となった。
米座は禁固2年。柴は禁固100日の禁固刑に服した後、会津に戻り、大沼・南会津郡長を務め、大正12(1923)年4月28日、85歳の天寿を全うする。
何とも…。大木仲益(坪井為春)塾の秀才であり、屈指の洋学者として知られた尚之助の後半生は、余りにも惨いものである。
縁もゆかりもなかった会津の為に尽力し、負け戦を戦い抜いた挙げ句に、苦難を承知で斗南まで従い。その暮らしを立て成すべく、しかも己事ではなく藩の為に奔走した人間が、誰からも見捨てられ、死んで逝ったのだ。
歴史に「もしも」はないが、山本覚馬に出会わなければ、会津の地を踏まなければ、維新後も学者として業績を残したであろう逸材である。
また、朝敵となり郷里・出石藩には戻る事が適わなかったのだろうが、どこぞに逃げる事も可能だった筈だ。彼が斗南を選んだ理由は不明であるが、八重との結婚生活で子を生してもおらず、四方や今で言う仮面夫婦であったのではないかとの一抹の疑念も払拭出来ない。
山本覚馬も八重(新島襄とは再婚前)も、既に地位を確率しており、尚之助の生活の援助を誰憚る事なく出来た筈である。〈続く〉
ランキングに参加しています。ご協力お願いします。
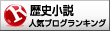
 にほんブログ村
にほんブログ村

逃走中であった米座省三が東京で逮捕され、手形は尚之助の手に戻るも、既に米は古米となり、相場も下落。取引相手に大損害を与える結果となり、ここでも訴訟が発生する。
詐欺罪として立件された米座は拘禁。尚之助と柴は保護観察状態に置かれるが、身元引受人の元での暮らしは困窮を極め、満足に食べる事も適わなかった程だったという。
後に尚之助は、己の独断だったと供述し、明治7(1874)年に函館へ連行される途中に重病に陥り、東京へと戻され、慢性肺炎の為、明治8(1875)年3月20日、東京医学校病院にて永眠する(享年39歳)。 裁判の判決は下されていなかったが、相続人無しということで、裁判は未決のまま終了となった。
米座は禁固2年。柴は禁固100日の禁固刑に服した後、会津に戻り、大沼・南会津郡長を務め、大正12(1923)年4月28日、85歳の天寿を全うする。
何とも…。大木仲益(坪井為春)塾の秀才であり、屈指の洋学者として知られた尚之助の後半生は、余りにも惨いものである。
縁もゆかりもなかった会津の為に尽力し、負け戦を戦い抜いた挙げ句に、苦難を承知で斗南まで従い。その暮らしを立て成すべく、しかも己事ではなく藩の為に奔走した人間が、誰からも見捨てられ、死んで逝ったのだ。
歴史に「もしも」はないが、山本覚馬に出会わなければ、会津の地を踏まなければ、維新後も学者として業績を残したであろう逸材である。
また、朝敵となり郷里・出石藩には戻る事が適わなかったのだろうが、どこぞに逃げる事も可能だった筈だ。彼が斗南を選んだ理由は不明であるが、八重との結婚生活で子を生してもおらず、四方や今で言う仮面夫婦であったのではないかとの一抹の疑念も払拭出来ない。
山本覚馬も八重(新島襄とは再婚前)も、既に地位を確率しており、尚之助の生活の援助を誰憚る事なく出来た筈である。〈続く〉
ランキングに参加しています。ご協力お願いします。










