土佐藩は、兼山の死後3カ月の寛文4(1664)年3月2日、武力を行使して野中家を取り潰す。
その罪状は、謀反の企てがあったと流言して人心を動揺させたとあるが、野中家の改易の理由として、3代藩主・忠豊の書状には下記のように記されている。
一、私欲依怙(えこ)による政治。
一、忠義・忠豊の離間を策したこと。
一、御蔵銀の恣(ほしいまま)な消費。
一、改替に反対して流言を放った事。
一、金銀を貪(むさぼ)り他国迄商売をやらせたこと。
一、諸法度を厳しく実施しながら自分はこれを守らなかった。
ほかに、郷士に勝手に知行を与えたこと、江戸上り下りの船などで分を越した奢りがあったと付け加えている。
兼山の長男・彝継(清七・一明)は、山内(安東 )左衛門佐の邸にて、姻戚関係にある、深尾帯刀、山内彦作 、山内左衛門佐の3名から野中家改易後の処置を申し渡されたのである。
正に死人に口なし。兼山存命中ではなく、死してからという辺りが片腹痛いである。こうなると冤罪としか考えようもない。
そして、兼山の妾 4名、兼山の子8名、譜代の家来を加えた22名は、船二艘に分乗して宿毛に遷される。正室に関しての記述が見付からないのだが、出家し法名栄順院と名乗り元禄12(1690)年まえ生きているので、もしかしたら彼女は実家のとりなしかなにかで罪を逃れたのかも知れない。
幽閉された兼山の子の名とその当時の年齢は下記の通り(長女、三男、四男は夭逝したと思われる)。
二女 米 高木四郎左衛門室 18歳
長男 彝継(清七・一明) 16歳
二男 明継(欽六) 15歳
五男 繼業(希四郎) 8歳
三女 寛 7歳
四女 婉 4歳
五女 将 3歳
六男 行繼(貞四郎) 2歳
米は高木四郎左衛門に嫁し、一女を設けていたものの、離婚させられ宿毛に送られている。
例え兼山に関しては、冤罪だったとしても、当時の武家社会ではこのような苦杯を舐めた人も少なくはない。例えば、江島生島事件において、当人の江島は罪一等を減じて高遠藩内藤清枚にお預けだったにも関わらず、江島の兄・白井平右衛門(旗本)は、切腹ではなく斬首、弟・豊島常慶は重追放といった重い措置であった。当人の罪一等を減じておきながら、縁者というだけで命を奪われたのではたまったものではない。こういった理不尽に命を失った者も少なくはない。
ただ、野中家に関しては、嫡男が清七一明を名乗っていたくらいなので、元服前である。改易して放逐もしくは、僧籍に入れれば済む事ではないか。しかも嫁した娘までといった仕打ちは、もはや常軌を逸しているとしか思えない。
思うに16歳であった長男・彝継(清七・一明)、15歳の二男・明継(欽六)が、時の土佐藩重臣たちをも脅かすくらいに、かなり優秀だったのだろう。こういった恐怖に苛まれた時こそ人は、保身の為に非情にもなれるのだ。
この仕打ちを仕掛けた孕石元政、生駒木工等、深尾出羽の人間性を疑うと共に、幾ら隠居したとはいえ藩主の父である土佐藩2代藩主・山内忠義は、手をこまねいていただけであったのか。忠義は、寛文4年11月24日に死去しているので、兼山の遺族に対しての沙汰が下りた際には存命である。
彼らにも親もあれば子もあった筈。良心の呵責に苛まれることはなかったのだろうか。
そして連座させられた譜代の家臣たちも、降って沸いたような災難を、如何に受け止めたのかと思うと、これまた気の毒、いや理不尽でならない。〈続く〉
ランキングに参加しています。ご協力お願いします。
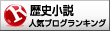
 にほんブログ村
にほんブログ村

その罪状は、謀反の企てがあったと流言して人心を動揺させたとあるが、野中家の改易の理由として、3代藩主・忠豊の書状には下記のように記されている。
一、私欲依怙(えこ)による政治。
一、忠義・忠豊の離間を策したこと。
一、御蔵銀の恣(ほしいまま)な消費。
一、改替に反対して流言を放った事。
一、金銀を貪(むさぼ)り他国迄商売をやらせたこと。
一、諸法度を厳しく実施しながら自分はこれを守らなかった。
ほかに、郷士に勝手に知行を与えたこと、江戸上り下りの船などで分を越した奢りがあったと付け加えている。
兼山の長男・彝継(清七・一明)は、山内(安東 )左衛門佐の邸にて、姻戚関係にある、深尾帯刀、山内彦作 、山内左衛門佐の3名から野中家改易後の処置を申し渡されたのである。
正に死人に口なし。兼山存命中ではなく、死してからという辺りが片腹痛いである。こうなると冤罪としか考えようもない。
そして、兼山の妾 4名、兼山の子8名、譜代の家来を加えた22名は、船二艘に分乗して宿毛に遷される。正室に関しての記述が見付からないのだが、出家し法名栄順院と名乗り元禄12(1690)年まえ生きているので、もしかしたら彼女は実家のとりなしかなにかで罪を逃れたのかも知れない。
幽閉された兼山の子の名とその当時の年齢は下記の通り(長女、三男、四男は夭逝したと思われる)。
二女 米 高木四郎左衛門室 18歳
長男 彝継(清七・一明) 16歳
二男 明継(欽六) 15歳
五男 繼業(希四郎) 8歳
三女 寛 7歳
四女 婉 4歳
五女 将 3歳
六男 行繼(貞四郎) 2歳
米は高木四郎左衛門に嫁し、一女を設けていたものの、離婚させられ宿毛に送られている。
例え兼山に関しては、冤罪だったとしても、当時の武家社会ではこのような苦杯を舐めた人も少なくはない。例えば、江島生島事件において、当人の江島は罪一等を減じて高遠藩内藤清枚にお預けだったにも関わらず、江島の兄・白井平右衛門(旗本)は、切腹ではなく斬首、弟・豊島常慶は重追放といった重い措置であった。当人の罪一等を減じておきながら、縁者というだけで命を奪われたのではたまったものではない。こういった理不尽に命を失った者も少なくはない。
ただ、野中家に関しては、嫡男が清七一明を名乗っていたくらいなので、元服前である。改易して放逐もしくは、僧籍に入れれば済む事ではないか。しかも嫁した娘までといった仕打ちは、もはや常軌を逸しているとしか思えない。
思うに16歳であった長男・彝継(清七・一明)、15歳の二男・明継(欽六)が、時の土佐藩重臣たちをも脅かすくらいに、かなり優秀だったのだろう。こういった恐怖に苛まれた時こそ人は、保身の為に非情にもなれるのだ。
この仕打ちを仕掛けた孕石元政、生駒木工等、深尾出羽の人間性を疑うと共に、幾ら隠居したとはいえ藩主の父である土佐藩2代藩主・山内忠義は、手をこまねいていただけであったのか。忠義は、寛文4年11月24日に死去しているので、兼山の遺族に対しての沙汰が下りた際には存命である。
彼らにも親もあれば子もあった筈。良心の呵責に苛まれることはなかったのだろうか。
そして連座させられた譜代の家臣たちも、降って沸いたような災難を、如何に受け止めたのかと思うと、これまた気の毒、いや理不尽でならない。〈続く〉
ランキングに参加しています。ご協力お願いします。











