この高尾が、奥州の去る大名家に身請けされるが、それを良しとせず、その大名の手に掛かり若い命を散らしたと、風の噂を左兵衛が耳にしたのは程なくしてのことであった。
「若様、知ってなすかい」。
「心太、朝っぱらから何事だ。若様は朝餉を召し上がっておる」。
近習の新八郎、弥七郎が、やれやれと顔を覗かせると、呉服橋御門内吉良家からそう遠くはない、安針町に小さな店を構える豆腐屋の心太が、いつものように右手にくしゃくしゃに読み尽くされた読売を掲げて息を弾ませている。
「また読売か。お前の読売は実に迷惑千万。若様にお見せする訳にはいかぬ」。
新八郎にこう言われても、
「それが、吉原一の三浦屋の高尾太夫が吊るし切りにされたってんでさ」。
その声に左兵衛は、「聞き捨てならず」とばかりに箸を投げ出した。
「心太、見せてみよ」。
言うが早いか、ひったくるように読売に目を走らせる左兵衛の姿に心太は頭を捻る。
「若様が吉原に興味があったとは知らなかった」。
「これ、心太。馬鹿を申すな」。
弥七郎も一応は心太を叱るが、内心は気になって仕方がない。
「何でもよ、去るお大名の身請け話を断ったところ、船遊びの最中に真っ二つに斬られて、墨田の川に打ち捨てられたってんだ」。
読売を読み終えた左兵衛は、あの堂々とした誇り高い高尾の笑みを思い浮かべていた。
「気の毒に」。
「あれっ、若様、高尾太夫を知ってなさるんですかい」。
「これ心太、若様がそのような者を見知っておられる訳がないであろう」。
新八郎がそう取り繕うが、当の左兵衛。
「これには身請けを断ったと書いてあるが、吉原の女郎は身請けを否めるものなのか」。
「おっと若様、乗ってきなすった。そりゃあ断ることなんぞできやしません。だけど、そこが高尾太夫の気っ風のいいとことで、何でも言い交わした男がいたらしいです」。
「好いた男がおれば、その者と添うことができるものなのか」。
「そりゃあ無理でしょうね。だけど、身体は売っても心は売らねえってのが高尾太夫だもんでさ」。
心太が続ける話は、屋形船から胴をまっ二つに斬り落とされた高尾の遺骸は、そのまま川に打ち捨てられたということであった。
件の大名は老臣の勧めで、ことが明るみに出る前に隠居願いを幕府に提出し受諾されたいた。
「お大名のお殿様とあっちゃ相手が悪いや。三浦屋さんも泣く泣く、高尾太夫の身請け金と見舞金で手を打ったって話だぜ」。
「遊女といえど、人ひとりを斬り殺しておいて、隠居で済むものなのか」。
「そりゃあ、お上のお裁きなんてそんなもんさ」。
「大名と遊女ではそれも致し方ないのでは」。
新八郎も同調するが、人の命の重さを思いあぐねる左兵衛には納得でき兼ねた。
「でもよ、荻生先生は違うぜ」。
心太が幾分自慢そうに名を出したのは、時の将軍・綱吉側近の柳沢吉保に抜擢された儒学者・荻生徂徠である。
「荻生先生って、お前知り合いか」。
ランキングに参加しています。ご協力お願いします。
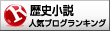
 にほんブログ村
にほんブログ村

「若様、知ってなすかい」。
「心太、朝っぱらから何事だ。若様は朝餉を召し上がっておる」。
近習の新八郎、弥七郎が、やれやれと顔を覗かせると、呉服橋御門内吉良家からそう遠くはない、安針町に小さな店を構える豆腐屋の心太が、いつものように右手にくしゃくしゃに読み尽くされた読売を掲げて息を弾ませている。
「また読売か。お前の読売は実に迷惑千万。若様にお見せする訳にはいかぬ」。
新八郎にこう言われても、
「それが、吉原一の三浦屋の高尾太夫が吊るし切りにされたってんでさ」。
その声に左兵衛は、「聞き捨てならず」とばかりに箸を投げ出した。
「心太、見せてみよ」。
言うが早いか、ひったくるように読売に目を走らせる左兵衛の姿に心太は頭を捻る。
「若様が吉原に興味があったとは知らなかった」。
「これ、心太。馬鹿を申すな」。
弥七郎も一応は心太を叱るが、内心は気になって仕方がない。
「何でもよ、去るお大名の身請け話を断ったところ、船遊びの最中に真っ二つに斬られて、墨田の川に打ち捨てられたってんだ」。
読売を読み終えた左兵衛は、あの堂々とした誇り高い高尾の笑みを思い浮かべていた。
「気の毒に」。
「あれっ、若様、高尾太夫を知ってなさるんですかい」。
「これ心太、若様がそのような者を見知っておられる訳がないであろう」。
新八郎がそう取り繕うが、当の左兵衛。
「これには身請けを断ったと書いてあるが、吉原の女郎は身請けを否めるものなのか」。
「おっと若様、乗ってきなすった。そりゃあ断ることなんぞできやしません。だけど、そこが高尾太夫の気っ風のいいとことで、何でも言い交わした男がいたらしいです」。
「好いた男がおれば、その者と添うことができるものなのか」。
「そりゃあ無理でしょうね。だけど、身体は売っても心は売らねえってのが高尾太夫だもんでさ」。
心太が続ける話は、屋形船から胴をまっ二つに斬り落とされた高尾の遺骸は、そのまま川に打ち捨てられたということであった。
件の大名は老臣の勧めで、ことが明るみに出る前に隠居願いを幕府に提出し受諾されたいた。
「お大名のお殿様とあっちゃ相手が悪いや。三浦屋さんも泣く泣く、高尾太夫の身請け金と見舞金で手を打ったって話だぜ」。
「遊女といえど、人ひとりを斬り殺しておいて、隠居で済むものなのか」。
「そりゃあ、お上のお裁きなんてそんなもんさ」。
「大名と遊女ではそれも致し方ないのでは」。
新八郎も同調するが、人の命の重さを思いあぐねる左兵衛には納得でき兼ねた。
「でもよ、荻生先生は違うぜ」。
心太が幾分自慢そうに名を出したのは、時の将軍・綱吉側近の柳沢吉保に抜擢された儒学者・荻生徂徠である。
「荻生先生って、お前知り合いか」。
ランキングに参加しています。ご協力お願いします。










