まさと呼ばれる老婆は弥七郎を見ると一瞬、はっと目を見開いたが、その場でゆっくりと茶を注ぎながら話を聞こうといった構えで居座っていた。
「で、新貝様。どのような物を御所望にございましょう」。
左隣に座る心太に脇腹を突つかれた弥七郎は、咳払いをした後、幾分上ずった声で、
「国元の妻への土産を」。
「ほう、奥方様にでございますか。お幾つくらいの方でございましょう」。
主人は、妻の年齢、風貌、好みの色など、左兵衛との打ち合わせにないことを矢継ぎ早に聞いてくるのだった。これには、弥七郎も冷や汗をかいた。
弥七郎の答えを聞くと、主人は手代に言い付けて、櫛や簪、紙入れなど、落ち着いた上品な品を幾つか用意させていた。
それを見て、まさは急いで下がって行く。恐らく律の元だろう。
半時の後、銀細工の玉簪を懐にした弥七郎が店の暖簾を出ると、まさが先回りし、
「新貝様」。
そう声を掛けるのだった。弥七郎は促され、今度は裏に回り田丸屋の住居に案内される。心太も付いて行くがまさに止められ、弥七郎のみが木戸を潜った。
「何を話してるんだ」。
心太が裏木戸の外でじれていると四半時後、戻った弥七郎は、安堵の表情を浮かべていた。
「弥七郎、上手くいったかい」。
「問題なかろう。だが、これでも聞き入れぬとあらば、手の打ちようがないな」。
微笑を称える弥七郎の顔をまじまじと見詰めた心太は、「まあ、これだけの男前じゃあ惚れるなって方が無理な話だ」と思ってはいたが、それを口に出して弥七郎を良い気にさせるものかと黙って、左兵衛の待つ茶屋へと急ぐのだった。
弥七郎の表情を読み取った左兵衛は、
「春霖もいつかは上がろう」。
子細を問わずそのまま歩き出すが、後方から心太が、「教えておくれよ」と弥七郎にじゃれついて、「うるさい。歩けぬではないか」と、何やら楽しそうにしていた。
万事上手くいったであろう律の問題はすっかり脳裏から消え失せた左兵衛は、先刻まで茶屋の床几に腰を下ろしていた、左目の下の黒子が妙に色気もあり、印象的ではあるが、目つき鋭いこと尋常ならなぬ二十歳前後の男のことが気に掛かっていた。
その男は左兵衛たちのほんの少し前を歩いている。
「あれっ、福太郎じゃねえかな」。
前を覗き込んだ心太が親しげに言う。
「心太、知り合いか」。
「うーん。随分会っちゃいねもんではっきりとはしねえが、福太郎だったような気がする…」。
心太は小走りに男を追い越して、行く手をたち塞ぐと、
「やっぱり福太郎だ」。
だが、男は目を反らして俯くと、
「どなたか存じませんが、お人違いでしょう」。
心太を交わし、足早に去って行った。
「おかしいな、福太郎だと思ったんだけどな」。
心太は頻りに頭を捻るのだった。
ランキングに参加しています。ご協力お願いします。
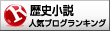
 にほんブログ村
にほんブログ村

「で、新貝様。どのような物を御所望にございましょう」。
左隣に座る心太に脇腹を突つかれた弥七郎は、咳払いをした後、幾分上ずった声で、
「国元の妻への土産を」。
「ほう、奥方様にでございますか。お幾つくらいの方でございましょう」。
主人は、妻の年齢、風貌、好みの色など、左兵衛との打ち合わせにないことを矢継ぎ早に聞いてくるのだった。これには、弥七郎も冷や汗をかいた。
弥七郎の答えを聞くと、主人は手代に言い付けて、櫛や簪、紙入れなど、落ち着いた上品な品を幾つか用意させていた。
それを見て、まさは急いで下がって行く。恐らく律の元だろう。
半時の後、銀細工の玉簪を懐にした弥七郎が店の暖簾を出ると、まさが先回りし、
「新貝様」。
そう声を掛けるのだった。弥七郎は促され、今度は裏に回り田丸屋の住居に案内される。心太も付いて行くがまさに止められ、弥七郎のみが木戸を潜った。
「何を話してるんだ」。
心太が裏木戸の外でじれていると四半時後、戻った弥七郎は、安堵の表情を浮かべていた。
「弥七郎、上手くいったかい」。
「問題なかろう。だが、これでも聞き入れぬとあらば、手の打ちようがないな」。
微笑を称える弥七郎の顔をまじまじと見詰めた心太は、「まあ、これだけの男前じゃあ惚れるなって方が無理な話だ」と思ってはいたが、それを口に出して弥七郎を良い気にさせるものかと黙って、左兵衛の待つ茶屋へと急ぐのだった。
弥七郎の表情を読み取った左兵衛は、
「春霖もいつかは上がろう」。
子細を問わずそのまま歩き出すが、後方から心太が、「教えておくれよ」と弥七郎にじゃれついて、「うるさい。歩けぬではないか」と、何やら楽しそうにしていた。
万事上手くいったであろう律の問題はすっかり脳裏から消え失せた左兵衛は、先刻まで茶屋の床几に腰を下ろしていた、左目の下の黒子が妙に色気もあり、印象的ではあるが、目つき鋭いこと尋常ならなぬ二十歳前後の男のことが気に掛かっていた。
その男は左兵衛たちのほんの少し前を歩いている。
「あれっ、福太郎じゃねえかな」。
前を覗き込んだ心太が親しげに言う。
「心太、知り合いか」。
「うーん。随分会っちゃいねもんではっきりとはしねえが、福太郎だったような気がする…」。
心太は小走りに男を追い越して、行く手をたち塞ぐと、
「やっぱり福太郎だ」。
だが、男は目を反らして俯くと、
「どなたか存じませんが、お人違いでしょう」。
心太を交わし、足早に去って行った。
「おかしいな、福太郎だと思ったんだけどな」。
心太は頻りに頭を捻るのだった。
ランキングに参加しています。ご協力お願いします。










