残暑厳しい昼下がり、呉服橋御門内吉良邸の中庭にて所在なげに過ごすのは、吉良家跡取りの左兵衛義周。その傍らには、近習である山吉新八郎盛侍に新貝弥七郎安村。
「こう暑くては何もする気も起きぬな」。
「左様でございます。ならば百物語でもするか」。
「二人でしたとて冬になっても終わらぬは」。
そんな新八郎と弥七郎には目もくれず、暑さも何のその、左兵衛は好きな絵を描いて過ごしていた。
そこへ、いつもの顔が揃う。
「若様、こう暑くちゃ、どうにもならねえや。どうです。隅田で船遊びなんか」。
一石橋を北に裏河岸を抜けた宝町通り近くの安針町の豆腐屋の倅、心太である。
「左様ではあるが…」。
「なんでい若様、今日は歯切れが悪りいや」。
「これ心太。無理を申すでない。若様は謹慎中だ」。
弥七郎が言うと、左兵衛は「これ」と目配せをするがもう遅い。
「どうしてさ、どうして謹慎させられてるんで」。
先の谷中延命寺事件の折り、寺社奉行の脇坂淡路守安禎が、左兵衛に御礼の品を届けたことからことが露見し、養父の上野介並びのその妻の富子に酷く叱られ、謹慎を申し渡されていたのだった。
「言いたくねえんならいいや。でもよ殿様と奥方様がそこまでお怒りになるってのは、若様が悪りいんだろうさ」。
「心太、そう言うな。余も参っておるのじゃ」。
「じゃあ、一学さんでも誘うか」。
「一学も同罪じゃ」。
一学とは用人の清水一学。農民から士分に取り立てられた逸材である。
がっくりとうな垂れる三人の前に、
「このようなことであろうと思い参りました」。
中庭の先には、左兵衛が虚ろに足元から見上げていくと見慣れた男の姿があった。
「紀伊国屋ではないか。本日は如何した」。
八丁堀に広大な邸宅を構える、お大尽と呼ばれる豪商・紀伊国屋文左衛門である。
「本日は、船遊びのお誘いに参りました次第で」。
「それは有り難いが、聞こえていたであろう。余は屋敷から出ることができぬのじゃ」。
「はい。聞こえておりました。ですが、若様がお叱りを受け、謹慎なさっていることをお知りになった淡路守様からのお誘いでございます」。
「それは真であるか」。
左兵衛は飛び起きた。
「はい。吉良様も快くご承知くださいました」。
「待て、紀伊国屋。義父上もご一緒なされるのか」。
「そのようにございます」。
「それでは羽が伸ばせぬではないか」。
左兵衛の呟くような声は、新八郎と弥七郎にしか届かなかった。そんな会話がなされる中、黙って遠ざかろうとする心太の後ろ姿が左兵衛の目に入る。
「これ、心太。何処へ行くのじゃ」。
船遊びの言い出しっぺの心太ではあったが、もはや己の出る幕はないと察し、静かに屋敷を出ようとしていたのである。左兵衛の声に振り向いた顔には、わずかに口元に笑みを浮かべているが、ふっと見せた悲しそうな表情に気が付いた弥七郎が、
「なあにお忍びだ。それに粋な江戸っ子の船遊びだ。淡路守様も無粋なことはおっしゃるまい」。
そう誘うが、「おいら、そんなに偉れえ御方とばかりじゃ気が休まらねえから行かねえよ」。どうにも色良い返事をしない心太に左兵衛も宥める。
「そちは余の幼馴染み。案ずることはない」。
そこに紀伊国屋が、
「お前さんは、船遊びをしたくないのかい」。
と、直接的に聞いてきたもので、返答に困った心太は「うん」とうな垂れてしまう。
「手前もお前さんも同じ商人。何を気に止むことがあるのだ。身分を気にして行けないと言うなら、手前もお供する訳にはいきませぬなあ、左兵衛様」。
心太の顔が一瞬にして輝きを取り戻した。
ランキングに参加しています。ご協力お願いします。
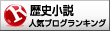
 にほんブログ村
にほんブログ村

「こう暑くては何もする気も起きぬな」。
「左様でございます。ならば百物語でもするか」。
「二人でしたとて冬になっても終わらぬは」。
そんな新八郎と弥七郎には目もくれず、暑さも何のその、左兵衛は好きな絵を描いて過ごしていた。
そこへ、いつもの顔が揃う。
「若様、こう暑くちゃ、どうにもならねえや。どうです。隅田で船遊びなんか」。
一石橋を北に裏河岸を抜けた宝町通り近くの安針町の豆腐屋の倅、心太である。
「左様ではあるが…」。
「なんでい若様、今日は歯切れが悪りいや」。
「これ心太。無理を申すでない。若様は謹慎中だ」。
弥七郎が言うと、左兵衛は「これ」と目配せをするがもう遅い。
「どうしてさ、どうして謹慎させられてるんで」。
先の谷中延命寺事件の折り、寺社奉行の脇坂淡路守安禎が、左兵衛に御礼の品を届けたことからことが露見し、養父の上野介並びのその妻の富子に酷く叱られ、謹慎を申し渡されていたのだった。
「言いたくねえんならいいや。でもよ殿様と奥方様がそこまでお怒りになるってのは、若様が悪りいんだろうさ」。
「心太、そう言うな。余も参っておるのじゃ」。
「じゃあ、一学さんでも誘うか」。
「一学も同罪じゃ」。
一学とは用人の清水一学。農民から士分に取り立てられた逸材である。
がっくりとうな垂れる三人の前に、
「このようなことであろうと思い参りました」。
中庭の先には、左兵衛が虚ろに足元から見上げていくと見慣れた男の姿があった。
「紀伊国屋ではないか。本日は如何した」。
八丁堀に広大な邸宅を構える、お大尽と呼ばれる豪商・紀伊国屋文左衛門である。
「本日は、船遊びのお誘いに参りました次第で」。
「それは有り難いが、聞こえていたであろう。余は屋敷から出ることができぬのじゃ」。
「はい。聞こえておりました。ですが、若様がお叱りを受け、謹慎なさっていることをお知りになった淡路守様からのお誘いでございます」。
「それは真であるか」。
左兵衛は飛び起きた。
「はい。吉良様も快くご承知くださいました」。
「待て、紀伊国屋。義父上もご一緒なされるのか」。
「そのようにございます」。
「それでは羽が伸ばせぬではないか」。
左兵衛の呟くような声は、新八郎と弥七郎にしか届かなかった。そんな会話がなされる中、黙って遠ざかろうとする心太の後ろ姿が左兵衛の目に入る。
「これ、心太。何処へ行くのじゃ」。
船遊びの言い出しっぺの心太ではあったが、もはや己の出る幕はないと察し、静かに屋敷を出ようとしていたのである。左兵衛の声に振り向いた顔には、わずかに口元に笑みを浮かべているが、ふっと見せた悲しそうな表情に気が付いた弥七郎が、
「なあにお忍びだ。それに粋な江戸っ子の船遊びだ。淡路守様も無粋なことはおっしゃるまい」。
そう誘うが、「おいら、そんなに偉れえ御方とばかりじゃ気が休まらねえから行かねえよ」。どうにも色良い返事をしない心太に左兵衛も宥める。
「そちは余の幼馴染み。案ずることはない」。
そこに紀伊国屋が、
「お前さんは、船遊びをしたくないのかい」。
と、直接的に聞いてきたもので、返答に困った心太は「うん」とうな垂れてしまう。
「手前もお前さんも同じ商人。何を気に止むことがあるのだ。身分を気にして行けないと言うなら、手前もお供する訳にはいきませぬなあ、左兵衛様」。
心太の顔が一瞬にして輝きを取り戻した。
ランキングに参加しています。ご協力お願いします。










