「奥女中が今度は、お城の牢の中で心の臓の病いでぽっくり逝っちまったらしい」。
「心太、いつ参ったのじゃ」。
呉服橋御門内の吉良邸に本日も沸いて出て来たかのような、裏河岸を抜けた宝町通りにほど近い安針町の豆腐屋の息子・心太である。吉良家の世継ぎである左兵衛義周の問いには答えず、
「それと、あの中村ってえ御徒衆も乱心したってえんで、蟄居閉門だってことさ」。
「また読売か」。
新八郎と弥七郎は些かうんざりしていた。
「ここんとこ、お城の側で切腹やら髪切りやらの騒動があっただろ。だから大奥や、お侍のおかしな話を書けば、読売が売れるのさ」。
それだけを伝えると、すでに心太の関心は新たな出来事へと向かっているかのようだった。
「どうした心太、腰が落ち着かないようだが」。
「いいや。何でもねえ。じゃあ若様、おいら店があるんで失礼します」。
「忙しないやつだな」。
心太は風のように走って行くのだった。
心太の関心が他所になら、こちら左兵衛の関心も非ぬ所に向いていた。
日を改め、左兵衛が向かったのは、養父母の吉良上野介義央と富子の元である。
「義父上、義母上。左兵衛、お願いの義があり参りました」。
願いの義と聞いて、富子は眉を上げる。後ろに控える新八郎、弥七郎の口元にも力が入る。
「何じゃ。左兵衛殿が強請るなど珍しいではないか。申してみよ」。
これまでのことを全く知らされていない上野介だけは、可愛い孫の申し出に目尻を下げるのだった。
「はい。御領地を一度この目で見とうございます」。
「何と、三河をとな」。
「はい。恥ずかしながら左兵衛は当家の領地のこと、民百姓の暮らしぶり、何も知りませぬ故、この目で見とうございます」。
「左兵衛殿、この義は成りませぬ」。
富子は立ち上がらんばかりの勢いである。
「上野や猿若町などとは話が違います。三河など遠過ぎます」。
普段滅多に声を張り上げることのない富子だけに、上野介も驚きに目を白黒させるが、「上野や猿若町とは何じゃ」。と聞いても誰もが口を噤む。
「中々のお心掛けではあるが、左兵衛殿が参られるとあれば行列を仕立てなければならぬ故、その支度にしばらくは掛かろうというものじゃ」。
当主らしい最もな意見である。
「義父上、行列は要りませぬ。ここに控えます新八郎、弥七郎と参る所存」。
ここまで言い掛けたが、それを遮ったのは富子であった。
「新八郎、弥七郎。その方らは左兵衛殿の守役でもあるのじゃ。如何にお宥めできぬのじゃ」。
矛先が新八郎、弥七郎に及び、二人は平伏したまま微動だにできなくなっていた。
「義母上様、これは左兵衛ひと人の考えにあれば、この者たちをお叱りくださりますな」。
平伏の侭胸を撫で下ろす新八郎、弥七郎であった。
「良いか左兵衛殿。そなたはいずれこの吉良家の当主になる身ですぞ。それが伴二人と三河まで旅をするなど危険極まりない。万が一、そのようなことになれば、この義母は毎夜眠ることすら覚束くまいて。年老いた義母の頼みです」。
富子にこう言われてしまえば、もう諦めるしかない。そもそも、無茶な話であることは左兵衛自身も重々に心得ているのだ。
ランキングに参加しています。ご協力お願いします。
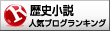
 にほんブログ村
にほんブログ村

「心太、いつ参ったのじゃ」。
呉服橋御門内の吉良邸に本日も沸いて出て来たかのような、裏河岸を抜けた宝町通りにほど近い安針町の豆腐屋の息子・心太である。吉良家の世継ぎである左兵衛義周の問いには答えず、
「それと、あの中村ってえ御徒衆も乱心したってえんで、蟄居閉門だってことさ」。
「また読売か」。
新八郎と弥七郎は些かうんざりしていた。
「ここんとこ、お城の側で切腹やら髪切りやらの騒動があっただろ。だから大奥や、お侍のおかしな話を書けば、読売が売れるのさ」。
それだけを伝えると、すでに心太の関心は新たな出来事へと向かっているかのようだった。
「どうした心太、腰が落ち着かないようだが」。
「いいや。何でもねえ。じゃあ若様、おいら店があるんで失礼します」。
「忙しないやつだな」。
心太は風のように走って行くのだった。
心太の関心が他所になら、こちら左兵衛の関心も非ぬ所に向いていた。
日を改め、左兵衛が向かったのは、養父母の吉良上野介義央と富子の元である。
「義父上、義母上。左兵衛、お願いの義があり参りました」。
願いの義と聞いて、富子は眉を上げる。後ろに控える新八郎、弥七郎の口元にも力が入る。
「何じゃ。左兵衛殿が強請るなど珍しいではないか。申してみよ」。
これまでのことを全く知らされていない上野介だけは、可愛い孫の申し出に目尻を下げるのだった。
「はい。御領地を一度この目で見とうございます」。
「何と、三河をとな」。
「はい。恥ずかしながら左兵衛は当家の領地のこと、民百姓の暮らしぶり、何も知りませぬ故、この目で見とうございます」。
「左兵衛殿、この義は成りませぬ」。
富子は立ち上がらんばかりの勢いである。
「上野や猿若町などとは話が違います。三河など遠過ぎます」。
普段滅多に声を張り上げることのない富子だけに、上野介も驚きに目を白黒させるが、「上野や猿若町とは何じゃ」。と聞いても誰もが口を噤む。
「中々のお心掛けではあるが、左兵衛殿が参られるとあれば行列を仕立てなければならぬ故、その支度にしばらくは掛かろうというものじゃ」。
当主らしい最もな意見である。
「義父上、行列は要りませぬ。ここに控えます新八郎、弥七郎と参る所存」。
ここまで言い掛けたが、それを遮ったのは富子であった。
「新八郎、弥七郎。その方らは左兵衛殿の守役でもあるのじゃ。如何にお宥めできぬのじゃ」。
矛先が新八郎、弥七郎に及び、二人は平伏したまま微動だにできなくなっていた。
「義母上様、これは左兵衛ひと人の考えにあれば、この者たちをお叱りくださりますな」。
平伏の侭胸を撫で下ろす新八郎、弥七郎であった。
「良いか左兵衛殿。そなたはいずれこの吉良家の当主になる身ですぞ。それが伴二人と三河まで旅をするなど危険極まりない。万が一、そのようなことになれば、この義母は毎夜眠ることすら覚束くまいて。年老いた義母の頼みです」。
富子にこう言われてしまえば、もう諦めるしかない。そもそも、無茶な話であることは左兵衛自身も重々に心得ているのだ。
ランキングに参加しています。ご協力お願いします。










