左兵衛の合図で一学が急ぎ戻ると、既にこと切れた芳造の変わり果てた姿と、その傍らには、それまで何処にいたのか中屋の娘が、芳造の胸を貫いた刃を両の手で握り締めたまま、腰を抜かして座敷にしゃがみ込む姿があった。
左兵衛は取って返すともはや罪人も亡き今、中屋のみに罪を問うても致し方あるまいと語ると、
「本来であれば、庄屋の称号を返上し蟄居しても足りぬところであるが、娘を思うあまりの親心としてこの度だけは許すとしよう。じゃが、変わりにその方に新田開発を命ずる。私財を投げ打っても百姓のために尽くせ。娘御は如何に相手が極悪人とはいえ、人を殺めた罪は免れぬ。覚悟せよ」。
だが、金目当てと薄々は分かっていても、それでも心のどこかでは男を信じたかった娘の、外れた箍が元に戻ることはなく、その目は宙を彷徨い夢うつつの中で生きているかのようでもある。
本来であれば磔獄門は否めないが、心を煩った娘に、格別の配慮を願う左兵衛は、岡山陣屋城代の鈴井源吾に、「身体に受けた傷は何時かは癒えようが、心の傷は時を経ても癒えることはない」。そう嘆願を残し江戸へと旅経つのであった。
「余も父上を見習い、新田開発や塩のための水路を作らなければのう」。
左兵衛たちを乗せた菱垣廻船はすでに三浦半島に迫っていた。
「しかし若様には参ったぜ。あんな捕り物やっちまうとはさ」。
心太は驚きを隠せない。
「なあに、毎度のことさ。お前もそのうちに慣れるだろうよ。なあ新八郎」。
「左様」。
「毎度って何だよ。若様、毎度って…」。
新八郎、弥七郎はただ笑っているだけである。
「ですが、幾ら親の仇とはいえ、あそこまで惨いことができるなど、到底信じられませぬな」。
「薬の知識は確かな様子。あの者も道を誤らねば、薬種のいい商いができましたでしょうに」。
一同は、これもまた、運命に翻弄された者の哀れと嘆くのだった。
「罪を犯す者も善良なる者も、元は水波であったというに」。
ほんのわずかな掛け違いが、人を悪しき者へと変えてゆく。左兵衛は人の弱さを改めて知る思いだった。
元禄十三年晦日。
左兵衛は月を愛でていた。だがこの月も直に雲に隠れよう。遠くの闇にかすかに寒雷が聞こえている。
「寒雷とは風流じゃ」。
稲妻の閃光が光る。
「新八郎、弥七郎。もう直ぐ年が明けるのう。次はどのような年になるであろう」。
「この年は若様のお陰で、いささか忙しゅうございました故、静かに過ごしたいものです」。
「それがしも、平穏無事に過ごしたいと思います」。
「その方らは夢がないのう。余はまだまだ見たいものや、やりたいことなどあり過ぎて困る程じゃ」。
三人はいつか必ず、「米沢で初日の出を見よう」と、誓うのだった。
明けて元禄十四年。この年、左兵衛の耳に飛び込んできた最初の事件は、江戸城中に於いて、浅野内匠頭長矩による吉良上野介義央への刃傷。三月十四日のことである。
そしてこれより二年足らずの元禄十五年十二月十五日未明。旧赤穂藩士により、吉良家は襲撃されるのである。 完
※「水波の如し~忠臣蔵余話~」本編はこれにて完結です。明日よりは、「水波の如し~外伝 風光る~」が始まります。
運命の元禄十五年十二月十五日。その時…。吉良左兵衛義周、山吉新八郎盛侍、新貝弥七郎安村、清水一学義久始め、吉良家の人々は如何に戦ったのか。後に幕府が下した裁定は。上杉家の人々のその後は。
そして、裏門隊に名まで連ねながら直前にて脱落。未だ真意は明らかでない、赤穂浪士最後の脱落者とされる毛利小平太元義のその謎とは…。
左兵衛の朋友・心太の目を通して、討入りそしてその後を最期まで描きます。泉岳寺までの赤穂浪士の足跡や、彼らの切腹で終演を迎えたとお思いの方に、是非知って頂きたい討入り事件の結末です。
本編を読んでいなくても、独立した物語になっておりますので、是非、吉良左兵衛義周の生涯を知ってください。
注・左兵衛は、元服後、家督を相続してからの呼称であり、本編中は、左兵衛ではありませんが、外伝にあたり、混乱を避ける為に、敢えて左兵衛で統一させて頂きました。
ランキングに参加しています。ご協力お願いします。
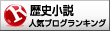
 にほんブログ村
にほんブログ村

左兵衛は取って返すともはや罪人も亡き今、中屋のみに罪を問うても致し方あるまいと語ると、
「本来であれば、庄屋の称号を返上し蟄居しても足りぬところであるが、娘を思うあまりの親心としてこの度だけは許すとしよう。じゃが、変わりにその方に新田開発を命ずる。私財を投げ打っても百姓のために尽くせ。娘御は如何に相手が極悪人とはいえ、人を殺めた罪は免れぬ。覚悟せよ」。
だが、金目当てと薄々は分かっていても、それでも心のどこかでは男を信じたかった娘の、外れた箍が元に戻ることはなく、その目は宙を彷徨い夢うつつの中で生きているかのようでもある。
本来であれば磔獄門は否めないが、心を煩った娘に、格別の配慮を願う左兵衛は、岡山陣屋城代の鈴井源吾に、「身体に受けた傷は何時かは癒えようが、心の傷は時を経ても癒えることはない」。そう嘆願を残し江戸へと旅経つのであった。
「余も父上を見習い、新田開発や塩のための水路を作らなければのう」。
左兵衛たちを乗せた菱垣廻船はすでに三浦半島に迫っていた。
「しかし若様には参ったぜ。あんな捕り物やっちまうとはさ」。
心太は驚きを隠せない。
「なあに、毎度のことさ。お前もそのうちに慣れるだろうよ。なあ新八郎」。
「左様」。
「毎度って何だよ。若様、毎度って…」。
新八郎、弥七郎はただ笑っているだけである。
「ですが、幾ら親の仇とはいえ、あそこまで惨いことができるなど、到底信じられませぬな」。
「薬の知識は確かな様子。あの者も道を誤らねば、薬種のいい商いができましたでしょうに」。
一同は、これもまた、運命に翻弄された者の哀れと嘆くのだった。
「罪を犯す者も善良なる者も、元は水波であったというに」。
ほんのわずかな掛け違いが、人を悪しき者へと変えてゆく。左兵衛は人の弱さを改めて知る思いだった。
元禄十三年晦日。
左兵衛は月を愛でていた。だがこの月も直に雲に隠れよう。遠くの闇にかすかに寒雷が聞こえている。
「寒雷とは風流じゃ」。
稲妻の閃光が光る。
「新八郎、弥七郎。もう直ぐ年が明けるのう。次はどのような年になるであろう」。
「この年は若様のお陰で、いささか忙しゅうございました故、静かに過ごしたいものです」。
「それがしも、平穏無事に過ごしたいと思います」。
「その方らは夢がないのう。余はまだまだ見たいものや、やりたいことなどあり過ぎて困る程じゃ」。
三人はいつか必ず、「米沢で初日の出を見よう」と、誓うのだった。
明けて元禄十四年。この年、左兵衛の耳に飛び込んできた最初の事件は、江戸城中に於いて、浅野内匠頭長矩による吉良上野介義央への刃傷。三月十四日のことである。
そしてこれより二年足らずの元禄十五年十二月十五日未明。旧赤穂藩士により、吉良家は襲撃されるのである。 完
※「水波の如し~忠臣蔵余話~」本編はこれにて完結です。明日よりは、「水波の如し~外伝 風光る~」が始まります。
運命の元禄十五年十二月十五日。その時…。吉良左兵衛義周、山吉新八郎盛侍、新貝弥七郎安村、清水一学義久始め、吉良家の人々は如何に戦ったのか。後に幕府が下した裁定は。上杉家の人々のその後は。
そして、裏門隊に名まで連ねながら直前にて脱落。未だ真意は明らかでない、赤穂浪士最後の脱落者とされる毛利小平太元義のその謎とは…。
左兵衛の朋友・心太の目を通して、討入りそしてその後を最期まで描きます。泉岳寺までの赤穂浪士の足跡や、彼らの切腹で終演を迎えたとお思いの方に、是非知って頂きたい討入り事件の結末です。
本編を読んでいなくても、独立した物語になっておりますので、是非、吉良左兵衛義周の生涯を知ってください。
注・左兵衛は、元服後、家督を相続してからの呼称であり、本編中は、左兵衛ではありませんが、外伝にあたり、混乱を避ける為に、敢えて左兵衛で統一させて頂きました。
ランキングに参加しています。ご協力お願いします。










