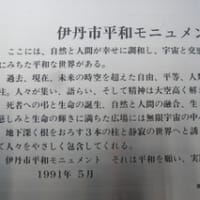顔
2010-01-06 | パパ
マルセル・デュシャンの「L.H.O.O.Q.」という作品がある。有名なモナリザの絵にひげを付けただけのなんとも、芸術愛好家をおちょくったような作品である。

しかし、この作品を絵画への単純ゆえに鋭い挑発であると考えることもできる。つまり、われわれは、絵という単に2次元平面に描かれた実物の影にすぎないものに、レオナルド・ダ・ヴィンチのモナリザだというだけで、イメージをふくらませ、そこに感動しているのではないのかと。だから、デュシャンのひげは、イメージを生み出す作品の効果を封じ込め、二次元で構成された絵という物質自体にわれわれを踏みとどまらせようとする。
絵とは、聖書の物語や人物、風景を二次元平面に描きイメージを作り出すものではなく、絵そのものの表現なのだというのが20世紀絵画の主題となっていく。
ナビ派の画家モーリス・ドニはこのことを明快に記している。
「絵画作品とは、裸婦とか、戦場の馬とか、その他なんらかの逸話的なものである前に、本質的に、ある一定の秩序のもとに集められた色彩によって覆われた平坦な面である。」
20世紀絵画において、ピカソと並ぶ巨匠アンリ・マティスが描く顔には、徐々に表情がなくなっている。彼が表現しようとしたのは、モデルの個性ではなく、顔という物質がもつ抽象的な形態である。ヴァンス礼拝堂の壁画では、顔の具体的な表情にはほとんど関心を払っていないためか、のっぺらぼうになるまで抽象化を推し進めている。



パリの美術学校でマティスと同期だったジョルジュ・ルオーは、マティスらの造形的探求のみで、自己の内面を絵画に向かって現そうとしない態度に批判的であった。彼は語っている。
「彼らは人間の心の奥底のことにはまったく無関心のようだ。だが、私にとってはそれこそが全生命だ。」と。
また「独語録」の中では
「秩序とは外から与えられるものではない。それは内部の世界から輝きでるものだ」と書いている。
ルオーにはピエロや職人などの人物像を描いた作品が多いが、その場合でも、自己の心の奥深くを見つめながら描き、絵に自己を重ね合わせようとした。


いつからだろう、日本人の顔が社会の中から消えてしまったのは?物や情報がいつでも手に入り、自身を孤独の沈黙から排除し、社会全体が空騒ぎしだしたころではなかったでしょうか。格差が拡大していく現実において、自身の豊かさだけを求め、他人に無関心でいられた時代は、終わろうとしている。他者へのまなざしが、自身の内面を深く理解することを前提とするならば、ルオーの絵は現代の閉塞した社会にこそふさわしい。

しかし、この作品を絵画への単純ゆえに鋭い挑発であると考えることもできる。つまり、われわれは、絵という単に2次元平面に描かれた実物の影にすぎないものに、レオナルド・ダ・ヴィンチのモナリザだというだけで、イメージをふくらませ、そこに感動しているのではないのかと。だから、デュシャンのひげは、イメージを生み出す作品の効果を封じ込め、二次元で構成された絵という物質自体にわれわれを踏みとどまらせようとする。
絵とは、聖書の物語や人物、風景を二次元平面に描きイメージを作り出すものではなく、絵そのものの表現なのだというのが20世紀絵画の主題となっていく。
ナビ派の画家モーリス・ドニはこのことを明快に記している。
「絵画作品とは、裸婦とか、戦場の馬とか、その他なんらかの逸話的なものである前に、本質的に、ある一定の秩序のもとに集められた色彩によって覆われた平坦な面である。」
20世紀絵画において、ピカソと並ぶ巨匠アンリ・マティスが描く顔には、徐々に表情がなくなっている。彼が表現しようとしたのは、モデルの個性ではなく、顔という物質がもつ抽象的な形態である。ヴァンス礼拝堂の壁画では、顔の具体的な表情にはほとんど関心を払っていないためか、のっぺらぼうになるまで抽象化を推し進めている。



パリの美術学校でマティスと同期だったジョルジュ・ルオーは、マティスらの造形的探求のみで、自己の内面を絵画に向かって現そうとしない態度に批判的であった。彼は語っている。
「彼らは人間の心の奥底のことにはまったく無関心のようだ。だが、私にとってはそれこそが全生命だ。」と。
また「独語録」の中では
「秩序とは外から与えられるものではない。それは内部の世界から輝きでるものだ」と書いている。
ルオーにはピエロや職人などの人物像を描いた作品が多いが、その場合でも、自己の心の奥深くを見つめながら描き、絵に自己を重ね合わせようとした。


いつからだろう、日本人の顔が社会の中から消えてしまったのは?物や情報がいつでも手に入り、自身を孤独の沈黙から排除し、社会全体が空騒ぎしだしたころではなかったでしょうか。格差が拡大していく現実において、自身の豊かさだけを求め、他人に無関心でいられた時代は、終わろうとしている。他者へのまなざしが、自身の内面を深く理解することを前提とするならば、ルオーの絵は現代の閉塞した社会にこそふさわしい。