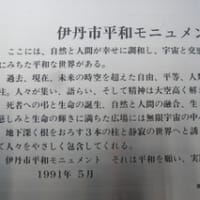眼の感覚
2010-01-15 | パパ
モネは眼の人であった。リアリティを光に求めた結果、対象は色の洪水の中に飲み込まれていく。対象の存在を色の洪水から救い出そうとしたのが、近代絵画の父セザンヌである。彼は、印象派展にも幾度か参加しているが印象派の一般的な特徴である対象の色への融解というものをどうしても許せず彼らから距離をとるようになる。そして自身のアトリエをパリから離れた故郷のエクス=アン=プロヴァンスに移し、サント・ヴィクトワール山などをモチーフに絵画制作を続けた。

セザンヌの絵は20世紀の新たな絵画のあり方を模索する若い画家たちにとってのバイブル的存在だった。実際、後期印象派の画家モーリス・ドニの「セザンヌ礼賛」には若い画家たちのセザンヌへの敬意がたくみに表現されている。

絵を描く行為とは、ものの在りようを2次元平面にどのように表現するかということである。エジプト文明の絵に現れる人間は、人体の各要素が一番美しいアングルで結合させて表現されているし、ルネサンスの時代には遠近法を発明し2次元平面に奥行を作り出している。どちらがより優れた絵画表現というのではなく、ものの在りようにおける絵画的表現の信仰の違いなのである。
しかしモネは、見る行為を眼と光の関係に極度に還元させた結果、もの自体の存在が光の渦の中に消えてしまう。それは、ものの在りようをどのように描くかという信仰を捨てることに等しかったのではないか?セザンヌがモネに敬意をはらいつつも、納得ができなかったのがこの部分なのである。
セザンヌは、見るという行為には懐疑的であり、ものの在りようは「眼の感覚」で表現できるという強い信念をもっていた。
眼の感覚とはなにか?それを理解するには、知覚と感覚について考えてみる必要がある。知覚というのは、身体の外にあるものを視覚や聴覚などを使って感じ取ることである。しかし、感覚はというと、なかなか難しい。そこで哲学者のベルクソンの考えを援用する。ベルクソンは、知覚の対象は身体の外に在るが、感覚の対象は身体の中に在るのだと考える。
たとえば、長い間帰っていなかった実家の匂いを嗅ぐとする。知覚レベルでは、臭覚を使って空間に漂う匂いを捕まえる。感覚は、身体の中に入り込んだ匂いによって変化した身体自身を感じとり、遠い昔の記憶を呼び覚ます。これが鼻におけるベルクソンがいう知覚と感覚の作用である。
セザンヌは眼にも知覚と感覚があると信じ、感覚は色を対象とすると考えた。
では、ものの在りようをどのように感覚で描くのだろうか?それに答えるには、セザンヌの自然に対して、抱いていた独特の考え方を説明しなければならない。
例えば、僕が山を見ているとする。知覚対象としての山は、僕がいるいないにかかわらずそこに聳え立っている。しかし、山の壮大さや色の美しさはといった感覚は、僕が山を見なければ存在しないものである。しかし、セザンヌはそれは違うのだという。山は、人がそこにいなくても、色を与えられて存在しているのだと。これは、色が光の反射であるという物理的事実と反するが、セザンヌにとっては、絵画を成立させるための信仰に近いものだったのだと思う。
自然はわれわれに向かって何かを表現させようと黙って存在しているのであって、眼を開き、眼の感覚の通路を介して、自然と合一し、それを絵に表現するのが画家の使命であるというのが、セザンヌの信仰なのである。彼は言っている。
「自分のささやかな感覚を現実化したい」と。
セザンヌにとってサント・ヴィクトワール山は、モチーフとしてではなく、画家に描くことを要求する自然の形として存在していたのかもしれません。


セザンヌの絵は20世紀の新たな絵画のあり方を模索する若い画家たちにとってのバイブル的存在だった。実際、後期印象派の画家モーリス・ドニの「セザンヌ礼賛」には若い画家たちのセザンヌへの敬意がたくみに表現されている。

絵を描く行為とは、ものの在りようを2次元平面にどのように表現するかということである。エジプト文明の絵に現れる人間は、人体の各要素が一番美しいアングルで結合させて表現されているし、ルネサンスの時代には遠近法を発明し2次元平面に奥行を作り出している。どちらがより優れた絵画表現というのではなく、ものの在りようにおける絵画的表現の信仰の違いなのである。
しかしモネは、見る行為を眼と光の関係に極度に還元させた結果、もの自体の存在が光の渦の中に消えてしまう。それは、ものの在りようをどのように描くかという信仰を捨てることに等しかったのではないか?セザンヌがモネに敬意をはらいつつも、納得ができなかったのがこの部分なのである。
セザンヌは、見るという行為には懐疑的であり、ものの在りようは「眼の感覚」で表現できるという強い信念をもっていた。
眼の感覚とはなにか?それを理解するには、知覚と感覚について考えてみる必要がある。知覚というのは、身体の外にあるものを視覚や聴覚などを使って感じ取ることである。しかし、感覚はというと、なかなか難しい。そこで哲学者のベルクソンの考えを援用する。ベルクソンは、知覚の対象は身体の外に在るが、感覚の対象は身体の中に在るのだと考える。
たとえば、長い間帰っていなかった実家の匂いを嗅ぐとする。知覚レベルでは、臭覚を使って空間に漂う匂いを捕まえる。感覚は、身体の中に入り込んだ匂いによって変化した身体自身を感じとり、遠い昔の記憶を呼び覚ます。これが鼻におけるベルクソンがいう知覚と感覚の作用である。
セザンヌは眼にも知覚と感覚があると信じ、感覚は色を対象とすると考えた。
では、ものの在りようをどのように感覚で描くのだろうか?それに答えるには、セザンヌの自然に対して、抱いていた独特の考え方を説明しなければならない。
例えば、僕が山を見ているとする。知覚対象としての山は、僕がいるいないにかかわらずそこに聳え立っている。しかし、山の壮大さや色の美しさはといった感覚は、僕が山を見なければ存在しないものである。しかし、セザンヌはそれは違うのだという。山は、人がそこにいなくても、色を与えられて存在しているのだと。これは、色が光の反射であるという物理的事実と反するが、セザンヌにとっては、絵画を成立させるための信仰に近いものだったのだと思う。
自然はわれわれに向かって何かを表現させようと黙って存在しているのであって、眼を開き、眼の感覚の通路を介して、自然と合一し、それを絵に表現するのが画家の使命であるというのが、セザンヌの信仰なのである。彼は言っている。
「自分のささやかな感覚を現実化したい」と。
セザンヌにとってサント・ヴィクトワール山は、モチーフとしてではなく、画家に描くことを要求する自然の形として存在していたのかもしれません。