先日 yu さんから【座右之銘・55】『Id sua sponte facerent quod cogerentur facere legibus』のブログ記事に対して次のコメントを頂いた。
***************************
(前略)
時代は下がりますが、マルクス・アウレリウス『自省録』の第7巻5節(岩波文庫 神谷美恵子訳)あたりに「指導理性」という言葉が出て参ります。 この言葉はこれ以降頻出しますが、特に注釈はなく、ただ「ト・ヘーゲモニコン」というルビのみが振られています。
『Meditations』(Penguin Classics)という本では「directing mind」と、極めてシンプルな言葉が使われているのに驚きましたが、「ト・ヘーゲモニコン」にはもっと深い意味が含まれているような気がします。
(後略)
***************************
この質問に答える前に、マルクス・アウレリウスやストア派に関する私の読書歴に触れたい。以前のブログ記事『私の語学学習(その23)』にも書いたように、学生時代ドイツ語に熱中していたころ、私はモンテーニュやショーペンハウアーからストア学派のことを知るようになった。その後ドイツ留学時に Reclam 文庫から出版されているこれらの哲人の本をあるだけ買い込んで帰国した。その中にマルクス・アウレリウスの『自省録』(Selbstbetrachtungen)もあった。 帰国後の24歳の春休みにこの本を読んだ。この本を読んで、ようやくこれ以前にモンテーニュやキケロ、セネカでストア学派の学説を読んでいて、今ひとつ全体像がつかめなかった、ストア学派の根本思想である『心の平静(ataraxia)』や『自然に即して生きる(Secundum naturam vivere)』の概念がよく理解できた。この後、続けてセネカの道徳論集や道徳書簡集を読了することで私はストア学派に心酔した。それは、思想的な内容もさることながら、主にセネカの巧みな弁論術(rhetoric)に惹かれたことが大きい。
(参照ブログ:『私の読書遍歴 -- 哲学から歴史へ』)

さて、学生の時に初めてマルクス・アウレリウス(Marcus Aurelius)を読んでから20数年経過して、ギリシャ語を独習したので、漸く彼のギリシャ語の原本を読むことが出来るようになった。私のギリシャ語は正直なところ、当時も今も相変わらず初心者レベルではあるが、ドイツ語や英語の対訳本を見ながら読み進めるという自称『アクアラング法』でプラトンやプルターク、果ては古典ギリシャ語で最高難度のツキディデースまで読んだ。
(参照ブログ:『語学訓練のアクアラング法』)
ところが、マルクス・アウレリウス(Marcus Aurelius)の『自省録』(ta eis heauton)を読み始めてすぐに、それまでの本とは全く違った、読みづらさを感じた。喩えて言えば、ごつごつした岩山を登るように、一歩一歩において非常にてこずる感触がした。難解と言われているツキディデースの『戦史』(Historia tou Peloponnesiakou Polemou)は確かに難しいのであるがそれは、急峻な坂を登る苦しさであり、道自体はいたってスムーズである。何故マルクス・アウレリウスの本が分かり難いのだろうか、と私なりに考えてみた結果、それは抽象名詞の連発にある、という結論に達した。
古典ギリシャ語というのは、専門家はどういうか知らないが、私個人の感想を述べると、極めて口語的な要素が強い言語である。日本語に喩えて言うと、文章文なのに、『えーっと。。。』、『それでですね、。。。』、『。。。しちゃってさぁ。。。』というような言い方がしょっちゅう出てくる。ひとことでいうと実にしまりのない書き方であるのだ。それに反してラテン語の文章文というのは極めて律儀な書き方をする。つまり無駄が少ない。この理解が正しいという前提で考えてみると母国語がラテン語であるマルクス・アウレリウスは、たとえギリシャ語をバイリンガルのレベルでマスターしているにしろ、習得言語であるギリシャ語で文章を綴るときに彼の母国語の癖が出たのであろうと、私は推察した。
マルクス・アウレリウスのごつごつ感には辟易したのだが、私がギリシャ語の独習を45歳の時に初めた時から、プラトンとこのマルクス・アウレリウスの本はどうしても原典で読んでみたいと念願していたので、途中で何度も放り出したい気持ちになったが、我慢を重ね、3ヶ月かけてようやく読了することができた。その意味でマルクス・アウレリウスのこの『自省録』は私にとっては二重の意味で思い出深い本である。
さて、マルクス・アウレリウスについての思い出話は、この辺りにしていよいよ本題に入ろう。
yu さんの質問を繰り返すと:
『自省録』(岩波文庫・神谷美恵子訳)の第7巻・5節の『指導理性』(ト・ヘーゲモニコン)という言葉は、英語では『directing mind』という極めてシンプル単語で訳されているが原語ではもっと深い意味を持っているのではないか?
まず、この箇所のギリシャ語の原文はと言うと:
kata proskhresin tou emou hegemonikou
であり、岩波文庫の訳では『私の指導理性の助けによって』となっている。また、英語とギリシャ語の対訳本である Loeb Classical Library #58 では『utilize my ruling Reason』と訳されている。ドイツ語の Reclam では『von meiner Geisteskraft unterstuetzt』と訳されている。
(ついでにいうと、この箇所に出てくる、proskhresis(προσχρησισ)という単語は、L&S の希英大辞典(Greek-English Lexicon、以下 L&S)によると、この箇所がこの単語の出典として引用されている。即ち、マルクス・アウレリウス以前のギリシャ人はこの単語を使っていなかったということだ。これが私が難しく感じた『抽象名詞』の一例である。)
さて、問題の το ηγεμονικον(to hegemonikon)であるが、元来 hegemonikon という単語は、英語の hegemony にもなった hegemon に由来している。 hegemon という名詞は hegeomai という動詞の派生語である。 hegeomai とは L&S では、『先に歩く、先導する』(go before, lead the way)というのが原義であると書かれている。それから『指導する』(lead, conduct)という意味が派生したと分かる。
hegeomai についてさらに語源にまで遡って調べてみよう。
Frisk の Griechisches Etymologisches Woerterbuch には次のような記述が見える。『hegeomai, ageomai はラテン語の sagio(追跡する、嗅ぎ付ける)とも関連している』。さらに、英語の語源辞典の金字塔である Skeat の Etymological Dictionary of the English Language の hegemony の項には、『 hegeomai は eg-agon(導く)やラテン語の ag-ere と関連がある。語根は AG(drive)。英語の Agent との関連を見よ』とある。
一方アメリカの大辞典の Webster's Third New International Dictionary, Unabridgedの hegemony の語源欄を見ると、hegeomai(guide, lead)と書かれていて、関連語源として、英語の SEEK が挙げられている。
以上の情報から、次のように結論付けられるだろう。
まず hegeomai というのは、『あちこちと探す』という原義から出発して、『道先を案内する』という単純な意味であったのが、次第に『リーダーとして人を指導して引っ張っていく』という意味が付与された、と言っていいだろう。
さて、hegemonikon の元である hegeomai の意味がそのようであると理解した上で、問題の『ト・ヘーゲモニコン』(to hegemonikon)の項を L&S で調べると次のように書かれている。
『the authoritative part of the soul (reason), especially in Stoic philosophy, Zeno; but also, the governing part of the universe, of the aether or sun, Chrysippus.』
(心の指令的な部分、理性。特にストア派のゼノンの意味。またクリュスッポスでは、宇宙を支配している理性的部分を指す。)
『ト・ヘーゲモニコン』について、この長たらしい説明を一言で訳すと『指導理性』や『ruling Reason』あるいは yu さんの指摘する『directing mind』で良いのではないかといえる。つまり語釈においては『directing mind』で問題がないのであるということだ。
しかし、問題は、『ト・ヘーゲモニコン』(directing mind)というのは何をどこに導いていくのかという語釈を離れた問題が残っている。(yu さんの疑問もこれがメインである。)
私の理解する範囲では、ストア派の根本の考えは、人間には他の動物にない『理性』というものがあり、これを自覚し、その理性の『導く』ところに忠実に従うことで初めて『心の平静』、つまり至福の境地に至ることができる、と言うことだ。この場合の理性(ratio)というのは、日本語でいうと『克己心』という訳がこの場合、一番ぴったりとしているのではないかと思う。つまり、善悪の判断をできる、という知的な部分よりも、濫りに欲望に負けない、あるいは怒りに任せない、という自己統御能力の高い人がストア派が目指す理想像なのである。
この意味で、『ト・ヘーゲモニコン』というのは、自分の外部に存在する指導者や指導理念というのではなく、自己の内部にある良心そのものであるという意味合いを強く持っている単語だと私は解釈したい。
***************************
(前略)
時代は下がりますが、マルクス・アウレリウス『自省録』の第7巻5節(岩波文庫 神谷美恵子訳)あたりに「指導理性」という言葉が出て参ります。 この言葉はこれ以降頻出しますが、特に注釈はなく、ただ「ト・ヘーゲモニコン」というルビのみが振られています。
『Meditations』(Penguin Classics)という本では「directing mind」と、極めてシンプルな言葉が使われているのに驚きましたが、「ト・ヘーゲモニコン」にはもっと深い意味が含まれているような気がします。
(後略)
***************************
この質問に答える前に、マルクス・アウレリウスやストア派に関する私の読書歴に触れたい。以前のブログ記事『私の語学学習(その23)』にも書いたように、学生時代ドイツ語に熱中していたころ、私はモンテーニュやショーペンハウアーからストア学派のことを知るようになった。その後ドイツ留学時に Reclam 文庫から出版されているこれらの哲人の本をあるだけ買い込んで帰国した。その中にマルクス・アウレリウスの『自省録』(Selbstbetrachtungen)もあった。 帰国後の24歳の春休みにこの本を読んだ。この本を読んで、ようやくこれ以前にモンテーニュやキケロ、セネカでストア学派の学説を読んでいて、今ひとつ全体像がつかめなかった、ストア学派の根本思想である『心の平静(ataraxia)』や『自然に即して生きる(Secundum naturam vivere)』の概念がよく理解できた。この後、続けてセネカの道徳論集や道徳書簡集を読了することで私はストア学派に心酔した。それは、思想的な内容もさることながら、主にセネカの巧みな弁論術(rhetoric)に惹かれたことが大きい。
(参照ブログ:『私の読書遍歴 -- 哲学から歴史へ』)

さて、学生の時に初めてマルクス・アウレリウス(Marcus Aurelius)を読んでから20数年経過して、ギリシャ語を独習したので、漸く彼のギリシャ語の原本を読むことが出来るようになった。私のギリシャ語は正直なところ、当時も今も相変わらず初心者レベルではあるが、ドイツ語や英語の対訳本を見ながら読み進めるという自称『アクアラング法』でプラトンやプルターク、果ては古典ギリシャ語で最高難度のツキディデースまで読んだ。
(参照ブログ:『語学訓練のアクアラング法』)
ところが、マルクス・アウレリウス(Marcus Aurelius)の『自省録』(ta eis heauton)を読み始めてすぐに、それまでの本とは全く違った、読みづらさを感じた。喩えて言えば、ごつごつした岩山を登るように、一歩一歩において非常にてこずる感触がした。難解と言われているツキディデースの『戦史』(Historia tou Peloponnesiakou Polemou)は確かに難しいのであるがそれは、急峻な坂を登る苦しさであり、道自体はいたってスムーズである。何故マルクス・アウレリウスの本が分かり難いのだろうか、と私なりに考えてみた結果、それは抽象名詞の連発にある、という結論に達した。
古典ギリシャ語というのは、専門家はどういうか知らないが、私個人の感想を述べると、極めて口語的な要素が強い言語である。日本語に喩えて言うと、文章文なのに、『えーっと。。。』、『それでですね、。。。』、『。。。しちゃってさぁ。。。』というような言い方がしょっちゅう出てくる。ひとことでいうと実にしまりのない書き方であるのだ。それに反してラテン語の文章文というのは極めて律儀な書き方をする。つまり無駄が少ない。この理解が正しいという前提で考えてみると母国語がラテン語であるマルクス・アウレリウスは、たとえギリシャ語をバイリンガルのレベルでマスターしているにしろ、習得言語であるギリシャ語で文章を綴るときに彼の母国語の癖が出たのであろうと、私は推察した。
マルクス・アウレリウスのごつごつ感には辟易したのだが、私がギリシャ語の独習を45歳の時に初めた時から、プラトンとこのマルクス・アウレリウスの本はどうしても原典で読んでみたいと念願していたので、途中で何度も放り出したい気持ちになったが、我慢を重ね、3ヶ月かけてようやく読了することができた。その意味でマルクス・アウレリウスのこの『自省録』は私にとっては二重の意味で思い出深い本である。
さて、マルクス・アウレリウスについての思い出話は、この辺りにしていよいよ本題に入ろう。
yu さんの質問を繰り返すと:
『自省録』(岩波文庫・神谷美恵子訳)の第7巻・5節の『指導理性』(ト・ヘーゲモニコン)という言葉は、英語では『directing mind』という極めてシンプル単語で訳されているが原語ではもっと深い意味を持っているのではないか?
まず、この箇所のギリシャ語の原文はと言うと:
kata proskhresin tou emou hegemonikou
であり、岩波文庫の訳では『私の指導理性の助けによって』となっている。また、英語とギリシャ語の対訳本である Loeb Classical Library #58 では『utilize my ruling Reason』と訳されている。ドイツ語の Reclam では『von meiner Geisteskraft unterstuetzt』と訳されている。
(ついでにいうと、この箇所に出てくる、proskhresis(προσχρησισ)という単語は、L&S の希英大辞典(Greek-English Lexicon、以下 L&S)によると、この箇所がこの単語の出典として引用されている。即ち、マルクス・アウレリウス以前のギリシャ人はこの単語を使っていなかったということだ。これが私が難しく感じた『抽象名詞』の一例である。)
さて、問題の το ηγεμονικον(to hegemonikon)であるが、元来 hegemonikon という単語は、英語の hegemony にもなった hegemon に由来している。 hegemon という名詞は hegeomai という動詞の派生語である。 hegeomai とは L&S では、『先に歩く、先導する』(go before, lead the way)というのが原義であると書かれている。それから『指導する』(lead, conduct)という意味が派生したと分かる。
hegeomai についてさらに語源にまで遡って調べてみよう。
Frisk の Griechisches Etymologisches Woerterbuch には次のような記述が見える。『hegeomai, ageomai はラテン語の sagio(追跡する、嗅ぎ付ける)とも関連している』。さらに、英語の語源辞典の金字塔である Skeat の Etymological Dictionary of the English Language の hegemony の項には、『 hegeomai は eg-agon(導く)やラテン語の ag-ere と関連がある。語根は AG(drive)。英語の Agent との関連を見よ』とある。
一方アメリカの大辞典の Webster's Third New International Dictionary, Unabridgedの hegemony の語源欄を見ると、hegeomai(guide, lead)と書かれていて、関連語源として、英語の SEEK が挙げられている。
以上の情報から、次のように結論付けられるだろう。
まず hegeomai というのは、『あちこちと探す』という原義から出発して、『道先を案内する』という単純な意味であったのが、次第に『リーダーとして人を指導して引っ張っていく』という意味が付与された、と言っていいだろう。
さて、hegemonikon の元である hegeomai の意味がそのようであると理解した上で、問題の『ト・ヘーゲモニコン』(to hegemonikon)の項を L&S で調べると次のように書かれている。
『the authoritative part of the soul (reason), especially in Stoic philosophy, Zeno; but also, the governing part of the universe, of the aether or sun, Chrysippus.』
(心の指令的な部分、理性。特にストア派のゼノンの意味。またクリュスッポスでは、宇宙を支配している理性的部分を指す。)
『ト・ヘーゲモニコン』について、この長たらしい説明を一言で訳すと『指導理性』や『ruling Reason』あるいは yu さんの指摘する『directing mind』で良いのではないかといえる。つまり語釈においては『directing mind』で問題がないのであるということだ。
しかし、問題は、『ト・ヘーゲモニコン』(directing mind)というのは何をどこに導いていくのかという語釈を離れた問題が残っている。(yu さんの疑問もこれがメインである。)
私の理解する範囲では、ストア派の根本の考えは、人間には他の動物にない『理性』というものがあり、これを自覚し、その理性の『導く』ところに忠実に従うことで初めて『心の平静』、つまり至福の境地に至ることができる、と言うことだ。この場合の理性(ratio)というのは、日本語でいうと『克己心』という訳がこの場合、一番ぴったりとしているのではないかと思う。つまり、善悪の判断をできる、という知的な部分よりも、濫りに欲望に負けない、あるいは怒りに任せない、という自己統御能力の高い人がストア派が目指す理想像なのである。
この意味で、『ト・ヘーゲモニコン』というのは、自分の外部に存在する指導者や指導理念というのではなく、自己の内部にある良心そのものであるという意味合いを強く持っている単語だと私は解釈したい。



















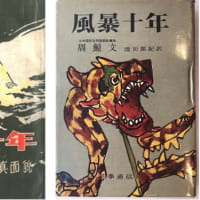








辞書で引くと「rational nature」という言葉が目に留まり、
以前、先生に「nature」についてお教え頂いたことを想い出しました。
沂風詠録:(第37回目)『セネカの本: De Vita Beata』
http://blog.goo.ne.jp/shizuo_asogawa/d/20100207
人間に生まれながら備わっている良心に「克己心」を加えたものとして、
指導理性を理解したいと思います。
これから理性という言葉が出て来た際は、もう少し解って読み進める
ことが出来そうです。
早速に、しかも詳細な説明を伺うことが出来、大変有難く存じます。