私が哲学に興味を抱いたきっかけは、高校時代に漢文の授業で荘子を読んだことであった。人間は自由に考えてよい、という彼の自由精神に触れて、それまで自分を縛っていた規律・規範・束縛は実はクモの網のような単なる形骸的なものに過ぎなかったことに気づかされた。大学に入ってショーペンハウアーを知り、彼の先鋭的な批判精神に惹かれた。そのショーペンハウアーを通じて、ようやく哲学の本丸ともいうべきギリシャ哲学に辿りついた。ディオゲネス・ラエルティオスの『ギリシャ哲学者列伝』(岩波文庫)には日本には決して見られない個性豊かなとがった哲学者が次々と登場する。そういったギリシャ哲学の中でも、私はとりわけプラトンとストアに魅せられたが、それは主として人としての生き方という面に関してであった。
しかしながら、その内にギリシャ哲学本流は形而上学であり、その根本命題は神ならびに物質の存在論であることに気づいた。これはギリシャ哲学が生れてから現在に至るまで一貫して哲学の最重要命題である。二千数百年もの間、一流の哲学者たちはずっとこのテーマに取り組んできたにも拘わらず現在に至るまで、一向に決着がついていない。それどころか、現在の哲学はこの点ではまったく思考停止で、混迷を極めている状態であると思える。この理由について、以前のブログ
沂風詠録:(第199回目)『リベラルアーツとしての哲学(その11)』
では『相対論や量子力学を無視』する点にあると述べた。
現代の哲学の難解な語句や、文体の晦渋さに付け加えて、もう一つの欠点は、存在論(ontology)を議論する上で、時間や空間の概念がニュートン力学から一歩も前進していないことである。 20世紀に入って、相対性理論や量子力学の登場で、時間や空間だけでなく物質の根源に関する認識がそれ以前とは決定的に異なった。つまり、時間や空間は独立して存在しているのではなく、重力場や観察者の移動速度に大きく依存していることが分かった。さらにアインシュタインの有名な式
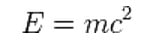
によって、物質の質量とエネルギーは等価だということが明らかになった。また量子力学によると、(素粒子レベルの)物質の存在は(現段階の人間には)確率論的にしかとらえることしかできないことが明らかにされた。つまり、 21世紀の現代の我々にとって、ニュートン力学が描いた世界や物質のあり方がもはや、かつての天動説のように古臭いものとなった。つまり、哲学的に存在論を論じる時に、相対性理論や量子力学に基づかない存在論は意味を失ったと言ってよい。
相対性理論や量子力学などの最新の科学的初見に基づいた存在論に関する哲学的議論は、私の知る限り見たことがない。というのも、最新の科学を理解し、かつ存在論も論じることができるには科学と哲学の両面においてかない高度な知識と能力を必要とするからである。そのような人物はめったに存在しないが、かなり良い線をいっているのが、アメリカ人のローレンス・クラウスである。

ローレンス・クラウスは物理学者でありながら、神の存在を否定するAtheistとして、生物学者のリチャード・ドーキンスとともに神学者たちと数々の激しい論争(debate)を繰り広げていて、その様子はYouTubeで確認できる。ここでいう神学者は欧米の根本宗教のキリスト教徒だけでなく、激烈さではキリスト教より優るイスラム教徒の神学者も含む。ローレンスは、「それまで全能の神でしか作り得ないと言っていた宇宙は、物理現象から自発的に創成されるということを主張している。その内容は、ローレンス・クラウスの著作『宇宙が始まる前には何があったのか?』(文藝春秋)のかなり詳しく書かれている。神学者たちが神の存在を主張するのは、現在の宇宙や生物などが作りだされたこと、言い換えれば、無から有を作りだすのは神にしかできないと信じているからであるが、ローレンスは現代の素粒子論、宇宙物理学から無から有が作りだされることが理論的に説明できると力説する。
この説明の根幹には、量子力学の理論によると、ゆらぎによって確率論的には短時間および微小空間においては、通常の物理現象、(具体的には熱力学法則)を破ることがあるという事実に基づいている。少し大げさにいえば、一片の氷は瞬間的には沸騰して、湯になることもあり得る、あるいは、谷底にあった石が瞬間的には山の頂上を越えて飛んでいくのもあり得るということだ。ただ、その時間幅や空間体積が、微小すぎるため、通常の観測には捕らえられない。しかし、実際に起っていることは、エサキダイオードの作動に見られるような物理現象として捕らえることができる。
この本によるローレンス・クラウスの立論は、多少粗けずりな部分もあるのは已むを得ないにしても、すくなくとも17世紀のニュートン力学を弊衣(へいい)のごとく脱ぎ捨て、20世紀の最新科学である量子力学にのっとって哲学者の虚妄のような存在論を打破している点は壮としなければなるまい。現代の哲学専攻者も彼のような視点をもって議論してくれることを強く望む。それでなければ、哲学・形而上学の未来はないといっていいだろう。
しかしながら、その内にギリシャ哲学本流は形而上学であり、その根本命題は神ならびに物質の存在論であることに気づいた。これはギリシャ哲学が生れてから現在に至るまで一貫して哲学の最重要命題である。二千数百年もの間、一流の哲学者たちはずっとこのテーマに取り組んできたにも拘わらず現在に至るまで、一向に決着がついていない。それどころか、現在の哲学はこの点ではまったく思考停止で、混迷を極めている状態であると思える。この理由について、以前のブログ
沂風詠録:(第199回目)『リベラルアーツとしての哲学(その11)』
では『相対論や量子力学を無視』する点にあると述べた。
=====================
現代の哲学の難解な語句や、文体の晦渋さに付け加えて、もう一つの欠点は、存在論(ontology)を議論する上で、時間や空間の概念がニュートン力学から一歩も前進していないことである。 20世紀に入って、相対性理論や量子力学の登場で、時間や空間だけでなく物質の根源に関する認識がそれ以前とは決定的に異なった。つまり、時間や空間は独立して存在しているのではなく、重力場や観察者の移動速度に大きく依存していることが分かった。さらにアインシュタインの有名な式
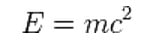
によって、物質の質量とエネルギーは等価だということが明らかになった。また量子力学によると、(素粒子レベルの)物質の存在は(現段階の人間には)確率論的にしかとらえることしかできないことが明らかにされた。つまり、 21世紀の現代の我々にとって、ニュートン力学が描いた世界や物質のあり方がもはや、かつての天動説のように古臭いものとなった。つまり、哲学的に存在論を論じる時に、相対性理論や量子力学に基づかない存在論は意味を失ったと言ってよい。
=====================
相対性理論や量子力学などの最新の科学的初見に基づいた存在論に関する哲学的議論は、私の知る限り見たことがない。というのも、最新の科学を理解し、かつ存在論も論じることができるには科学と哲学の両面においてかない高度な知識と能力を必要とするからである。そのような人物はめったに存在しないが、かなり良い線をいっているのが、アメリカ人のローレンス・クラウスである。

ローレンス・クラウスは物理学者でありながら、神の存在を否定するAtheistとして、生物学者のリチャード・ドーキンスとともに神学者たちと数々の激しい論争(debate)を繰り広げていて、その様子はYouTubeで確認できる。ここでいう神学者は欧米の根本宗教のキリスト教徒だけでなく、激烈さではキリスト教より優るイスラム教徒の神学者も含む。ローレンスは、「それまで全能の神でしか作り得ないと言っていた宇宙は、物理現象から自発的に創成されるということを主張している。その内容は、ローレンス・クラウスの著作『宇宙が始まる前には何があったのか?』(文藝春秋)のかなり詳しく書かれている。神学者たちが神の存在を主張するのは、現在の宇宙や生物などが作りだされたこと、言い換えれば、無から有を作りだすのは神にしかできないと信じているからであるが、ローレンスは現代の素粒子論、宇宙物理学から無から有が作りだされることが理論的に説明できると力説する。
この説明の根幹には、量子力学の理論によると、ゆらぎによって確率論的には短時間および微小空間においては、通常の物理現象、(具体的には熱力学法則)を破ることがあるという事実に基づいている。少し大げさにいえば、一片の氷は瞬間的には沸騰して、湯になることもあり得る、あるいは、谷底にあった石が瞬間的には山の頂上を越えて飛んでいくのもあり得るということだ。ただ、その時間幅や空間体積が、微小すぎるため、通常の観測には捕らえられない。しかし、実際に起っていることは、エサキダイオードの作動に見られるような物理現象として捕らえることができる。
この本によるローレンス・クラウスの立論は、多少粗けずりな部分もあるのは已むを得ないにしても、すくなくとも17世紀のニュートン力学を弊衣(へいい)のごとく脱ぎ捨て、20世紀の最新科学である量子力学にのっとって哲学者の虚妄のような存在論を打破している点は壮としなければなるまい。現代の哲学専攻者も彼のような視点をもって議論してくれることを強く望む。それでなければ、哲学・形而上学の未来はないといっていいだろう。


















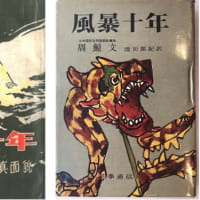








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます