15世紀半ばに始まった大航海時代にオランダは、ポルトガルやスペインよりは後発でありながら、結局は東南アジアにおける香料貿易の独占に成功する。その中心地となったのがバタビア、すなわち現在のインドネシアの首都・ジャカルタである。
この地に、オランダ東インド会社という世界最初(あるいは最初期?)の株式会社が商館を置き、インドネシアの香料の輸出だけでなく、日本へ商品(鹿皮など)を盛んに輸出していた。貿易の様子は、『バタビア城日誌』という日記に克明に記録されていたようだ。その抄訳が平凡社東洋文庫(村上直次郎・訳)から3冊本で出版されている。流石に、「 Dutch Account」と言われるように、経済的観念が発展していた(?)オランダ人だけあって、きちんとした数字が載せられている。
きちんとした数字と言えば、日本史の専門家はかなり数字にうるさい人が多いようだ。特別に調べた訳ではないが、日本史関連の本を読んでいると、時々、妙に細かい数字が出てきて驚くことがある。今、たまたま手近にある本で、2例を示そう。
例1:室町時代の米価の変動
「…米価の値動きは激しい。…応永21年(1414年)の10月には石当たり639文、11月には677文、それが翌年の2月には752文と、1.18倍の値上がりとなっている。…しかも米価の地域による差は激しい。…応永20年12月、矢野庄米価、石当たり654文、同年、京都937文で、1.43倍、応永 21年11月、矢野庄米価677文、京都952文で、1.4倍である。」
(出典:『室町時代』P.125、中公新書 脇田晴子)
例2:九州、湯布院の庄屋の姓
「大友軍として文禄の役に参陣した者を記す『豊後侍着到記』によると、「湯布院衆」は 23人いる。その姓は、右田7人、荒木7人、怒留湯3人、厚2人、幸野1人、八坂1人、白仁1人、針1人であり、江戸期における庄屋の姓(荒木、幸野、溝口、立川、日野、衛藤、田中、伊美、種木、阿南、新谷など)と大幅に違っている。」
(出典:『逃げる百姓、追う大名』P.92、中公新書、宮崎克則)
後者の『逃げる百姓、追う大名』には、これ以外にもっと細かい数字が記載されている個所がある。例えば「並柳村の本田畑・新地・年貢合計」( P.99)という表には、実に、7桁もの数字がずらりと並ぶ!例えば、慶長10年からの並柳村の年貢の合計は、次のように細かい数値が記されている。
28石48921、29石91969、32石55213、87石3688、74石82224、120石52011…
私にはこのような詳細な数字は、あまり重要ではないように思えるが、筆者たちは、正確な数字を挙げることは意味があると考えているようだ。

正確な数値の最たるものは、1533年にスペイン人・ピサロがインカ王・アタワルパから奪い取った身代金を計算した数字だ。岩波新書に『インカ帝国』(泉靖一)という本があるが、P.257には身代金が「30億395万520円」と示されている。これは、筆者が勝手に妄想した数字ではなく、身代金として集められた金の重量に、執筆当時(1959年、昭和34年)の1オンス( 28グラム)の金の値段、1万2627円を掛けて産出した額である。
このような細かい数値まで出す理由は果たしてあるのだろうか?
問題点は、まず当時(1533年)インカ帝国にグラム単位まで正確に測定できる秤があったかどうかだ。当然のことながらなかったはずだ。2番目に、金の値段は常に流動的であるということだ。執筆当時の 1959年だけでなく、現在でも金の価格は日々流動している。他にも要因はいろいろとあるが、この計算においては、正確な数字を使うことには全く意味がないことは明らかだ。
このような計算をする場合、「有効数字」という概念が役に立つ。簡単な例でいうと、スーパーで大根を買う時、200円より、10円でも安いと、安いと感じる。一方、車を買う時、 200万から1万円程度値引きされても全く安いと思わない。10万円ならなんとか安いと思うだろう。このように、金額の絶対額では、片や10円、片や10万円と随分異なるが、実はどちらも同じ感覚で判断しているのだ。この場合、どちらも有効数字が2ケタ(大根 20x円、車 2,0xx,xxx円)であり、それ以下の数字、つまり x の数字は意味をなさないのだ。
これからすると、インカ王・アタワルパの身代金を一円単位まで出す必要がなく、大体、 30億円程度と示すのが合理的である。さらに、この30億円という額は、1959年当時の物価で計算しているが、現在(2018年)の価値に直すと、金1グラムが4700円位なので1オンスが13万円、この結果、身代金は300億円程となる。ざっと金塊6トン分だ。
本論からは離れるが、話のついでに、国王の身代金として300億円がどの程度のものなのか考えてみよう。
元日本金属工業常務で、金属考古学、計量史が専門の新井宏氏は、「欧州通貨と巨額な身代金」という文をWebで公開している。
そこでは、4人の例を挙げているが、金貨はだいたい4グラムの金を含むので、(2018年の現在価値で)金貨一枚を 2万円と見て、私が計算したところ次のようになる。
1.リチャード獅子王 = 15万マルク = 120億円
2.フランス王の聖ルイ九世 = 50万リーブル = 50億円
3.フランス王フランソワ一世 = 40万デュカート = 80億円
4.カテリーナ・スフォルツァ伯爵夫人 = 2.5万デュカート = 5億円
これらの値と比較すると、インカ王・アタワルパの300億円は途方もなく高いと言える。それだけでなく、アタワルパの場合は、ついでに銀も奪取された。金は一部屋一杯の分量だが、銀は二部屋一杯の分量だった。歴史的に銀は金の1/10の値段が相場であったので、二部屋分の銀は60億円と見積もれる。結局、インカ王・アタワルパの身代金は〆て360億円ということになる。
新井宏氏の文章に、歴史的な金の価値について次のような貴重な指摘が見える。
「いつの時代、どの地域でも、金1グラムで買える米や小麦粉の重量は、ほぼ20キロ程度。今でも国際的に見れば、大体そんなところであろうか。簡単なことなので、ぜひ覚えておくと良いと思う。 」
【閑話休題】
さて、理科系では、さまざまな数値情報を整理して、本質的特徴を捕まえるために、有効数字やオーダー(Order=桁)という概念を使うが、ここで指摘したように、(一部の?)歴史学者にはそういった根本的な概念が欠如している。それがひいては、現在の教育をゆがめているように私には思える。つまり、正確な数値を覚えることが正しくて、アバウトな数値を知っていることはダメだと考えていることだ。
たとえば、歴史の試験で答案用紙に「。。。という事件が起きたのはだいたい1400年ごろ」では ×(罰点)だ。しかし、一旦、社会にでればアバウトな数値は氾濫している。例えば、ビールなどの消費量ではたいてい「今年は東京ドーム X杯分のビールが飲まれた」と報道している。これも正確を期すなら、ビール瓶、ビール缶、ビール樽の出荷本数にそれぞれの容積を掛けるとミリリットル単位で正しい値を得ることができるがが、誰もそのようかことを求めない。東京ドームの容量(大きさ)を正確に知らなくても、「何杯分」と聞いた途端に、イメージが頭の中に浮かんでくる。

つまり記憶に残すためには、アバウトなデータからイマジネーションを膨らませて覚える方が有効であるのだ。例えば、江戸時代にオランダ人が長崎の出島に滞在していたが、そのサイズは次のようである。
長崎の出島 = 70m x 190-233 m
縦は:東側、西側ともに約70m
横は:北側約190m、南側約233m、周囲約 563m
総面積は約1万5千平方メートル。
さて、この数字は正確ではあるものの、はたして記憶に長く残るのだろうか?
私は、子供のころから記憶力には自信がなく、このような細かい数値などは全く覚えておくことができない。それで、私は自分ではこのような場合次のようなプロセスに分解にして覚えることにしている。
1.全体の形は扇型
2.縦・横は 100m x 200m
3.但し、若干これよりも小さい
4.面積は、東京ドームの1/3
まず、数値を含まず、ざっくりと全体の形(扇型)を捕える。ついで、縦横の長さの細かな数字は全て端折って、100m x 200m と覚える。つまり、私の記憶における出島の大きさに関する有効数字は1桁である。ただ、これだと計算した面積は2万平方メートルと本当の数字より大きくなるので、「少し小さい目」と覚える。最後に、イメージ的に、東京ドームを引き合いにして覚えておく。このように数段階に分解するのは、一見、複雑なようでも、この方がすっきりと理解でき、長く記憶に残る。
皆さんの学生時代を思い返してほしい。歴史などでは年代の細かい数字まできちんと覚えたとしても、試験が終わればすぐに忘れてしまっていたはずだ。確かに細部まできちんと覚えるとテストの点は良いかもしれないが、本質を掴んでいない限り、細部にこだわった記憶は意味を為さない。一方、ざっくりとでもいいが、わしづかみに要点をつかんだ方がはるかに記憶に長く残る。
私は、現在の教育の一番の阻害要因は、あまりにも細部にこだわる点だと思っている。それが典型的に現れているのが、大学入試のセンター試験だ。そこでは、正確な知識でないものは一顧だにされない。センター試験で高得点を取るために教師も生徒も何でもかんでも「正確」に覚えようと必死になっている。こっけいなのは、英語の問題で、正しい発音記号を覚えていて満点でも、いざ話すとなると、全くでたらめな発音という人もいることだ。
日本人の利点として、細部にまでわたるこだわる几帳面さが挙げられる。それは、「この道一筋」とか「一意専心」という単語で表わされているような職人気質だ。ただ、この面が行き過ぎると、いわば「木を見て森を見ず」というような視野狭窄に陥る。あるいは、正確さや完璧な出来栄えを最高の価値のあるものと見なし、ささいな欠点(瑕疵)でもあるとすべて減点する風潮ともつながっている。私は日本の利点を認めるには吝かではないが、グローバル社会では必ずしも日本の価値観がそのまま通用しないことも知っている。今後、グローバルで活躍する日本人はこの点に注意してほしいと願うものだ。
【参照ブログ】
【麻生川語録・14】『20倍違うと世界が違って見える』
この地に、オランダ東インド会社という世界最初(あるいは最初期?)の株式会社が商館を置き、インドネシアの香料の輸出だけでなく、日本へ商品(鹿皮など)を盛んに輸出していた。貿易の様子は、『バタビア城日誌』という日記に克明に記録されていたようだ。その抄訳が平凡社東洋文庫(村上直次郎・訳)から3冊本で出版されている。流石に、「 Dutch Account」と言われるように、経済的観念が発展していた(?)オランダ人だけあって、きちんとした数字が載せられている。
きちんとした数字と言えば、日本史の専門家はかなり数字にうるさい人が多いようだ。特別に調べた訳ではないが、日本史関連の本を読んでいると、時々、妙に細かい数字が出てきて驚くことがある。今、たまたま手近にある本で、2例を示そう。
例1:室町時代の米価の変動
「…米価の値動きは激しい。…応永21年(1414年)の10月には石当たり639文、11月には677文、それが翌年の2月には752文と、1.18倍の値上がりとなっている。…しかも米価の地域による差は激しい。…応永20年12月、矢野庄米価、石当たり654文、同年、京都937文で、1.43倍、応永 21年11月、矢野庄米価677文、京都952文で、1.4倍である。」
(出典:『室町時代』P.125、中公新書 脇田晴子)
例2:九州、湯布院の庄屋の姓
「大友軍として文禄の役に参陣した者を記す『豊後侍着到記』によると、「湯布院衆」は 23人いる。その姓は、右田7人、荒木7人、怒留湯3人、厚2人、幸野1人、八坂1人、白仁1人、針1人であり、江戸期における庄屋の姓(荒木、幸野、溝口、立川、日野、衛藤、田中、伊美、種木、阿南、新谷など)と大幅に違っている。」
(出典:『逃げる百姓、追う大名』P.92、中公新書、宮崎克則)
後者の『逃げる百姓、追う大名』には、これ以外にもっと細かい数字が記載されている個所がある。例えば「並柳村の本田畑・新地・年貢合計」( P.99)という表には、実に、7桁もの数字がずらりと並ぶ!例えば、慶長10年からの並柳村の年貢の合計は、次のように細かい数値が記されている。
28石48921、29石91969、32石55213、87石3688、74石82224、120石52011…
私にはこのような詳細な数字は、あまり重要ではないように思えるが、筆者たちは、正確な数字を挙げることは意味があると考えているようだ。

正確な数値の最たるものは、1533年にスペイン人・ピサロがインカ王・アタワルパから奪い取った身代金を計算した数字だ。岩波新書に『インカ帝国』(泉靖一)という本があるが、P.257には身代金が「30億395万520円」と示されている。これは、筆者が勝手に妄想した数字ではなく、身代金として集められた金の重量に、執筆当時(1959年、昭和34年)の1オンス( 28グラム)の金の値段、1万2627円を掛けて産出した額である。
このような細かい数値まで出す理由は果たしてあるのだろうか?
問題点は、まず当時(1533年)インカ帝国にグラム単位まで正確に測定できる秤があったかどうかだ。当然のことながらなかったはずだ。2番目に、金の値段は常に流動的であるということだ。執筆当時の 1959年だけでなく、現在でも金の価格は日々流動している。他にも要因はいろいろとあるが、この計算においては、正確な数字を使うことには全く意味がないことは明らかだ。
このような計算をする場合、「有効数字」という概念が役に立つ。簡単な例でいうと、スーパーで大根を買う時、200円より、10円でも安いと、安いと感じる。一方、車を買う時、 200万から1万円程度値引きされても全く安いと思わない。10万円ならなんとか安いと思うだろう。このように、金額の絶対額では、片や10円、片や10万円と随分異なるが、実はどちらも同じ感覚で判断しているのだ。この場合、どちらも有効数字が2ケタ(大根 20x円、車 2,0xx,xxx円)であり、それ以下の数字、つまり x の数字は意味をなさないのだ。
これからすると、インカ王・アタワルパの身代金を一円単位まで出す必要がなく、大体、 30億円程度と示すのが合理的である。さらに、この30億円という額は、1959年当時の物価で計算しているが、現在(2018年)の価値に直すと、金1グラムが4700円位なので1オンスが13万円、この結果、身代金は300億円程となる。ざっと金塊6トン分だ。
本論からは離れるが、話のついでに、国王の身代金として300億円がどの程度のものなのか考えてみよう。
元日本金属工業常務で、金属考古学、計量史が専門の新井宏氏は、「欧州通貨と巨額な身代金」という文をWebで公開している。
そこでは、4人の例を挙げているが、金貨はだいたい4グラムの金を含むので、(2018年の現在価値で)金貨一枚を 2万円と見て、私が計算したところ次のようになる。
1.リチャード獅子王 = 15万マルク = 120億円
2.フランス王の聖ルイ九世 = 50万リーブル = 50億円
3.フランス王フランソワ一世 = 40万デュカート = 80億円
4.カテリーナ・スフォルツァ伯爵夫人 = 2.5万デュカート = 5億円
これらの値と比較すると、インカ王・アタワルパの300億円は途方もなく高いと言える。それだけでなく、アタワルパの場合は、ついでに銀も奪取された。金は一部屋一杯の分量だが、銀は二部屋一杯の分量だった。歴史的に銀は金の1/10の値段が相場であったので、二部屋分の銀は60億円と見積もれる。結局、インカ王・アタワルパの身代金は〆て360億円ということになる。
新井宏氏の文章に、歴史的な金の価値について次のような貴重な指摘が見える。
「いつの時代、どの地域でも、金1グラムで買える米や小麦粉の重量は、ほぼ20キロ程度。今でも国際的に見れば、大体そんなところであろうか。簡単なことなので、ぜひ覚えておくと良いと思う。 」
【閑話休題】
さて、理科系では、さまざまな数値情報を整理して、本質的特徴を捕まえるために、有効数字やオーダー(Order=桁)という概念を使うが、ここで指摘したように、(一部の?)歴史学者にはそういった根本的な概念が欠如している。それがひいては、現在の教育をゆがめているように私には思える。つまり、正確な数値を覚えることが正しくて、アバウトな数値を知っていることはダメだと考えていることだ。
たとえば、歴史の試験で答案用紙に「。。。という事件が起きたのはだいたい1400年ごろ」では ×(罰点)だ。しかし、一旦、社会にでればアバウトな数値は氾濫している。例えば、ビールなどの消費量ではたいてい「今年は東京ドーム X杯分のビールが飲まれた」と報道している。これも正確を期すなら、ビール瓶、ビール缶、ビール樽の出荷本数にそれぞれの容積を掛けるとミリリットル単位で正しい値を得ることができるがが、誰もそのようかことを求めない。東京ドームの容量(大きさ)を正確に知らなくても、「何杯分」と聞いた途端に、イメージが頭の中に浮かんでくる。

つまり記憶に残すためには、アバウトなデータからイマジネーションを膨らませて覚える方が有効であるのだ。例えば、江戸時代にオランダ人が長崎の出島に滞在していたが、そのサイズは次のようである。
長崎の出島 = 70m x 190-233 m
縦は:東側、西側ともに約70m
横は:北側約190m、南側約233m、周囲約 563m
総面積は約1万5千平方メートル。
さて、この数字は正確ではあるものの、はたして記憶に長く残るのだろうか?
私は、子供のころから記憶力には自信がなく、このような細かい数値などは全く覚えておくことができない。それで、私は自分ではこのような場合次のようなプロセスに分解にして覚えることにしている。
1.全体の形は扇型
2.縦・横は 100m x 200m
3.但し、若干これよりも小さい
4.面積は、東京ドームの1/3
まず、数値を含まず、ざっくりと全体の形(扇型)を捕える。ついで、縦横の長さの細かな数字は全て端折って、100m x 200m と覚える。つまり、私の記憶における出島の大きさに関する有効数字は1桁である。ただ、これだと計算した面積は2万平方メートルと本当の数字より大きくなるので、「少し小さい目」と覚える。最後に、イメージ的に、東京ドームを引き合いにして覚えておく。このように数段階に分解するのは、一見、複雑なようでも、この方がすっきりと理解でき、長く記憶に残る。
皆さんの学生時代を思い返してほしい。歴史などでは年代の細かい数字まできちんと覚えたとしても、試験が終わればすぐに忘れてしまっていたはずだ。確かに細部まできちんと覚えるとテストの点は良いかもしれないが、本質を掴んでいない限り、細部にこだわった記憶は意味を為さない。一方、ざっくりとでもいいが、わしづかみに要点をつかんだ方がはるかに記憶に長く残る。
私は、現在の教育の一番の阻害要因は、あまりにも細部にこだわる点だと思っている。それが典型的に現れているのが、大学入試のセンター試験だ。そこでは、正確な知識でないものは一顧だにされない。センター試験で高得点を取るために教師も生徒も何でもかんでも「正確」に覚えようと必死になっている。こっけいなのは、英語の問題で、正しい発音記号を覚えていて満点でも、いざ話すとなると、全くでたらめな発音という人もいることだ。
日本人の利点として、細部にまでわたるこだわる几帳面さが挙げられる。それは、「この道一筋」とか「一意専心」という単語で表わされているような職人気質だ。ただ、この面が行き過ぎると、いわば「木を見て森を見ず」というような視野狭窄に陥る。あるいは、正確さや完璧な出来栄えを最高の価値のあるものと見なし、ささいな欠点(瑕疵)でもあるとすべて減点する風潮ともつながっている。私は日本の利点を認めるには吝かではないが、グローバル社会では必ずしも日本の価値観がそのまま通用しないことも知っている。今後、グローバルで活躍する日本人はこの点に注意してほしいと願うものだ。
【参照ブログ】
【麻生川語録・14】『20倍違うと世界が違って見える』



















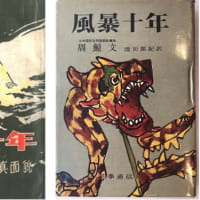








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます