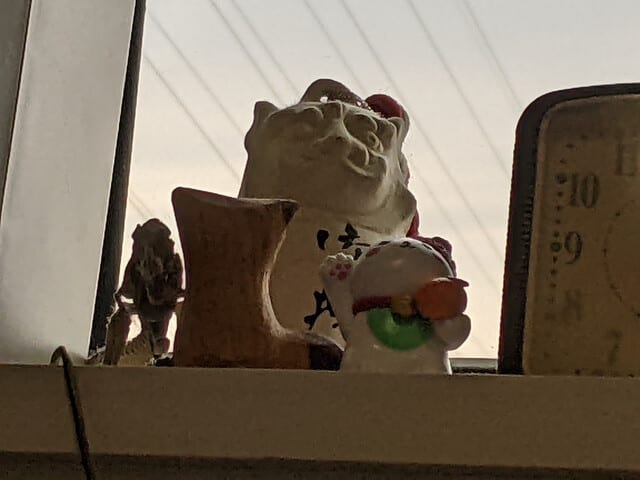コウノトリをからかわなかった子に、赤ちゃんをつれていってやりましょう。その子たちはいい子だったからね。」
コウノトリをからかわなかった子に、赤ちゃんをつれていってやりましょう。その子たちはいい子だったからね。」
「じゃ、まっ先にうたいはじめた、あの悪い、いじわるの子は?」と、若いコウノトリたちは言いました。
「僕たち、あの子はどうしてやりましょう?」
「そのお池にはね、死んだ夢を見て死んでしまった赤ちゃんもいるから、それをあの子のところへ持っていってやりましょう。死んだ小さい弟を持って行くんだもの、あの子はきっと泣きだしてしまうでしょう。だけど、ほら、あのいい子のこと、おまえたちも忘れはしないでしょう?生きものをからかうのはよくないことだ、と言った、あのいい子には、小さい妹と弟とを持っていってやりましょう。そして、あのいい子はペーターという名前だから、おまえたちもみんな、ペーターと呼ぶことにしましょうね。」
こうして、なにもかも、お母さんの言ったとおりになりました。 それで、コウノトリはみんなペーターという名前になり、今でも、そう呼ばれているのですよ。
――「コウノトリ」(大畑末吉訳)
さきほどNHKの「プロジェクトX」で、神戸の高齢パンダの介護番組をやってた。心臓病にかかった神戸の高齢のメスパンダ(おいしいササや林檎しか食べないという人間だったら嫁のもらい手がいないやつである)の健康診断や腹水を抜く治療の奮闘記である。あまりにグルメなパンダなので、粉ミルクと林檎ジュースをまぜた小学生が喜びそうな液体を舐めるのに夢中にさせておいて、腹部から水をぬくという世界初の治療が行われた。おかげでこのメスパンダ、人間でいえば100歳ぐらい生きたそうだ。
しかし、死んだパンダの献花台で号泣するひとたちをみてて、ジュースに依存して苦しみを忘れるパンダと我々が似ていることは勿論、――昔からわれわれは獣と一緒に暮らしてたわけだからもうそういう生活に戻らないと情緒不安定できついんじゃねえかな、まじめなはなし――と思った。
パンダの気持ちはわからないが、我々の死生観がどこまでも死への恐怖が生を萎縮させる馬鹿馬鹿しい状況になっており、多く行きのこるのが正義みたいな、戦時中の、多く死ねば正義、をひっくり返しただけの思想が猛威をふるっている。人が死ぬことを人だけで考えているからおかしなことになるのではなかろうか。ハイデガーでさえ、石とかミツバチと比べて議論をしていたというに。思春期までの体験として、人の死を体験するのが大事とかはよく言われるけど、つまり、――たくさんの動物を看取る経験の上に必要とすべきじゃないかと思う。人の死に対する思考は単独では何処に飛んでいくか分からないものでまったくもって観ていられないというのが、人の歴史ではなかろうか。大衆も、左右どちらも、例えば「犬死」に観念に、実際の犬の死が全く入り込んでいない。
しかしそれは、必ずしも即物的な体験のことではなく、「犬死」における文学的な処理問題である。
戦争責任を問われて
その人は言った
そういう言葉のアヤについて
文学方面はあまり研究していないので
お答えできかねます
思わず笑いが込みあげて
どす黒い笑い吐血のように
噴きあげては止り また噴きあげる
三歳の童子だって笑い出すだろう
文学研究果さねばあばばばばとも言えないとしたら
四つの島
笑ぎに笑ぎてどよもすか
三十年に一つのとてつもないブラック・ユーモア
野ざらしのどくろさえ
カタと笑ったのに
笑殺どころか
頼朝級の野次ひとつ飛ばず
どこへ行ったか散じたか落首狂歌のスピリット
四海波静かにて
黙々の薄気味わるい群衆と
後白河以来の帝王学
無音のままに貼りついて
ことしも耳すます除夜の鐘
茨木のり子の「四海波静」でも扱われている、昭和天皇の「戦争責任」を「言葉のアヤ」「文学方面」に帰する例の発言についてはいろいろ研究があるんだろうが、天皇みずから、戦争責任については、政治や科学でなく、むろん責任者自身でもなく、文学方面で決着していいとの発言であり、むしろ我々にとってよろこぶべき事態である。戦後の文学的戦争責任論争の泥仕合が存在を認められたわけである。
茨木のり子は天皇の発言にびっくりしたのではなく、そこには、野ざらしの髑髏がバックの合唱隊の唸りのようにきこえているのである。それは、戦前から何も変わらないもの除夜の鐘となる。こういう人ことでないと、人は簡単に、責任と罪を分離し、戦後を謳歌できた。かかる転向犯罪者は多く、例えば、敗戦を境に価値観がひっくり返って大人たちの反対のことを言い出したというおきまりの言い方への信仰もその者達を勇気づけた。しかし、彼らは別に普遍的な何かを見たのではなく、特に学校でそれを感じた世代があったんだろうと思う。事実、価値観が文字通り「ひっくり返った」ことはないからだ。ひっくり返ったような言い方をせざるを得ないのは教育的な現場だ。いまもそうである。大岡信が茨木のり子との対談(岩波文庫『茨木のり子詩集』)で言っていたけど、その「ひっくり返った」勢いがちょうど15歳ぐらいだった連中は青春として体験されたが、茨木のような上の世代はそうではないと。わたくしの小学校のときの担任は、敗戦の時に小学校高学年で大江健三郎の世代。すると、戦後の解放と言うより、元軍人の先生とかへの恐怖みたいなものの体験が印象に残ってると言ってた。大江の小説にもそういう要素がある。だからこそ、大江の戦後は、リアルなのである。