カンザス州西部の小麦畑がひろがる小高い平原に位置するホルカム村。
1959年11月、ホルカム村のリヴァーヴァレー農場主のハーバード・ウィリアム・クラッター(48歳)と妻のボニ―(45歳)娘のナンシー(16歳)息子のケニヨン(15歳)の4人が手足を縛られた上に、至近距離から猟銃で撃たれて死亡するという事件が起こる。
2人組の犯人は逮捕され、死刑になる。
これは、実際にあった事件を作者が取材をして書いたノンフィクション小説。
「冷血」と「カポーティ」の名前は前から知っていた。それは書評などで目にすることが多かったから。
しかし、実際の内容も、昨年「カポーティ」の映画が上映されたことも知らず、ほとんど何も知らずに読んだ。
登場人物を丁寧に書いているので、その心情がとても良く伝わってくる。
読んでいて1番感じたのは、なんの落ち度もないのに命を絶たれてしまった、クラッター家の無念さだった。
現代もそうだが、殺人事件や過失致死事件が起こった時、大事にされているのは今を生きている命で、死んでしまった命のことがあまり考えられていないということ。
加害者の二人、ペリー・スミスとディック・ヒコックを殺人者にさせた理由は、幼い頃の育てられかたや事故による後遺症や、確かに色々あると思う。
実際に接することで同情心が沸き起こるのも分かる気がするが、そんな時は死んでしまった人達のことは考えていないのだろうと思う。
生きていることに、多少でも喜びを見せ、生きる方法を探るペリーやディックに対して自分は苛立ちを感じた。
死刑に賛成か反対かと言われると、冤罪ということもあるので、なんともいえなくなってしまうが、犯した罪は償わなくてはならないと思う。
少なくても、精神鑑定で責任能力がないと判断され、短期間に社会に戻ることには反対だ。
責任能力云々よりも、殺したという事実の方が重いだろう。
「目には目を、歯には歯を」は適切なのではないかという気もする。しかしそれを判断するのが、間違いを犯す人間というのが難しい。
1959年11月、ホルカム村のリヴァーヴァレー農場主のハーバード・ウィリアム・クラッター(48歳)と妻のボニ―(45歳)娘のナンシー(16歳)息子のケニヨン(15歳)の4人が手足を縛られた上に、至近距離から猟銃で撃たれて死亡するという事件が起こる。
2人組の犯人は逮捕され、死刑になる。
これは、実際にあった事件を作者が取材をして書いたノンフィクション小説。
「冷血」と「カポーティ」の名前は前から知っていた。それは書評などで目にすることが多かったから。
しかし、実際の内容も、昨年「カポーティ」の映画が上映されたことも知らず、ほとんど何も知らずに読んだ。
登場人物を丁寧に書いているので、その心情がとても良く伝わってくる。
読んでいて1番感じたのは、なんの落ち度もないのに命を絶たれてしまった、クラッター家の無念さだった。
現代もそうだが、殺人事件や過失致死事件が起こった時、大事にされているのは今を生きている命で、死んでしまった命のことがあまり考えられていないということ。
加害者の二人、ペリー・スミスとディック・ヒコックを殺人者にさせた理由は、幼い頃の育てられかたや事故による後遺症や、確かに色々あると思う。
実際に接することで同情心が沸き起こるのも分かる気がするが、そんな時は死んでしまった人達のことは考えていないのだろうと思う。
生きていることに、多少でも喜びを見せ、生きる方法を探るペリーやディックに対して自分は苛立ちを感じた。
死刑に賛成か反対かと言われると、冤罪ということもあるので、なんともいえなくなってしまうが、犯した罪は償わなくてはならないと思う。
少なくても、精神鑑定で責任能力がないと判断され、短期間に社会に戻ることには反対だ。
責任能力云々よりも、殺したという事実の方が重いだろう。
「目には目を、歯には歯を」は適切なのではないかという気もする。しかしそれを判断するのが、間違いを犯す人間というのが難しい。
















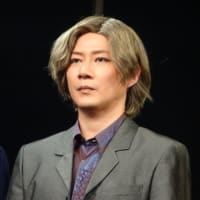
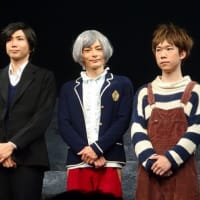









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます