
ドラマ「太陽にほえろ!」(日本テレビ系)の「ジーパン刑事」役に端を発し、以後、映画「野獣死すべし」、ドラマ「探偵物語」(日本テレビ系)などへの出演によって、一癖も二癖もあるハードボイルド・アウトロー路線を突き進み、カリスマ的な人気を獲得していた松田優作。役者としてまさに人気絶頂にあったこの時期、優作さんは、突如、78年のアルバム「Uターン」のリリース以来遠ざかっていた、ミュージシャンとしての活動を本格的に再開することを宣言。新作シングル・アルバムの製作、そして初の大々的なライブツアーを敢行する事を明らかとし、その間は俳優としての活動は最大限セーブする方針を打ち出します(この点はこのヒットスタジオ出演時の司会者との歌に入る前のトークの中でも触れられています)。この方針に従い、ヒットスタジオにもプロモーション活動の一環という意味合いで、元・ゴールデンカップスのエディ藩率いる彼の演奏グループ(エディ藩グループ)をバッグに従えて登場する事となりました。
このヒットスタジオ出演時に披露されたのはアルバム「TOUCH」から「YOKOHAMA HONKY TONK BLUES」と同アルバムからのシングルカット作「白昼夢」、そしてライブツアーの主要ナンバーとして採譜したラリー・ウィリアムスの「BONY NORONIE」の3曲。各曲約2分ずつ、計6分弱に及ぶ、月曜1時間時代のヒットスタジオとしては異例の長さでした。当時からテレビ番組で滅多に歌を歌うことがなかった優作さんに、思う存分歌える環境を与えようとした当時のスタッフの彼に対する配慮が、その演奏時間の長さにも垣間見えてきますし、この当時の他の同世代俳優とは明らかな「別格」ぶりも分かろうというものです。
さて、このシーン、私はヒットスタジオ史上屈指ともいえる「人間的」で、また、以前どこかの記事でも書いた事ですが、「歌を演じるとはかくあるべき」を地で行く良質のステージングだったと思っております。
一見、このシーンだけを抜き出してみると、既定のヒットスタジオのイメージとはかけ離ている印象を受けますが、あえて既成の番組カラーを排する演出を取ったことが、このシーンの印象をより際立たせていたという感がしてきます。
また、本職は役者であるということもあって、彼自身の中にも恐らく歌というものは「歌う」のではなく芝居と同じであくまでも「演ずる」ものであるという理解がきっとあったのだろうと思います。カーリーヘアにサングラス、無精髭。光沢のある茶色のスーツに黒いシャツという「ダーク」な風貌。ハスキーで迫力的なボーカルを聞かせ、その場にいた出演者・スタッフらの心までをも掌握してしまう、その圧倒的な存在感。さながら、「野獣死すべし」「蘇える銀狼」などで演じた狂気と人間臭さに溢れた男をそのまま歌の中でも演じきっているのではないか?という想いさえさせてくれる。そんな「危険な香り」がする印象的な場面でした。
1曲目の「YOKOHAMA HONKY TONG BLUES」、2曲目の「白昼夢」では、マイクスタンドを持ちながら前かがみの姿勢でブルースを歌い上げるその姿に、虚無感漂う空間の中で、無表情の奥にどこか、反社会的な行動をも肯定してしまうような、危険でまた人間的な魅力もある男の「日常」が、そしてラストの「BONNY MORONIE」では、それまでとは一転して、片手に持ったタンバリンを激しく叩きながら歌うその姿に、その男の「非日常」=「直情的ともいえる欲望の発散」が連想される。
しかしながら、それが全く100%演技であるというわけではなく、どこかに、彼自身もこのステージの中で演じている男を許している、同情している、自らのライフスタイルに通ずるものを感ずる、といった感情を抱きながらの歌唱であったとも見て取れる気がします。この部分に「歌を演じること」の真骨頂を見たように私は思いました。
彼は生い立ちから色々と複雑なところがあったようで、また時に仲間と意見が対立するときは喧嘩沙汰となることも結構多かったと聞きます。ある種の「現状・体制・権力」に対するアレルギー、というものが実際にあったのだろうと。それ故に、「演技」にもそういったリアリティ、或いは「無法なことが広く許容されている」という、その役柄に対するある種の憧憬がどこかしらに見え隠れしていたのだろうと思います。
役者というのは、単に台本どおり演じるだけが能ではありません。それなら本職俳優でなくても芸人であっても歌手であってもできる事です。
本物の役者というものは、私が考えるには、与えられた役柄の人物に対して、ストイックなまでに、今までの自己の経験・思想・生活を照らし合わせながら、肯定・否定、或いは畏敬・軽蔑の念というものを抱き、自分なりの人物像を形成した上で、自らの姿・声を通じてその人物を「血の通った」存在へと昇華させてゆける、そういう表現のプロフェッショナルであるべきです。
残念ながら今の日本の人気俳優の中ではそういった「本物の役者」はなかなかいないように思います(単に私があまり今のドラマ等をみないからかもしれないですが・・・)。その意味でも、今でも、数少ない「プロフェッショナル」だった優作さんが、役者の世界のトップリーダーとして活躍していてくれたら・・・という思いがする次第です。
彼が亡くなった直後のヒットスタジオで、このシーンのノーカット再放送が行われましたが、その際、当時の司会者だった加賀まりこは彼の何人にも変え難いその才能を惜しみ、号泣しながら哀悼のコメントを述べると同時に、「芸能界という世界はこういう非凡な才能ある人をすぐに殺してしまう」という持論を述べていたのがとても衝撃的でもありました。
もしそれがリアルな表現であるとするならば、残念ながら日本のエンターテイメント界では一生「本物のプロ」と呼べる存在は育たない。つまり「本物」が異端として排除される、とても閉鎖的で、必要のない「馴れ合い」の世界が日本のエンタ界の実体なのだろうと・・・。加賀さんがどういう真意で述べたものかは分からないのですが、そういう意見をいわば「内輪」の人でお持ちの人がいるということは、多かれ少なかれ、そういった部分があるということなのだろうと・・・。彼女の言葉はいわば一種のそういう部分に対する「警鐘」であり、また優作さんの姿を見て、もっとストイックに芸に打ち込んで欲しい、という「願い」もあったのかもしれません。毒舌も多く、あまり番組司会者としてはどうか・・・と思うところも多かった加賀さんですが、この言葉には説得力を感じたものです。この優作さんの唯一の出演シーンに遭遇するたびにいつも、加賀さんの上の言葉がセットで私は思い浮かんできます。
<当日披露した曲目の補足、及び松田優作さんの経歴については、「同項目<2> 補足」を参照の事>
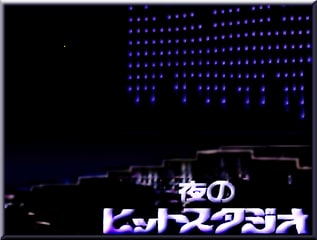











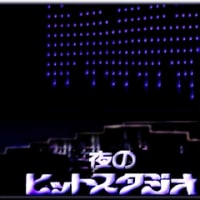
最近でもCSでの再放送などで久々に観る機会にも恵まれ懐かしさに耽っておりました。
ワタクシ個人的なる感想から言えば、当時は彼の演技や歌はショーケンの後追い、二番煎じ的なる部分が垣間見られ、演技、歌共にそれほど感動的なるイメージは殆どありませんでした。
後年は確かに良い役者に成長していったと思います。
resisitance-kさんが仰る通り、>「歌を演じるとはかくあるべき」を地で行く良質のステージング・・だったとは思います。しかし、この当時に受けた印象は70年代後半に既にそのような表現でステージをこなしていた萩原健一そのものであり、又ヘアースタイル、無精髭、スーツに黒シャツ、細めのタイなどのダークな風貌もショーケンそのままであるという印象しかありませんでした。
それにこの当時以前から松田優作はショーケンの物真似という有り難くない評価が付いて回っておりました。
松田優作の唄、演技、パフォーマンスはどれも素晴しいものである事には間違いありませんが、評価は分かれると思いますが、如何せんショーケンの後追いでしかないというのが当時の感想です。
松田優作はワタクシも大好きな役者の一人でもあります。このような風貌やハードボイルドな役柄から脱皮したあたり・・映画「家族ゲーム」あたりになるのでしょうか、よく判りませんが、それ以降からが「本物」の役者になってきたなぁというのがワタクシの個人的なる感想でもあります。
彼の場合は若くしての「死」というものが、彼自身を半ば伝説化している部分が年月とともに増大していっている感さえあるようにも思えてなりません。
ここではそれまでのキャラクターは完全封印され、カーリーヘアは普通のミディアムがすこし伸びたような頭、付け髭に、袴・着物姿、という出で立ちで主人公を演じていました。
なぜここまでそれまでの路線とは異なる作品に出たのか?私もそこが不思議でした。イメージチェンジというにはあまりにも激変振り。一体ナニを優作さんにそうさせたのか・・・?
「アナログ日記」さんの見解を読んでおりまして、優作さんなりに「コピー」という悪評に相当悩み続けていたというのがあって、あえてこれまでの「我」を一発で消せる、新たな表現の場を模索していたのかもしれません。そう考えると、一時期、俳優業の仕事のオファーを断ってまで、歌手としてコンサートツアーをやったこともその延長線上によるものであったとも判断できるのかもしれませんね。そう考えると、上記の私の疑問も何となく晴れたような気がします。
私の世代からすれば、こういう「独特の貫禄」をもった30代俳優の存在が今の役者の世界には手薄、あるいは皆無という実情を考慮すると、やはり優作さんの、まだ30歳前後という年齢でのあの抜群の存在感、舞台映え、演技力、凄みというのは、「賞賛」に値するのです。間違いなく10年、20年に1人の名役者であったことは確かだ、というのは私の意見でございます・・・(ただ、確かにひばりさんもそうですが、どうも過度に伝説化されすぎているきらいはありますね・・・。私もそこは不満ではあります。「負」の部分も全て含めての、優作さんであり、ひばりさんであり、裕次郎さんであるわけです。その辺も客観的な視点に立ってその人物の魅力というものを探るのが筋だろうとは思いますね)。
優作さんが亡くなったのは89年秋、私がまだ小学校3年か4年の頃ですので、リアルタイムで彼の演技なりトークなりを見た覚えというのはあまりなく、後年になって「太陽にほえろ」「探偵物語」「家族ゲーム」などのビデオ・再放映を通じて彼の演技がどういうものだったのか、というのを始めて具体的に知った口で、彼が生前、特に「殺人遊戯」「探偵物語」のあたりまでは「ショーケンの二番煎じ」の評があったということは実はほとんど知りませんでした(汗)。確かによくよく考えて見ますと、この10ヶ月前、「大阪で生まれた女」で出たときのショーケンさんは、まさに無精髭で「危険な香り」に溢れた風貌でしたよね・・・。それの「真似」といわれてみれば、なるほどそう考える事もできますね・・・。
私の無知を恥じておりますとともに大変貴重なご意見、賜りました事、本当に有難うございました。
リアルタイムでその歌手、その俳優、そのドラマ、その歌というものに触れている方の意見、特に「アナログ日記」さんはそうですが、非常に私のような、「後から知った」という世代の人間にはとても参考になる事ばかりです。ご自由にこれからも当ブログにお越しの際には論評等も是非お願いいたします。