昨日、「異常」という語を用いて話を書いた。
では、「異常」ってなんだろう。そして「正常」ってなんだろう。
その定義は実に曖昧だ。
まず、昨日書いたように、その境界が曖昧だということがある。
だが、「境界が曖昧だ」という問題の背後には、
それは、同一次元で議論される内容だという前提がある。
ところが、「正常」と「異常」には、いくつもの次元がある。
そして立場が違えば、あるいは時代や文化が違えば、
その正常と異常はまったく逆転することもある。
その観点からすると、「正常」と「異常」の概念それ自体が曖昧である。
たとえば、女性社員がせっせと男性社員にお茶くみをする場面。
それは日本では(特に一昔前の日本では)実に正常なふるまいとされた。
ところがたとえばオーストラリアなどでは異常に受け取られるらしい。
逆に、男性が女性にお茶をくむ場面はオーストラリアでは正常とされ、
日本では異常とされた。
食事の仕方にしても、
食事するときには無駄な会話をせず黙って食べるというのが正常で、
そこでわいわいと話をしながら食べるというのが異常だとする考え方もあれば
逆に、わいわいと話をしながら食べるのが正常で
そこに会話がないのは異常だとする考え方もある。
そこで、正常と異常について、その枠組みは一体なんなのか、
考えてみようと思った次第である。
『精神・心理症状学ハンドブック』(日本評論社)によると、
「正常」とは、①価値的正常value norm、②統計的正常statistical norm、
③個体的正常individual normがあるとされる。
この観点がとても整理に役立つので、この枠組みに則って、考えてみることとする。
価値的正常・異常の定義に従えば、
社会の構成員の多くが望ましいと考えられる状態が正常であり、
望ましくないと考えられる状態が異常である。
統計的正常・異常の定義に従えば、
その集団内の当該変数分布の平均値(あるいは中央値)の周囲の値をとるものが正常で、
それよりも低い値やそれよりも高い値をとるものが異常である。
個体的正常・異常の定義に従えば、個人のある時点の状態が
その個人の通常の値より偏っていれば異常といえる。
たとえば身長で考えた場合、ある程度の平均的な身長の範囲にあれば、
正常であるとされる。
(たとえば正規分布している場合、
平均身長±1標準偏差の範囲であれば68.2%の人が、
平均身長±2標準偏差の範囲であれば95.4%の人が入る。)
それより背の高い者も低い者も異常とされる。
これは統計的正常・異常による判断である。
それに対して、肌年齢などを考えた場合、その人の年齢の人が属する
平均的な肌年齢の周囲の範囲にあれば、それは身長の場合と同様、
正常とされる。これは統計的正常・異常による判断である。
ところが、その範囲を超えて若い肌年齢のところに位置づいていても、
それは異常とはされない。
これは、価値的正常・異常による判断である。
肌年齢は若いほどいいとされている価値が共有されているからである。
この場合、「“異常に”若い」と表現されたりするが、
ここでの“異常”という言葉は、その価値的正常を強調するために用いられる。
ところが、その、肌年齢が異常に若かった人、
考えやすくするために、たとえば実年齢より12歳くらい若かった人が、
ストレスか何かで急に肌が10歳も年をとってしまったとする。
つまり、実年齢より2歳若いくらいになったとする。
2歳くらい若い人というのは、おそらく、
その年齢集団の中で、平均的な範囲におさまるだろう。
なので、かえって、統計的には正常になったということになる。
また、2歳若いというのは、なお、価値的にも正常とされる。
しかし、その人にとっては大事件であり、異常事態である。
明らかに、その人の平生の状態とは異なっているからである。
これが、個体的正常・異常による判断である。
体温なども同様で、その人の平生の体温に比べて明らかに上昇があったとき、
たとえば平熱が34度くらいの低体温の人であれば
35.5度くらいでも発熱という。
これも、個体的正常・異常による判断である。
このように、どの軸をあてはめるかによって、正常か異常かの判断は異なる。
だが、どの変数にどの軸をあてはめるかに規則はない。
たとえば虫歯を考えてみる。
虫歯は放っておくとよくない。なので虫歯があるということは
価値的正常の観点からとらえると異常である。
しかし、成人人口中の半分以上は虫歯がある。
なので、統計的には虫歯がある方が正常であり、
虫歯がない人は異常だということになるのである。
また、それまで虫歯がなかった人に新たに虫歯ができてしまったというような場合は、
やはり虫歯があるということが、個体的正常・異常においても異常と判断される。
スピード違反にしてもそうである。
スピード違反は法律違反であり価値的には異常である。
しかし、多くの人がスピード違反をしている。
よって統計的にはスピード違反をしている方が正常である。
実際、速度制限を遵守して走っていると、
後ろからひどい攻撃を受けたりするものだ。
それが怖くて頑張っていつになく速度を上げて運転した場合、
そのスピード違反は個体的正常・異常においても異常とされる。
別の組み合わせも考えられる。
たとえば、オリンピックで優勝するとか、主役を射止めるなどは、
明らかに統計的には異常である。
しかしながら価値的には正常であり、多くの支持を集めることができる。
そしてそれは、個体的に正常か異常かは、その人によって異なる。
何連覇も更新していた人が優勝した場合は、そのことは個体的に正常であり、
シンデレラ的に主役に抜擢された場合は、そのことは個体的に異常である。
芸術家などもそうだろう。
個体的正常・異常というのは、そもそも、
それぞれの人の状態を考慮する必要があるものであるため、
その判断が個人によって異なるのは当たり前である。
だが、価値的正常・異常というのも、個人によって異なることがある。
たとえばティーカッププードルという犬がいるが、
あれは犬という種からみると異常な小ささに思われるのだが、
そのサイズが「小さくてかわいい」とされると価値的には正常とされる。
だが、自然ということに価値を置く人には、やはり価値的に異常とされるだろう。
冒頭で書いた食事の例も、価値的に正常か異常かという判断は、
文化によって異なると思われる。
さらに、日常においては、統計的正常・異常と、価値的正常・異常の軸は
そこまで独立しておらず、容易に入れ替わったり
相互依存的であったりするように思う。
たとえば冒頭のお茶くみの例。
昔の女性であれば、ほとんど誰もが(統計的正常)男性社員にお茶を淹れただろうし、
それは、価値的に正常な行為とされた。
そして、それは価値的に正常な行為とされたから、誰もがお茶を淹れ、
結果として統計的にも正常な行為とされるという状態が維持され続け、
そして多くの人がその価値を支持するということによって、
その価値的正常がさらに維持されるということもあるだろう。
一番分かりやすいのが流行である。
バブル時代、女性の眉毛は太かった。
そういう人が多くて(統計的正常)、かわいいとされた(価値的正常)。
かわいいとされたから、皆がそうしたとも考えられるし、
皆がそうしたからかわいいような気がしたのかもしれない。
だが今、バブル時代のような眉毛をしていたらただの手抜きとされる。
統計的にも異常であるし、価値的にも異常である。
ここから考えられることは、
絶対的な価値をおくことが難しい場合、統計的基準が
価値的基準を作り上げていくところがあるのではないかということである。
もちろん、新しい価値が統計的正常をもたらすこともある。
たとえばエコ。
エコという行為は、価値的に正常とされ、以前は少数の人しか意識していなかったが、
その価値が広く行き渡って、多くの人が価値的に正常とされる行為をするようになる。
それによって、エコにつながる行為をする人が、価値的にも統計的にも正常となる。
だが、この「価値が広まる」という過程では、
やはり、人に支持されるという、統計的正常に近づく過程が存在し、
それを支持する人が少数派である間は、やはりあまり普及せず、
少数派ながらもある分岐点にまで達すると、その後は爆発的に拡大するという
そういう流れがあるように思う。
その意味では、統計的正常というものは、
価値的正常を形成する力があるように思うのだ。
さらにいうと、以前から価値基準があったとはいえ、
それは正常・異常の判断を伴うものではなかったのに、
統計的正常・異常によって価値的正常・異常も判断されるようになるような
ケースもある。
現在、95%以上の人が高校に進学する。
よって、高校に進学することは統計的に正常であり、
また社会にも受け入れられるという点からみると、
価値的に正常でもあるわけである。
だが、社会が求めるからこそ高校進学が増え、
結果として統計的正常がもたらされたとも考えられる。
そしてその統計的正常がもたらされたことによって、
「高校に行かない」という決断が、
以前はさほど価値的異常としての意味をもたなかったのに
明確に価値的に異常であるとして否定されるということが
起こりうるのではないかと思う。
つまり、少数派であるということが、それ自体は、
価値的には正常でも異常でもないかもしれないのに、
少数派であるというそれだけで、価値的にも異常であるかのように
思われるということがあるように思うのだ。
判断基準がよく分からないとき、
「皆がいいと言っているならきっといいことなんだろう」と
統計的正常の判断をそのまま価値的正常の判断としてしまっているからだろう。
つまり、正常・異常を判断する次元は複数考えられるのであるが
それは明確に使い分けられてはいない。
そのことが、正常・異常の意味を余計に混沌とさせているようなのだが、
ひいては、自分のものの見方も偏らせているように思う。
よって、このこと、すなわち、価値的正常・異常の判断は、
統計的正常・異常の判断によって形成される可能性があるかもしれないということは、
自覚されるべきである。
それは、無意味な正常・異常のラベル付けを抑制してくれるかもしれないし、
さらに、自分がとらわれていることからの解放を促す副効用があるようにも思う。
自分がいいと思っていること、価値を感じていること、
でもそれは本当は、皆がそう思っているからそう思っているだけかも…。
そう思うことは、自分の価値を疑うことにつながるので、
自分を不安にさせてしまうことかもしれない。
だが、自分を苦しめている価値のいくつかからは解放してくれることかもしれない。
そこで求めているものは、本当に価値とされるべきものなのか、
統計的基準の正常に入りたいというだけであって
価値的にどうであるかどうかとはまったく別の話なのではないか、
その観点から見直すと、少し楽になるかもしれない。
それでも、社会で生きていると、統計的正常の呪縛から
解放されることは難しいことがある。
ここから先は、仲間のアイディアの借用であるが、
その場合は、最低限、「多数派を善」とする統計的正常の呪縛から解放されると、
楽になれるかもしれないということを指摘することが出来る。
たとえばプレミア商品などの例。
あれは、「数が少ないから価値がある」とされるものである。
これも、価値的正常・異常という判断が、
統計的正常・異常の判断によって左右されているという点では同様である。
しかしながら、統計的に異常であるということが、価値を形成している点では
逆の現象である。
もともと価値的正常・異常の判断のしようがなかったところに、
統計的正常・異常の判断によって価値的判断がなされるようになることは
日常では少なくない。
つまり、その価値基準自体に大した価値がないことも少なくないのだ。
それに気づくと、統計的正常から自由になれる。
だが、統計的正常は大きな力をもっているように思われるため、
そこから逃れきることは案外難しいかもしれない。
その場合は、もう1つの統計的正常からの解放、
統計的に異常だからこそ価値とされることもある、という発想の転換によって、
やはり私たちは自由になれるようである。
では、「異常」ってなんだろう。そして「正常」ってなんだろう。
その定義は実に曖昧だ。
まず、昨日書いたように、その境界が曖昧だということがある。
だが、「境界が曖昧だ」という問題の背後には、
それは、同一次元で議論される内容だという前提がある。
ところが、「正常」と「異常」には、いくつもの次元がある。
そして立場が違えば、あるいは時代や文化が違えば、
その正常と異常はまったく逆転することもある。
その観点からすると、「正常」と「異常」の概念それ自体が曖昧である。
たとえば、女性社員がせっせと男性社員にお茶くみをする場面。
それは日本では(特に一昔前の日本では)実に正常なふるまいとされた。
ところがたとえばオーストラリアなどでは異常に受け取られるらしい。
逆に、男性が女性にお茶をくむ場面はオーストラリアでは正常とされ、
日本では異常とされた。
食事の仕方にしても、
食事するときには無駄な会話をせず黙って食べるというのが正常で、
そこでわいわいと話をしながら食べるというのが異常だとする考え方もあれば
逆に、わいわいと話をしながら食べるのが正常で
そこに会話がないのは異常だとする考え方もある。
そこで、正常と異常について、その枠組みは一体なんなのか、
考えてみようと思った次第である。
『精神・心理症状学ハンドブック』(日本評論社)によると、
「正常」とは、①価値的正常value norm、②統計的正常statistical norm、
③個体的正常individual normがあるとされる。
この観点がとても整理に役立つので、この枠組みに則って、考えてみることとする。
価値的正常・異常の定義に従えば、
社会の構成員の多くが望ましいと考えられる状態が正常であり、
望ましくないと考えられる状態が異常である。
統計的正常・異常の定義に従えば、
その集団内の当該変数分布の平均値(あるいは中央値)の周囲の値をとるものが正常で、
それよりも低い値やそれよりも高い値をとるものが異常である。
個体的正常・異常の定義に従えば、個人のある時点の状態が
その個人の通常の値より偏っていれば異常といえる。
たとえば身長で考えた場合、ある程度の平均的な身長の範囲にあれば、
正常であるとされる。
(たとえば正規分布している場合、
平均身長±1標準偏差の範囲であれば68.2%の人が、
平均身長±2標準偏差の範囲であれば95.4%の人が入る。)
それより背の高い者も低い者も異常とされる。
これは統計的正常・異常による判断である。
それに対して、肌年齢などを考えた場合、その人の年齢の人が属する
平均的な肌年齢の周囲の範囲にあれば、それは身長の場合と同様、
正常とされる。これは統計的正常・異常による判断である。
ところが、その範囲を超えて若い肌年齢のところに位置づいていても、
それは異常とはされない。
これは、価値的正常・異常による判断である。
肌年齢は若いほどいいとされている価値が共有されているからである。
この場合、「“異常に”若い」と表現されたりするが、
ここでの“異常”という言葉は、その価値的正常を強調するために用いられる。
ところが、その、肌年齢が異常に若かった人、
考えやすくするために、たとえば実年齢より12歳くらい若かった人が、
ストレスか何かで急に肌が10歳も年をとってしまったとする。
つまり、実年齢より2歳若いくらいになったとする。
2歳くらい若い人というのは、おそらく、
その年齢集団の中で、平均的な範囲におさまるだろう。
なので、かえって、統計的には正常になったということになる。
また、2歳若いというのは、なお、価値的にも正常とされる。
しかし、その人にとっては大事件であり、異常事態である。
明らかに、その人の平生の状態とは異なっているからである。
これが、個体的正常・異常による判断である。
体温なども同様で、その人の平生の体温に比べて明らかに上昇があったとき、
たとえば平熱が34度くらいの低体温の人であれば
35.5度くらいでも発熱という。
これも、個体的正常・異常による判断である。
このように、どの軸をあてはめるかによって、正常か異常かの判断は異なる。
だが、どの変数にどの軸をあてはめるかに規則はない。
たとえば虫歯を考えてみる。
虫歯は放っておくとよくない。なので虫歯があるということは
価値的正常の観点からとらえると異常である。
しかし、成人人口中の半分以上は虫歯がある。
なので、統計的には虫歯がある方が正常であり、
虫歯がない人は異常だということになるのである。
また、それまで虫歯がなかった人に新たに虫歯ができてしまったというような場合は、
やはり虫歯があるということが、個体的正常・異常においても異常と判断される。
スピード違反にしてもそうである。
スピード違反は法律違反であり価値的には異常である。
しかし、多くの人がスピード違反をしている。
よって統計的にはスピード違反をしている方が正常である。
実際、速度制限を遵守して走っていると、
後ろからひどい攻撃を受けたりするものだ。
それが怖くて頑張っていつになく速度を上げて運転した場合、
そのスピード違反は個体的正常・異常においても異常とされる。
別の組み合わせも考えられる。
たとえば、オリンピックで優勝するとか、主役を射止めるなどは、
明らかに統計的には異常である。
しかしながら価値的には正常であり、多くの支持を集めることができる。
そしてそれは、個体的に正常か異常かは、その人によって異なる。
何連覇も更新していた人が優勝した場合は、そのことは個体的に正常であり、
シンデレラ的に主役に抜擢された場合は、そのことは個体的に異常である。
芸術家などもそうだろう。
個体的正常・異常というのは、そもそも、
それぞれの人の状態を考慮する必要があるものであるため、
その判断が個人によって異なるのは当たり前である。
だが、価値的正常・異常というのも、個人によって異なることがある。
たとえばティーカッププードルという犬がいるが、
あれは犬という種からみると異常な小ささに思われるのだが、
そのサイズが「小さくてかわいい」とされると価値的には正常とされる。
だが、自然ということに価値を置く人には、やはり価値的に異常とされるだろう。
冒頭で書いた食事の例も、価値的に正常か異常かという判断は、
文化によって異なると思われる。
さらに、日常においては、統計的正常・異常と、価値的正常・異常の軸は
そこまで独立しておらず、容易に入れ替わったり
相互依存的であったりするように思う。
たとえば冒頭のお茶くみの例。
昔の女性であれば、ほとんど誰もが(統計的正常)男性社員にお茶を淹れただろうし、
それは、価値的に正常な行為とされた。
そして、それは価値的に正常な行為とされたから、誰もがお茶を淹れ、
結果として統計的にも正常な行為とされるという状態が維持され続け、
そして多くの人がその価値を支持するということによって、
その価値的正常がさらに維持されるということもあるだろう。
一番分かりやすいのが流行である。
バブル時代、女性の眉毛は太かった。
そういう人が多くて(統計的正常)、かわいいとされた(価値的正常)。
かわいいとされたから、皆がそうしたとも考えられるし、
皆がそうしたからかわいいような気がしたのかもしれない。
だが今、バブル時代のような眉毛をしていたらただの手抜きとされる。
統計的にも異常であるし、価値的にも異常である。
ここから考えられることは、
絶対的な価値をおくことが難しい場合、統計的基準が
価値的基準を作り上げていくところがあるのではないかということである。
もちろん、新しい価値が統計的正常をもたらすこともある。
たとえばエコ。
エコという行為は、価値的に正常とされ、以前は少数の人しか意識していなかったが、
その価値が広く行き渡って、多くの人が価値的に正常とされる行為をするようになる。
それによって、エコにつながる行為をする人が、価値的にも統計的にも正常となる。
だが、この「価値が広まる」という過程では、
やはり、人に支持されるという、統計的正常に近づく過程が存在し、
それを支持する人が少数派である間は、やはりあまり普及せず、
少数派ながらもある分岐点にまで達すると、その後は爆発的に拡大するという
そういう流れがあるように思う。
その意味では、統計的正常というものは、
価値的正常を形成する力があるように思うのだ。
さらにいうと、以前から価値基準があったとはいえ、
それは正常・異常の判断を伴うものではなかったのに、
統計的正常・異常によって価値的正常・異常も判断されるようになるような
ケースもある。
現在、95%以上の人が高校に進学する。
よって、高校に進学することは統計的に正常であり、
また社会にも受け入れられるという点からみると、
価値的に正常でもあるわけである。
だが、社会が求めるからこそ高校進学が増え、
結果として統計的正常がもたらされたとも考えられる。
そしてその統計的正常がもたらされたことによって、
「高校に行かない」という決断が、
以前はさほど価値的異常としての意味をもたなかったのに
明確に価値的に異常であるとして否定されるということが
起こりうるのではないかと思う。
つまり、少数派であるということが、それ自体は、
価値的には正常でも異常でもないかもしれないのに、
少数派であるというそれだけで、価値的にも異常であるかのように
思われるということがあるように思うのだ。
判断基準がよく分からないとき、
「皆がいいと言っているならきっといいことなんだろう」と
統計的正常の判断をそのまま価値的正常の判断としてしまっているからだろう。
つまり、正常・異常を判断する次元は複数考えられるのであるが
それは明確に使い分けられてはいない。
そのことが、正常・異常の意味を余計に混沌とさせているようなのだが、
ひいては、自分のものの見方も偏らせているように思う。
よって、このこと、すなわち、価値的正常・異常の判断は、
統計的正常・異常の判断によって形成される可能性があるかもしれないということは、
自覚されるべきである。
それは、無意味な正常・異常のラベル付けを抑制してくれるかもしれないし、
さらに、自分がとらわれていることからの解放を促す副効用があるようにも思う。
自分がいいと思っていること、価値を感じていること、
でもそれは本当は、皆がそう思っているからそう思っているだけかも…。
そう思うことは、自分の価値を疑うことにつながるので、
自分を不安にさせてしまうことかもしれない。
だが、自分を苦しめている価値のいくつかからは解放してくれることかもしれない。
そこで求めているものは、本当に価値とされるべきものなのか、
統計的基準の正常に入りたいというだけであって
価値的にどうであるかどうかとはまったく別の話なのではないか、
その観点から見直すと、少し楽になるかもしれない。
それでも、社会で生きていると、統計的正常の呪縛から
解放されることは難しいことがある。
ここから先は、仲間のアイディアの借用であるが、
その場合は、最低限、「多数派を善」とする統計的正常の呪縛から解放されると、
楽になれるかもしれないということを指摘することが出来る。
たとえばプレミア商品などの例。
あれは、「数が少ないから価値がある」とされるものである。
これも、価値的正常・異常という判断が、
統計的正常・異常の判断によって左右されているという点では同様である。
しかしながら、統計的に異常であるということが、価値を形成している点では
逆の現象である。
もともと価値的正常・異常の判断のしようがなかったところに、
統計的正常・異常の判断によって価値的判断がなされるようになることは
日常では少なくない。
つまり、その価値基準自体に大した価値がないことも少なくないのだ。
それに気づくと、統計的正常から自由になれる。
だが、統計的正常は大きな力をもっているように思われるため、
そこから逃れきることは案外難しいかもしれない。
その場合は、もう1つの統計的正常からの解放、
統計的に異常だからこそ価値とされることもある、という発想の転換によって、
やはり私たちは自由になれるようである。














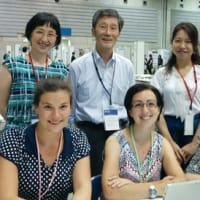





正常と異常の概念はかなり文化的、歴史的、社会的な影響を受けて流動的なものだと思います。
それに、それらを二項対立的に明確に峻別するのも難しいと、多くの人は知っていると思うのですが・・、わりかし簡単にこれらの言葉を用いて何かを説明することってありがちですよね。
私はずっと障害研究をしてきて、いま、特別支援教育というのを教えていて、正常・異常の概念がかなりあやふやなところがあるのですが、みなそれぞれある意味ではDifferentなのですから、何か意図があってそれらを峻別し用いているとしか考えられない側面もみえてきます
ところで、昨日、神○大学で○岡先生に会ってきました。お久しぶりでしたが、お元気そうでなによりです。ハーマンスはこられますか? 私もできるだけ参加しようと思っていますので、お会いできたら嬉しいです
補足:昔、私が見ているリンゴの「赤色」とほかの人が見ているリンゴの「赤」が違ってるかもしれんと、ふと思ったことがあり、そればっかり考えていると崩壊しそうなので「違ってたら違ってたでまあいいやん」と自分に言い聞かせた思い出があります
正常・異常がそのまま健康・病気になるわけでもないんですよね。
ハーマンス、行きますよ。
それまでにやらねばならない事が…