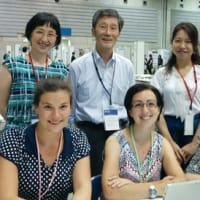ハーマンスの『対話的自己論』では、
思想はもちろん、小説のあり方や美術の変遷など、
多様なジャンルにおける“対話”の出現と、
それによる形式の変化がまとめられています。
小説については、登場人物のことを全知する著者がいて
その視点から語る「全知の神」の様式と、
登場人物が自由に動き回るようになる形態、
登場人物が勝手に対話を初めてそこから物語が展開される様式とが
区別されます。
つまり、“対話”の出現によって、大きく世界の構造が変わることを、
いろんな例を出して説明してくれています。
さて、『主人公は僕だった』という映画では、
その2つの様式の妙を味わうことができます。
さらに、ハーマンスが指摘した以上の対話のあり方が見てとれます。
ある小説家が物語を書いているのですが、
実は、実在する男の物語であり、
(書き手もそれを知らず、全知の著者としてそれを書いている)
その男の現実に、書き手のナレーションが聞こえ始め、
日常がそれまでとは違ったものになってくる。
男はなんとか小説家を見つけ出し、対話を始めます。
登場人物が勝手に対話を始めるだけではなくて、
登場人物がその小説の世界を越えて、書き手と対話する。
そんな話になっています。
思想はもちろん、小説のあり方や美術の変遷など、
多様なジャンルにおける“対話”の出現と、
それによる形式の変化がまとめられています。
小説については、登場人物のことを全知する著者がいて
その視点から語る「全知の神」の様式と、
登場人物が自由に動き回るようになる形態、
登場人物が勝手に対話を初めてそこから物語が展開される様式とが
区別されます。
つまり、“対話”の出現によって、大きく世界の構造が変わることを、
いろんな例を出して説明してくれています。
さて、『主人公は僕だった』という映画では、
その2つの様式の妙を味わうことができます。
さらに、ハーマンスが指摘した以上の対話のあり方が見てとれます。
ある小説家が物語を書いているのですが、
実は、実在する男の物語であり、
(書き手もそれを知らず、全知の著者としてそれを書いている)
その男の現実に、書き手のナレーションが聞こえ始め、
日常がそれまでとは違ったものになってくる。
男はなんとか小説家を見つけ出し、対話を始めます。
登場人物が勝手に対話を始めるだけではなくて、
登場人物がその小説の世界を越えて、書き手と対話する。
そんな話になっています。