台湾風俗誌 第一集
第一章 台湾人の出産
第1節 病囝 (ビイキア)つわり
婦人懐胎の始めを病囝 と称する、これ内地(日本の事)の「ツワリ」なり、病囝 婦人の身体生理状態は内地婦人のツワリと異なるところは無く、唾液は頻りに出て酸味を欲し時々頭痛あり、又悪寒嘔吐を催し、心気万事に懶き等皆同じ。
第2節 迷信
病囝 より臨月に至るまでの間、衛生上の注意としへて別に記すべきことなし、ただ迷信的注意が二三あり、胎児は胎神(タイシヌ)なる神の支配を受け居るものなれば、若し此の怒りに触る時は胎児を奪われると云う。
この胎神は妊婦の居住する家屋内に在りて或時は箱、或時は桶、籠などいずれの所に居るや一定せず、もし不知の間(知らない間)に妊婦が此らに触る時は、胎神怒りて妊婦を病ましむ、此時妊婦は道士と称する祈祷者を呼び来り、「安胎」(アヌタイ)と称する祈祷をなす、道士は病囝 者(妊婦の枕辺)にて鉦笛を鳴らし数時間にわたって読経した後ち符(フ)と称する呪文を書きたるものを床柱或いは門柱に貼布し、尚お呪文を唱えつつ、湯または水を飲ましめ、之を以って胎神去り、胎児安全を得たるものとなす風習あり、
又「換斗」(オアタウ)という語あり、これ己に懐胎せる胎児を祈祷の結果女の子または男の子に変胎せしむるものなりと云う、その方法は先ず「青瞑」(セエメエ)と称する盲目の祈祷者又は、道士に請い、米桝に根ある芙蓉花を植え祈祷者と共に神廟に持ち行き、牲醴香燭を供え、道士神前にて読経し、婦人はその傍らに香を焚き紙を焼き(銭紙と称するもの)三跪九拝し心中に換斗(変胎)を祈り、数時にして家に歸る。これより三日間室内に於いて祈祷を繼續し、のち芙蓉花を庭前に植え以て變胎し終わりたるものなりと言う。
此時詣づる廟は臨水婦人廟(リムツイフジンビオ)又は「註生娘娘」(ツウシイニウニウ)の廟にして此れ等の神は胎児を授けるの神なりという。
妊婦室内に於いて物品を縛する時は手足灣曲せる俗に茗荷児(ミョウガジ)なるもの生ず、又剪刀を以て挟む時は無耳児(ムジジ)生じ、錐(きり)又は針にて物を貫けば盲目児(モウモクジ)、物を焼けば焼爓児(ショウランジ)、傀儡戯(クワイライギ)を観れば無骨児(ムコツ)、牛を牽く縄を跨ぐ時は12ヶ月にして児生まれ、喪家の演出したる芝居を観れば不吉なりと言う、又夜間外出すれば黒虎神に触れ必ず凶あり、盂蘭盆会(ウラボンエ)の時妊婦の腰桶を庭前に露出する時は普度公(ポオトオコン)の怒りに触れて凶あり。死人の棺に触れるれば、児夭折(ジヨウセツ)すると云う(其他迷信の部参照)
第3節 男子系統主義
何れの国の人と雖も出生を慶び、子孫を愛し、其増殖繁栄を希うは人類の通情なり、特に支那人種に於いて甚だ深きものあり、其亜流たる台湾人に於いて又異なる所なし、之れ古来より宗桃継承及祭祀(ソウテイケイショウサイシ)の制度を重んじたるに起因すべきも亦原則として系統主義にしてその系統に非ざるものは其宗桃(ソウテイ)を祭を得ず且つ男系主義にして宗を承け祭りを繼ぐものは必ず男子なり又嫡長主義にして長を尊び幼これに次ぐ又直系主義にして父の後を襲うものは子、子の後を襲うものは孫ならざるべからずと云うに起因するものなるべし、そうして婦女懐胎するときは常に孕婦の身体を安静にし精神の異常の感動を與へ身体に過度の勞を与うる如きを戒む、昔は儒教の教義により胎教と稱し、古人の教育を重んじ、胎内に在るときより已に其端を開く教育、即ち挙止端正に其見聞する所悉く禮(レイ)に合わしむる等の事ありしも今の台湾に於いては見る能はざる事なり。
第4節 臨月
臨月に近づけば産婦の房中は介抱の婦人のみ出入りし他人の往来を避けるものとす、但し下流の婦人は朝に田野に出で、夕べに家に帰るを常にするを以って以上の禁を守る事なし。
本島婦人の子女を産するに二様あり、一は眠床(ビヌツン)に於いてし、一は床下に於いてす。中流以下は多く床下に於いてなすものなり、床下に於いてなすモノは先づ床上に草蓆(ござ)を敷き更に破れたる布褌を重ね上に油紙を布きてなす、床外(ショウグワイ)に於いてするものは床外に枯草又は藁を布き産褥となし傍らに「子桶」(キアタン)と称する桶を置き臨産の時床より下り産褥に移りて産し汚物はこの桶の内に収む。
臨月に当たり突然腹痛起こり、或いは止み、或いは起こり、1、2日乃至4、5日にして胎水来たり腹痛止まざるものあり、之を弄産(ラヌサヌ)と云う、又臨産の一ヶ月前突然腹痛起こりて未だ出産せず、之を「試産」(チイゴエ)と云う如此き時は土人は十三味(ザプサアビイ)、又は成化湯(シエンホアタン)と
稱する安産の薬を用ふ
第5節 臨産
臨産に至れば産婆(只産に経験のある婆)及び近隣の婦女二三人産婦両肩及び腰辺を扶翼し、産婆は兒の出ずるのを待って手を以って之を接受し臍帯を断ちて布に包む、一面傍らの人、産婦を介抱し床上を清め産婦を被(ポエ)(布団)に靠らしむ、この時四壁風の入るの出ずるを防ぎ、力めて安静を保たしむ、産婦は逆上其他眩暈に陥り易きを以って酢を焼き之を嗅がせしむこと一日数回す、又未だ食物を取らざる幼児卽乳児の溺,(いばり:尿の事)に熱湯を混ぜて飲ませる、
之は精神を興奮して血暈にかからないようにする為の豫防(よぼう)なり、之を安胎薬(アヌタイイオ)と云う、又は人参を用いるものもあります。
第6節 産婆
産婆は「拾囝婆」(キノキアポオ)又は「收生婆」(シウシポオ)と云ふ、技術なく、免状なく、僅かに經驗あるものの之をなす、但し近来臺灣各地の醫院に於て助産婦(土人婦女)を養成しあるを以って将来大に區別あるを見るべし
第7節 胞衣
胞衣は瓶に収め紅紙を以て密封し庭隅又は宅前の畑中に埋む、若し火の為め焼くる(野焼ケ等)ことあらば其兒必ず火の為に死すとす云ひ又初産の臍帯を保存し置き他日成長の後他人と訴訟するに際し之を帯び行けば大膽となり必ず訴訟に勝つと云ふ
第8節 難産
難産なるに遇えば家人外に出で槌にて地を打つときは胎児乍ち生ると云ふ、又天公祖(チエヌコンソオ)に「求苦求難キウクキウナン」と稱す祈りをなし、尚ほ出生せざるときは胎神の祟りなりとし道士を請ひ「催生」(ツイシエン)と稱する祈祷をなす
第9節 俯伏産
小兒出産の際俯伏し出でたるものは親及び親族に祟りをなすと云ふ(明治41年臺南南梓仙渓里二重渓庄陳水連の妻張氏糟なるもの俯伏産をなしたるを以て大いに之を恐れ嬰兒を厭殺し罪人となりたることあり)
第10節 死産
胎兒死産なるとき又は産後直に死したるときは死兒を水中に棄てざれば鬼(クイ:怪物)と化し祟りをなすのみならず将来子を孕まずと云ふ
第11節 難産の種類
難産に種々あり「倒産」即ち逆産は足より出ずるもの土人之を「倒蹈蓮花」(トオタアリエンホエ)と云ふ、又「倒産」あり即ち手より生ずるもの土人之を「担横生」(タンホアシー)又は「討鹽生」(タウイアムシイ)と云ふ、「偏産」即ち頭編して一方にあるものにして土人之を「担欹生」(タンキアシイ)と云ふ、「坐産」即ち臀部を露すものにして土人之を「坐斗」(セエタウ)と云ふ、頭正産なるもい臍帯肩に絆はるに因り出でざるもの土人之を「帯素珠」(トアソオツウ)と云ふ
第12節 双兒
双生兒の場合は先出を長とし、後出を幼となすと云ふ、蓋し白虎通に「男子先生ヲ称シ 兄ト後生ヲ弟ト云々」と
之れ同日に生まれたるときも亦通用するものなりと云ふ、又『昔腠公一生二女、李黎生、一生、一男一女、竝以前生爲長』と云ふ、本島に於いても之に則れるものなる可く一生三兒、四兒皆之に倣ふと云ふ
第13節 妻妾の兒
妻妾同時に出産したる時は妻出を長とし、妾出を幼とす、兩妾同時に出産したるときは前妾の出を長とし、後妾の出を幼とす、又神廟(シヌビオ)に至りを擲筶(ポアポエ)行ひ長幼を決するものもありと云ふ
第14節 産湯
兒生るれば直に布に湯を含ましめ其身體を拭ひ甘草、糖水を飲ましめ、産婦にいは桔餅(キツビア)と稱する柑橘の糖漬を與ふ、而して臍帯は4、5日にして落ち去ると云ふ
第15節 産後の式
産後産婦には紅花(薬名)肉、胡麻油にて煎りたる猪の肝臓、酒少量、糯米飯等を與へ身體を安静ならしめ、
而して産後3日に至れば産婆が来たり浴せしめ、後ち命名し、親族朋友来たり祝意を表す、古之を三朝(サムチャウ)の禮と稱し、種々贈物をなす、今之を為すと雖も産家は油飯(イウブン)、米𥼚等を作り之を各家に分ち、富家は祝宴を開くのみ、俗に之を「湯餅」(ツンビア)と云ふ
第16節 月內(ゴエライ)
産後一箇月を「做月內」(ソヲゴエライ)と稱し、豚肉、鶏豚の腎臓、肝臓及び素麺等を胡麻油を以つて煮、酒を加へたるものを與ふ、之れ衰弱及び貧血を囘復せしめんが為なり
第17節 満月 (モアゴエ)
生後一箇月を「満月」と称す、祖母小兒の髪を剃る(又稀に24孝を因みて24日に剃るものあり)先づ洗面器に水を入れ石一箇、銭12文、葱少々、鶏卵一箇を入れ、葱を砕き其汁を髪に注ぎ、頭髪に卵の黄仁(キミ)を塗り温めて之を剃る、蓋し石は頭部の速かに強堅とならん為め、銭は成長の後福貴とならん為め、葱汁は毛髪濃黒とならんむる為め、卵は胎垢(タイコオ)を去らん為めなりと云ふ、髪を剃り終わりて小兒を抱き戸外に出で「鶏箠」(ケツエ)と稱する割竹を於いて地を打ち左の童歌を歌ふ
肉鳶々々(バツヒオバツヒオ)、飛上山(ポエチウソア)、囝仔快做官(ギンナアコアイソオコア)、肉鳶飛高高(バツヒオポエコアコアヌ)、囝仔中狀元(ギンナアチオンナオンゴアヌ)、肉鳶飛低低(バツヒオポオケエケエ)、囝仔快做父(ギンナアコアソベエ)(鳶よ鳶よ汝飛びて山に上らば小兒もち大官にならん、汝飛びて高く上らば亦狀元とならん、汝飛びて低く下らば小兒も亦父とならん)
蓋し其小兒の将来を祝ふの意に出づ、若し女子ならんか只「肉鳶肉鳶」と云ふのみなりと云ふ
此日親戚朋友慶祝の為小兒の衣服、帽、履、銀牌、獅帽(鳳又は獅子の飭ある帽子)、又芭蕉、蝋燭、紅龜(アンクワ:亀の形の餅)、紅餅(アンビア:紅き餅)等を贈る之を満月(モアゴエ)の禮と稱す
産家に於ては菓物又は紅龜の其十分の八を取り、十分の二を贈家に返戻す、又別に油飯、(イウブヌ)米𥼚、(ビイコオ:砂糖を入れたる硬飯)を作り答禮す、産後一箇月に満たらざる間は決して外出せず、若し出づるときは神佛の怒に觸れ必ず病む、
之れ身體の汚れあるを以てなりと云ふ、家人も又其室に出入りせず、只掃箒の下婢及び食事を持ち運ぶもののみ其室に入るものとす
第18節 収涎(シウノア)
小兒産後4箇月に至れば産家より「収涎餅等」(シウノアビア)と称する菓子を製して各家に送る、蓋し小兒の涎を止むるの意より出づ、其他親族朋友の贈物は1箇月の際と略ぼ同一なり
第19節 週歳
小兒一箇年に至れば之を「做週歳」(ソオシウホエ)と云ふ(一に試し週うの禮と云ふ)卽ち第一囘の誕生日なり、此日親戚故来たり祝し書畫、筆、墨、紙等の十二種の物品を送る、此時小兒を正堂に連れて行き、祖先の神靈を拝せしめ、後十二種の物品を篩の中に入れ小兒をして之を取らしむ、第一に取りたるものを以て其兒の将来を祝するものとす、例えば筆、墨、書畫、雞肉、鶏腿、豚の肉、算盤、秤、銀、葱、田土、包布等にして 若し算盤、秤等を取れば商人となり、筆墨と取れば能書となり、鶏肉を取れば大食にて身體健全なり等の縁起を祝ふものなり
又此の日は最終の祝日なるを以て盛んに宴を張り人を招待す、若し初産なるときは生後十二日に於て盛んなる祝慶をなす
第一章 台湾人の出産
第1節 病囝 (ビイキア)つわり
婦人懐胎の始めを病囝 と称する、これ内地(日本の事)の「ツワリ」なり、病囝 婦人の身体生理状態は内地婦人のツワリと異なるところは無く、唾液は頻りに出て酸味を欲し時々頭痛あり、又悪寒嘔吐を催し、心気万事に懶き等皆同じ。
第2節 迷信
病囝 より臨月に至るまでの間、衛生上の注意としへて別に記すべきことなし、ただ迷信的注意が二三あり、胎児は胎神(タイシヌ)なる神の支配を受け居るものなれば、若し此の怒りに触る時は胎児を奪われると云う。
この胎神は妊婦の居住する家屋内に在りて或時は箱、或時は桶、籠などいずれの所に居るや一定せず、もし不知の間(知らない間)に妊婦が此らに触る時は、胎神怒りて妊婦を病ましむ、此時妊婦は道士と称する祈祷者を呼び来り、「安胎」(アヌタイ)と称する祈祷をなす、道士は病囝 者(妊婦の枕辺)にて鉦笛を鳴らし数時間にわたって読経した後ち符(フ)と称する呪文を書きたるものを床柱或いは門柱に貼布し、尚お呪文を唱えつつ、湯または水を飲ましめ、之を以って胎神去り、胎児安全を得たるものとなす風習あり、
又「換斗」(オアタウ)という語あり、これ己に懐胎せる胎児を祈祷の結果女の子または男の子に変胎せしむるものなりと云う、その方法は先ず「青瞑」(セエメエ)と称する盲目の祈祷者又は、道士に請い、米桝に根ある芙蓉花を植え祈祷者と共に神廟に持ち行き、牲醴香燭を供え、道士神前にて読経し、婦人はその傍らに香を焚き紙を焼き(銭紙と称するもの)三跪九拝し心中に換斗(変胎)を祈り、数時にして家に歸る。これより三日間室内に於いて祈祷を繼續し、のち芙蓉花を庭前に植え以て變胎し終わりたるものなりと言う。
此時詣づる廟は臨水婦人廟(リムツイフジンビオ)又は「註生娘娘」(ツウシイニウニウ)の廟にして此れ等の神は胎児を授けるの神なりという。
妊婦室内に於いて物品を縛する時は手足灣曲せる俗に茗荷児(ミョウガジ)なるもの生ず、又剪刀を以て挟む時は無耳児(ムジジ)生じ、錐(きり)又は針にて物を貫けば盲目児(モウモクジ)、物を焼けば焼爓児(ショウランジ)、傀儡戯(クワイライギ)を観れば無骨児(ムコツ)、牛を牽く縄を跨ぐ時は12ヶ月にして児生まれ、喪家の演出したる芝居を観れば不吉なりと言う、又夜間外出すれば黒虎神に触れ必ず凶あり、盂蘭盆会(ウラボンエ)の時妊婦の腰桶を庭前に露出する時は普度公(ポオトオコン)の怒りに触れて凶あり。死人の棺に触れるれば、児夭折(ジヨウセツ)すると云う(其他迷信の部参照)
第3節 男子系統主義
何れの国の人と雖も出生を慶び、子孫を愛し、其増殖繁栄を希うは人類の通情なり、特に支那人種に於いて甚だ深きものあり、其亜流たる台湾人に於いて又異なる所なし、之れ古来より宗桃継承及祭祀(ソウテイケイショウサイシ)の制度を重んじたるに起因すべきも亦原則として系統主義にしてその系統に非ざるものは其宗桃(ソウテイ)を祭を得ず且つ男系主義にして宗を承け祭りを繼ぐものは必ず男子なり又嫡長主義にして長を尊び幼これに次ぐ又直系主義にして父の後を襲うものは子、子の後を襲うものは孫ならざるべからずと云うに起因するものなるべし、そうして婦女懐胎するときは常に孕婦の身体を安静にし精神の異常の感動を與へ身体に過度の勞を与うる如きを戒む、昔は儒教の教義により胎教と稱し、古人の教育を重んじ、胎内に在るときより已に其端を開く教育、即ち挙止端正に其見聞する所悉く禮(レイ)に合わしむる等の事ありしも今の台湾に於いては見る能はざる事なり。
第4節 臨月
臨月に近づけば産婦の房中は介抱の婦人のみ出入りし他人の往来を避けるものとす、但し下流の婦人は朝に田野に出で、夕べに家に帰るを常にするを以って以上の禁を守る事なし。
本島婦人の子女を産するに二様あり、一は眠床(ビヌツン)に於いてし、一は床下に於いてす。中流以下は多く床下に於いてなすものなり、床下に於いてなすモノは先づ床上に草蓆(ござ)を敷き更に破れたる布褌を重ね上に油紙を布きてなす、床外(ショウグワイ)に於いてするものは床外に枯草又は藁を布き産褥となし傍らに「子桶」(キアタン)と称する桶を置き臨産の時床より下り産褥に移りて産し汚物はこの桶の内に収む。
臨月に当たり突然腹痛起こり、或いは止み、或いは起こり、1、2日乃至4、5日にして胎水来たり腹痛止まざるものあり、之を弄産(ラヌサヌ)と云う、又臨産の一ヶ月前突然腹痛起こりて未だ出産せず、之を「試産」(チイゴエ)と云う如此き時は土人は十三味(ザプサアビイ)、又は成化湯(シエンホアタン)と
稱する安産の薬を用ふ
第5節 臨産
臨産に至れば産婆(只産に経験のある婆)及び近隣の婦女二三人産婦両肩及び腰辺を扶翼し、産婆は兒の出ずるのを待って手を以って之を接受し臍帯を断ちて布に包む、一面傍らの人、産婦を介抱し床上を清め産婦を被(ポエ)(布団)に靠らしむ、この時四壁風の入るの出ずるを防ぎ、力めて安静を保たしむ、産婦は逆上其他眩暈に陥り易きを以って酢を焼き之を嗅がせしむこと一日数回す、又未だ食物を取らざる幼児卽乳児の溺,(いばり:尿の事)に熱湯を混ぜて飲ませる、
之は精神を興奮して血暈にかからないようにする為の豫防(よぼう)なり、之を安胎薬(アヌタイイオ)と云う、又は人参を用いるものもあります。
第6節 産婆
産婆は「拾囝婆」(キノキアポオ)又は「收生婆」(シウシポオ)と云ふ、技術なく、免状なく、僅かに經驗あるものの之をなす、但し近来臺灣各地の醫院に於て助産婦(土人婦女)を養成しあるを以って将来大に區別あるを見るべし
第7節 胞衣
胞衣は瓶に収め紅紙を以て密封し庭隅又は宅前の畑中に埋む、若し火の為め焼くる(野焼ケ等)ことあらば其兒必ず火の為に死すとす云ひ又初産の臍帯を保存し置き他日成長の後他人と訴訟するに際し之を帯び行けば大膽となり必ず訴訟に勝つと云ふ
第8節 難産
難産なるに遇えば家人外に出で槌にて地を打つときは胎児乍ち生ると云ふ、又天公祖(チエヌコンソオ)に「求苦求難キウクキウナン」と稱す祈りをなし、尚ほ出生せざるときは胎神の祟りなりとし道士を請ひ「催生」(ツイシエン)と稱する祈祷をなす
第9節 俯伏産
小兒出産の際俯伏し出でたるものは親及び親族に祟りをなすと云ふ(明治41年臺南南梓仙渓里二重渓庄陳水連の妻張氏糟なるもの俯伏産をなしたるを以て大いに之を恐れ嬰兒を厭殺し罪人となりたることあり)
第10節 死産
胎兒死産なるとき又は産後直に死したるときは死兒を水中に棄てざれば鬼(クイ:怪物)と化し祟りをなすのみならず将来子を孕まずと云ふ
第11節 難産の種類
難産に種々あり「倒産」即ち逆産は足より出ずるもの土人之を「倒蹈蓮花」(トオタアリエンホエ)と云ふ、又「倒産」あり即ち手より生ずるもの土人之を「担横生」(タンホアシー)又は「討鹽生」(タウイアムシイ)と云ふ、「偏産」即ち頭編して一方にあるものにして土人之を「担欹生」(タンキアシイ)と云ふ、「坐産」即ち臀部を露すものにして土人之を「坐斗」(セエタウ)と云ふ、頭正産なるもい臍帯肩に絆はるに因り出でざるもの土人之を「帯素珠」(トアソオツウ)と云ふ
第12節 双兒
双生兒の場合は先出を長とし、後出を幼となすと云ふ、蓋し白虎通に「男子先生ヲ称シ 兄ト後生ヲ弟ト云々」と
之れ同日に生まれたるときも亦通用するものなりと云ふ、又『昔腠公一生二女、李黎生、一生、一男一女、竝以前生爲長』と云ふ、本島に於いても之に則れるものなる可く一生三兒、四兒皆之に倣ふと云ふ
第13節 妻妾の兒
妻妾同時に出産したる時は妻出を長とし、妾出を幼とす、兩妾同時に出産したるときは前妾の出を長とし、後妾の出を幼とす、又神廟(シヌビオ)に至りを擲筶(ポアポエ)行ひ長幼を決するものもありと云ふ
第14節 産湯
兒生るれば直に布に湯を含ましめ其身體を拭ひ甘草、糖水を飲ましめ、産婦にいは桔餅(キツビア)と稱する柑橘の糖漬を與ふ、而して臍帯は4、5日にして落ち去ると云ふ
第15節 産後の式
産後産婦には紅花(薬名)肉、胡麻油にて煎りたる猪の肝臓、酒少量、糯米飯等を與へ身體を安静ならしめ、
而して産後3日に至れば産婆が来たり浴せしめ、後ち命名し、親族朋友来たり祝意を表す、古之を三朝(サムチャウ)の禮と稱し、種々贈物をなす、今之を為すと雖も産家は油飯(イウブン)、米𥼚等を作り之を各家に分ち、富家は祝宴を開くのみ、俗に之を「湯餅」(ツンビア)と云ふ
第16節 月內(ゴエライ)
産後一箇月を「做月內」(ソヲゴエライ)と稱し、豚肉、鶏豚の腎臓、肝臓及び素麺等を胡麻油を以つて煮、酒を加へたるものを與ふ、之れ衰弱及び貧血を囘復せしめんが為なり
第17節 満月 (モアゴエ)
生後一箇月を「満月」と称す、祖母小兒の髪を剃る(又稀に24孝を因みて24日に剃るものあり)先づ洗面器に水を入れ石一箇、銭12文、葱少々、鶏卵一箇を入れ、葱を砕き其汁を髪に注ぎ、頭髪に卵の黄仁(キミ)を塗り温めて之を剃る、蓋し石は頭部の速かに強堅とならん為め、銭は成長の後福貴とならん為め、葱汁は毛髪濃黒とならんむる為め、卵は胎垢(タイコオ)を去らん為めなりと云ふ、髪を剃り終わりて小兒を抱き戸外に出で「鶏箠」(ケツエ)と稱する割竹を於いて地を打ち左の童歌を歌ふ
肉鳶々々(バツヒオバツヒオ)、飛上山(ポエチウソア)、囝仔快做官(ギンナアコアイソオコア)、肉鳶飛高高(バツヒオポエコアコアヌ)、囝仔中狀元(ギンナアチオンナオンゴアヌ)、肉鳶飛低低(バツヒオポオケエケエ)、囝仔快做父(ギンナアコアソベエ)(鳶よ鳶よ汝飛びて山に上らば小兒もち大官にならん、汝飛びて高く上らば亦狀元とならん、汝飛びて低く下らば小兒も亦父とならん)
蓋し其小兒の将来を祝ふの意に出づ、若し女子ならんか只「肉鳶肉鳶」と云ふのみなりと云ふ
此日親戚朋友慶祝の為小兒の衣服、帽、履、銀牌、獅帽(鳳又は獅子の飭ある帽子)、又芭蕉、蝋燭、紅龜(アンクワ:亀の形の餅)、紅餅(アンビア:紅き餅)等を贈る之を満月(モアゴエ)の禮と稱す
産家に於ては菓物又は紅龜の其十分の八を取り、十分の二を贈家に返戻す、又別に油飯、(イウブヌ)米𥼚、(ビイコオ:砂糖を入れたる硬飯)を作り答禮す、産後一箇月に満たらざる間は決して外出せず、若し出づるときは神佛の怒に觸れ必ず病む、
之れ身體の汚れあるを以てなりと云ふ、家人も又其室に出入りせず、只掃箒の下婢及び食事を持ち運ぶもののみ其室に入るものとす
第18節 収涎(シウノア)
小兒産後4箇月に至れば産家より「収涎餅等」(シウノアビア)と称する菓子を製して各家に送る、蓋し小兒の涎を止むるの意より出づ、其他親族朋友の贈物は1箇月の際と略ぼ同一なり
第19節 週歳
小兒一箇年に至れば之を「做週歳」(ソオシウホエ)と云ふ(一に試し週うの禮と云ふ)卽ち第一囘の誕生日なり、此日親戚故来たり祝し書畫、筆、墨、紙等の十二種の物品を送る、此時小兒を正堂に連れて行き、祖先の神靈を拝せしめ、後十二種の物品を篩の中に入れ小兒をして之を取らしむ、第一に取りたるものを以て其兒の将来を祝するものとす、例えば筆、墨、書畫、雞肉、鶏腿、豚の肉、算盤、秤、銀、葱、田土、包布等にして 若し算盤、秤等を取れば商人となり、筆墨と取れば能書となり、鶏肉を取れば大食にて身體健全なり等の縁起を祝ふものなり
又此の日は最終の祝日なるを以て盛んに宴を張り人を招待す、若し初産なるときは生後十二日に於て盛んなる祝慶をなす













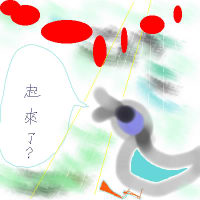
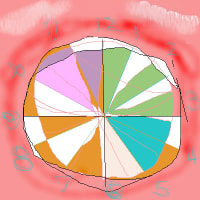

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます