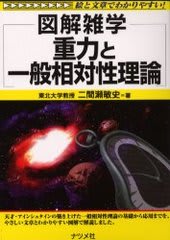『記憶力を強くする』で鮮烈デビューした著者が大脳生理学の最先端の知識を駆使して、記憶のメカニズムから、意識の問題まで中高生を相手に縦横無尽に語り尽くす。「私自身が高校生の頃にこんな講義を受けていたら、きっと人生が変わっていたのではないか?」と、著者自らが語る珠玉の名講義。
出版社:講談社(ブルーバックス)
帯に『しびれるくらいに面白い!』という文句が入っているが、それも納得のおもしろさである。
脳科学という最新の学問を平易な言葉で、講義形式で語りかけるように叙述されているので、興味を持ってサクサクと読み進むことができる。書かれている内容も興味深いものが多いというのもあるのだろう。
脳の地図は後天的なもので、体が決めており、脳は体という効率の悪い乗り物のせいで能力を使いこなせていない、という部分には特に驚かされる。人間の脳がある種の柔軟性を持っていることを示すものだろうが、その視点はいままで知らなかったことなので、まさに目からうろこである。
また脳があいまいにつくられているからこそ、より柔軟な対応ができるという視座や、後半に出てくるシナプスのメカニズムやアルツハイマーに関する具体的な話題は理系人間にとってはたまらないくらいにおもしろかった。
さてそんな風に優れた部分を上げればきりがないのだが、その中でももっとも心に残ったのは、脳科学の考え方が哲学と通じるものがあるという点である。
そんなこと著者自身は述べていないが、その類似性は明らかだ。
たとえば「目ができたから世界が世界としてはじめて意味を持った」という文章や(人間にとっての三原色が赤・緑・青になっただけという部分には震えた)、違う動物ならば人間とは違う世界が広がるという部分などはフッサールを始めとした現象学に通じるものがあるし、言葉が意識の典型例だという話はソシュールやウィトゲンシュタインの言語論を思わせる。特に「言葉→心→汎化」のプロセスは驚きである。
哲学と脳科学はまったく逆の方向性と思っていただけにその相関性には感動するものがあった。
異なる部分の学問でも実はどこかでつながっている。そんなことを気付かされて、理系の職種につく理系人間としてはいろいろ考えさせられるものがあった。
評価:★★★★★(満点は★★★★★)