どうもこんにちは。廃墟の真ん中で一目瞭然ってそんなに偉いんかと叫ぶケモノこと僕です。もはや廃墟ッ! 疑いなくッ,廃墟ッ! カイジッ! ってことで,お前そんなことより他にやることあるだろ,ウン? ということについては,軽やかに分裂排除いたしまして――というか,頑張ります――リハビリテーションの一環としてご理解いただきながら,ちょっと気になること,これありにつき,明日出頭すべし,ということで,
まあこの本,売れているそうです。売れているそうですが,懸命なる読者諸賢ならお分かりのとおり,推して知るべし,という内容で(たとえば.引用文献明示なし,云々),非常に残念な感じでありますが,しかしこれが売れているという事実を,民度の低さ,リテラシーの低さのせいにして嘆いても,DISってもしょうがないのです(もちろんそうする意味はあるけど)。見たい! 一目瞭然したい! そういう僕含む愚民のキモチ,分かってほしいのですよ。騙されてる,というよりはもう,全力で騙されにいってる,としか思えない暴挙ではありますが,見たいもの見たい,そのキモチはCan't Stopなわけですよ。
まじめに言うと,こういう方向性,ないわけではないと思うけど,現段階では大雑把過ぎて,まあちょっとアレだなという感じですね。現時点の人類の科学力では無理ですから,自然,超科学に頼らざるを得ない,といったところでしょうかね。
ま,というところで,本題いきたいわけですけど(なんなんだ),ちょっと前(つうか去年),こういうニュースがあって,興奮した人も多かろうと思ったのが,
■脳から知覚映像を読み出す ~ヒトの脳活動パターンから見ている画像の再構成に成功~
http://www.atr.co.jp/html/topics/press_081211_j.html
であります。こちらは正々堂々『ニューロン』誌に掲載されてるわけですから,もうこれ,憚ることなく,スゴイ研究なわけですけど,改めて,画期的な研究と岩猿を聖天大斉もといいわざるを得ないわけですけど,スゴイ研究であることは今さら僕が言うまでもないので,海賊の一味のコックさんもとい賛辞は蛇足と思いますので割愛。神谷先生については過去に記事ありですので,ご覧ください。
http://blog.goo.ne.jp/psy-pub/e/f9e6d70fcea21ed09adbb7ea0ca17882
http://blog.goo.ne.jp/psy-pub/e/da09227ec52b1e77a339f3ed015c68da
いやあスゴイ,スゴイ。
で,まあ,これに限らず,基礎も臨床も認知全盛花盛りの心理学業界,もう明らかに,「見る」が旬,と思うわけですけど,そういったことは,たとえば,
こういう研究花盛りの現況をみれば,これ明らかなわけですよね。うん明らか明らか。てかこれ良書です!
あとは諸悪の根源インターネット(笑)! 諸悪の根源かどうかはさておいて,もうこれ,視覚重視すぎ! ネットをする資格は視覚なんだとツマンネエだじゃれを言いたくなるほど,もう視覚。私はむしろ逆で資格より目。視覚なかったら楽しめやしない。どうなんですかね。まあこんなところでどうなんですかねといったところでしょうがないけど,本当にしょうがないのかよくわかりませんけどね。
あと,発達障害ブームが始まったのか,最中なのか,終わったのか,僕はよくわかりませんけど(わからないことばっかりだよ),
TEACCHのキモは「視覚構造化」ということですが,発達障害の中核である自閉症において,視覚構造化の重要性がうたわれることと,発達障害(と診断される)子どもの数が増えているということと,現代が視覚優位社会であることは,結びつけて語るに十分な必然性があるように思われますし,実際,そのような語り方をする専門家の先生もいたように記憶している次第ですね。
と言うわけで,現代人には必須の視覚,なわけでして,そんな状況下では,こういうサイバーパンクも登場し,
■義眼をウエブカメラに換装したいと望む米国美人アーチスト
http://chiquita.blog17.fc2.com/blog-entry-3771.html
PKディックもビックラ仰天,流れよわが涙,もとい,流れよわが視覚映像(オンラインで),なんて凄すぎるよな!
つうことで猫も杓子も視覚,視覚,「おい,その四角い画面(ディスプレイ)に映る君の「ココロ」は何色だい?」という自作のオヤジポエムを自由律俳句と称して,サラリーマン川柳欄に投稿したくなるくらい,視覚優位なんでありますが,で,こっからお得意の我田引水,手前勝手のソモソモ論,ブチかましたいと思うわけですよ。
ま,しょの~,だいたいやね~,みみずだっておけらだってあめんぼだってみんなみんな生きているんだと歌われている,その当のみみずさん,これ,目がないわけですよ。無視覚。そのクラシックな風体を見るに,なんとなく太古の歴史からの連綿たる流れを感じさせてくれる生物界の重鎮,みみずさまには,目はございません。その事実忘れてはならんわけです(ホンマかよ)。
ま,みみずひめはさておき,でも,これ,視覚ってのは何ぞや,と考えますと,これ,すなわち「光の感知」といえますな。光の感知という点でいえば,もう植物においても実装配備されてる由緒正しい機能なわけでして,これ,なかなか「生物の本質的な機能ですよ?」感が満載なわけで,みみずより植物様のほうが歴史も古く,より本質的なのでございますわよ的なサツアイかまされたひにゃあ,こちとらブチ切れですよ。じゃあ,フラクタル無機鉱物が,有機物スープが,コアセルベートが,光を感知しますか? とね。……もはや(そもそも)科学的でもなんでもない,小学生の口げんか的な因縁に過ぎないわけですけど,そう思うわけですね。
ということで,いわゆる五感ですけど,視覚,聴覚,嗅覚,味覚,触覚,のうち,嗅覚と味覚はこれ,生体内での化学反応つう高尚な機能ですので,これは高次だと勝手に断定しまして,残るは視覚,聴覚,触覚ですが,聴覚と触覚はこれ似ている,すなわち,聴覚はしょせん鼓膜の振動(しょせん男の行く道は坂道)ですから,もうこれ,ほとんど触覚といって差し支えないわけでして,で,視覚と聴覚,の最終対決,もちろん始原は,触覚であると,思うわけです。昆虫様においては,単眼・複眼なんて飾りです,偉い人にはそれがわからんのです。それよりもガンダムの角のごとくの触覚ですよ。プラモのガンダムも角がなければただのジム,という諺もあるとおり(ないです),触覚大勝利宣言ここにしたいわけですね。
といいつつ,たとえば,現代の大宗教こと科学,その標榜するは客観性,ということで,もう名は体を表わすのとおり,明らかに視覚ってのは,それに沿うわけですよな。見て分かる,それが客観,実に分かりやすいわけで,それに引き換え,客体とかいわれても,なんかピンとこない。科学にしろメディアにしろインターネットにしろ,それは見るものであって,肌で感じるものではないのでして,昔はやった穿った言い方で「皮膚感覚が云々」とかありましたけど,メタファーにしても適当すぎるわけで,もはやそんな言葉は日常感覚ではあんまり了解できないつうか,見ることのリアリティ(あるいは非リアリティ)には遠く及ばない気がするんですよね。
実際,見ることの心理学と,触ることの心理学,どっちが研究やりやすいかなんて,問うのもバカらしいわけでして,上記の神谷先生の画期的成果,これをたとえば触覚に置き換えると,他人の触覚を触って分かる,って言われてもなんかよく分からんわけで,それに引き換え,なんでしょう,この,視覚というものの手軽さは! 論文にしろ学会発表にしろ,最大にアピールできるのが視覚なんですよね,当たり前なんだけど。
結局科学とか客観性とか,極言すれば,相互の意味了解,につきるわけで,するってえと,その意味了解とやらがしやすいものに人気が集まるのはこれ必然。したがって,視覚優位社会の完成,アーハン?
というわけで,われわれは「触覚」を失い続けている! などという,誠にありきたりな,そしてそっからグッドオールドデイズまるだしの若者批判に突入したくなる気持ちを抑えつつ,しかし本当にわれわれが失ったものってなんだろう? というのを郷愁抜きに考えるのは必要かもしれない。
まあそもそも臨床心理学とか発達心理学とか,失われたものを取り戻せ(あるいは新たに獲得せよ)つうのがわりと至上命題のところがありますけど,まあたとえば愛着とかね,愛着がない!とか言ったって,そもそも愛着あるってなによとか,昔は愛着あったのかよ,とかいう言い方もできますれば,また,じゃあ心理学的に正しい「愛着ある子育て」実行すれば,絶対幸せになれるのか? とかいうインネンをつけることも可能なわけで,結局,そういった概念だって,ほんの一側面に過ぎないわけで(もちろん重要な一側面ですが),そういう意味では批評的なんですよね。つまり,それが何かを直接生み出すわけではなく,生み出された何かに対する一批評,ということですな。すると科学は批評か,答えはYES AND NO。
と抽象的な言葉遊びに逃げつつも,人生の実践においては,もちろん批評は批評でしかなく,メタな人生はないですから,人生の実践における実践的介入において,摩訶不思議な事態が起こる,ということを否定することはできません。もちろん摩訶不思議なままで良いとも思ってませんけど,摩訶不思議であることはもうしょうがないわけです。
で,
もうね。触覚を刺激する活動のオンパレードですよ。身体を追求して精神に還る。その身体の追求の仕方が独自すぎてマジスゴイ。
この一見,郷愁をさそうような,非常に泥臭い実践,進化の過程を再体験するなんつう,手前勝手なストーリーの元,繰り広げられる活動の数々,これを「そんなもの科学的裏づけがない」と一蹴することはあまりにも簡単ですが,簡単ですが,科学的な裏づけのある人生を送っても幸せになれるとは限らないわけで,だいたい僕自身の人生に科学的裏づけなんてないわけでして(ある人いたら教えてほしい),そんなら楽しそうなほうがイイ! ということもできますな。
あと,この本の面白いところは,序文を小泉英明さんが書いている,ということです。まああやしいオカルト本の場合,「名誉教授」のおじいちゃんをだまくらかして権威付けをするという姑息なことをやったりしますが,この本の場合は,小泉英明さん,皆さんご存知の光トポグラフィーの開発者である,日本の誇る研究者,もちろんノーベル賞候補の専門家にして日本の知の至宝が書いている,というところは,もうそれだけで興味が湧いてくるわけですね。
で,この小泉さんの序文,さくらんぼ保育を褒めよ讃えよに終始してたら,どうしようもないですけど,さにあらず! この秘密を解明したいなどと,研究者魂丸出しで,実に熱いんですね。あたかも共同研究者を募ってるかのような序文で,さすがにノーベル賞級の研究者は一味違うと思い知るわけです。
齊藤先生のお話自体は,さすがにもう相当のおばあちゃんということもあり,ご老境ならではの粘りのなさ,説明のなさがあるんですけど,実践例はとにかく面白いです。宗教的になっていきそうで,なっていかないのは,目的と対象がはっきりしてるからでしょうね。
しかし,この妙なる実践をメタしちゃおう,つまりこれでもって現代社会批評しちまおうとなると,そこには当然落とし穴が待ってるわけで,科学・非科学限らず,メタはすべて,落とし穴が待ってるわけです。そういう意味では日常的実感ってのは確かな面もあれば,一方でデタラメな面もあるわけですよね。
で,
を今読んでます! という話につながったところでめでたしめでたし。え? 内容? まあそれは読んでみてくださいな。
それでは!
 | 心の病は脳の傷―うつ病・統合失調症・認知症が治る田辺 功西村書店 2008-12売り上げランキング : 307 by G-Tools |
まあこの本,売れているそうです。売れているそうですが,懸命なる読者諸賢ならお分かりのとおり,推して知るべし,という内容で(たとえば.引用文献明示なし,云々),非常に残念な感じでありますが,しかしこれが売れているという事実を,民度の低さ,リテラシーの低さのせいにして嘆いても,DISってもしょうがないのです(もちろんそうする意味はあるけど)。見たい! 一目瞭然したい! そういう僕含む愚民のキモチ,分かってほしいのですよ。騙されてる,というよりはもう,全力で騙されにいってる,としか思えない暴挙ではありますが,見たいもの見たい,そのキモチはCan't Stopなわけですよ。
まじめに言うと,こういう方向性,ないわけではないと思うけど,現段階では大雑把過ぎて,まあちょっとアレだなという感じですね。現時点の人類の科学力では無理ですから,自然,超科学に頼らざるを得ない,といったところでしょうかね。
ま,というところで,本題いきたいわけですけど(なんなんだ),ちょっと前(つうか去年),こういうニュースがあって,興奮した人も多かろうと思ったのが,
■脳から知覚映像を読み出す ~ヒトの脳活動パターンから見ている画像の再構成に成功~
http://www.atr.co.jp/html/topics/press_081211_j.html
であります。こちらは正々堂々『ニューロン』誌に掲載されてるわけですから,もうこれ,憚ることなく,スゴイ研究なわけですけど,改めて,画期的な研究と岩猿を聖天大斉もといいわざるを得ないわけですけど,スゴイ研究であることは今さら僕が言うまでもないので,海賊の一味のコックさんもとい賛辞は蛇足と思いますので割愛。神谷先生については過去に記事ありですので,ご覧ください。
http://blog.goo.ne.jp/psy-pub/e/f9e6d70fcea21ed09adbb7ea0ca17882
http://blog.goo.ne.jp/psy-pub/e/da09227ec52b1e77a339f3ed015c68da
いやあスゴイ,スゴイ。
で,まあ,これに限らず,基礎も臨床も認知全盛花盛りの心理学業界,もう明らかに,「見る」が旬,と思うわけですけど,そういったことは,たとえば,
 | 赤ちゃんの視覚と心の発達山口 真美 金沢 創東京大学出版会 2008-09売り上げランキング : 127768 by G-Tools |
こういう研究花盛りの現況をみれば,これ明らかなわけですよね。うん明らか明らか。てかこれ良書です!
あとは諸悪の根源インターネット(笑)! 諸悪の根源かどうかはさておいて,もうこれ,視覚重視すぎ! ネットをする資格は視覚なんだとツマンネエだじゃれを言いたくなるほど,もう視覚。私はむしろ逆で資格より目。視覚なかったら楽しめやしない。どうなんですかね。まあこんなところでどうなんですかねといったところでしょうがないけど,本当にしょうがないのかよくわかりませんけどね。
あと,発達障害ブームが始まったのか,最中なのか,終わったのか,僕はよくわかりませんけど(わからないことばっかりだよ),
 | 自閉症児のためのTEACCHハンドブック―自閉症療育ハンドブック (学研のヒューマンケアブックス)佐々木 正美学習研究社 2008-03売り上げランキング : 103839 by G-Tools |
TEACCHのキモは「視覚構造化」ということですが,発達障害の中核である自閉症において,視覚構造化の重要性がうたわれることと,発達障害(と診断される)子どもの数が増えているということと,現代が視覚優位社会であることは,結びつけて語るに十分な必然性があるように思われますし,実際,そのような語り方をする専門家の先生もいたように記憶している次第ですね。
と言うわけで,現代人には必須の視覚,なわけでして,そんな状況下では,こういうサイバーパンクも登場し,
■義眼をウエブカメラに換装したいと望む米国美人アーチスト
http://chiquita.blog17.fc2.com/blog-entry-3771.html
PKディックもビックラ仰天,流れよわが涙,もとい,流れよわが視覚映像(オンラインで),なんて凄すぎるよな!
つうことで猫も杓子も視覚,視覚,「おい,その四角い画面(ディスプレイ)に映る君の「ココロ」は何色だい?」という自作のオヤジポエムを自由律俳句と称して,サラリーマン川柳欄に投稿したくなるくらい,視覚優位なんでありますが,で,こっからお得意の我田引水,手前勝手のソモソモ論,ブチかましたいと思うわけですよ。
ま,しょの~,だいたいやね~,みみずだっておけらだってあめんぼだってみんなみんな生きているんだと歌われている,その当のみみずさん,これ,目がないわけですよ。無視覚。そのクラシックな風体を見るに,なんとなく太古の歴史からの連綿たる流れを感じさせてくれる生物界の重鎮,みみずさまには,目はございません。その事実忘れてはならんわけです(ホンマかよ)。
![みみずひめ [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51fnqNN0WHL._SL160_.jpg) | みみずひめ [DVD]鳥居みゆきビクターエンタテインメント 2009-01-21売り上げランキング : 345 by G-Tools |
ま,みみずひめはさておき,でも,これ,視覚ってのは何ぞや,と考えますと,これ,すなわち「光の感知」といえますな。光の感知という点でいえば,もう植物においても実装配備されてる由緒正しい機能なわけでして,これ,なかなか「生物の本質的な機能ですよ?」感が満載なわけで,みみずより植物様のほうが歴史も古く,より本質的なのでございますわよ的なサツアイかまされたひにゃあ,こちとらブチ切れですよ。じゃあ,フラクタル無機鉱物が,有機物スープが,コアセルベートが,光を感知しますか? とね。……もはや(そもそも)科学的でもなんでもない,小学生の口げんか的な因縁に過ぎないわけですけど,そう思うわけですね。
ということで,いわゆる五感ですけど,視覚,聴覚,嗅覚,味覚,触覚,のうち,嗅覚と味覚はこれ,生体内での化学反応つう高尚な機能ですので,これは高次だと勝手に断定しまして,残るは視覚,聴覚,触覚ですが,聴覚と触覚はこれ似ている,すなわち,聴覚はしょせん鼓膜の振動(しょせん男の行く道は坂道)ですから,もうこれ,ほとんど触覚といって差し支えないわけでして,で,視覚と聴覚,の最終対決,もちろん始原は,触覚であると,思うわけです。昆虫様においては,単眼・複眼なんて飾りです,偉い人にはそれがわからんのです。それよりもガンダムの角のごとくの触覚ですよ。プラモのガンダムも角がなければただのジム,という諺もあるとおり(ないです),触覚大勝利宣言ここにしたいわけですね。
といいつつ,たとえば,現代の大宗教こと科学,その標榜するは客観性,ということで,もう名は体を表わすのとおり,明らかに視覚ってのは,それに沿うわけですよな。見て分かる,それが客観,実に分かりやすいわけで,それに引き換え,客体とかいわれても,なんかピンとこない。科学にしろメディアにしろインターネットにしろ,それは見るものであって,肌で感じるものではないのでして,昔はやった穿った言い方で「皮膚感覚が云々」とかありましたけど,メタファーにしても適当すぎるわけで,もはやそんな言葉は日常感覚ではあんまり了解できないつうか,見ることのリアリティ(あるいは非リアリティ)には遠く及ばない気がするんですよね。
実際,見ることの心理学と,触ることの心理学,どっちが研究やりやすいかなんて,問うのもバカらしいわけでして,上記の神谷先生の画期的成果,これをたとえば触覚に置き換えると,他人の触覚を触って分かる,って言われてもなんかよく分からんわけで,それに引き換え,なんでしょう,この,視覚というものの手軽さは! 論文にしろ学会発表にしろ,最大にアピールできるのが視覚なんですよね,当たり前なんだけど。
結局科学とか客観性とか,極言すれば,相互の意味了解,につきるわけで,するってえと,その意味了解とやらがしやすいものに人気が集まるのはこれ必然。したがって,視覚優位社会の完成,アーハン?
というわけで,われわれは「触覚」を失い続けている! などという,誠にありきたりな,そしてそっからグッドオールドデイズまるだしの若者批判に突入したくなる気持ちを抑えつつ,しかし本当にわれわれが失ったものってなんだろう? というのを郷愁抜きに考えるのは必要かもしれない。
まあそもそも臨床心理学とか発達心理学とか,失われたものを取り戻せ(あるいは新たに獲得せよ)つうのがわりと至上命題のところがありますけど,まあたとえば愛着とかね,愛着がない!とか言ったって,そもそも愛着あるってなによとか,昔は愛着あったのかよ,とかいう言い方もできますれば,また,じゃあ心理学的に正しい「愛着ある子育て」実行すれば,絶対幸せになれるのか? とかいうインネンをつけることも可能なわけで,結局,そういった概念だって,ほんの一側面に過ぎないわけで(もちろん重要な一側面ですが),そういう意味では批評的なんですよね。つまり,それが何かを直接生み出すわけではなく,生み出された何かに対する一批評,ということですな。すると科学は批評か,答えはYES AND NO。
と抽象的な言葉遊びに逃げつつも,人生の実践においては,もちろん批評は批評でしかなく,メタな人生はないですから,人生の実践における実践的介入において,摩訶不思議な事態が起こる,ということを否定することはできません。もちろん摩訶不思議なままで良いとも思ってませんけど,摩訶不思議であることはもうしょうがないわけです。
で,
 | 生物の進化に学ぶ乳幼児期の子育て斎藤 公子かもがわ出版 2007-08売り上げランキング : 103117 by G-Tools |
もうね。触覚を刺激する活動のオンパレードですよ。身体を追求して精神に還る。その身体の追求の仕方が独自すぎてマジスゴイ。
この一見,郷愁をさそうような,非常に泥臭い実践,進化の過程を再体験するなんつう,手前勝手なストーリーの元,繰り広げられる活動の数々,これを「そんなもの科学的裏づけがない」と一蹴することはあまりにも簡単ですが,簡単ですが,科学的な裏づけのある人生を送っても幸せになれるとは限らないわけで,だいたい僕自身の人生に科学的裏づけなんてないわけでして(ある人いたら教えてほしい),そんなら楽しそうなほうがイイ! ということもできますな。
あと,この本の面白いところは,序文を小泉英明さんが書いている,ということです。まああやしいオカルト本の場合,「名誉教授」のおじいちゃんをだまくらかして権威付けをするという姑息なことをやったりしますが,この本の場合は,小泉英明さん,皆さんご存知の光トポグラフィーの開発者である,日本の誇る研究者,もちろんノーベル賞候補の専門家にして日本の知の至宝が書いている,というところは,もうそれだけで興味が湧いてくるわけですね。
で,この小泉さんの序文,さくらんぼ保育を褒めよ讃えよに終始してたら,どうしようもないですけど,さにあらず! この秘密を解明したいなどと,研究者魂丸出しで,実に熱いんですね。あたかも共同研究者を募ってるかのような序文で,さすがにノーベル賞級の研究者は一味違うと思い知るわけです。
齊藤先生のお話自体は,さすがにもう相当のおばあちゃんということもあり,ご老境ならではの粘りのなさ,説明のなさがあるんですけど,実践例はとにかく面白いです。宗教的になっていきそうで,なっていかないのは,目的と対象がはっきりしてるからでしょうね。
しかし,この妙なる実践をメタしちゃおう,つまりこれでもって現代社会批評しちまおうとなると,そこには当然落とし穴が待ってるわけで,科学・非科学限らず,メタはすべて,落とし穴が待ってるわけです。そういう意味では日常的実感ってのは確かな面もあれば,一方でデタラメな面もあるわけですよね。
で,
 | オオカミ少女はいなかった 心理学の神話をめぐる冒険鈴木 光太郎新曜社 2008-10-03売り上げランキング : 2193 by G-Tools |
を今読んでます! という話につながったところでめでたしめでたし。え? 内容? まあそれは読んでみてくださいな。
それでは!












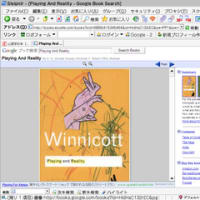


というか,廃墟にコメント痛みいります!
飯を喰ってやがて死ぬまでは、生きてますよ!
しびれる台詞です。
しばし考えましたが,たぶんホウ統が文字化けしたんだろうと思いますし,そして確かにホウ統のセリフですので,おっしゃるとおりなのでございます。
何かのお役にたてると思います。
参考までに
太陽出版
伊達浩二 著者
黄金色に輝いた道
同書,労作であるのでしょうし,少なからずの興味を持つところですが,文脈を考慮しない,このような純然たる宣伝のようなコメントはたいへん残念に思います。