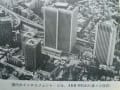失われた景観 戦後日本が築いたもの, 松原隆一郎, PHP新書 227, 2002年
・現代日本の景観について。似たような問題設定の本があったっけ、と思ったら参考文献の第1冊目として挙げられていました。『うるさい日本の私』 問題設定は似ていても、その問題へのアプローチの仕方は全く異なり、オモシロオカシク・ヤワラカクというのではなく、あくまでもアカデミックな雰囲気。景観やその他環境問題について興味があり、その勉強のために読むような、やや硬めの内容です。
・個人的には、景観の良し悪しはどうやって判断するのか、その評価法について興味があったのですが、それに関する記述は無く、飽くまでも行政や経済の立場からの考察でした。
・外を歩くときに注意して空を見上げてみると、本書で指摘されているように、こんな田舎でも想像以上にたくさんの電線が張り巡らされていることにはじめて気がつきました。慣れって恐ろしい。
・収録された事例。第一章:ロードサイド・ショップが生み出した均質な郊外景観(国道16号線)。第二章:公共事業による生活景観の破壊(神戸)。第三章:マンション建設締め出しに端を発した自治体による条例策定(神奈川県・真鶴町)。第四章:電線類地中化(東京都・阿佐ヶ谷)。
・「けれども私は、清潔で新しくはあっても秩序のないことにかけてこれほど突出している景観を持つ国は、世界に類を見ないと感じている。そもそもそうした感覚、つまり景観が荒廃しているという共通の認識がないことじたいについても、絶望的な気分にさせられてしまう。」p.10
・「ついでにいうと、私は道路に白あるいは黄で交通標識をしるすペンキについても塗り方の無神経さが気に食わない。」p.15
・「視野を電線で区切られず、そぐわぬペンキを塗られず、景色により自分の居場所が分かり、せめて旅行先では看板の洪水にみまわれず、暮らしている町では過去との連続を実感していたい――私が景観に望むのは、そうした些細なことである。」p.16
・「つまり私を批判する人々は生活を支える経済の振興を望んでいるのであり、私が日々の暮らしで手放しがたく考える景観は、経済活動によって危機にさらされているのである。」p.16
・「ある景観を醜悪と断じるには、対比すべき景観の美しさに感服した体験を有していなければならない。」p.36
・「ロードサイドビジネスの看板は、歩く人にではなく自動車で走りぬける人の目に留まるように工夫されているために、単純でけばけばしいものとなった。」p.48
・「結局のところ、我が国では、日常景観を守るような社会的政治的制度はいまだ十分には整備されていないのである。住吉川訴訟が暴き出したのは、住民の福祉向上に専心するはずの社会主義政権にしてからが住民の日常生活を維持しようとはしていないという事実であった。」p.94
・「これまで日本の景観は、都市計画家や行政など一部の人々によって論じられ、しかし現実には経済の趨勢によって形作られてきた。それに対して日本における景観の崩壊理由を経済や法の特質にまで遡って分析し、政治論や認識論を駆使して対案を提起した点で、真鶴の条例は衝撃的であった。」p.117
・「それゆえ葬式の折りに派手な色彩の服を着ておれば、顰蹙を買う。だが、葬式に列席する際の服装は慣行によって決まっているだけであり、公権力が規制しているわけではない。服装と建築物に対する規制とは、どこがどう違うのだろうか。」p.121
・「日常景観には、地域によって異なり、数値化しえない質をともなうという性格がある。」p.131
・「チャールズ皇太子というとダイアナ妃がらみの話題ばかりが連想されるが、イギリスではそれ以外に、特異なポジションから言論界に切り込み、物議を醸してきた人物という顔が知られている。」p.143
・「景観を維持し発展させるのは条例ではなく、文化や政治、経済を貫いて条例を支える精神である。」p.159
・「「架空電線」は、欧米の主要都市の中心地には存在していない。対照的に我が国では、とりわけ住宅街で電線は増える一方である。そのことを普段国内で生活しているとき我々は意識していないのだが、80年代以降の円高で急増した海外渡航者によりコントラストの明瞭な違いに突如さらされ、その存在に気づく。」p.177
・「本書は日常景観を汚して省みない日本社会がどのようなものであるのかを描くことを目的としている。そうした意図の背景となっているのが、自分の記憶を呼び起こしてくれるはずの景観が失われつつあることに対する、右記のようなごく個人的な心情である。それは個人的ではあるが、普遍的でもあると信じている。」p.223
?かんぎゅうじゅうとう【汗牛充棟】 (柳宗元「唐故給事中陸文通墓表」の「其為レ書、処則充二棟宇一、出則汗二牛馬一」から。ひっぱるには牛馬が汗をかき、積み上げては家の棟木にまで届くくらいの量の意)蔵書が非常に多いことのたとえ。
・現代日本の景観について。似たような問題設定の本があったっけ、と思ったら参考文献の第1冊目として挙げられていました。『うるさい日本の私』 問題設定は似ていても、その問題へのアプローチの仕方は全く異なり、オモシロオカシク・ヤワラカクというのではなく、あくまでもアカデミックな雰囲気。景観やその他環境問題について興味があり、その勉強のために読むような、やや硬めの内容です。
・個人的には、景観の良し悪しはどうやって判断するのか、その評価法について興味があったのですが、それに関する記述は無く、飽くまでも行政や経済の立場からの考察でした。
・外を歩くときに注意して空を見上げてみると、本書で指摘されているように、こんな田舎でも想像以上にたくさんの電線が張り巡らされていることにはじめて気がつきました。慣れって恐ろしい。
・収録された事例。第一章:ロードサイド・ショップが生み出した均質な郊外景観(国道16号線)。第二章:公共事業による生活景観の破壊(神戸)。第三章:マンション建設締め出しに端を発した自治体による条例策定(神奈川県・真鶴町)。第四章:電線類地中化(東京都・阿佐ヶ谷)。
・「けれども私は、清潔で新しくはあっても秩序のないことにかけてこれほど突出している景観を持つ国は、世界に類を見ないと感じている。そもそもそうした感覚、つまり景観が荒廃しているという共通の認識がないことじたいについても、絶望的な気分にさせられてしまう。」p.10
・「ついでにいうと、私は道路に白あるいは黄で交通標識をしるすペンキについても塗り方の無神経さが気に食わない。」p.15
・「視野を電線で区切られず、そぐわぬペンキを塗られず、景色により自分の居場所が分かり、せめて旅行先では看板の洪水にみまわれず、暮らしている町では過去との連続を実感していたい――私が景観に望むのは、そうした些細なことである。」p.16
・「つまり私を批判する人々は生活を支える経済の振興を望んでいるのであり、私が日々の暮らしで手放しがたく考える景観は、経済活動によって危機にさらされているのである。」p.16
・「ある景観を醜悪と断じるには、対比すべき景観の美しさに感服した体験を有していなければならない。」p.36
・「ロードサイドビジネスの看板は、歩く人にではなく自動車で走りぬける人の目に留まるように工夫されているために、単純でけばけばしいものとなった。」p.48
・「結局のところ、我が国では、日常景観を守るような社会的政治的制度はいまだ十分には整備されていないのである。住吉川訴訟が暴き出したのは、住民の福祉向上に専心するはずの社会主義政権にしてからが住民の日常生活を維持しようとはしていないという事実であった。」p.94
・「これまで日本の景観は、都市計画家や行政など一部の人々によって論じられ、しかし現実には経済の趨勢によって形作られてきた。それに対して日本における景観の崩壊理由を経済や法の特質にまで遡って分析し、政治論や認識論を駆使して対案を提起した点で、真鶴の条例は衝撃的であった。」p.117
・「それゆえ葬式の折りに派手な色彩の服を着ておれば、顰蹙を買う。だが、葬式に列席する際の服装は慣行によって決まっているだけであり、公権力が規制しているわけではない。服装と建築物に対する規制とは、どこがどう違うのだろうか。」p.121
・「日常景観には、地域によって異なり、数値化しえない質をともなうという性格がある。」p.131
・「チャールズ皇太子というとダイアナ妃がらみの話題ばかりが連想されるが、イギリスではそれ以外に、特異なポジションから言論界に切り込み、物議を醸してきた人物という顔が知られている。」p.143
・「景観を維持し発展させるのは条例ではなく、文化や政治、経済を貫いて条例を支える精神である。」p.159
・「「架空電線」は、欧米の主要都市の中心地には存在していない。対照的に我が国では、とりわけ住宅街で電線は増える一方である。そのことを普段国内で生活しているとき我々は意識していないのだが、80年代以降の円高で急増した海外渡航者によりコントラストの明瞭な違いに突如さらされ、その存在に気づく。」p.177
・「本書は日常景観を汚して省みない日本社会がどのようなものであるのかを描くことを目的としている。そうした意図の背景となっているのが、自分の記憶を呼び起こしてくれるはずの景観が失われつつあることに対する、右記のようなごく個人的な心情である。それは個人的ではあるが、普遍的でもあると信じている。」p.223
?かんぎゅうじゅうとう【汗牛充棟】 (柳宗元「唐故給事中陸文通墓表」の「其為レ書、処則充二棟宇一、出則汗二牛馬一」から。ひっぱるには牛馬が汗をかき、積み上げては家の棟木にまで届くくらいの量の意)蔵書が非常に多いことのたとえ。