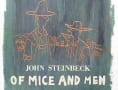生物学個人授業, 岡田節人 南伸坊, 新潮文庫 み-29-1(6519), 2000年
・生物学分野の大家、岡田節人氏を先生とし、生徒として南伸坊氏が受けた講義の記録。
・細かい知識ではなく、大雑把に『どんな感じか』をつかむには格好の書。この本の後、養老猛司氏(解剖学)などを招き、「個人授業」はシリーズ化。
・「「もう一つ、大事なことがある!」 ときた 「いいですか? それは、生命は絶えたことがない! ということや。これを知らんアホがおるのや。ピンときとらんアホが!」 といきなりおこってます。」p.20
・「体細胞というのは一代で終わりでございます。生殖細胞、いつまでも絶えることがない」p.21
・「遺伝子やDNAには、ファンがいないんや。暗いイメージで、応援団あらへん。応援団ないさかい、研究の費用を得るにも苦労する。」p.22
・「あの本は面白いよ。生物学を学びたければ、『ジュラシック・パーク』を読みなさい。特に、前の三分の一ぐらいの、かなり科学的なことの書いてある部分を、飛ばし読みせんと、全部読んでみい。大学程度の生物学がみんな書いてある。」p.23
・「そうなのだ。死の話というのは、みんな本当は「自分が死ぬ話」なんですよ。死の美学だの、死の価値だの、神秘だのエロチシズムだの、色々いうけど、それは具体的に「自分が死ぬ」っていうことが、結局はわからない恐ろしさを話してるっていうことなんですね。」p.26
・「命という言葉には、哲学と生物学で抽象のレベルが違っているという話。「生命は絶えたことがない!」というフレーズを、もう一度書き留めておきましょう。」p.32
・「生命を失うようなガンが発生する生物は、えらい限られております。(中略)イモリには、ガンはほとんどありません。発ガン物質をなんぼ注射しても食べさせてもガンにはなりません。何でイモリにはガンがないのや?(中略)つまり、再生のような現象をやることによって、ガンを克服してしもうとるんです」p.36
・「細胞同士がくっつくというのは、どういう仕組みになっているのか、何故、心臓は心臓の細胞同士だけでくっついて、心臓になるのか? そのカラクリがわかれば、細胞同士のくっつき方の弱い転移するガン細胞を、一つ所に固定しておくことができる。(中略)ガンが人を死に至らしめるのは、ガン細胞が、ガン細胞同士でしっかりくっついていないからだというわけでした。」p.40
・「南 本当に、恐竜を生き返らせることは可能ですか? 岡田 残念ながらノーであります。(中略)いちばん大事なことは、DNAは物質であって、生きているものではないということです。」p.56
・「私にとっての生きものとはこうなります。 「生きものとは、自らの故障を自らで見つけ、自らで治癒するようなしなやかさをもったシステムである」 生きもののしなやかな性質こそは、私をとらえてやまない「生きものの魅力」であり、しなやかさとは生きものへのオマージュであります」p.63
・「「ひとことで言うたら、発生というのは、オタマジャクシはカエルの子、いうことですなあ」」p.77
・「子供のころから、虫が好きという人がいます。ボクが面白そうだな、と思う人にはそういう人が多いんです。養老猛司先生とか、岡田先生とか。」p.79
・「「分化というのは仮の姿なんですよ。本質的には、何も変わっとらん、卵のときと。見かけは筋肉やら神経やらえらい違うとるが、あれは仮の姿や、逆から見たらいいんです」(中略)「分化を語れなければ、発生は語れません」」p.82
・「すべての細胞はおなじ遺伝子をもっているけれども、どの遺伝子が使われるかは、細胞によって違うのです。すべての遺伝子が常に働いているのではない。異なった遺伝子群が働くことが分化の実態なんでした。これを岡田先生は「宝の持ち腐れ作戦」と名づけました。 では、この遺伝子の働きのスイッチをONにしたりOFFにしたりするのはなんなのでしょう。これもまた遺伝子なんでした。」p.99
・「ホメオボックスの発見は、生物学を変えた。レベルを一つ違うものに上げたんです。体のマクロな成り立ちを遺伝子の言葉で説明できる。これがキイだ! と、かなりの人がすぐに気づいたはずや、1984年のことです。」p.101
・「ちなみに、岡田先生がホメオティック・ジーンに日本語で命名するなら「巨視的形態統括者」にするとのことです。」p.107
・「エボリューションというのは発展、生物学的には、多様性が増えたということや。一種類から始まって、35億年の歴史の間で8000万種まで多様性をきわめてきたと、そこに進化の一番大きな意味がある、ということですね」p.124
・「甲虫のね、体のサイズが10分の1になると種類が100倍になっとる、というルールが成立するというのです。」p.134
・「細胞間を接着できるような物質をつくり出す遺伝子というのがあればこそ、多細胞生物ができるんですからね。カドヘリンの歴史をたどれば、多細胞生物の起源が分かる。」p.144
・「生物の分類にはランクがありまして、一番下がスピーシス(種)、そのスピーシスの幾らかのよく似たものを集めてジーナス(属)、そのジーナスを集めてトライブ(族)、そのトライブを集めてファミリー(科)となる。(」p.150
・「私の経験からいうと、生物の科学についての話題のなかで、多くの人たちを麻薬の如くに引きつけているのは、獲得された形質は遺伝するか? というものでしょう。そして皆さんは、獲得形質も少しは遺伝する、という答えを生物学からなんとか引き出したいと期待しておられるとしか思えないのです。獲得形質の遺伝は起こりません。」p.157
・「生きものについての科学のあり方とは、「共通のこと」と「異なっていること」とのはざまの悩みである、ともいえるのです。」p.173
・「なにもいまさら「生きものは複雑である」と言って偉ぶってみせることはありません。私はもっといい言葉を使っています。それは「生きものは、よくできている」という言葉です。同じことだと思われるかもしれませんが、えらく違います。」p.179
・「最近の私の心境では、50の生命の解釈論よりも、ある一つの生きものが演ずる一つの現象を、ちょっと深くみるほうが、ずっとおもろい。そのおもろいことから、生きているとはどういうことかを具体的に感得していただければ、という立場を、最近とっております。」p.180
・「すべての生物の中で、再生能力が最も貧弱なのが人間です。治せるものといったら、怪我くらいなものです。」p.198
・「常にある程度の余裕をもって生きている、それが「生きもの」なのかもしれません。その余裕のことを、私は「損得ぼちぼち」と、至って関西風に表現いたしました。」p.203
・「わかる快感というのは、わかったつもりでいたことを、こなごなに砕かれる快感なのだ。人間はわかった時に快感を感じるようにセットされている、とボクは思ってる。わかった風なことを書いてしまいましたが、もちろん砕かれるべき常識、知識もまた、ためこんでいなければ、その快感も少ないんですけどね。」p.204
・「この私のいう、 "わかるテーマの生物学" は、たぶんネオ・マクロ生物学と呼んでおいてもよいと思う。あるいは、古くからの "生命体" という言葉を復活させて生命体生物学を(漢字の好きな人は)あててもよい。」p.216
《チェック本》 マイケル・クライトン『ジュラシック・パーク』
・生物学分野の大家、岡田節人氏を先生とし、生徒として南伸坊氏が受けた講義の記録。
・細かい知識ではなく、大雑把に『どんな感じか』をつかむには格好の書。この本の後、養老猛司氏(解剖学)などを招き、「個人授業」はシリーズ化。
・「「もう一つ、大事なことがある!」 ときた 「いいですか? それは、生命は絶えたことがない! ということや。これを知らんアホがおるのや。ピンときとらんアホが!」 といきなりおこってます。」p.20
・「体細胞というのは一代で終わりでございます。生殖細胞、いつまでも絶えることがない」p.21
・「遺伝子やDNAには、ファンがいないんや。暗いイメージで、応援団あらへん。応援団ないさかい、研究の費用を得るにも苦労する。」p.22
・「あの本は面白いよ。生物学を学びたければ、『ジュラシック・パーク』を読みなさい。特に、前の三分の一ぐらいの、かなり科学的なことの書いてある部分を、飛ばし読みせんと、全部読んでみい。大学程度の生物学がみんな書いてある。」p.23
・「そうなのだ。死の話というのは、みんな本当は「自分が死ぬ話」なんですよ。死の美学だの、死の価値だの、神秘だのエロチシズムだの、色々いうけど、それは具体的に「自分が死ぬ」っていうことが、結局はわからない恐ろしさを話してるっていうことなんですね。」p.26
・「命という言葉には、哲学と生物学で抽象のレベルが違っているという話。「生命は絶えたことがない!」というフレーズを、もう一度書き留めておきましょう。」p.32
・「生命を失うようなガンが発生する生物は、えらい限られております。(中略)イモリには、ガンはほとんどありません。発ガン物質をなんぼ注射しても食べさせてもガンにはなりません。何でイモリにはガンがないのや?(中略)つまり、再生のような現象をやることによって、ガンを克服してしもうとるんです」p.36
・「細胞同士がくっつくというのは、どういう仕組みになっているのか、何故、心臓は心臓の細胞同士だけでくっついて、心臓になるのか? そのカラクリがわかれば、細胞同士のくっつき方の弱い転移するガン細胞を、一つ所に固定しておくことができる。(中略)ガンが人を死に至らしめるのは、ガン細胞が、ガン細胞同士でしっかりくっついていないからだというわけでした。」p.40
・「南 本当に、恐竜を生き返らせることは可能ですか? 岡田 残念ながらノーであります。(中略)いちばん大事なことは、DNAは物質であって、生きているものではないということです。」p.56
・「私にとっての生きものとはこうなります。 「生きものとは、自らの故障を自らで見つけ、自らで治癒するようなしなやかさをもったシステムである」 生きもののしなやかな性質こそは、私をとらえてやまない「生きものの魅力」であり、しなやかさとは生きものへのオマージュであります」p.63
・「「ひとことで言うたら、発生というのは、オタマジャクシはカエルの子、いうことですなあ」」p.77
・「子供のころから、虫が好きという人がいます。ボクが面白そうだな、と思う人にはそういう人が多いんです。養老猛司先生とか、岡田先生とか。」p.79
・「「分化というのは仮の姿なんですよ。本質的には、何も変わっとらん、卵のときと。見かけは筋肉やら神経やらえらい違うとるが、あれは仮の姿や、逆から見たらいいんです」(中略)「分化を語れなければ、発生は語れません」」p.82
・「すべての細胞はおなじ遺伝子をもっているけれども、どの遺伝子が使われるかは、細胞によって違うのです。すべての遺伝子が常に働いているのではない。異なった遺伝子群が働くことが分化の実態なんでした。これを岡田先生は「宝の持ち腐れ作戦」と名づけました。 では、この遺伝子の働きのスイッチをONにしたりOFFにしたりするのはなんなのでしょう。これもまた遺伝子なんでした。」p.99
・「ホメオボックスの発見は、生物学を変えた。レベルを一つ違うものに上げたんです。体のマクロな成り立ちを遺伝子の言葉で説明できる。これがキイだ! と、かなりの人がすぐに気づいたはずや、1984年のことです。」p.101
・「ちなみに、岡田先生がホメオティック・ジーンに日本語で命名するなら「巨視的形態統括者」にするとのことです。」p.107
・「エボリューションというのは発展、生物学的には、多様性が増えたということや。一種類から始まって、35億年の歴史の間で8000万種まで多様性をきわめてきたと、そこに進化の一番大きな意味がある、ということですね」p.124
・「甲虫のね、体のサイズが10分の1になると種類が100倍になっとる、というルールが成立するというのです。」p.134
・「細胞間を接着できるような物質をつくり出す遺伝子というのがあればこそ、多細胞生物ができるんですからね。カドヘリンの歴史をたどれば、多細胞生物の起源が分かる。」p.144
・「生物の分類にはランクがありまして、一番下がスピーシス(種)、そのスピーシスの幾らかのよく似たものを集めてジーナス(属)、そのジーナスを集めてトライブ(族)、そのトライブを集めてファミリー(科)となる。(」p.150
・「私の経験からいうと、生物の科学についての話題のなかで、多くの人たちを麻薬の如くに引きつけているのは、獲得された形質は遺伝するか? というものでしょう。そして皆さんは、獲得形質も少しは遺伝する、という答えを生物学からなんとか引き出したいと期待しておられるとしか思えないのです。獲得形質の遺伝は起こりません。」p.157
・「生きものについての科学のあり方とは、「共通のこと」と「異なっていること」とのはざまの悩みである、ともいえるのです。」p.173
・「なにもいまさら「生きものは複雑である」と言って偉ぶってみせることはありません。私はもっといい言葉を使っています。それは「生きものは、よくできている」という言葉です。同じことだと思われるかもしれませんが、えらく違います。」p.179
・「最近の私の心境では、50の生命の解釈論よりも、ある一つの生きものが演ずる一つの現象を、ちょっと深くみるほうが、ずっとおもろい。そのおもろいことから、生きているとはどういうことかを具体的に感得していただければ、という立場を、最近とっております。」p.180
・「すべての生物の中で、再生能力が最も貧弱なのが人間です。治せるものといったら、怪我くらいなものです。」p.198
・「常にある程度の余裕をもって生きている、それが「生きもの」なのかもしれません。その余裕のことを、私は「損得ぼちぼち」と、至って関西風に表現いたしました。」p.203
・「わかる快感というのは、わかったつもりでいたことを、こなごなに砕かれる快感なのだ。人間はわかった時に快感を感じるようにセットされている、とボクは思ってる。わかった風なことを書いてしまいましたが、もちろん砕かれるべき常識、知識もまた、ためこんでいなければ、その快感も少ないんですけどね。」p.204
・「この私のいう、 "わかるテーマの生物学" は、たぶんネオ・マクロ生物学と呼んでおいてもよいと思う。あるいは、古くからの "生命体" という言葉を復活させて生命体生物学を(漢字の好きな人は)あててもよい。」p.216
《チェック本》 マイケル・クライトン『ジュラシック・パーク』