
「世界観」と言う言葉が頻繁に、そして普通の事のように使われるようになっているけれども、その時期に日本にほとんどいないせいもあって、未だに意味が全くわからないでいる。
それで、調べてもみるのだけれど、あまりきちんとした定義が無いようで、書かれているものを読むと言う方法では無理そうだと最近感じている。
世界観と言う言葉を知ったのはもう随分と以前だけれど、その界隈の人たちの事はわからないが、90年代の最後のあたりでは自分は聞いていなかった気がする。97年位に何か忘れたけれど「もののけ姫」のチケットを貰って観たあたりではそんな言葉は聞かなかった。それ以前にも同世代で宮崎アニメ大好きな人たちがいて、いくつか観せてもらった時には彼らはそんな事言ってはいなかった。だから一般化したのは2000年に入ってからじゃないかと考える。
そもそも、もののけ姫姫あたりの時点では、確かに宮崎監督は話題の人ではあったと思う。アニメで壮大な設定で、テレビ番組の派生でなくいきなり映画館で上映しても大丈夫な作品を作れる人がそういなかったから。そして、文部省が推薦して安心して子供達に見せられるし、どうしたわけかチケットを無料でばら撒いても商売として成り立つ、そんな事ができる人は他にいなかった。と、単にすごいなと思って無料チケットで観ていた。
話は戻って、その世界観なのだけれど、書いてあるものではどうやら、物語の「設定」の延長のようなものと考えられているらしい。それが、物語の様式や雰囲気、個々の規範を含むものとして世界観と規定されるとか。
そうなると、わからないのは、よく作品を鑑賞した人が、「世界観が良い」と言う。世界観が良いだけなら、物語としての展開や結論のようなものはどうなんだ?と言うところに言及していない事になってしまう。お話が途中で終わってわからないまま、疑問が多く残るままであっても世界観はあるわけで、それに関しては鑑賞しないのだろうか?と思ってしまう。
でも、世界観は良いと評される作品を見ると、それも何となくわかる気がしてくる。なぜなら、エンディングまで行って、「だから何よ?」と言うものが多いからだ。
はは〜ん。もしかすると、これって、あれか!と思い当たる。
日本の文学作品の独特なあれ、「描く」と言うやつの別の言い方じゃないだろうか?と。例えば、川端康成の「雪国」を読むとする。主人公の男が雪国の温泉地へ行って芸妓といろいろあり、その他にもう1人女が出てきて死ぬ。こうした物語が年単位のスケールで書かれている。さて、読む方はその場面場面である感覚を持つ事になるが、登場人物のはっきりした心情はついに書かれない。女の1人が死んで、ああこれはこうだったのかな?で終わってしまう。要は、描いているがその芯の部分に関しては著者は書かないで済ましている。だから全体を通してぼんやりとしていて、ちゃんと解釈しようと思うとかなりの困難を伴う。
逆に言えばぼんやりさせているからこそ奥が深いと言うか、想像力を掻き立てる。
つまり、世界観は言葉として新しく導入されたものではあるにせよ、日本には昔からあった「描く」作品を単語として補足しているのではないかと言う事だ。
でも、作品によっては無責任な感じがするものが多いのも事実。ある作品などは結局、世界観が良いで誰もそれ以上に言わないのを良い事に、小学校の壁にあった「廊下を走るな」のポスターの役割しかさせていない。それは、間違った事は言っていないし、正しい事ではあるが、じゃあ、具体的にどうするの?どうするべきなの?と言うのは見る者任せだ。
スパイダーマンなら、パワーを持つ者の責任と言うのをセリフの中で言っているし、ハルクを仲間に加えるのに必要な理由をきちんと言葉に出して言っている。が、世界観作品では言わない。それは、描く事に主眼があるからだろう。言ってしまうと解釈の幅が狭くなって世界観では語られなくなってしまう。だから、できるだけ見る側に任せて学校ポスターで終わりにしていると言えなくもない。

















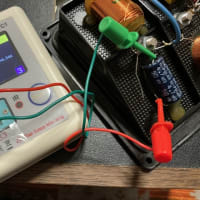
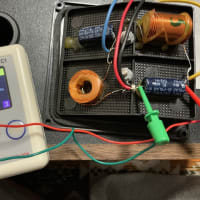

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます