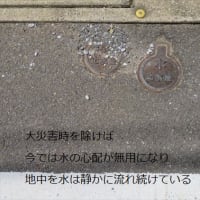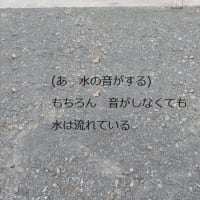メモ2021.12.4 ― 共感覚から (追記2021.12.5)
本書は、割りとていねいに「共感覚」研究の現状をたどっている。まず、「共感覚」は次のように現象する。
共感覚者は、あたりまえの世界を、あたりまえでないかたちで経験している。言葉には味が、名前には色がそれぞれ伴い、数字の連なりは、空間内を進んでいく。共感覚の大半の定義では、通常の感覚に加えて別の感覚が存在するという点が強調されている。例えば、フルートの音は、パステル系のレモン色に感じられる。この音は、聴覚と視覚の両方によって感知されているわけだが、レモン色が、フルートの音に取って変わっているわけでもない。これらは同時に存在しているのである。このことから、共感覚は、もう一つの感覚とされている。もちろん、共感覚者にしてみれば、この感覚が通常とは別のものとは感じられない。というのも、彼らにとってこの体験が慣れ親しんできた、ごく普通のものだからだ。
(『カエルの声はなぜ青いのか?―共感覚が教えてくれること』P17 ジェイミー・ウォード 青土社 2012年1月)
本書は、割りとていねいに「共感覚」研究の現状をたどっている。まず、「共感覚」は次のように現象する。
共感覚者は、あたりまえの世界を、あたりまえでないかたちで経験している。言葉には味が、名前には色がそれぞれ伴い、数字の連なりは、空間内を進んでいく。共感覚の大半の定義では、通常の感覚に加えて別の感覚が存在するという点が強調されている。例えば、フルートの音は、パステル系のレモン色に感じられる。この音は、聴覚と視覚の両方によって感知されているわけだが、レモン色が、フルートの音に取って変わっているわけでもない。これらは同時に存在しているのである。このことから、共感覚は、もう一つの感覚とされている。もちろん、共感覚者にしてみれば、この感覚が通常とは別のものとは感じられない。というのも、彼らにとってこの体験が慣れ親しんできた、ごく普通のものだからだ。
(『カエルの声はなぜ青いのか?―共感覚が教えてくれること』P17 ジェイミー・ウォード 青土社 2012年1月)
「共感覚」と呼ばれているものも人間的な感覚の有り様のひとつには間違いない。しかし、「共感覚」をもたない多数の人々にとっては、そのことはふしぎなものに見える。例えば、次のような記述がある。
二〇〇四年三月一四日のことだ。ダニエル・タメットは、円周率の二万二五一四桁の暗唱に見事成功し、ヨーロッパ新記録を達成した。所要時間は、五時間九分だった。・・・中略・・・ではダニエルは、どうやってπの桁を覚えたのだろう?ここは、ダニエルに詳しく語ってもらおう。
数字の並びを見つめていると、私の頭は、色、かたち、それに質感で満たされるようになります。そしてそれらが自然に一つになって、視覚イメージの風景が現れるのです。一つ一つの数字を思いだす場合には、頭の中で色々なかたちと質感をただ見直すだけで、お目当ての数字が浮かんできます。πのような、ただそれを読めばいいものの、しかしとてつもなく長い数字の場合には、数字の並びを幾つかに区分けすることにしています。
区分けの長さは、数字に応じて変わります。例えば、頭の中で、ある数字が異常に明るく、その次の数字が逆に、ひどく暗い場合には、その二つの数字をバラバラに思い浮かべます。逆に、なめらかな数字が連続した場合には、まとめて覚えることになります。
(以下略)
ダニエル・タメットもリチャード・ファインマンと同じ共感覚者である。ダニエルは、共感覚を生かしつつ、数字にまつわる雑多な共感覚体験を一つにまとめ上げることで、空間内に「風景」を生み出すことができる。こうした一連の風景の流れを辿っていくと、そこに潜んでいる数字を探り当てるためのヒントが見つかる。ダニエルは、三ヶ月を費やして、一連の数字を構成している幾つもの多彩な部分を覚えていった。πの桁を一度に諳んじようなどとは過去に一回も思わなかったにもかかわらずである。図8(※)は、ダニエルが思い描いたπの最初の一〇〇桁のイメージだ。
ダニエルにはこのほかにも、際立った能力がある。英米のテレビ局で放映されたドキュメンタリー番組『ブレインマン』の制作に携わったさい、ダニエルは、たった一週間でアイスランド語が話せるようになったのだ。最終テストはテレビの生インタビューで、それはもちろんアイスランド語で行われた。過去にも、リトアニアの学校で教育プログラムに携わりながら、リトアニア語を独習した経験を持つダニエルは、現在一〇ヶ国語を操る。ダニエルが説明してくれたことによると、脳は、パターンをことのほか好むらしく、ある言語をマスターするというのは、こうしたパターンをつかむことなのだそうだ。共感覚は、一つの単語や単語同士の間に存在している音や文字のパターンに慣れるためのお手軽な方法を提供してくれる。事実、多くの共感覚者が、言語習得を得意なことの一つと報告しているのだ。その後ダニエルは、会社を立ち上げ、より直観的に言語を習得したいと考える人たちを支援している。
ダニエルは、共感覚者であると同時に、自閉症者でもある。
多くの自閉症者が、数字のパターンや順序に引きつけられるが、その内の約一〇パーセントは、記憶、計算、デッサンについて驚異的な能力を持っている。ダニエルも同じく、驚くべき計算力を備えており、小数点一〇〇位近くまでの割り算をやってのけるのだ。ダニエルの場合、数字への偏愛や熱意を誘発しているのはたぶん、自閉症なのだろうが、共感覚も同じように、計算にまつわる諸々の経験と深くかかわっているのだろう。
三七の五乗(37×37×37×37×37=69,343,957)は、天辺から時
計回りに走っている小さめの円が集まってできた大きな円みたいに
見えます。筆算は一度もしたことがありません。なぜなら、答えは
いつだって、頭の中で出てしまいますし、「できあいの」やり方よ
り、共感覚によって生み出されたかたちを頭に思い浮かべて答えを
出す方が、私にはずっと楽だからなのです。
(『同上』P190-P193)
ダニエル・タメットという名前は、自閉症関係で耳にした覚えがあると思ったら、『ぼくには数字が風景に見える』という彼の本を読んでいた。たぶん松本孝幸さんのホームページで最初に出会ったのだと思う。自分のパソコンにファイル検索をかけてみたら、2007年10月の「読書ノート」があった。彼自身による「共感覚」は、
数字を見ると色や形や感情が浮かんでくるぼくの体験を、研究者たちは「共感覚」と呼んでいる。共感覚とは複数の感覚が連動する珍しい現象で、たいていは文字や数字に色が伴って見える。
(『ぼくには数字が風景に見える』P13 ダニエル・タメット 講談社 2007.6.11)
思い返してみると、ぼくにははじめからいまのように数字が共感覚をともなって見えていた。数字がぼくにとっての第一言語だ。つまりぼくは数字を使って考えたり感じたりする。感情というのはぼくには理解しにくく、対応の仕方に困るものなのだが、数字を使うと理解しやすくなる。
(『同上』P18)
ある言葉からぼくがイメージする色と感情が、その言葉の意味とつながっているので、言葉に命を吹き込むことができるのだ。
(『同上』P23)
本書では、「共感覚はなぜ存在するのかという問題に決定的な答えを出すのは時期尚早だ。」(『同上』P236)と述べて「共感覚」というのは、現状はよくわかっていないとしている。
ところで、その時の「読書ノート」に、「わたしたちは数字を単に概念として見、感じ、使っているが、ダニエル・タメットは数字に色や形や風景を見ることができている。これは人類が数というものを考え出したときの初源を考えると、はじまりの数は単なる概念ではなく、ダニエル・タメットの見るような世界として存在したのではなかろうか。」とメモしている。そのことは、なぜだか現在にまで残っている「共感覚」というものは、人類の初源的な感覚の有り様だったのかもしれないという捉え方につながる。
「内側から見た自閉症」を追究されている松本孝幸さんは、『動物感覚』を書いたアメリカの自閉症者のテンプル・グランディンの「自閉症は、動物から人間へいたる道の途中にある駅のようなものだ。」という言葉をよく引用され、自閉症は、人類が感覚中心の世界把握の段階から世界を抽象化や概念化してきた段階の中の、感覚中心の世界把握の段階を保存しているのだと捉えられている。
わたしも、松本孝幸さんの「自閉症」の捉え方の流れで、「共感覚」も人類の初源的なありかたとその名残というような感じを持っている。なぜ残存しているのかはわからないが、存在しているのは確かである。
最後に、このメモで記しておかなくてはいけないことがある。松本孝幸さんが「内側から見た自閉症」で記していた記憶があるが、他人が自転車に乗っているのを見ているだけですぐに自転車に乗れたり、他人がピアノを弾いているのを見ていて自分がすぐにピアノが弾けるようになる人々が自閉症の人々の中にはいるそうである。普通の感覚では、きちんと練習を積み重ねていかないと不可能に見えることである。
親鸞は、修道を重ねて、一段一段と段階を経て徐々に仏の境地に近づいていく「竪超」(じゅちょう)に対して、「横超」(おうちょう)を、すべての段階を横様に飛び越えて、一挙に目的に達する、すなわち、凡夫が凡夫のままで、直ちに仏に成るものだという見方をしている。前者は自力、後者は他力と対応している。わたしたちのこの人間界での普通の感覚である「竪超」からすると、「共感覚」は「横超」に対応しているように見える。
わたしたちは、わたしたちの現在の有り様から自身を見てしまうが、生命の発生にかぎらず、まだまだ自身をよくわかっていないのだ。このことから類推すれば、植物や動物の「感覚(のようなもの)」の有り様もまた、わたしたち人類から見たら「横超」みたいなものかもしれないし、あるいは深い所で共有しているものがあるのかもしれない。
図8(※)
区分けの長さは、数字に応じて変わります。例えば、頭の中で、ある数字が異常に明るく、その次の数字が逆に、ひどく暗い場合には、その二つの数字をバラバラに思い浮かべます。逆に、なめらかな数字が連続した場合には、まとめて覚えることになります。
(以下略)
ダニエル・タメットもリチャード・ファインマンと同じ共感覚者である。ダニエルは、共感覚を生かしつつ、数字にまつわる雑多な共感覚体験を一つにまとめ上げることで、空間内に「風景」を生み出すことができる。こうした一連の風景の流れを辿っていくと、そこに潜んでいる数字を探り当てるためのヒントが見つかる。ダニエルは、三ヶ月を費やして、一連の数字を構成している幾つもの多彩な部分を覚えていった。πの桁を一度に諳んじようなどとは過去に一回も思わなかったにもかかわらずである。図8(※)は、ダニエルが思い描いたπの最初の一〇〇桁のイメージだ。
ダニエルにはこのほかにも、際立った能力がある。英米のテレビ局で放映されたドキュメンタリー番組『ブレインマン』の制作に携わったさい、ダニエルは、たった一週間でアイスランド語が話せるようになったのだ。最終テストはテレビの生インタビューで、それはもちろんアイスランド語で行われた。過去にも、リトアニアの学校で教育プログラムに携わりながら、リトアニア語を独習した経験を持つダニエルは、現在一〇ヶ国語を操る。ダニエルが説明してくれたことによると、脳は、パターンをことのほか好むらしく、ある言語をマスターするというのは、こうしたパターンをつかむことなのだそうだ。共感覚は、一つの単語や単語同士の間に存在している音や文字のパターンに慣れるためのお手軽な方法を提供してくれる。事実、多くの共感覚者が、言語習得を得意なことの一つと報告しているのだ。その後ダニエルは、会社を立ち上げ、より直観的に言語を習得したいと考える人たちを支援している。
ダニエルは、共感覚者であると同時に、自閉症者でもある。
多くの自閉症者が、数字のパターンや順序に引きつけられるが、その内の約一〇パーセントは、記憶、計算、デッサンについて驚異的な能力を持っている。ダニエルも同じく、驚くべき計算力を備えており、小数点一〇〇位近くまでの割り算をやってのけるのだ。ダニエルの場合、数字への偏愛や熱意を誘発しているのはたぶん、自閉症なのだろうが、共感覚も同じように、計算にまつわる諸々の経験と深くかかわっているのだろう。
三七の五乗(37×37×37×37×37=69,343,957)は、天辺から時
計回りに走っている小さめの円が集まってできた大きな円みたいに
見えます。筆算は一度もしたことがありません。なぜなら、答えは
いつだって、頭の中で出てしまいますし、「できあいの」やり方よ
り、共感覚によって生み出されたかたちを頭に思い浮かべて答えを
出す方が、私にはずっと楽だからなのです。
(『同上』P190-P193)
ダニエル・タメットという名前は、自閉症関係で耳にした覚えがあると思ったら、『ぼくには数字が風景に見える』という彼の本を読んでいた。たぶん松本孝幸さんのホームページで最初に出会ったのだと思う。自分のパソコンにファイル検索をかけてみたら、2007年10月の「読書ノート」があった。彼自身による「共感覚」は、
数字を見ると色や形や感情が浮かんでくるぼくの体験を、研究者たちは「共感覚」と呼んでいる。共感覚とは複数の感覚が連動する珍しい現象で、たいていは文字や数字に色が伴って見える。
(『ぼくには数字が風景に見える』P13 ダニエル・タメット 講談社 2007.6.11)
思い返してみると、ぼくにははじめからいまのように数字が共感覚をともなって見えていた。数字がぼくにとっての第一言語だ。つまりぼくは数字を使って考えたり感じたりする。感情というのはぼくには理解しにくく、対応の仕方に困るものなのだが、数字を使うと理解しやすくなる。
(『同上』P18)
ある言葉からぼくがイメージする色と感情が、その言葉の意味とつながっているので、言葉に命を吹き込むことができるのだ。
(『同上』P23)
本書では、「共感覚はなぜ存在するのかという問題に決定的な答えを出すのは時期尚早だ。」(『同上』P236)と述べて「共感覚」というのは、現状はよくわかっていないとしている。
ところで、その時の「読書ノート」に、「わたしたちは数字を単に概念として見、感じ、使っているが、ダニエル・タメットは数字に色や形や風景を見ることができている。これは人類が数というものを考え出したときの初源を考えると、はじまりの数は単なる概念ではなく、ダニエル・タメットの見るような世界として存在したのではなかろうか。」とメモしている。そのことは、なぜだか現在にまで残っている「共感覚」というものは、人類の初源的な感覚の有り様だったのかもしれないという捉え方につながる。
「内側から見た自閉症」を追究されている松本孝幸さんは、『動物感覚』を書いたアメリカの自閉症者のテンプル・グランディンの「自閉症は、動物から人間へいたる道の途中にある駅のようなものだ。」という言葉をよく引用され、自閉症は、人類が感覚中心の世界把握の段階から世界を抽象化や概念化してきた段階の中の、感覚中心の世界把握の段階を保存しているのだと捉えられている。
わたしも、松本孝幸さんの「自閉症」の捉え方の流れで、「共感覚」も人類の初源的なありかたとその名残というような感じを持っている。なぜ残存しているのかはわからないが、存在しているのは確かである。
最後に、このメモで記しておかなくてはいけないことがある。松本孝幸さんが「内側から見た自閉症」で記していた記憶があるが、他人が自転車に乗っているのを見ているだけですぐに自転車に乗れたり、他人がピアノを弾いているのを見ていて自分がすぐにピアノが弾けるようになる人々が自閉症の人々の中にはいるそうである。普通の感覚では、きちんと練習を積み重ねていかないと不可能に見えることである。
親鸞は、修道を重ねて、一段一段と段階を経て徐々に仏の境地に近づいていく「竪超」(じゅちょう)に対して、「横超」(おうちょう)を、すべての段階を横様に飛び越えて、一挙に目的に達する、すなわち、凡夫が凡夫のままで、直ちに仏に成るものだという見方をしている。前者は自力、後者は他力と対応している。わたしたちのこの人間界での普通の感覚である「竪超」からすると、「共感覚」は「横超」に対応しているように見える。
わたしたちは、わたしたちの現在の有り様から自身を見てしまうが、生命の発生にかぎらず、まだまだ自身をよくわかっていないのだ。このことから類推すれば、植物や動物の「感覚(のようなもの)」の有り様もまた、わたしたち人類から見たら「横超」みたいなものかもしれないし、あるいは深い所で共有しているものがあるのかもしれない。
図8(※)

(追記2021.12.5)
「共感覚」に直接触れられているわけではないが、これに関連すると思われる吉本さんの言葉がある。わたしが『吉本さんのおくりもの(旧名 データベース 吉本隆明を読む)』( http://dbyoshimoto.web.fc2.com/ )で取りあげた項目からの引用である。
「言葉の吉本隆明②」項目505「発生期の状態の保存・発動」。
①
6 原始的な感覚の世界と臨死体験・超能力(引用者註.小見出し)
それから、もう一つは目で見て人を識別するとか、自然を識別するということは目だけが働いていると考えないほうがよい。一番初めに手で触ったとか、母親と言葉にならない言葉でコミュニケーションを成り立たせていたとかという、手の触覚とか、音とか、「あわわ」言葉の音とか、そういうことも含めて、目で見る識別の仕方の中に全部総合的に含まれているのだというふうに考えたほうがよいという考え方になります。つまり、もっと言いますと、大脳皮質の奥のほうに、原始的な哺乳類の時代からあった脳の一番奥のほうにある部分を取ってくれば、そこでは目の感覚とそれから耳の感覚とか、におい、鼻の感覚とか、味わいの、口の感覚とかは全部どこかでつながっていた時代というのがあって、それが総合的につながっていて分化していない時代があった、そういう時期があったということが言えることになります。
②
例えば、よく立花さんの本が出ていますけれども、臨死体験みたいのがあるでしょう。そうすると、臨死体験は何かと言ったら、要するに死に損なってと言いますか、死にそうになって意識が薄れてきてしまって、それでほかの内臓器官もあまり働かなくなって死にそうだと、そういうふうになっていくと自分の目の意識が体外に離れてしまって、ちょっと天井のほうに上がって、死にそうになっている自分とその周りの自分を手当てしているお医者さんとか、看護婦さんとか、泣いている近親の人とかというのを、自分が上のほうからちゃんと見えるというふうな体験があるわけです。それは臨死体験の一つなのです。なぜそういうのが可能かということがあるわけです。
だけど、いずれにせよそういう臨死体験が難しいところは何かというと、どうして目はつぶってしまっているのに、もう死ぬ間際ですから、人間というのは目をつぶってしまったら見えるわけがないし、意識が薄れるばかりなのに、どうしてそういうふうに死にそうになっている自分を上のほうから自分が見ることができるのだということが不思議ではないか、おかしいではないかということが、いずれにせよ帰着するのはそこであるわけで、それを結論付けるのはなかなか難しいわけです。だから、宗教家は宗教家で、それはあの世にいく始まりなのであるというふうにちゃんと言ってしまって、あの世というのはそれからずっと飛んでいったあの世へ行くんだよと言って、それで行くのだけれど、普通はどこか死の向こうに人が立っていて、「おまえ、ここからもう来るな」と言われて、戻ってきたら意識が覚めたというふうなそういう話になるわけです。つまり、そういうことというのが一番難しいところは、死に損なって衰えた意識しかないのに、どうしてそれが上の天井のほうから自分で自分が見えるのか、あるいは自分の周辺が見えるのかということが不思議だということになるわけです。それはなぜかと言うと、人の考え方が、専門家で分かれてしまうのはそこのところだと思います。そういうことはないのだと、それは錯覚で後からくっ付けてそういうことを言っているだけなんだというふうに言いたいところですけど。
僕も多少は臨死体験の報告集みたいなものを集めたり、読んだりしたことがありますけれど、自分の体を自分の上から見ていて、周囲の人が動いているのを見ていて、何を言ったか見えていると、どうしてもそう思わないとならないなと思える体験報告は多いのです。それを疑うことはできますけれども、それはないはずだと根拠もまたないのです。そうすると、僕が思うには、その一番よい説明の仕方は今申しましたとおり、目の感覚とか、耳の感覚とか、人間の五感というのは非常に発生の初めの頃、つまり母音だけしかなくて民族語に分かれていない、そういう言葉時代の時までさかのぼってしまうと、全部連結していると考えられるということができます。そうしますと、死にそうになっても一番後まで残っているのは耳です。耳の感覚です。声が一番残りますから、耳の感覚で声が聞こえるという体験ができる限りは、目も見えてしまうということが可能なのだというふうに考えるのが、僕の考え方では今のところ一番よろしいのではないかなと思っています。
でも、そうなんだとあまり断定したくはないのです。世の中でも不明なことは断定したくはないわけです。断定はしませんけれど、考え方としては一番よいのではないかなと思う。宗教家みたいに「いや、来世というのがあるんだよ」と言ってしまうことも、なんとなくちょっとあれだし、「いや、そういうのは大でたらめだし、病気の一種で幻覚を見ているだけだよ」と言うのも何となくそうではないよと思えるところもあるわけです。だから、それもあまり言えないから、結局非常に意識が薄れていって、あらゆる内臓もそうだし、五感も死にそうになって衰えてきた。ある時点になると、あらゆる人間の感覚は全部連結してということが言えて、そうすると耳だけ聞こえさえすれば、必ず見えてしまうということはありえるのだよ、そういうふうな理解の仕方をするのがよいのではないかなと、今のところ僕は思います。つまり、断定はしませんから「そうではない」と言われても困ってしまうわけですけれど、そうだと思う。
③
それから、子どもでも、子どもも本当に確かめたことがないからわからないのですけれど、テレビや何かで時々やるのです。子どもに内緒で紙に図形みたいなものを書いたものを子どもに「当ててごらん」と言うと、子どもがそのくしゃくしゃに丸めた紙を耳に当てたり、こういうところに当てたりするのです。しばらくやっていて、「何だ」と。「ここに書いてあるとおりのことを書いてみな」と言って紙に書かせて、それで開けるとちゃんとできているということが、まぐれではない数だけ、意味がある数だけちゃんとあるわけです。出てくるわけです。それで、大体三歳未満の子どもは当たりやすい。四歳から上になってしまうと駄目だ、大人になるとまして駄目だとなるわけです。そうすると、三歳未満ということに何か意味を付けるとすれば、要するに非常にまだ「あわわ」言葉をやっている時代に、いろいろ耳が聞こえない耳のコミュニケーションをやっているだけで、いろいろなことが、母親が何を考えているのか、見ているのか、何を言おうとしているのかというのをわかってしまうわかり方というのが、切れずにと言いますか、非常によく保存されているとすれば、そういうことはありうるなと考えることができます。
(「顔の文学」 ほぼ日の『吉本隆明の183講演』 A165、講演テキストより 講演日時:1994年11月24日)
※①と②の前半は、連続した文章です。
「言葉の吉本隆明②」項目505「発生期の状態の保存・発動」。
①
6 原始的な感覚の世界と臨死体験・超能力(引用者註.小見出し)
それから、もう一つは目で見て人を識別するとか、自然を識別するということは目だけが働いていると考えないほうがよい。一番初めに手で触ったとか、母親と言葉にならない言葉でコミュニケーションを成り立たせていたとかという、手の触覚とか、音とか、「あわわ」言葉の音とか、そういうことも含めて、目で見る識別の仕方の中に全部総合的に含まれているのだというふうに考えたほうがよいという考え方になります。つまり、もっと言いますと、大脳皮質の奥のほうに、原始的な哺乳類の時代からあった脳の一番奥のほうにある部分を取ってくれば、そこでは目の感覚とそれから耳の感覚とか、におい、鼻の感覚とか、味わいの、口の感覚とかは全部どこかでつながっていた時代というのがあって、それが総合的につながっていて分化していない時代があった、そういう時期があったということが言えることになります。
②
例えば、よく立花さんの本が出ていますけれども、臨死体験みたいのがあるでしょう。そうすると、臨死体験は何かと言ったら、要するに死に損なってと言いますか、死にそうになって意識が薄れてきてしまって、それでほかの内臓器官もあまり働かなくなって死にそうだと、そういうふうになっていくと自分の目の意識が体外に離れてしまって、ちょっと天井のほうに上がって、死にそうになっている自分とその周りの自分を手当てしているお医者さんとか、看護婦さんとか、泣いている近親の人とかというのを、自分が上のほうからちゃんと見えるというふうな体験があるわけです。それは臨死体験の一つなのです。なぜそういうのが可能かということがあるわけです。
だけど、いずれにせよそういう臨死体験が難しいところは何かというと、どうして目はつぶってしまっているのに、もう死ぬ間際ですから、人間というのは目をつぶってしまったら見えるわけがないし、意識が薄れるばかりなのに、どうしてそういうふうに死にそうになっている自分を上のほうから自分が見ることができるのだということが不思議ではないか、おかしいではないかということが、いずれにせよ帰着するのはそこであるわけで、それを結論付けるのはなかなか難しいわけです。だから、宗教家は宗教家で、それはあの世にいく始まりなのであるというふうにちゃんと言ってしまって、あの世というのはそれからずっと飛んでいったあの世へ行くんだよと言って、それで行くのだけれど、普通はどこか死の向こうに人が立っていて、「おまえ、ここからもう来るな」と言われて、戻ってきたら意識が覚めたというふうなそういう話になるわけです。つまり、そういうことというのが一番難しいところは、死に損なって衰えた意識しかないのに、どうしてそれが上の天井のほうから自分で自分が見えるのか、あるいは自分の周辺が見えるのかということが不思議だということになるわけです。それはなぜかと言うと、人の考え方が、専門家で分かれてしまうのはそこのところだと思います。そういうことはないのだと、それは錯覚で後からくっ付けてそういうことを言っているだけなんだというふうに言いたいところですけど。
僕も多少は臨死体験の報告集みたいなものを集めたり、読んだりしたことがありますけれど、自分の体を自分の上から見ていて、周囲の人が動いているのを見ていて、何を言ったか見えていると、どうしてもそう思わないとならないなと思える体験報告は多いのです。それを疑うことはできますけれども、それはないはずだと根拠もまたないのです。そうすると、僕が思うには、その一番よい説明の仕方は今申しましたとおり、目の感覚とか、耳の感覚とか、人間の五感というのは非常に発生の初めの頃、つまり母音だけしかなくて民族語に分かれていない、そういう言葉時代の時までさかのぼってしまうと、全部連結していると考えられるということができます。そうしますと、死にそうになっても一番後まで残っているのは耳です。耳の感覚です。声が一番残りますから、耳の感覚で声が聞こえるという体験ができる限りは、目も見えてしまうということが可能なのだというふうに考えるのが、僕の考え方では今のところ一番よろしいのではないかなと思っています。
でも、そうなんだとあまり断定したくはないのです。世の中でも不明なことは断定したくはないわけです。断定はしませんけれど、考え方としては一番よいのではないかなと思う。宗教家みたいに「いや、来世というのがあるんだよ」と言ってしまうことも、なんとなくちょっとあれだし、「いや、そういうのは大でたらめだし、病気の一種で幻覚を見ているだけだよ」と言うのも何となくそうではないよと思えるところもあるわけです。だから、それもあまり言えないから、結局非常に意識が薄れていって、あらゆる内臓もそうだし、五感も死にそうになって衰えてきた。ある時点になると、あらゆる人間の感覚は全部連結してということが言えて、そうすると耳だけ聞こえさえすれば、必ず見えてしまうということはありえるのだよ、そういうふうな理解の仕方をするのがよいのではないかなと、今のところ僕は思います。つまり、断定はしませんから「そうではない」と言われても困ってしまうわけですけれど、そうだと思う。
③
それから、子どもでも、子どもも本当に確かめたことがないからわからないのですけれど、テレビや何かで時々やるのです。子どもに内緒で紙に図形みたいなものを書いたものを子どもに「当ててごらん」と言うと、子どもがそのくしゃくしゃに丸めた紙を耳に当てたり、こういうところに当てたりするのです。しばらくやっていて、「何だ」と。「ここに書いてあるとおりのことを書いてみな」と言って紙に書かせて、それで開けるとちゃんとできているということが、まぐれではない数だけ、意味がある数だけちゃんとあるわけです。出てくるわけです。それで、大体三歳未満の子どもは当たりやすい。四歳から上になってしまうと駄目だ、大人になるとまして駄目だとなるわけです。そうすると、三歳未満ということに何か意味を付けるとすれば、要するに非常にまだ「あわわ」言葉をやっている時代に、いろいろ耳が聞こえない耳のコミュニケーションをやっているだけで、いろいろなことが、母親が何を考えているのか、見ているのか、何を言おうとしているのかというのをわかってしまうわかり方というのが、切れずにと言いますか、非常によく保存されているとすれば、そういうことはありうるなと考えることができます。
(「顔の文学」 ほぼ日の『吉本隆明の183講演』 A165、講演テキストより 講演日時:1994年11月24日)
※①と②の前半は、連続した文章です。