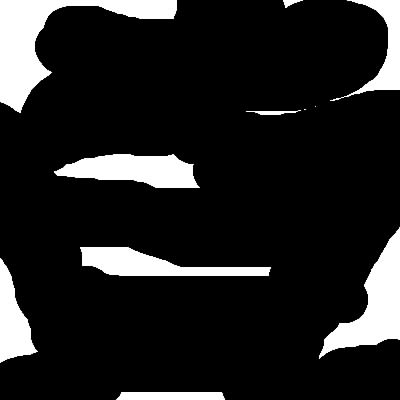
年に一度の建国祭はセブズーの町の広場にたくさんの市が出る。それはいつ頃から始まったのか分からないが、始祖セブ王を讃える祭りだった。セブ王の噴水の周りには色とりどりの、のぼりや旗が立てられていた。長い丸太の木の棒を柱にして、そこに反物の布を縦に広げたような細長いのぼりが何本も広場の中央に立てられているのだ。その真下に行くと、首を折るようにして見上げなければならなかった。のぼりの向こうは青い空だった。空に浮かぶ雲が動くと、のぼりが倒れて来そうで、怖かった。そののぼりや、旗の図柄は、セブ王を主題にしたものから、市民の生活を描いたものまで様々だった。セブズーの町の区画毎に旗を出すことになっている。建国祭は市民の祭りだった。その日は学校も休みで、エミー達は朝から広場の祭り会場に入り、珍しい青空市を見て回ったり、大道芸の見物の輪に入ったりして祭りを楽しんでいた。
「あっ、あれよ。」エミーが驚いたように叫んだ。
「なんだい。」カルパコが訊いた。
「ほら、あそこ!」
「あそこって、あの魚屋のことか。」
「そう、あの魚屋よ。確かにそうだわ。あの台、間違いないわ。」
「おい、エミー、なに言ってるんだ。」
「ねえ、カルパコ、私が見た夢の中でも建国祭をやっていたの。ここでね。台の上に魚を並べて骸骨の魚屋が魚を売っていたわ。そのときの台と同じよあれ。」
「魚はいらんかね。取りたての魚はいらんかね。」
魚屋の威勢のいい声が、広場に響いていた。
「魚屋さん。ちょっと聞きたいことがあるのですけど。」
「なんだい、穣ちゃん。こっちは忙しいんだ!手短に頼むぜ。」
「ねえ、魚屋さん。もしかしてずっと、ずぅーと前から、ここにお店を出してない?」
「先祖代々魚屋さぁ!ここは、昔からこの店と決まってるんだよ。」
「もしかしたら、おじいさんの代から?」
「先祖代々魚屋だって言ってるだろ。」
「ごめんなさい。」
「おっと、お客さん!この魚どうだい?新鮮で安いよ!買った、買った!」
魚屋はエミーを無視して商売を始めた。エミーとカルパコはしばらく魚屋を見ていたが、諦めてその場を離れた。
「一体どうしたんだ、エミー。」訳が分からないというようにカルパコはエミーに訊いた。
「間違いないわ。私が見た魚屋さんはあの人のおじいさんかなんかだわ。今は死んで、黄泉の国で魚屋をやっているのよ。」
「何か信じられないなぁ・・・・本当なのか?」とカルパコは訊いた。
「ええ、違いないわ。それほど記憶がはっきりしているんだもの。」エミーが興奮しながら言った。
「おぉーい!!!」
聞き覚えのある叫び声が後ろからした。振り向いてみると、ダルカンとエグマが立っていた。
「ダルカン!エグマ!あなた達も、来ていたのね。」
「ええ、そうよ。何か珍しい物が売ってるかもしれないと思ってね。」
「珍しい物?」
「何かすごい掘り出し物とかさ。異国の品物なんかも出ているらしいぜ。」
「何か見つけた?」
「いやあー、まだ来たばっかりなんだ。」
「おっ!偶然だな。俺達も今来たばかりさ。」
「じゃあ、四人で、いろいろ回ってみましょうか。」
「オッケー!じゃあ、買い物でもしようぜ。」
「ええ。」
四人は歩きだした。広場はかなりの群衆が出ていた。下を向いて歩いているとすぐ人にぶつかりそうだった。
「どこの店へいこうか?」辺りを見回しながらエミーが言った。
「あそこの店がいいんじゃない?」エグマが、人がたくさん来ている店を指さした。何を売っているのか分からないが、大変な人垣が出来ていた。
「えぇー。あそこかよ。人込みの中って苦手なんだよなぁ・・。」ダルカンがぐずぐずして反対した。
「じゃぁ、とりあえず人が少なそうな店を探しましょうか。」
ちょうどその時だった。どこからか、不気味なうめき声のようなものが聞こえてきた。
「なにかしら?すごく不気味だわ。」
「なんの声だろう。何かすごく気になるぜ!行ってみようか。」
「広場の噴水の方から聞こえるわ。」
その声は何種類も聞こえた。何かを叫んでいる。奇妙な声が聞こえてくるのだ。何人かが奇声を上げて争っているようにも聞こえた。
「行ってみよう。」
セブ王の噴水の周りにはたくさんの、のぼりや旗が立てられていて、一番華やかな感じがしている。先程は気が付かなかったのだが、そこにいつの間にか特設の舞台が作られていた。何人かの作業員がまだ働いていて、その舞台の上に幕が張られていた。そしてその幕には、『サンロット二十周年記念 セブズー喉自慢大会』と書かれていた。
不思議な声はその周辺から聞こえていたのだ。おそらく喉自慢大会に出る人達が声の調整をするために、発声練習をしていたのだ。舞台の周りで何人かがおなかに手を当てて素っ頓狂な声を出しているのが見えた。
「変なうめき声の正体はこれだったのか。」
「そうらしいわね。でもこんな大会があるなんて知らなかったわ。」
「面白そうじゃないか。見て行くか。」
「そうだな。みんな必死で声を出してるぜ。」
「でもいつから始まるんだろう?」
「だれかに聞いてみましょうか。」
「聞くってだれに聞けばいいんだ。」
「あの人なんかどう?何か関係者みたいよ。」エミーが女の人を指さして言った。
「あのう。」エグマが女性に近寄り声をかけた。
「はい?あ、あなたも出場したいのね。受付はあっちよ。」
「いえ、違うんです。」
「じゃあ、なぁに?」
「あの、この大会はいつ始まるんですか。」
「歌のコンクールはもうすぐ始まるわ。ほら、皆練習してるでしょう。よかったらあなた達も出ない。人数はまだ足りないぐらいだから。」
「ええっ私はいいです。」
「おい、エミー、お前出てみろよ。」カルパコが突然エミーの肩をたたいて言った。
「そうだ、エミー、ちょうどいいじゃないか。」
「えっ、私が?」
「そうよ、エミー、あなたならぴったりよ。ねえ、お姉さん、一等の賞金はいくらですか。」エグマが会場の女性に訊いた。
「そうね、賞金は五百ルーよ。すごいでしょう。」
「やった、エミー、五百ルーよ、すごいじゃない。今日の市場で好きなものが買えるじゃない。」エグマはもう勝ったつもりになっている。
「おいおい、エグマ、まだ優勝した訳ではないんだぜ。」
「気の早い奴だな。まず勝ち進むにはどんな歌がいいか、考えなきゃな。」皆はもうエミーが出るものと決めつけて話が沸騰している。
「ちょっとあなた達、まだ出るって決めた訳ではないでしょう。」エミーが抗議した。
「そうそう、だから早く受付に行かなくちゃ。」
「受付は、あそこだ。いこうぜ。」
「え・・?」エミーはもう呆れてまともに口も利けない。
「おーいエミー、早く、早く。」カルパコが受付で呼んでいる。
エミーはとうとう皆に無理やり推されて、申し込みの受付を済ませてしまった。
「でも何を歌えばいいのよ。」
「エミーなら大丈夫よ。どんな歌だっていけるよ。」
「そうだよ。エミーの好きな歌をうたえばいいのさ。優勝間違いなし。」
「みんなもう、いい加減なこと言うんだから。」
「エミー、俺は昨日のエミーに感動したんだぜ、歌手になるって話しさ。だとしたらうたう歌は決まってるじゃないか。」カルパコが言った。
「カルパコ、分かったわ。私やってみる。母さんの歌で。」
「その通りだ、エミー。」カルパコは心から喜んでいるように見えた。
「ありがとうカルパコ。」エミーは嬉しかった。
エミーが何回か歌の練習をするうちに、喉自慢大会は始まった。改めて会場を見ると、サンロットが審査員席に座っていた。エミーの心がワッと声を上げた。エミーの出番は最後だったが、急にドキドキしてくるのを押さえることが出来なかった。次々と応募者が登場して、歌をうたった。うまい者がいると思えば、とんでもない歌手も現れて会場は大変な賑わいだった。
いよいよエミーの出番になった。舞台に上がると、今まで感じたことのない緊張感が生まれて来た。エミーにとって初めての舞台だった。エミーの頭は真っ白になった。自分が何をしているのか分からなかった。エミーはしばらく舞台に出て突っ立ったままなすすべもなかった。
「エミー、しっかりしろ!」カルパコが舞台の下で叫んだ。
「エミー、頑張って!」エグマも声をかけた。
「エミー、」ダルカンの声が飛んだ。
真っ白になったエミーの頭に、カルパコやエグマの声が届いた。舞台の上でようやくエミーは自分を取り戻し、同時に不思議な落ち着きがやって来た。余計な考えはなくなっていた。エミーはヅウワンの事だけを考えていた。バックルパーを前にして、まるで包み込むように 優しく歌っていたヅウワンの姿、そしてその歌の響き。心をそのまま揺り動かすようなリズム。ヅウワンのすべてがエミーの心の中に広がって来た。
エミーは歌い始めた
風が世界をわたり
私はあなたの過去をわたる
雨が世界を潤し
私はあなたの心を濡らす
太陽は世界を照らし
私はあなたの未来に生きる
大空に小鳥があそぶように
夢は今も心の中に生きている
今も心に生まれてる
エミーの歌は、うたうというよりも、語るように聞こえた。それはエミー自身が自分の心の中でヅウワンの面影を見つめ、それをなぞるように歌ったためだった。無論それはエミーのすべてが現れたような、深い歌唱とはならなかったが、エミーの才能を十分予感させるものだった。
歌い終わったエミーにカルパコやエグマ、ダルカンばかりではなく、会場の多くの聴衆が大きな拍手を送った。
エミーが歌い終わると、サンロットが舞台に出て来て、自分の歌をうたった。華やかなうっとりするような歌声が会場に広がった。広場の群衆が一斉に集まって来た。サンロットは群衆のアンコールを受けて二曲も歌うことになった。
サンロットの歌が終わると、いよいよ審査の発表があった。色々な賞が発表され、その度に拍手が起こり、名を呼ばれた者は舞台に上がって賞状を受け取った。
エミーより、カルパコやエグマの方が興奮して賞の発表がある度に訳の分からない叫び声を上げた。エミーはいつまでたっても呼ばれなかった。優秀賞にも名が出なかった。期待と不安が渦巻いた。
「さて、いよいよ最優秀賞の発表です。さあ、多くの出場者の中から最優秀に選ばれた方は、おおっ、まだ子供さんです。」司会者が引っ張った。会場がどよめいた。
「最優秀はエミー・マリス!」会場に大きな拍手が起こった。
カルパコもダルカンもエグマもエミーも、揉みくちゃに抱き合いながら飛び上がった。エミーは心を躍らせて舞台に上がった。サンロットが舞台の上でエミーに賞状と賞金を渡した。
「おめでとう、エミー。」
「ありがとうございます。」エミーは丁寧にお辞儀をした。
「エミー、あなたには才能があるわ。歌手になりなさい。」
「私になれるでしょうか。」
「ヅウワンを越えるかもしれないわよ。」
「私も、母さんのように歌をうたいたいと思うようになりました。」
「よかった。ヅウワンもそれを望んでいたのよ。」
「本当ですか。でも母さんは一言もそんなことは言わなかった。」
「本当の歌は、本当に自分が歌いたいと思ったときにしか歌えない。ヅウワンはいつもそう言ってたわ。だからあなたにもそう願ったのよ。あなたが自分でそれを言い出すまで、ヅウワンは待っていたの。」
「そうなんですか。」
「あなたの名前、どうして付けられたか知っている?」
「いいえ、」
エミーは自分の名があまり好きではなかった。何かちょっと外国的で安っぽい感じがして一時期それで悩んだことがあったのを思い出した。
「エミーっていう名はね、ヅウワンが付けたのよ。あなたが将来大歌手になって外国にでも行くようになったら、どこに行っても通用する名前なんだってね。」
「母さんがそんなことを、」
「分かる?ヅウワンはあなたが生まれる前から、あなたが歌手になって世界の人々のために歌をうたうことを夢見ていたのよ。」
「初めて聞きました。母さんのそんな話し。」
「ヅウワンは偉いわ。あなたのことを自分の子というより神様の子のように考えていたのよ。だから自分の考えを押しつけないで、ゆっくりあなたが成長していくのを見守っていたのだわ。」
「神様の子?」
「そう、ヅウワンにとってあなたはねえエミー、神様からの預かりものだったのよ。ヅウワンはいつもそんな風に考えていたわ。」
エミーは胸の中に甘酸っぱいものが一杯に溢れて来るのを感じた。
「サンロット、私を、母さんのような歌手にして下さい。」
「厳しいわよ。あなたに耐えられるかしら。」
「どんなことでも耐えて見せます。」
「いいわ。あしたからレッスンを始めましょう。」
突然拍手が起こった。エミーは舞台の上に立っているのを忘れていた。その時だった。空がにわかに曇り、突然突風が広場を吹き抜けた。屋台のテントが吹き飛んだ。至る所から悲鳴が聞こえた。セブ王の噴水の周りに立てられたのぼりや旗が強風にあおられて歪んだ。そしてその何本かが固定している紐を切って倒れ始めた。
のぼりの太い柱がエミーの立っている舞台を直撃したのだ。群衆がクモの巣を散らすように悲鳴を上げながら逃げ出した。
エミーとサンロットがそれに気付くよりも柱が倒れかかる方が早かった。あっという間に太い柱が舞台の上に倒れかかって来た。逃げ遅れたエミーとサンロットは悲鳴と同時に柱の下敷きになってしまった。一瞬の出来事だった。
「エミー!」カルパコが舞台に駆け上がって来た。ダルカンもエグマもやって来た。三本の丸太が舞台の上に交差して倒れていた。
「大丈夫か、エミー。」
エミーは丸太の下敷きに成っていた。
「エミー!」カルパコが駆け寄ると、エミーは顔を上げた。エミーの体は丸太の交差したその隙間に挟まれて、辛うじて助かっていた。丸太の下から引き出されたエミーは、肩を打っただけで助かった。エミーが助け出された舞台の床に太い丸太が交錯して転がっていた。その丸太の間に黄色いふだが挟まっていた。エミーのお守りだった。カルパコは丸太を持ち上げながらゆっくり引き抜いた。黄色いふだは丸太に挟まれて今にも半分に千切れそうになっていた。
エミーの倒れていたすぐよこにサンロットが足を挟まれて倒れていた。何人も舞台に駆け登り丸太を持ち上げてサンロットを助け上げたが、サンロットの右足は紫色に膨れ上がっていた。サンロットはそのままタンカーに乗せられて病院に運ばれた。広場では何人かが怪我をしたようだった。路上にうずくまる者や、肩を借りて歩く人の姿があった。いくつかの露店はめちゃめちゃになっていた。飛んだ物を拾い集めてもう一度市を開くものや、それを潮に店をたたむ者が広場にざわめき、やがて落ち着きを取り戻した。人は半数に減っていた。
サンロットの右足は骨折していたが、それ以上に大きな怪我はなかった。全治二カ月と診断された。
「うたえない代わりに、あなたをみっちり仕込んで上げるわ。」サンロットはあまりめげた様子もなく、エミーにベッドの上からほほ笑みかけた。
「お願いします。」
そう言って、エミー達はサンロットの病室を出た。
次を読む



























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます