
11/6 雨上がりの午後 色づいた大イチョウを仰ぐことができた
場所は

奥羽牧場の奥
樹のまわりを一巡りできた














解説板 法身国師 ほっしんこくし の手植えと伝えられているという
【参考】


法身塚 十和田市洞内
北金ヶ沢、根岸、法量、宮田の各大イチョウの今は・・・・・・・・・・

11/6 雨上がりの午後 色づいた大イチョウを仰ぐことができた
場所は

奥羽牧場の奥
樹のまわりを一巡りできた














解説板 法身国師 ほっしんこくし の手植えと伝えられているという
【参考】


法身塚 十和田市洞内
北金ヶ沢、根岸、法量、宮田の各大イチョウの今は・・・・・・・・・・

鷹架沼とフラットな地形
県立郷土館の秋の自然観察会に参加した。
西風が強く、アラレも降ってくる天気だったが
地質や植物などについて学んだ。

下北縦貫道六ヶ所インターで降りて、鷹架野鳥の里森林公園へむかった。
左のピークは吹越烏帽子岳

鷹架沼 この対岸が鷹架野鳥の里森林公園 西風強し

風波を避ける水禽の群れ

公園の地面 エゾスナゴケ

ノコンギク

アキグミ

ナギナタコウジュ

オオバクロモジ

チマキザサ

同 蛾の幼虫の食痕

ヨモギハムシ

アキアカネ ?

ブナ 寒冷低地のブナ・・・・
地質関係は

観察会資料より 猿子沢地区露頭の位置

観察した露頭

同

同
解説
● 標高25mの海成段丘である。
● 形成のしくみを単純に考えれば、波の浸食で台地が削られ、海底にフラットに堆積したものが、海面の低下または陸の隆起によって、元の陸に戻り、標高25mまで隆起したかたちだということになる。
● では、何時から隆起したものか・・・・?
● 地層のどのレベルまでが海底であったのか・・・・?
● 貝化石は見当たらないが、礫と砂の色が海であった証拠となり、かつ、砂にはクロスラミナと呼ばれる斜め模様の波の跡が見られる。波に砂が運ばれた跡だ。浸食の勢いが強い時には礫が混じる。
● ここの地層の上部は赤茶色で、陸になってから堆積したものだ。何時から海が引いたのかを調べたいが、赤茶の層に挟まれている火山灰に注目したい。火山灰は同一時に堆積するので、時期を調査するうえで都合のよいものだから。
● そこでこの挟まれた火山灰を分析し、調べると、北海道の洞爺カルデラ形成時のものだと判明した。その時期は11万年前の噴火である。
● したがって、ここの段丘が陸化したのはそれ以前のことだと解る。
● ならば、どうして陸化したのか? 海水面が下がったのか?
● 氷河時代には、氷期と間氷期が10万年周期で繰り返されてきたという。12万年前は間氷期で現在と同じくらいの暖かさであったという。それが氷期にむかい海面が低下し、12万年前にここが陸化したとみられる。そこに洞爺カルデラの火山灰が積もったのだ。
● その上部はロームであるが粘土化している。
● そして、大きな広い段丘がつくられ、六ヶ所から小川原湖にかけて更に広い段丘となり、風も強く、高木も生育しずらい地帯となった。現在でも、畑作や牛馬の放牧地となっている。
● ここの段丘堆積は、1600万年前の鷹架層の上にできている。
● 陸化した頃の氷期には、ここには植生が無かったものとみられる。氷期のピークは2万年前であり、その後急激に温暖化が進み、植生が入り炭化している。黒い部分の下は1万年分あり、縄文時代は黒土の部分である。南部地方ではその下に十和田火山の軽石層が入る。
● 陸地の隆起と寒冷化による海面低下は、幾筋かの河川による陸の浸食が促進され谷をつくったが、それらの海への出入り口か゛塞がれて、尾駮沼、鷹架沼、市柳沼、田面木沼、小川原湖が出来たと見られる。
【参考資料】①
水野 裕
昭和42年「青森県の地質と地下資源」「地形」「海岸段丘」より
はじめに
海岸段丘とは海岸地域において海岸線にほぼ平行して存在する階段状の段地をさし、これは土地の間歇的隆起または海面の間歇的低下によって形成されたもので、幾段もの階段状の段丘は、土地の隆起または海面の低下の回数をそのままあらわしているわけである。また段丘面の上には段丘礫層とよばれる円礫層がのっていることが多いが、これは礫浜や浸食台の上にうすく礫をのせたまま隆起して海岸段丘がつくられたためである。
海岸段丘は日本の地形の著しい特徴をなすもので、青森県においても西海岸・津軽半島沿岸・下北半島沿岸など各所に典型的なものがみられる。
日本のように造山帯に属している地域では地盤運動がさかんなため、海岸段丘の分布範囲が広いということはわかるが、欧米大陸のように地盤運動のそれほど激しくない地域にも海岸段丘は多くみられるのである。
これは地盤が不動であっても、大陸氷河の消長に由来する海岸昇降の結果できたものであり、E.Suessはこのような海面の昇降を、グレーシアル・ユースタシー(Glacial eustasy)と名付けている。すなわちグレーシアル・ユースタシーは洪積世以後の氷期および間氷期という気候変化によるもので、氷期の気温低下は極地の氷床の拡大と海水面の低下の原因となり、また氷期と氷期の間の暖かい間氷期には逆に海水面の上昇という現象を起こすのである。
現在、両極地方の氷が完全にとけた場合には、約60mも海面が上昇するといわれているが、かつての間氷期にも氷床の後退によって海面が上昇したことが考えられ、この時の海底面は当然、現在海岸段丘として残っているはずである。
わが国では関東地方の下末吉面(模式地は横浜市北方にあり、現在標高50mの台地)がこの間氷期の海面上昇によってできた段丘面とされており、この下末吉面に対比される段丘面が後述の西津軽地方をはじめ県内各所にみられるのである。

【参考資料】② 「インド洋」より

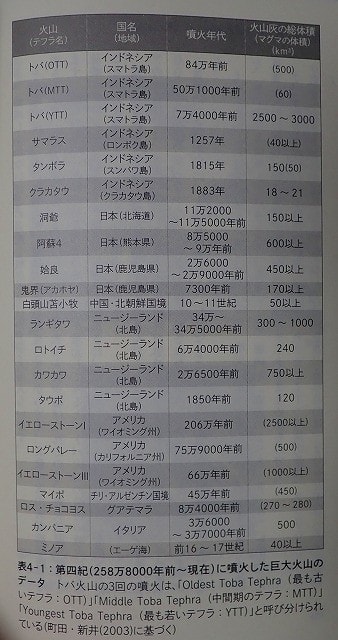
【参考資料】③ 六ヶ所村郷土館の展示資料より



山の上に貝化石、海が上がったり下がったり、陸が隆起したり?・・・・・・
多島海、海底火山、深海、浅海、東西圧縮、氷床の盛衰・・・・・・・・・・・・
岩木山も八甲田山も雪化粧をし
紅葉は見頃だが峠道は通行止めだという・・・
そこで 日曜日 天気も良いので
おにぎりを持って
八甲田の麓原を徘徊ドライブすることにした

田代平の長吉平より

同上

田代平の箒場から 八幡岳を望む
風力発電施設の建設が進んでいる

石倉山放牧地

同上 南八甲田の乗鞍・矢櫃・猿倉岳

同 北八甲田の雪化粧 ブナ林

雛岳とそれに重なる高田大岳 八甲田大岳も

箒場から 雛岳

箒場 ハウチワカエデ

ブナ

イタヤカエデ

赤倉岳

前岳

酸ヶ湯 八甲田大岳

酸ヶ湯 雪に追われてもみじは降る

同上 大岳登山口

酸ヶ湯温泉 フィーバー

ナナカマド

酸ヶ湯 湯坂

萱野茶屋 シナノキは 春一番に芽吹き 秋一番に落葉する
おにぎりを食す
麓原のドライブは 幸畑ーー馬立場ーー箒場ーー石倉山牧場ーー火箱沢ーー酸ヶ湯ーー萱野茶屋ーー雲谷
と徘徊した・・・・・・
今 水曜日は 街中も紅葉している

野辺地沖
風
作詞 C.Gロセッティ
訳詞 西條八十
作曲 草川 信
♫ ♪ 誰が風を 見たでしょう
僕もあなたも 見やしない
けれど木の葉を ふるわせて
風は 通りぬけて行く ♬ ♫
宮澤賢治は 「風の又三郎」などで
見える風を さまざまに表現している・・・
いまや ドロリとした 大気の大循環の中で
プロペラを回して 風を見える化し
その力で 電気を起こし
また 風を起こして
飛行機やドローンのように
大気の中を およいで行くことができる
県内で風力発電が始まって30年
昨年の 青森県の発電量は国内トップという
三方と真ん中が海で
そこを行き来する 風の丘は
立地条件にすぐれている
船から、田畑から、道路から
毎日 風が見えるようになったのだ・・・

六ヶ所村 尾駮

吹越烏帽子から北部上北を望む

同 山頂から

吹越烏帽子 を望む 六ヶ所村

野辺地沖の船上から

ハマナスラインから

地理院地図
蟹田は“風のまち”、吹越は風の通り道、陸奥湾を挟み屏風山に
つながるラインは夏も冬も強い風が吹く・・・・・・

竜飛岬で試験研究がおこなわれたと・・・・・

屏風山

屏風山

屏風山の畑地

屏風山 メロンロード 岩木山

八幡岳地区 石倉山牧場 放牧牛

同上

同上 変電・送電施設

建設中 長いブレードの運搬

八幡岳
【参考資料】①

Web東奥
【参考資料】②
宮澤賢治 見える風表現
宮澤賢治作「」風の又三郎より
風が出て来てまだ刈っていない草は一面に波を立てます。
「電信ばしらも倒さな。」「屋根もとばさな。」「ランプも消さな。」「風車もぶっ壊さな。」
ました。
【参考資料】③

大気の大循環 wekipediaより
9/26 子ども劇場の梵珠山登山ヘルパーに参加した
爽やかな 見通しのきく 秋日和
紅葉には少し早いが
さまざまな赤い実を見つけ
クリやトチの落ちた道を踏みしめ
両ストックで汗を流した

大釈迦から梵珠山・468m を望む
左方では太陽光発電等の工事が進んでいる
集合場所の県自然ふれあいセンターのまわりでは・・・









いよいよ登山開始

マンガンの道 から登る
ブナ林

ヒバ林 ヒバの稚樹

陸奥湾展望所

越口 かつてここの峠を越えて マンガン鉱を運んだのだと・・・・・

シダの見本園的な斜面

寺屋敷広場の オクトリカブト

山頂からの眺め

山頂の芝地で昼食

頂上の観音像 明治に前田野目などの人たちが建てたと・・・・・・
いざ下山・・・・サワグルミの道

寺屋敷広場 コウライテンナンショウ

同広場 クサギ

クサギ

同広場 大きなブナ ウロがあり 小さい子はくぐれる

ユキザサ


『サワグルミの道』を下る


キバナアキギリ

『日本海型ブナ林』の景観

登山道わきの法面に見られた地層 ❔
梵珠山は新第三紀中新世の地質だとされる・・・・・・・・・・・・・・
「赤い実」は検索しきれていない・・・