CDの失われた20kHz以上の音をR-K1000-Nは補完するが、TAPE出力から補完された音が出てくるか確かめた。
家にピンケーブルがあるか探したら、液晶テレビについてきたものを見つけた。本当にあり合わせであるが、これを使ってR-K1000-NのTAPE端子から出力を取って、ラステームのアナログ入力につなげてみた。
まず、音は出た。そして、R-K1000-Nの高域補完モードをOFFにすると、いかにもCDという音に変わるので、TAPE出力から高域を補完した音を取れることが確認できた。あり合わせのピンケーブルで心配したが、出てきた音は素晴らしかった。スタンゲッツのクールベルベットなど、CDは平坦な音だが、R-K1000-Nの高域補完モードの音は情緒があってとても良かった。レコードの音は変幻自在で時には厳しく、時にはやさしくという音だが、R-K1000-Nの高域補完モードもそんな感じの音。これまで、CDで癒されることは難しかったが、高域補完した音だと癒されるためにCDの音を聞きたいと思える。今回の試みは、なかなかのヒットだと思う。
R-K1000-Nでのアナログ変換、ラステーム302Pでのデジタル変換と相当情報がロスしているはずだが、かなりいい音だ。それだけ、高域補完の有効性が高いということか。R-K1000-NのDAC直前のデジタル信号が取り出せると良いのだが、私の今のスキルでは無理。
家にピンケーブルがあるか探したら、液晶テレビについてきたものを見つけた。本当にあり合わせであるが、これを使ってR-K1000-NのTAPE端子から出力を取って、ラステームのアナログ入力につなげてみた。
まず、音は出た。そして、R-K1000-Nの高域補完モードをOFFにすると、いかにもCDという音に変わるので、TAPE出力から高域を補完した音を取れることが確認できた。あり合わせのピンケーブルで心配したが、出てきた音は素晴らしかった。スタンゲッツのクールベルベットなど、CDは平坦な音だが、R-K1000-Nの高域補完モードの音は情緒があってとても良かった。レコードの音は変幻自在で時には厳しく、時にはやさしくという音だが、R-K1000-Nの高域補完モードもそんな感じの音。これまで、CDで癒されることは難しかったが、高域補完した音だと癒されるためにCDの音を聞きたいと思える。今回の試みは、なかなかのヒットだと思う。
R-K1000-Nでのアナログ変換、ラステーム302Pでのデジタル変換と相当情報がロスしているはずだが、かなりいい音だ。それだけ、高域補完の有効性が高いということか。R-K1000-NのDAC直前のデジタル信号が取り出せると良いのだが、私の今のスキルでは無理。











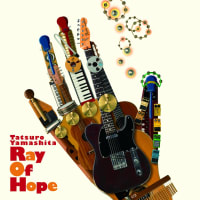








先日Nmodeのアンプを試聴してきました。これは、デジタルアンプという点と、価格破壊で評判という点で、ラステームの対抗馬となり得るアンプだと思います。トライパスチップということもあるのかやはり馴染みのあるデジタルアンプの音だったので、これならRSDA302Pのシリーズ電源化で十分拮抗できるだろうと読んでスルーしました。
当初、R-K1000のTape Outにはそれなりのアナログアンプを奢ってやるつもりでおりましたが、今回、価格破壊デジタルアンプも十分戦力になり得るということがわかったので、暫くはこのまま価格破壊路線で遊んでみようと思います。
なにやら高級な意地悪心を愉しんでいる自分に気づきますが、これは信助さんの遊びに巻き込まれたためでしょうか。機器構成まで信助さんと似てきています(笑)。Tape Outのテストができた暁には、また感想など書き込ませていただきたく存じます。
RSDA302PとRDA-520を聞き比べたところ、RDA-520の方が太い音でした(ぱっと聞いて分かるぐらい)。RSDA302Pの方が高域の量感が多いのですが、しゃりしゃりしている感じがしなくもなかったです、RDA-520の方は高域の量感が少ないのですが、なめらかな音でした(R-K1000のようにぬめっとした感じとは違います)。その時、私だったらRSDA302Pを選ぶと思いました(自分の家でしゃりしゃりしている印象はないので)。一般的にはRDA-520を選ぶ人の方が多いかも知れないと思いました。しかし、自分のシステムで使った見ないと結論が出ないと思います。
RSDA302PはACアダプター(視聴室のは一般的なスイッチング電源だと思う)、RDA-520は内蔵のトロイダルトランスなので、その差が音に出ている気がしました。他にトランス内蔵型のを聞いたのですが(機種名は忘れてしまいました)、それもRDA-520と似た傾向の音がしていましたから。
繋ぎのつもりで入手したR-K1000でしたが、それに自作スピーカーとND-S1とを組み合わせたシステムからの音はそれまで使っていたいっぱしの機材の音よりもずっと良いのです。この経験で、安いヤツで上位機種を喰うことの面白さに開眼しました。
ところで、RSDA302Pよりも更に後発となるRDA-212やRDA-520などの音は聴かれましたか?RSDA302Pの品質が意外に良いとのことですので、後発のこれらも候補に入れてもよいかと考えはじめたところです。信頼している信助さんから意見していただけるとありがたく存じます。
例のものはあまり良くない気がしています。ちょっとやり過ぎのような印象を受けました。まだ少ししか使っていないので、これから感想が変わる可能性もあります。Snow lepardで動かないみたいで、ノートブックにLepardをわざわざインストールして使いました。機械に問題があるみたいで、突然爆音が鳴り出したりと恐ろしいです。なので、常用マシンにはならないと思います。
takmaiosさん、
R-K1000の評価から私とtakmaiosさんは似た感覚を持っているように感じています。Crown D-45よりRSDA302Pの方が帯域は広い(特に高域方向)のでRSDA302Pはtakmaiosさんの好みに合うかも知れません。私がRSD202を使ったことがあれば、良かったのですが。
ND-S1ですね。この製品は心にとめておこうと思います。
これを一聴してその瞬間私はAME法から卒業させられてしまいました。もはや移行期ではなく、円盤回転による音楽再生の時代が完全に終わったことを感じました。ぜひ一度試してみられてください。
CDドライブのピックアップサーボモーター、PC内のファンモーター、LAN経由のノイズなどから離れていられることがこの音の良さの秘密なのではないでしょうか。この方法が今後の音楽再生の主流になっていくだろうと感じております。
しかし、これはCrown D-45にも通じることですが、駆動力はあっても帯域が狭く感激のない音であったために手放してしまいました。RSDA302Pは聴いておりませんが、信助さんの感想からすると私の使っていたRSD202とはかなり異なる傾向のようですね。これは意外です。
私もプロケーブルの音を一旦通過した人間ですので、信助さんの仰ることよく共感できますよ。TAPE出力に関してはKENWOODの技術の方が勘違いしている可能性もありますね。
私もTAPE出力の音をすぐにでも聴いてみたいのですが、しかし、最近の引越しを機に音を印新したく、これまでのステレオ装置を全部処分品してしまっております。
そこで当面の繋ぎとして一台で何でもできるR-K1000を導入した次第です。今のところ、下流に繋ぐまともなパワーアンプの手持ちがありませんので、TAPE出力の感想をすぐに差し上げることができません。どうぞ気長にお待ちください。
R-K1000の音の感想はtakmaiosとほぼ同じです。海外のメーカーの名をつけて洒落た筐体に入れたら、50万でも売れるような気がします。でも、私個人の意見からしますと、つまらない音ですし、いくつかの音が捨てられている印象があるので好奇心旺盛な中学生が使うにはかわいそうな気がしました。
takmaiosさんは、ラステームのデジアンを聞いたことがあるようにお見受けしましたが、ラステームのデジタルアンプもそんな印象でしたか(S/Nは良いのに頭打ち感があって抜けきらない)?私はRSDA309Pを持っていますが、なかなかいい音だと思っていますし、これまで使って来たアナログアンプ(NEC A-10III, 金田式完全対称(型番忘れました), Crown D-45, Yoshii9専用アンプ等)よりずっと良い印象を持っています。駆動力があって、且つ細かい音がよく聞こえるというのがRSDA309Pの印象です。
拙宅にもR-K1000届きました。S/Nが良くて綺麗な音ですね。ただ、やはりデジタルアンプ然としたベールがかかっているような雰囲気はどうしても感じますね。喩えるなら、CG加工された綺麗な写真だけど、産毛や毛穴が見えてこないので発情させてもらえないーーそんな感じでしょうか。信助さんちのメインコンポの地位を奪うにいたらなかったのも同じ理由からでしょうか?
ラステームも含めて、デジタルアンプと呼ばれるものは大抵こういう印象(S/Nは良いのに頭打ち感があって抜けきらない)がありますが、これはやっぱり最終段のローパスフィルターのせいなのかしら?
それにしても、この音がこの価格でというのは驚きです。電子機器に於いてだけは良い時代になったものですね。今の中学生が羨ましい。なにせ、お年玉をためて買った初めてのステレオセットで一昔前のハイエンドオーディオを凌駕しちゃうこともできるんですから。
えっ、KENWOODの技術の方がそう言っていましたか。もし、そうなら、それも納得できるのですが。
今、TAPE outからの出力を高域補完機能をOn, Offして比べてみたのですが、やはり差があって、Onにした方が伸びやかで好きな音でした。KENWOODの技術の方の話が本当だとすると、高域補完機能Onの2次的な影響で音が変わっているのかも知れません。
聴感道徳が似ているためでしょうか、信助さんの仰る一々が自分にも合点がいくことばかりで、毎度首肯しながらROMしておりました。
丁度複数のデジタル入力を必要としていたところに、この記事を読んで高域補完機能があることを知り、フィデリックスのハーモネーターなき今これしかないとてR-K1000の購入を決めました。
ポチッたあとで、念のためにKENWOODの技術に確認してみたのですが、「高域補完機能はTape outでは有効にならない」とのことでした。「パワーアンプ段を通る回路でのみ高域補完機能が有効になる」とのことで、前段から取り出すのは難しいようでした。
私の知識が浅いために回答をうまく引き出せなかったという可能性もあります。信助さんも問い合わせてみられてはいかがでしょうか。
http://hp.vector.co.jp/authors/VA018963/upconv_001.htm
20kHz以上を補間の他にサンプリングレートを上げると、音のツブが細かくなった感じでこれもまたいいです。
ファイルサイズが大きくなるのと仮想環境でWindowsを動かしてるのでちょっと遅いのが難点ですが、安いWindows機なら数万で売ってることを考えるとINTELじゃないMacユーザーもそれだけの為にWinを買ってもいいかなとも思います。
早々にレスいただき有り難うございます。
ご説明よくわかりました。近いうちに、試してみます。
早々にレスいただき有り難うございます。
ご説明よくわかりました。近いうちに、試してみます。
tape outは音量調節と連動していないので、パワーアンプにつなぐ場合、間にプリアンプがいると思います。もし、パワーアンプにボリュームが付いていれば、これを利用することも可能だと思います。
k1000はCDの20 kHz以上の音を補完して付け加えてくれるのが良く、tapa outから高域補完した音を取り出すことが出来るので、このやり方で使っています。マニュアルを見ると、高域補完のOn, Offの仕方が書いてありますので、音の違いを確かめてみるとおもしろいと思います。
小生も同じk1000を所有しており、音質については信助さまと同じ印象を持っております。私の場合はアナログパワーアンプに繋ごうと思っておりますが、tape outからピンケーブルでパワーアンプに接続すると、k1000がプリアンプとして作動するということでしょうか?
やはり、高域補正した音をデジタルで出力する商品があると良いですよね。たとえアナログだとしても高域補正の効果は絶大です。すでに技術的な問題は全くないと思うので、どこかのメーカーがやってくれると良いのですが...
ffさん、
ソフトについて教えて下さりありがとうございます。
CDの音を見ると、やはり、ぶった切っちゃっていましたか、
http://www.arizona-software.ch/audioxplorer/plug-ins.html
CDからリッピングした音源でマックのスピーカーだと当然のことながら見事に18kHzが出てませんね。
なかなか面白いので一度お試しください。
ぶった切っちゃうと、それが無くなる為に不自然になるようです
だから、20kHz以下の音をあらかじめ干渉後の音に加工して出力してくれる製品もあるそうですね
どこの製品かはわかりませんが
私も今どうしようか考えています。
これがデジタル出力があるとよいのですが,ステレオminiのアナログしかないのですよね。
今、学会に参加するために日本に来ています。学会会場の無線LANから書き込み中。昼ご飯の休憩中で、さぼっているわけではないですよ。
私は江川先生がフィデリックスの製品をデモで使っていたという程度のことしかしらないので、東北大学や筑波が先に提唱していたんでしょうね。
Frieve Audioも出来るんですね。2種類の補正法があって自然な補正の方はコンピュータ負荷が高いとありますが、Kenwoodのアルゴリズムはどの程度なものなんでしょうね?音の出だしの遅延もないですし、リアルタイムでやっているんだからすごいと思います。
高域の補正機能は本当に良いですよ(もっとも20 kHz以下の音をいじっていないかどうか確認することは出来ないのですが)。マクセルの補正機能付きヘッドホンDACを買いました。もう生産終了品で48kHzまで補正するものです。確か九州工業大学の研究室が独自で作ったアルゴリズムを採用していると思います。アメリカに帰ったら試してみます。
こんなの見つけました。Winですけど。
http://cheapaudio.blog23.fc2.com/blog-entry-41.html
BootcampでWin起動して試すこともできますでしょう?
1984年に筑波大学の先生が超高域再生の必要性を示す論文を発表したとあります。
http://www.fidelix.jp/products/ahs/index.html
先の記憶はこれと江川理論がごちゃまぜになっているかもしれませんが,記憶の中では筑波大学ではなく確か東北大学での実験だったという印象が強いです。
新聞にも小さく載ったような記憶です。
その当時フィデリックスのハーモネータがあったかどうか定かではありませんが,CDが出てから何年も経っていなかったと思います。
それにしても以前はあまり興味がなかったのですが,20KHz以上の信号補間はよさそうですね。
毎日、ケンウッドのTape出力の音を聞いていますが、かなり良いです。CDに対して持っていた最後の不満はこれだったんだと分かりました。
ご存知かもしれませんが、20kHz以上を付加する機器をハーモネーターというそうで、専用の機器が出ていました。
http://www.koizumi-musen.com/AH-120K.htm
120kHzまで発生させることが出来るそうです。
ただデジタルIN/OUTはないようなのがちょっと残念です。
ffさん、いろいろ調べて下さってありがとうございます。メーカーの解説からだと20kHz以上を足しているかどうか、判断が難しいですね。イコライザー的なもののような気がします。
excitifierかどうかわかりませんが、「補正機能」が今回の話題のものに近いと思います。
メーカーの解説をみると、「補正機能 - アーティストがリスナーに聞いてほしいと思う音質そのままを再生。録音の過程で失われた周波数やニュアンスや力強さを残さずお伝えします」とのことなので、他のフィルターが脚色だとしたら、まさしくこのフィルターが補正してくれるものだと思います。
audiohijackの方だと、メーカーサイト(http://www.rogueamoeba.com/audiohijackpro/)からダウンロードしていただいて、OSX用の無料Excitifierプラグインがあるので(http://mac.softpedia.com/get/Audio/Excitifier.shtml)ダウンロードしていただいて、/Library/Audio/Plug-ins/VST/にプラグインを入れれば使えます。
フォルダがない場合は作って入れてください。
Hearの方がわかりやすく簡単ですが、AudioHijackの方はプラグイン形式でOSX用のオーディオプラグインなら追加していけるので拡張性が高く便利です。
エフェクトをかけた後の音をオーディオデータとして書き出せるので、他の再生機器で扱えるファイルにできるのも魅力ですね。
というのはそういう意味だったのですか。
その場合取り出されたデジタル信号のサンプリング周波数とかビット数はどうなるんでしょう。
仮に取り出せたとして,ラステームのRSDA302Pだとデジタル受けが44.1/48KHzじゃありませんか?
アンプがデジタル信号をフィックスしないかも。
http://www.kenwood.co.jp/products/home_audio/acoustic/r_k1000_n/index.html
しかし,DACチップの中で超高域を付加している場合は無理みたいです。
excitifier系のエフェクトというのがどこにあるのかわかりませんでしたが,弄ってみるところころ音が変わりますね。
楽しいのですけれど,どれが本当の音か解らなくなるし,「よい塩梅」に止めるのが難しいところです。これを使うとなるとよほど経験を積まないと無茶苦茶になりそうです。
グライコ,コンプレッサー,リバーブ何でもそうですけど。
勉強になりました。
「原音に含まれる高域の倍音を強調してそれを原音に加えることによって音を前面に出す「ハーモニックエキサイター」」
とあります。
で「ハーモニックエキサイターとは、ハイパスフィルターに通した音を半波クリップさせたものを原音にMIXする方式で、要は無理矢理倍音を作り出すものです。」とあります。
http://homepage2.nifty.com/nori-no_dtm-seikatsu/gloss/ae/30A830AD30B530A430BF30FC.htm
ですので,やはり,原音(入力された信号)に含まれていない周波数を付加するものではないようですね。
クリップという意味はよく解りませんが。
Audio Unitは192KHzまでの処理をしてると思ったので、効果ありそうな気もするのですけど。
私の買ったケンウッドのコンポの中身はフルデジタルなので、高域を付加したデジタル信号は中を通っているはずです。これを取り出せたら良いんですが。。。出来る人は簡単にできてしまうんだと思います。
高域が必要ならハイサンプリングで録音してそのニュアンスを損なわないようにサンプリングレートを落とします。その段階で各チャンネルにエフェクトをかけて2chにミックスしたときに意図した音になるようにするでしょう。ですので,例えば44.1KHzに落としてから20KHz以上の周波数を付加するなんてことは考えてもいないんじゃないでしょうか。
もしそうした方向を求めるなら,デジタル入出力付のフルーエンシーDAC搭載機,あるいはレガートリンクコンバージョン搭載機といった民生用再生機器からさがすしかないでしょう。ケンウッドの単品コンポなんかにないですかね。
ffさんに紹介して頂いたリンクを見てみたのですが、楽器用の製品もいろいろありますね。オーディオ用に応用すると意外な効果があるかも知れませんね。
20KHzを超える周波数を付加して(擬似的に作り出して)再生する製品としてフィデリックスのSH-20K,パイオニアのレガートリンクコンバージョン,あるいはフルーエンシーDACというDAコンバーターの方式などがあります。ケンウッドの製品もこれらに属するのでしょう。
これに対して録音やマスタリングで使われるエフェクタは,エフェクタに放り込まれた音源が持つ周波数成分を操作して臨場感,迫力,リアリティなどを高める手法で,音源が持つ周波数成分を超えた周波数成分を生成付加するものではありません。
ご案内のWaveEmphasizerもシェルビングタイプのイコライザーと同様の効果を持つものとされています。この機器は24bitsに対応していますが,対応サンプリング周波数は44.1KHzと48KHzなので,再生周波数帯域はせいぜいDAT止まりです。ですので,20KHz以上の超高域成分(40~50KHzまで)が必要だという主張とは別のものだと思います。
でも機械好きにはとても魅力がありますね。ちと高いけどムニュムニュ・・・
イコライザーと違って倍音を擬似的に引き上げるので、イコライザーのような違和感がなくてハリが出てきます。
デジタルIN/OUTで探すとこのあたりでしょうか。
http://www.digimart.net/inst_detail.do?instrument_id=DS00535522
ちょっと高いです。
エフェクターはなかなか検索でうまく引っかからないですね。
だとしたら、エキサイターをかませればどんなアンプでもいけそうな気がするのですが、ちょっと違うんでしょうか