皆様、おはようございます。今朝は愛媛松山・道後温泉からのスタートです。
さてさて。
昨日アップロードした英語ブログ、大変好評でして(^^♪
既に13か国の方々がご覧頂いており、過去最高値のPV数です。
いいですね~♪ 徐々に皆さん、本質を求め始めましたね。
というわけで。
つい先ほど和文ブログもアップロードしました。
「本当の問題」に切り込みます。
ぜひ、ご覧下さい。
そして・・・いつものとおり「シェア」して頂ければ幸いです!(「いいね!」あるいは「twitter」にて(^^)/)
拙著最新刊はこちらから↓どうぞ!
http://www.amazon.co.jp/甦る上杉慎吉-天皇主権説という名の亡霊-原田-武夫/dp/4062191768/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1411850010&sr=1-1
これを読まれないと・・・「これから」についていけませんよ★
実は道後温泉にて、原稿の初校、ようやく校正終わったのですよ~
いや~大変だった!(´・ω・`)
では!
佳き日曜日を★
http://blog.goo.ne.jp/shiome/e/3d854b93e10ddbde753bdda0c4704da4
https://www.facebook.com/iisia.jp/posts/740545362683354

(出典:宮内庁)
今、「アベノミクスは一体どうなってしまうのか」という議論が喧しく行われている。それもそのはず、円安・ドル高に振れて株価も続伸し始めたかと思ったらば「有志国連合(coalition)」によるシリア領内での空爆が開始。結果として円高・ドル安へとあらためて振れ、平均株価が崩落するといった具合に、今の日本株マーケットにおける展開が「大本営発表」が繰り返すような実体経済の回復に伴うものではおよそなく、ややもすれば出口を失いかけている可能性すら出始めているからである。
その様な中、率直言うとここに来て「外生的なリスク要因」としてはどちらかというとダーク・ホースであった「韓国金融崩壊に伴うショック」というファクターが首をもたげ始めている。紙幅の都合があるので詳細は追って別の場所においてということにさせて頂ければと思うが、グローバル・マクロ(国際的な資金循環)の波が明らかに逆回転し始めたこのタイミング(2014年9月末)において、どうやら餌食は我らが隣国になりそうな気配が出始めているのである。用心に越したことはなく、またそれが「現実」となった場合には果たしてどこまで我が国に波及効果が生じるのかをあらかじめ検討しておく必要がある。
だがこれらはある意味、結局のところ「さざ波」に過ぎず、その底流にあるものとして私たちが考えるべき本当のことと比べれば所詮、些末なことなのかもしれない。それではここでいう「私たちが考える本当のこと」とは一体何なのだろうか。―――端的に言うならばそれは、これから我が国が突入する「事実上のデフォルト処理」の中で如何なる国制を目指すべきかという問題である。
このことを理解するためには次の「事実」をこれから書いていく話の大前提として読者の頭の中で確認しておく必要がある:
●前提1
我が国は国内外の経済危機が究極のレヴェルにまで達する時、その処理と併せて国制の根幹としての「天皇制」について状況に適合的な形へと自らの意思で変化させてきた経緯があること
●前提2
現在進行形である「アベノミクス」は実のところ事実上のデフォルト処理を行うための演出の一つに過ぎず、とどのつまり我が国経済は一時的に急激な資産バブルがあらためて発生した後、今度は破綻の寸前にまで追い詰められること。しかもそれらはすべて我が国における中核的な権力による意図的な戦略に基づくものであるということ
まず前者であるが教科書的な解説を越えて、近代以降に生じた本当の展開を簡単に描くとこうなる:
―幕末に世界マーケットが初めての深刻な不況に見舞われる中、米欧と我が国との間において金銀交換レートを巡る混乱が勃発。他方で国内においては深刻な債務危機が生じる中、これらを一挙解決すべく(=債務帳消し、金本位制の導入)、「明治維新」が行われ、天皇制は「大日本帝国憲法」に基づくものへとヴァージョン・アップされた
―昭和恐慌とそれに続く世界大恐慌の中でグローバル・マクロ(国際的な資金循環)が著しく滞り始めたため、まずは我が国より「開戦」へと踏み切るがその後、あえなく「敗戦」。その結果、GHQという名の米国による「日本管理」が行われる中、我が国の帝国議会が審議・可決する形で「日本国憲法」を制定。天皇制はそれに基づく「象徴天皇制」へとヴァージョン・アップされた
我が国においては戦後、「それでも天皇制は封建体制とファシズムの残滓であるから排除すべき」という左翼史観か、あるいは「日本国憲法は押しつけられたものだから無効だ」という”保守”史観しか存在してこなかった。そのため、実のところ「グローバル・マクロ」「我が国の憲法」「天皇制の在り方という意味での国制」というトリニティ(三位一体)が連動して動いているという冷静な認識をもって我が国の歴史が語られることは皆無だったのである。
だが、冷静に考えるならば結局のところそういうこと、なのである。歴史を人物史中心に熱く語るのはエンターテイメントとしては良いだろうが、それは国家論のレヴェルでいうとまやかしでしかない。つまり「本当のこと」を透徹する目を曇らせるまやかしでしかないのである。とりわけ国家統治が世界統治の一環であり、そこでは「世界における根源的な階層」としての各国王族たちが連携してグローバル・マクロ(国際的な資金循環)を廻すことこそが本質として営まれているという現実を踏まえるならば、そうしたエンターテイメント史観はある意味、そうした世界運営に伴い市井に暮らす私たちが時に強いられることになる激痛を感情的にケアするための「ホオタイ」に過ぎないのである。したがっていわゆる「司馬遼太郎史観」を今ここで打ち捨てなければ話は始まらない。
以上を踏まえていうならば我が国においてこれから「本当のこと」もまたこれまでと同じはずなのである。我が国においてこれから起きることを分かりやすいように分解していうとこうなる:
―事実上のデフォルト処理に向けた意図的な誘導
―それを通じて起こす内政上の混乱を起爆剤とした「国制変更を求める議論」の高揚
―そうした議論の結果としての「憲法改正」と「天皇制のヴァージョン・アップ」
しかるに我が国世論においては未だに「アベノミクスだから株高になるのか」「賃金は果たして上がるのか」といった”さざ波の議論”しか行われていない。しかしこれまで私が2010年以降発表してきた数多くの著作において明らかにしてきたとおり、それは上記でいうところの「事実上のデフォルト処理に向けた意図的な誘導」の中のほんのひとコマに過ぎない「我が国マーケットにおける資産バブルの惹起(=「日本バブル」)に関するものなのである。話は明らかに「その次」へと向かっていることを今、冷静に認識しておく必要があるのだ。

(「天皇主権説」を主張した上杉愼吉)
この未だ誰も論じていない本当の論点について端的に指摘し、公論を促すべく、私は来る10月23日に最新刊「甦る上杉愼吉 天皇主権説という名の亡霊」を講談社より上梓する予定である。ただしその刊行日まで未だ日があるということと、私たち日本人がこれから均しく直面することになるこの問題が余りにも巨大であり、同時に複雑であり、さらには喫緊のものであることから、このコラムを通じてこれから複数回にわけて読者の理解のため、「補論」を記していこうと考えている次第である。
デフォルト、すなわち「国家債務不履行」がなぜ政治体制の問題になるのかといえば、それは民主主義による政治運営の失敗を意味するからである。私たち日本人は学校教育を通じて「民主主義こそ正しい政治運営の手法」と刷り込まれてきている。だが、それをフルフレッジで推し進めた結果がこの様なのである。国家破綻のツケが自らにまわってきた時(=ペイオフを理由にした預金のヘアカット(一部召し上げ)とそれを通じた国家債務の事実上の相殺)、市井に暮らす私たち日本人が果たして「そう、私たち自身が責任を負うべきなのです」などと粛々と述べることが出来るだろうか。―――何かが起きると全て「他人のせい」にし、インターネット上でバッシングを繰り返す習癖を身につけてしまった私たち日本人が「自己責任」という民主主義の大原則を事ここに及んで認めるとは到底考えられない。
だからこそ「新しい体制」「国制刷新」へと話は続いていくと言うわけなのである。その中でやり玉にあげられるのはGHQという名の米国が我が国に刷り込もうと画策してきたアメリカン・デモクラシーという意味での民主主義システムに他ならない。「これまでとは全く違うやり方はないのか」が激しく議論される中、今や歳費の無駄遣いを行うマシーンでしかないことがまずは地方自治レヴェルで露呈し始めている代議制民主主主義というシステムはいよいよ打ち捨てられるに至るのだ。

こう述べると必ず「それではファシズムか?独裁か??」と単純な議論を繰り広げようとする向きもいるのではないかと思う。上述の左翼史観の持ち主が特にそうであるはずだ。だがご安心あれ、これまでの左翼歴史教育の結果、一時的に熱狂はしたとしても我が国世論が「唯我独尊」のデマゴーグを最後の最後まで支持はしないのであって、そのことは「橋下徹大阪市長」を巡る顛末で既に明らかなのである。

国家破綻の時まで早ければあと2年と迫った今、始めるべきは「為替談義」や「株談義」、さらには床屋談義の域を出ないマスメディアが繰り広げる「永田町談義」などでは全くない。今こそ必要なのは「国家破綻を越えて、この国がどうあるべきなのか」という国制刷新の議論なのである。そしてその際に中心的な課題に据えられるべきは我が国における中核的な権威である「天皇」であり、その国制という意味での「天皇制」なのである。さらにいえばそれを記した「憲法」でもあるのだ。
以後複数回にわたり、この点についての卑見を今の段階から述べ、広く読者諸兄、そして愛すべき我が国の同胞諸兄に広く問題提起することとしたい。
原田武夫記す
(2014年9月28日 道後温泉にて)
なぜ今「天皇主権説」再考なのか・その1 (連載「パックス・ジャポニカへの道」)
http://blog.goo.ne.jp/shiome/e/3d854b93e10ddbde753bdda0c4704da4
http://blog.goo.ne.jp/nobody-loves-you/e/574f46442d1096fe1e46b99cc95d3f3d
http://blog.goo.ne.jp/nobody-loves-you/e/be45cab151801be8aa42b65ca94d0c9d
http://blog.goo.ne.jp/nobody-loves-you/e/0d59a985eb861fc8528d6b1a0ec182a7
(※拡散希望!) なぜ今、「天皇主権説」再考なのか?・その5(完)
http://blog.goo.ne.jp/nobody-loves-you/e/0907778b0f221a340eb8a4db068a745a
http://blog.goo.ne.jp/nobody-loves-you/e/48b287c92ca50d47b2cd877fbd8c5e26
歴史の藻屑として消え去ってしまったかのように見える「天皇主権説」
http://blog.goo.ne.jp/nobody-loves-you/e/153c6726110164c9980b279c45c189db
http://blog.goo.ne.jp/nobody-loves-you/e/8187c2ce28b538d279025a13f298fdbe
苦悶する安倍外交:一体何が欠けており、「世界の根源的な勢力」は何を不満に感じているのか?
http://blog.goo.ne.jp/nobody-loves-you/e/262e5a303367245517471ff838c15a1d
「より大きな何か」が私たちを救い出すことになると、そう想う次第です
http://blog.goo.ne.jp/nobody-loves-you/e/2cc90c76b728d9f33e9134803cf515e2
なぜ今「ロスチャイルド家と徳川家」なのか? 明治維新の真相とそれが導く明日の世界
http://blog.goo.ne.jp/nobody-loves-you/e/dbaa961b164c44716767f6608a1eff8a
謎の仏貴婦人が与えてくれた、重大なヒント ~「小泉脱原発宣言」と日本デフォルト(上)~
http://blog.goo.ne.jp/nobody-loves-you/e/bfa313dd99c73c2d2cefa8d408fd1c5e
唐突な小泉元首相の発言に隠された「秘密」 ~「小泉脱原発発言」と日本デフォルト(下)~
http://blog.goo.ne.jp/nobody-loves-you/e/0b5c6a45e25e77768c8411e7b647290f
http://blog.goo.ne.jp/nobody-loves-you/e/29c17d085e82261a54d8c064422ea20b













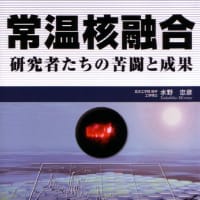





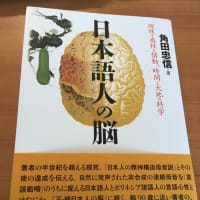
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます