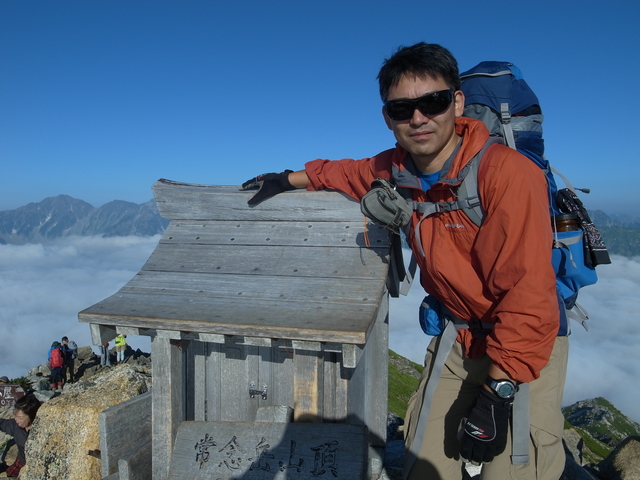「カラマーゾフの兄弟」の中に、次兄のイワンが幼児虐待について末っ子のアリョーシャと語り合っている箇所がある。ドストエフスキーの文章は長いので多少省略してたが、掲載する。
イワンは無神論のニヒリストである。神を認めていない。虐待された幼児になんの罪があるのか。そして、かわいそうな子供たちはどのように救われるのか。その償いなくして、世界調和などというものは認めないと彼はいう。
幼児虐待は現在になって急に増えてきたというわけでなく、また日本だけの問題でもない。世界中に起こっている古くて新しい問題である。
「人間の多くは一種の特別な資質を備えているものなんだ。それは幼児虐待の嗜好だよ。子供たちのかよわさが迫害者の心を駆り立てるのさ。逃げ場もなく頼るべき人もいない子供たちの天使のような信じやすい心、これが迫害者のいまわしい血を燃え上がらせるんだ。もちろん、どんな人間の中にもけだものが潜んでいる。怒りやすいけだもの、痛めつけられるいけにえの悲鳴に性的快感を催すけだもの、放蕩の末に痛風だの肝臓病などという病気を背負い込んだけだもの、などがね」
「小さな女の子を両親が虐待した話がある。五歳のかわいそうな女の子を教養豊かな両親はありとあらゆる手段で痛めつけたんだ。理由なぞ自分でも分からないまま、殴る、鞭を打つ、足蹴にするといった始末で女の子の全身をあざだらけにしたものだ。
そして、この上なく念のいった方法に行きついた。真冬の寒い日に、女の子を一晩中便所に閉じ込めたんだよ。それも女の子がウンチを知らせなかったという理由でね。その罰に顔中にもらしたうんこをなすりつけたり、うんこを食べさせたりするんだ。それも実の母親がそんなことをするんだ。しかもこの母親は子供のうめき声が聞こえてくるというのに、ぬくぬくと寝ていられるんだからな。一方、自分がどんな目に合わされているか理解もできない小さな子供が、真っ暗な寒い便所の中で悲しみに張り裂けそうな胸をちっぽけな拳でたたき、涙を流しながら「神様に守ってください」と泣いて頼んでいるというのにな。お前にはこんなばかな話が分かるかい」
「俺は、やがて鹿とライオンがわきに寝そべるようになる日や、切り殺された人間が起き上がって、自分を殺したやつと抱擁するところをこの目で見たいんだよ。なんのためにすべてがこんな風になってきたかを悟るとき、俺はその場に居合わせたい。地上のあらゆる宗教はこの願望の上に創造されているんだし、俺もそれを信じている。
しかし、それにしてもこの子供達はどうなるんだ。その時になって俺はあの子供達をどうしてやればいいんだ。たとえ、苦しみによって永遠の調和を買うために、すべての人が苦しまなければならぬとしても、その場合、子供たちに一体なんの関係があるんだ」
「憎しみあう人たちが、『主よ、あなたは正しい』と叫び抱擁しあうことが本当に起こるかもしれない。しかし、俺はそれを全面的に拒否する。なぜなら、そんな調和は、くさい便所で涙を流しながら神様に祈った子供の涙にさえ値しないからだ。あの子の涙が償われずじまいだからさ。その子供を虐待した人々を赦すことはできない。この世界中に赦す権利を持っているような存在がはたしてあるんだろうか」
「人を幸福にし、最後には人々に平和と安らぎを与える目的で、人類の運命という建物を作ると仮定してごらん。ただそのためにはどうしても必然的に、せいぜいたった一人かそこらのちっぽけな存在を、例えば例の小さな拳で胸を叩いて泣いた子供を苦しめなくてはならない、そしてその子の償われぬ涙の上に建物の土台を据えねばならないとしたら、お前はそういう条件で建築家になることを承諾するだろうか。答えてくれ。嘘をつかずに」
「いいえ、承諾しないでしょうね」アリョーシャが低い声で言った。
「それじゃ、お前に建物を作ってもらう人たちが、幼い受難者のいわれなき血の上に築かれた自分たちの幸福を受け入れた後、永久に幸福であり続けるなんて考えをお前は認めることはできるかい」
「いいえ、認めることはできません、お兄さん」アリョーシャは言った。「兄さんは今、赦す権利をもっているような存在があるのだろうかといったでしょう。でもそういう存在はあるんですよ。その人(キリスト)ならすべてを赦すことはできます。その人自身、あらゆるもののために罪なき自己の血を捧げたんですからね」
この話を語った後、有名な大審問官の話に移っていく。
イワン・カラマーゾフの無神論は非常に強力な思想でそれを完全に否定することは難しい。正直言って、私も無神論に近い。
末っ子のアリョーシャカラマーゾフはイワンに対し、そのような思想を持っていたら自殺するしかありませんと宣告する。
私は、無神論であっても、自殺することはないと思っているが。
この、両者の思想上の対決は、ドストエフスキーの心の中の葛藤でもある。