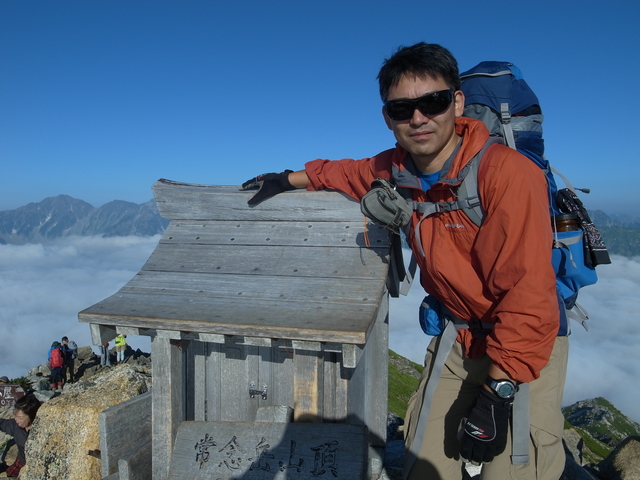前回のブログで、小泉八雲が出てきたので、ちょっと彼について書いてみます。
ギリシア生れのイギリス人です。
1890年に来日し、松江中学の教師になったあと、小泉セツと結婚しました。
のちに、小泉八雲と改名し、東京帝国大学、早稲田大学の講師として英文学を教えました。
「怪談」が有名で、耳なし芳一とか雪女とか、今読んでも面白いです。
小泉八雲は、地域の人から昔の怖い話を聞いて、それを物語にしている。
その意味で、民俗学という言葉がなかった時代の先駆け的な存在です。
民俗学というと、まっさきに柳田国男を思い浮かべますよね。
しかし、彼の「遠野物語」を読んでもさっぱり面白くない。怒られるかな。
しかし、小泉八雲の話はすごく面白い。
この違いはどこにあるのでしょうか?
思うに、柳田国男は、村人たちから聞いた話をそのまま記述しています。
事実は事実としてそのまま提示するジャーナリストの手法です。
これに対し、小泉八雲の話は、たぶん、彼風にアレンジされている。
話にきちんと謎が提示されています。
謎を解いていくという、物語の構造になっている。
ちょうど時代は、シャーロック・ホームズの時代です。
謎を問いていく推理小説的なスタイルは、イギリス文学の得意とするところですね。
この手法に、大きな差があるのではないかと思っています。
たとえば、雪女です。
柳田国男の遠野物語では、
103「小正月の夜、または冬の満月の夜は、雪女が出て遊ぶといわれている。雪女はどこからともなく里を訪れるそうだ。遠野の子供達は、夜遅くまでソリ遊びをしているが、十五日の夜に限り、雪女が出るから早く帰れ、と言われる。だから、雪女を見たものはとても少ない」
と書かれています(読みやすくしてる)。
だからなに?って感じがしませんか。
これに対し、小泉八雲の書いた雪女は、きっちりとしたストーリーです。
「耳なし芳一」もけっこう面白いですが、「忠五郎の話」が割と好きです。
「忠五郎の話」のあらすじをちょっと紹介しますね。
小石川にイケメンで賢い足軽がいた。非の打ち所のない好青年だった。
しかし、彼が夜な夜な出かけて、朝に帰ってくる。
それを、他の足軽に見つかった。
どうも最近、顔色も良くない。いったい、どこに出かけているのか?
そのことを忠五郎に問いただしてみた。
彼は川辺で綺麗な女性と出会い、恋に落ちてしまったそうだ。
そして…
面白そうでしょ。いちおう怪談話ですが、ミステリーとしても、恋愛モノとしても読めます。
真夏に怪談話もいいですよ。涼しくなります。よかったらどうぞ。
怪談風朗読 小泉八雲「忠五郎の話」