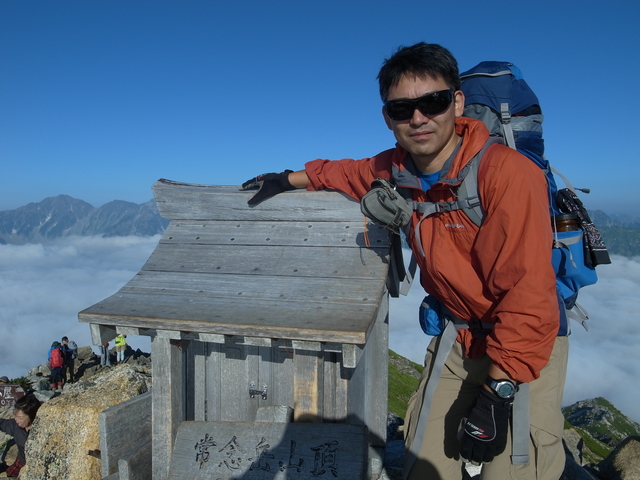楽しい冬山登山のはずだった。しかし、急激な天候の変化で状況は一変した。激しい吹雪と降り積もる雪で身動きがとれなくなってしまったのだ。
丸三日、ツェルトの中で過ごさなけらばならなかった。しかし、三日間が限界だった。
ツエルトの中は、僕のほかに三人いた。彼女の千春と親友の大介、その彼女の祐実だ。
千春と祐実は寒さで低体温症になっていた。大介は度重なる雪かきのせいで凍傷になっていた。コンロのガスは使いきり、食べ物もほとんど食べ尽くした。残っているのは、少しばかりの飴とクッキーだけだった。
この四人の中で、動けるのは僕だけだった。
本当なら僕もこのツェルトの中でじっとしていたかった。しかしそれはできなかった。動ける僕がなにかしなければ、三人は死んでしまうからだ。
時間は刻々と過ぎていく。僕はどうすればいいのだろうか。
雪がなく通常の状態ならば、二時間ほどで下山できる。しかし、この大雪では何倍もの時間がかかるだろう。雪は腰のあたりまで降り積もっていた。この過酷なルートをラッセルしながら下山できるのだろうか。自信がなかった。
困難な状況になったらじっとしていろ、というのが山のセオリーだった。その場から動かず救助を待つのがベターな選択のように思えた。
そろそろ家族は、連絡のない僕たちを心配して遭難したと騒ぎ始めているに違いない。そうすれば救助隊が出動する。その可能性に賭けるのも一つの方法だった。
ふと隣で寝袋に入って寝ている千春の顔を見た。顔は青白く唇は紫になっていた。このままでは低体温で死んでしまう可能性があった。
僕は彼女の細い肩を寝袋ごと引き寄せた。彼女はぼんやりと目を開けた。ゆっくり彼女に顔を近づけてキスをした。唇は乾いてかさかさしていた。
大丈夫だからね、と彼女の耳元でつぶやいた。彼女は弱々しくうなずいた。
ツエルトの入り口のチャックを開け外を見た。嵐はやんでいた。依然、曇り空だったが、吹雪いてはいなかった。風も収まっていた。
僕は登山靴のひもを締め、マフラーを首に巻いた。頬をバンバンと二回たたいて気合いを入れた。
「大介」と張りつめた声で彼を呼んだ。
「どうした?」
「ちょっくら行ってくるわ。あとは頼んだ」
「そうか、死ぬなよ」そう言うと、大介は分厚い手袋をしたまま手をあげ、僕の方に差し出した。
僕はその手をタッチして、外に出た。