親鸞聖人750回大遠忌法要の始まりです。作法は、ご本山制定の宗祖讃仰(しゅうそさんごう)作法。導師は、若(息子)です。中央仏教学院にての2年間の勉学の成果を出しなさいと息子には話してありました。
内陣(ないじん)に、全法中(僧侶の事)が着座した状態から、導師が一人立ち上がり、宗祖=親鸞聖人に焼香する祖師前焼香(そしぜんしょうこう)から始まります。
一番手前が、導師である息子。

①上記の状態から祖師前焼香のために、親鸞聖人のお厨子(ずし)まで移動し、焼香をします。これを祖師前焼香の呼びます。一番奥にて、焼香する導師。

②そして、ご本尊(阿弥陀如来様)前の礼盤(らいばん)に移動し、登礼盤(とうらいばん)作法にて礼盤に座ります。参詣されたご門徒の皆さんから、若(息子)の姿に有難く涙がこぼれたと聞かされました。ご門徒なればこそです。


③役稚児さんが華籠(けろう)を法中方へ運びます。華籠(けろう)と呼ぶ皿(さら)の中には、蓮(はす)の花を連想した紙でできた葩(けは)と呼ぶ花が入っています。


葩(けは)裏表


④その後は、御堂悠輝さん演奏するシンセサイザーの音色の中で、作法に従い導師と法中と讃歌衆(さんかしゅう)=コーラスによる頂礼文(ちょうらいもん)。写真は、演奏中の御堂悠輝さんと頂礼文を歌う讃歌衆の皆さん

⑤三奉請(さんぶじょう)のために、内陣では僧侶全員は起立。そして、葩(けは)を三回に渡って散華(さんげ)するのですが、ここで一工夫をしました。役稚児さんが、満堂の参詣者の皆さんで埋まる外陣中央の赤毛氈に並び、内陣の法中と同じように散華(さんげ)したのです。これは、三重県でも初めての試み。散華とは、葩(けは)を散らす作法。写真中央には、役稚児さんが散華した葩(けは)が舞い落ちる様子が撮影されています。チラチラと舞い降り、まるでお浄土に降る蓮(はす)の華(はな)です。参詣の皆さんも、大喜びでした。

この時、役稚児さんが使用した天舞散華(てんまいさんげ)と呼ぶ特別の葩(けは)。

散華が終了し戻る役稚児さん。参詣の皆さんも、可愛い役稚児さんに笑顔。写真、右下の参詣者の顔に注目。満面の笑みです。でも、小さくて見えませんね・・・・ごめんなさい。

⑥正信偈です。参詣の皆さんも一緒になっての正信偈。

普通は、この時に僧侶が行道(ぎょうどう)と呼ぶ作法をします。行道とは、阿弥陀様の周りを廻る作法です。ご本尊前で、散華をします。しかし、これも廃止しました。法中(僧侶)座ったまま、役稚児さんが行道する稚児行道(ちごぎょうどう)に切り替えたのです。これも、恐らく三重県では初めての試み。これが、参詣者の皆さんには大変好評となりました。古き伝統のなかにも革新的な試みが必要なのです。何が、参詣の皆さんには一番訴えるのかを考えれば答えは自ずから出てきます。


写真中央には、ヒラヒラと舞う天舞散華(てんまいさんげ)が・・・・

写真は、内陣側からみた稚児行道する役稚児さん。居並ぶ法中の奥に、行道する役稚児さんの姿が撮影されています。

⑦作法は、和讃・念仏と移ります。写真は、内陣で全員起立し、和讃・念仏を唄う法中の皆さん。

そして、讃歌衆の皆さん。

法要は、無事に修了しました。
内陣(ないじん)に、全法中(僧侶の事)が着座した状態から、導師が一人立ち上がり、宗祖=親鸞聖人に焼香する祖師前焼香(そしぜんしょうこう)から始まります。
一番手前が、導師である息子。

①上記の状態から祖師前焼香のために、親鸞聖人のお厨子(ずし)まで移動し、焼香をします。これを祖師前焼香の呼びます。一番奥にて、焼香する導師。

②そして、ご本尊(阿弥陀如来様)前の礼盤(らいばん)に移動し、登礼盤(とうらいばん)作法にて礼盤に座ります。参詣されたご門徒の皆さんから、若(息子)の姿に有難く涙がこぼれたと聞かされました。ご門徒なればこそです。


③役稚児さんが華籠(けろう)を法中方へ運びます。華籠(けろう)と呼ぶ皿(さら)の中には、蓮(はす)の花を連想した紙でできた葩(けは)と呼ぶ花が入っています。


葩(けは)裏表


④その後は、御堂悠輝さん演奏するシンセサイザーの音色の中で、作法に従い導師と法中と讃歌衆(さんかしゅう)=コーラスによる頂礼文(ちょうらいもん)。写真は、演奏中の御堂悠輝さんと頂礼文を歌う讃歌衆の皆さん

⑤三奉請(さんぶじょう)のために、内陣では僧侶全員は起立。そして、葩(けは)を三回に渡って散華(さんげ)するのですが、ここで一工夫をしました。役稚児さんが、満堂の参詣者の皆さんで埋まる外陣中央の赤毛氈に並び、内陣の法中と同じように散華(さんげ)したのです。これは、三重県でも初めての試み。散華とは、葩(けは)を散らす作法。写真中央には、役稚児さんが散華した葩(けは)が舞い落ちる様子が撮影されています。チラチラと舞い降り、まるでお浄土に降る蓮(はす)の華(はな)です。参詣の皆さんも、大喜びでした。

この時、役稚児さんが使用した天舞散華(てんまいさんげ)と呼ぶ特別の葩(けは)。

散華が終了し戻る役稚児さん。参詣の皆さんも、可愛い役稚児さんに笑顔。写真、右下の参詣者の顔に注目。満面の笑みです。でも、小さくて見えませんね・・・・ごめんなさい。

⑥正信偈です。参詣の皆さんも一緒になっての正信偈。

普通は、この時に僧侶が行道(ぎょうどう)と呼ぶ作法をします。行道とは、阿弥陀様の周りを廻る作法です。ご本尊前で、散華をします。しかし、これも廃止しました。法中(僧侶)座ったまま、役稚児さんが行道する稚児行道(ちごぎょうどう)に切り替えたのです。これも、恐らく三重県では初めての試み。これが、参詣者の皆さんには大変好評となりました。古き伝統のなかにも革新的な試みが必要なのです。何が、参詣の皆さんには一番訴えるのかを考えれば答えは自ずから出てきます。


写真中央には、ヒラヒラと舞う天舞散華(てんまいさんげ)が・・・・

写真は、内陣側からみた稚児行道する役稚児さん。居並ぶ法中の奥に、行道する役稚児さんの姿が撮影されています。

⑦作法は、和讃・念仏と移ります。写真は、内陣で全員起立し、和讃・念仏を唄う法中の皆さん。

そして、讃歌衆の皆さん。

法要は、無事に修了しました。












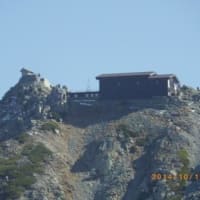







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます