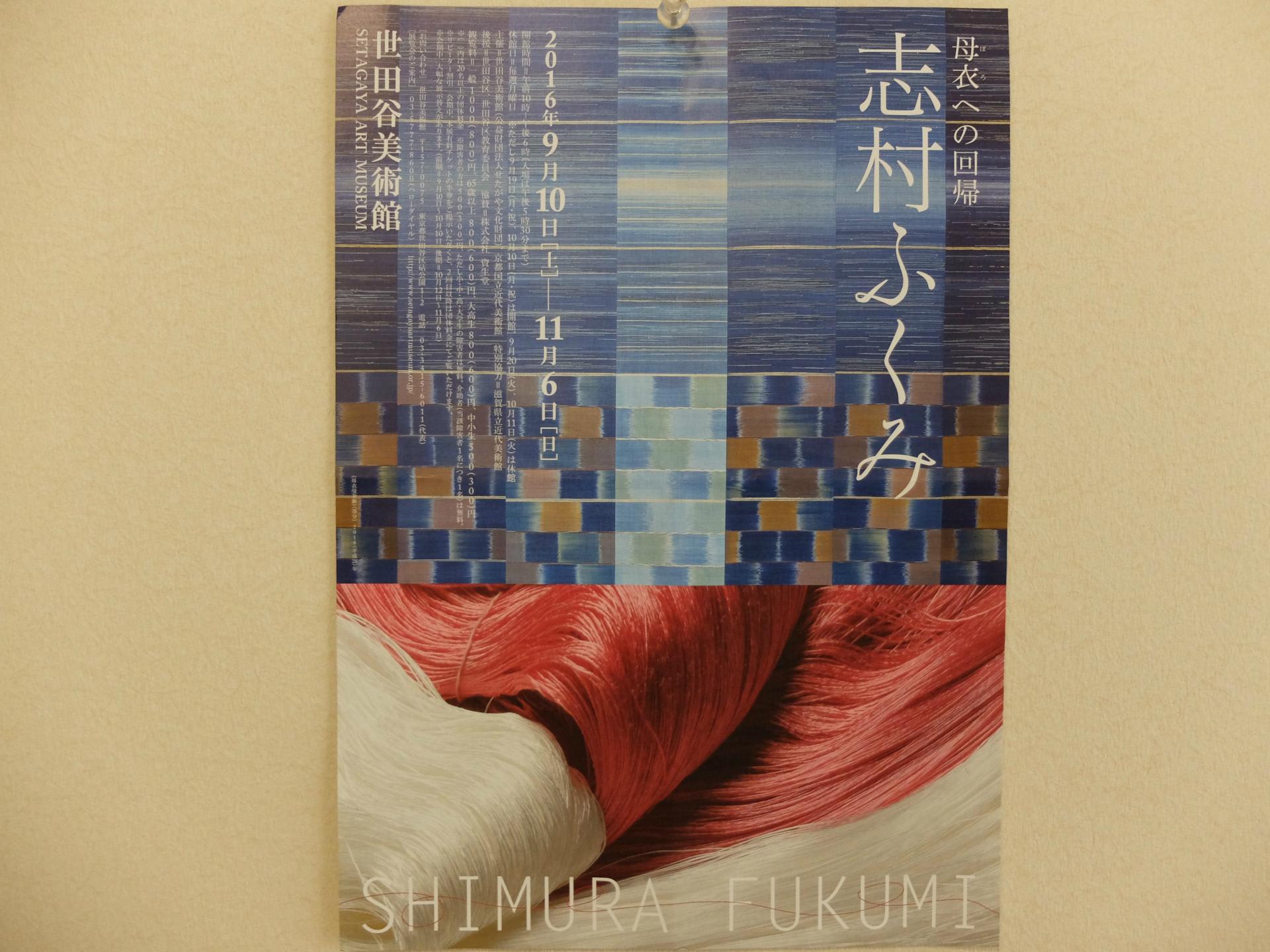臨済宗の宗祖臨済禅師1150年、臨済宗中興の祖白隠禅師250年の遠諱記念として、禅宗の臨済宗、黄檗宗の15派の合同の記念事業としての展覧会。京都国立博物館に続いて東京国立博物館で開催されているので、行ってみた。
混雑してるかと思いきや行列もなく快適に見ることができた。
臨済宗の歴史や15派の各本山の設立の経緯、それにかかわる人々の紹介、肖像画や坐像など、臨済宗を支援した武将の肖像画、仏像・仏画、障壁画、茶道具、禅画など、国宝19件、重要文化財102件、など240点が展示されている。
臨済宗の本山には、建仁寺、相国寺、妙心寺、大徳寺、南禅寺、東福寺、天竜寺など、京都だけでもそうそうたる寺院があり、それらが所有する美術品はとんでもなくたくさんあると思うが、その一部が一堂に集められている。
禅画については、白隠筆は9点、仙厓筆は3点が展示されている。見るものが多くて2時間はかかった。良く知らないお坊さんの肖像画がたくさん展示されており、やや辟易ぎみになるが、これは禅宗では、師は一人前とみとめた弟子に悟りの証拠として自らの肖像画を与えるのが通例になっているようで、高僧の肖像画が多く描かれたからだろう。