
前回のブログ投稿の続き3回目。
山口周著「世界のエリートはなぜ『美意識』を鍛えるのか?」から。
(エキスパートは「美意識」に頼る)
厳密に論理的な思考を積み重ねて生み出したうち手と、
直観的にフワッと思いついたうち手では、
どちらの方がより有効なのか?
チェスの実験では、アマチュアとワールドクラスの選手の間には、
読みの深さ、つまり読んでいる手数についてはほとんど差が無かった。
違ったのは、ワールドクラスのプレーヤーの場合、
最終的に選んだ一番良い手が、読みの最初の数手の中に常に含まれていたこと。
アマチュアはたくさん手を読んでも、
最後まで一番良い手が含まれていませんでした。
チェスの実力の差は、思考の粘りにあるのではなく、
直観的にスジの良い手を思い浮かべられるかという点にあった。
最終的には直観こそがエキスパートの条件と確認された。
では、厳密に思考を積み重ねていく思考技術や
思考体力は意味がないのか?そんなことはありません。
フワッと思い浮かんだ手が本当に正しいのか検証するために、
厳密な思考を使っています。
山の片側から厳密な思考を積み重ねながら、山の反対側からは
直観に導かれたアイデアの正しさを検証するという
トンネルを山の両側から掘り進めて一つの道筋にするような
知的作業をやっているのです。
<多田コメント>
羽生さんは、思い浮かんだ5つくらいの手を深く読んで選ぶようです。
可能な手は何百種類もあり、制限時間の中ですべてを検討することは
不可能です。最有力な手が、ぱっと頭に浮かび、それを深く
先読みして指し手を検討しています。
チェスの実験で言えば、
フワッと正解が浮かぶかどうかが、
プロとアマチュアの違い。
しかし、直観が大事だからといって、
論理思考が不要というわけではありません。
思いついた直観が正しいのか、論理思考によって確かめるのです。
(直観と美意識はどんな関係があるのか?)
私(山口周)は、
直観と美意識は強くつながっていると考えています。
フワッと浮かんだアイデアが優れたものであるかどうか
を判断するためには、結局のところ、それが「美しいかどうか」
という判断つまり美意識が重要になる。
将棋の羽生さんの言葉。
「美しい手を指す、美しさを目指すことが、結果として
正しい手を指すことにつながると思う。正しい手を指すために
どうするかではなく、美しい手を指すこと目指せば、
正しい手になるだろうと考えています。このアプローチの方が
早いような気がします。」
「美しいと感じられるとき、それはなんらかの目的に適っている」
と哲学者カントは指摘しました。
将棋は数学のゲーム理論で言えば「二人零和有限確定完全情報ゲーム」。
これは「完全な先読みが可能」であり、「数学的な解がある」ということ。
このような営みの最高峰に位置する人が、
難しい判断の基準として「論理」よりも「美意識」を用いている。
その一方で、はるかに非論理的な要素が複雑に入り混じる経営
という営みにおいて、過剰に「論理」が重んじられ、
「美意識」が軽んじられている。
<多田コメント>
・羽生さんは、美しさを、正しさを選ぶ際の基準にしています。
・同じく将棋の谷川元名人は「光速の寄せ」と言われ、
最短距離での勝利にこだわります。これも一つの美学。
・カントの指摘は、美しさには一種の普遍性がある、ということ。
(ビジョンと美意識)
日本企業にはビジョンがなかった。
高度成長期には世界のトップグループに対し、
同じことをもっと安く、もっと早くできるように工夫して追いつくのが
一番シンプルで有効な戦略だった。
しかし90年代から状況が変わりました。
日本がトップランナーになってしまったので、
後追いするべき標的を失って迷走し始めたのです。
サル真似をするべき対象がなくなった状態で、
考えることもなく、ひたすらに頑張る、努力することを続ければ、
どういうことになるか結果は明白。
何の成果も出せないままに、ただ徒労感だけがつのり、
最後は行き倒れるしかありません。
自社のビジョンは多くの人を共感させるものになっているか?
ここでも重要になってくるのは「理性」ではなく「感性」。
どんなに戦略的に合理的な物であっても、人をワクワクさせ、
自分もぜひ参加したいと思わせるような「真・善・美」がなければ、
それはビジョンとは言えません。
「アジアで売り上げトップ」のようなものはビジョンではなく、
単なる目標であり、命令でしかない。
「何がクールなのか」ということを
外側にさがしていくような知的態度ではなく、
むしろ「これがクールなのだ」ということを
提案していくような創造的態度での経営。
<多田コメント>
・トップの企業には模倣すべき相手はいません。
・「何がクールなのか」を外側に探しにいくのでなく、
「これがクールなのだ」ということを提案する
・魅力的なビジョンの提示は、企業だけでなく、
行政においても、そして政治家においては最も重要な仕事。
・資本主義の経済成長が鈍化し、先進国内での所得の2極化が進む中で、
世界が大きな転換期にきている現在、政治の役割として
みんながワクワクできる次の社会を提示しなければなりません。
(マッキンゼーがデザイン会社を買収)
コンサルタント大手のマッキンゼーは、2015年にデザイン会社LUNARを買収。
LUNARは、アップル、グーグルなどを顧客に持つデザインの大手。
マッキンゼーは、サイエンス重視のアプローチの限界を感じ、
機能面での競争から情緒面での競争へシフトを図り、
コンサルティングの世界に「アート」を取り込もうとしているのではないか。
かつてマッキンゼーは、クラフトに偏重していた企業組織の意思決定に
事実と論理に軸足をおいた「サイエンス」を導入しました。
しかし、多くの企業が追随し、正解がコモディティ化・陳腐化。
また、クリティカルシンキング等のスキルは、
問題をシンプルな因果関係として捉えることで、解決策を見つけます。
事象の因果関係が静的でシンプルな構造として整理できるならば、
これは有効なアプローチなのですが、世界はどんどんVUCAになっており
適用しにくくなっています。
一方、デザイン会社の問題解決アプローチは、
もっと動的であり、最初から解を捉えにいく。
厳密な因果関係の整理は、
要素の変化が絶え間ない世界ではあまり意味をなさない。
直観的に把握される「解」を試してみて、試行錯誤を繰り返しながら、
最善の回答に至ろうとする。
アップルの強みはブランドに付随するストーリーと世界観にある。
製品の外観もテクノロジーも簡単にコピーできますが、
世界観とストーリーは決してコピーできない。
この二つを天然資源のように豊富に持っているのが日本という国。
システムの変化があまりに早く、明文化されたルールの整備が
システムの進化に追いつかない世界においては、
自然法的な考え方が重要になってきます。
内在化された「真・善・美」の基準に適っているかどうかを判断する力。
様々な意思決定を明文化されたルールのみに従って行っていたのでは、
決定的な誤りを犯してしまう可能性がある。それを避けるためには
極めて戦略的で合理的なやり方。
<多田コメント>
3月5日の投稿のように、英国の美術系大学院大学に、
なだたるグローバル企業が幹部候補生を送り込んでいます。
そして、世界でナンバーワンといわれるコンサルタント会社
マッキンゼーはデザイン会社を買収しました。
著者の山口さんは、
サイエンス重視のアプローチの限界を感じ、
機能面での競争から情緒面での競争へシフトを図り、
コンサルティングの世界に「アート」を取り込もうとしているのではないか
と推測しています。
ニューヨークでは、
せっかく大学院を出て経営学修士MBAの資格を得ても
仕事がないためタクシー運転手をしている人もいると聞きます。
そして一方では、資本主義経済の中で勝ち抜くために、
先見性のある企業はアートの力を取り入れ始めています。
これが今後の世界の潮流になるでしょう。
人が夢中になるようなコンテンツや、ブランドを創造するには、
人間に対する理解、人の心に対する深い洞察が必要です。
科学の実験や計算で答えは出てきません。
人間の心を深く研究する学問分野は文科系。特に人文科学。
自然学は自然を研究する学問であるのに対し、
人文学は、人間・人為の所産を研究の対象とします。
具体的には、
哲学、法学、政治学、経済学、倫理学、宗教学、歴史学、人文地理学、
文化人類学、民俗学、言語学、文学、芸術学、教育学、心理学など。
大学教育において「文系は役に立たないから廃止しろ」
という考え方や意見は、とんでもないのです。
日本政府は、日本が進むべき方向を間違えていると感じます。
(参考)
平成27年6月8日 文部科学大臣通知
「国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて」
1 組織の見直し
(1)「ミッションの再定義」を踏まえた組織の見直し
「ミッションの再定義」で明らかにされた各大学の強み・特色・社会的役割を
踏まえた速やかな組織改革に努めることとする。
特に教員養成系学部・大学院、人文社会科学系学部・大学院については、18
歳人口の減少や人材需要、教育研究水準の確保、国立大学としての役割等を踏ま
えた組織見直し計画を策定し、組織の廃止や社会的要請の高い分野への転換に積
極的に取り組むよう努めることとする。














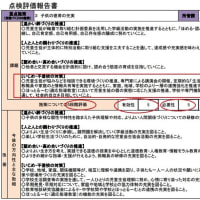











「劣化するオッサン社会の処方箋2020-03-08」
昔の日本企業の幹部は、りっぱな教養も持った人たちでした。しかし、1970年代に大学のレジャーランド化が進んだ結果、70~80年代にかけて大学を卒業し企業へ就職した世代、つまり今の企業の最高幹部たちは無教養世代なのです。
<ブログからの引用>
・70年代に絶滅した「教養世代」
1970年前後まで教養主義は大学のキャンパスの規範的文化だった。
当時の大学生は10日に1冊くらい教養書を読んでおり、
ほとんど読まない学生はわずか1.8パーセント。
哲学や思想は、「システムを批判的に思考する技術」。
しかし、70~80年代にかけて大学はレジャーランド化し、
学生はどんどんバ カになっていった。
90年代の実学世代の黎明までの10年間は、
「知的真空」の状態が続いた。
・90年代以降に勃興した「実学世代」
昭和の「大きなモノガタリ」が終焉し、社会で支配的になった
「新しいモノガタリ」は「グローバル資本主義」。
その結果、若者には経営学や会計学など、
手っ取り早く年収を上げる学問が重視されるようになった。
・上層部と実行部隊の乖離
教養世代の管理職は引退し、
現在の社会システム上層部は「知的真空世代」が独占し、
その下を「実学世代」が固める歪んだ構造になっている。