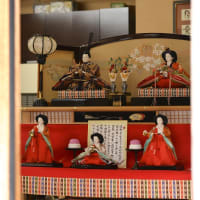神功皇后と葛城襲津彦(かずらきのそつひこ)
 第14代仲哀(ちゅうあい)天皇(日本武尊(やまとたけるのみこと)の子)は、再び朝廷に背いた熊襲(くまそ)を討伐する際、神のお告げに従わなかったために崩御されたました。
第14代仲哀(ちゅうあい)天皇(日本武尊(やまとたけるのみこと)の子)は、再び朝廷に背いた熊襲(くまそ)を討伐する際、神のお告げに従わなかったために崩御されたました。それを知った皇后の気長足姫尊(おきながたらしひめのみこと)(神功皇后)は、悲しみ、自ら神のお告げを聞き、夫を崇った神の名を知ると丁重に祀りました。
そして熊襲、土蜘蛛を次々に征伐したあとで、新羅を討伐しようと考えたのです。
皇后は、臨月にもかかわらず、自ら軍を率いて、新羅を降伏させました。
新羅と対立していた百済王は喜び、にちに七枝刀(ななさやのたち)などの宝物を献じたといわれています。
その後、皇后が産んだ誉田天皇(ほむたのすめらみこと)が第15代応神天皇となったのです。
現在、石上神宮に伝わる七支刀がこの時に百済から献上された七枝刀にあたるとも推測されています。
「日本書紀」では、神功皇后の巻の中で「魏志(ぎし)」倭人伝の文章を引用し、魏に朝貢した倭の女王卑弥呼を神功皇后に擬するような編集をしたともいわれています。
神功皇后、応神天皇、仁徳天皇に仕えた豪族に葛城襲津彦(かずらぎのそつびこ)という人物がいます。
襲津彦は、葛城氏の始祖で、新羅への派遣や朝鮮外交で活躍した人物なのです。
襲津彦の娘である磐之媛命(いわのひめのみこと)は、第16代の仁徳天皇の皇后となり、その子である履中(りちゅう)、反正(はんぜい)、允恭(いんぎょう)天皇が次いで天皇になるなど、葛城氏は天皇家と外戚関係を築き上げ、権勢を誇ったのです。
室宮山古墳
室宮山(むろみややま)古墳は、巨勢山々塊の西北部に位置します。
西側丘尾を切断し、主軸をほぼ東西に向け、三段に構成された前方後円墳で全長238m、後円部径105m、前方部幅約110m、同部高約22m、クビレ部幅約75mを測ります。
周濠は全周を巡る盾形のものとみられ、北側の周堤に接してネコ塚古墳(一辺60mの方墳)という部塚があります。
宮山古墳の主体部は、後円部に墳丘軸をはさんで南北に2基の竪穴式石室が存在し、前方部にも多数の銅鏡が発見されたという施設の存在が知られています。
埋葬者ですが、古くは武内宿禰が有力視されたのですが、近年では葛城襲津彦の説が有力となっています。
特徴としては、長持式石棺の蓋石上面は格子亀甲文とよばれる矩形の装飾的な削り窪みがあり津堂城山古墳の石棺に類例があるだけという貴重な石棺なのです。また、竪穴式でこの長持式の石棺を見学できるのはこの古墳だけなのです。
石室周囲の埴輪列の様子がはっきりと判った古墳で豪華な形象埴輪は特に有名です。