古の宇陀を彩った人たち
 宇陀という地域は、「古事記」「日本書紀」といった多くの書物に度々登場し、古い地名や伝承などが数多く残っている地で、宇陀の歴史を彩ったのは何も男性だけでなく、日本初の女帝である推古天皇や女人高野といわれる室生寺を再興させるために人力を尽くした桂昌院など数多くの女性が歴史の舞台に登場してきます。
宇陀という地域は、「古事記」「日本書紀」といった多くの書物に度々登場し、古い地名や伝承などが数多く残っている地で、宇陀の歴史を彩ったのは何も男性だけでなく、日本初の女帝である推古天皇や女人高野といわれる室生寺を再興させるために人力を尽くした桂昌院など数多くの女性が歴史の舞台に登場してきます。・・・天照と共にした姫・・・
第11代垂仁(すいにん)天皇の第四皇女の倭姫(やまとひめ)は、天照大神のために安定して神事を続けることができる場所を求め各地を巡ったのです。
御杖代(みつえしろ)として大和国から伊賀・近江・美濃・尾張の諸国を経て伊勢の国に入り、皇大神宮(伊勢神宮内宮)を創建したとされています。
御杖代とは依代(よりしろ)として神に仕える者の意味で、倭姫が伊勢神宮を創建するまでに天照大神の神体を順次祀った場所は「元伊勢」と呼ばれる。
・・・日本初の女帝・・・
聖徳太子の叔母である推古(すいこ)天皇は、日本初の女帝であり、東アジア初の女性君主で、聖徳太子を摂政に、天皇を中心とした国の体制づくりを進めた人物です。
日本書紀に、推古19年(611年)5月条に菟田野で推古天皇一行が薬猟をしたという記載があります。これは史料で確認できるわが国最初の薬猟の記録です。
薬猟とは、宮中行事の一つで、男性は薬効の大きい鹿の角をとり、女性は薬草を摘んだと言われています。
・・・波乱の人生の末・・・
横佩の右大臣藤原豊成卿の息女である中将姫は、継母の讒言(ざんげん)によって14歳で菟田野日張山に追いやられたのですが、武士嘉藤太の情により命を助けられここに草庵を結び、2年6ヶ月の間念仏三昧の生活を送ったのです。
その後、父の豊成公がこの地に遊猟に来た際、偶然に再開し奈良の都へ帰るが、仏道への志強く當麻寺で出家し、當麻曼茶羅を感得した。その後、日張山に建立した堂に手ずから刻んだ自らの影像と嘉藤太夫婦の形像を安置して日張山青蓮寺と名付けられたのです。
・・・仏教再興に力を尽くした女性・・・
徳川家光の側室で、5代将軍・綱吉の生母である桂昌院ですが、女人高野で名高い室生寺に多額の寄進を行い、仏塔を修復するなどして再興に人力を尽くしました。
寺の表門の前にある「女人高野室生寺」と彫られた石碑の上部には、九目結紋という紋が彫られており、これは桂昌院の実家である本庄家の家紋です。また、境内には桂昌院の五輪塔もあり室生寺の堂塔を修繕した功績を讃えています。
















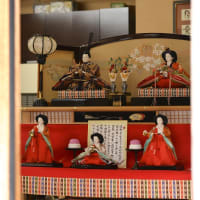



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます