立春大吉
2010-02-06 | 動詞

今年2010年は2月3日が節分で,おとといの2月4日が立春でした。
今では節分といえば,立春の前日だけを指すようになりましたが,元来,節分とは「季節を分ける」ことから,季節の始まりを示す立春,立夏,立秋,立冬の前日のことをいいました。
昔は「立春正月」などといい,一年の始まりを立春付近に求めたのです。
立春と言えば‘가게 기둥에 입춘(店の柱に立春)’といういいまわしを知ってますか。この입춘というのは입춘 대길〈立春大吉〉の略です。
입춘 대길というのは,立春の日に吉運を祈って正門などに張り付ける文句のことです。입춘 대길のほかに건양다경〈建陽多慶〉などとも書いたりしました。
가게 기둥에 입춘というのは,そのような札が,店の柱に貼り付けてあっては似合わないという意味です。つまり,ふさわしくない,不似合いだということのたとえです。
さて가게ということばが出てきましたので,この話をしましょう。
가게というのは小さな店のことを言いますが,元来,漢字語の假家[가가]からきたことばです。
「假家」というのは仮に建てられた家という意味ですが,昔,道ばたに仮に建てた家で品物を売ったことからそう言われるようになったのです。
当時の「店」は一般の人にも品物を売っていましたが,主として官庁に物資を供給していました。中でも一番大きいのは전〈廛〉,その次が방〈房〉,そしてその次が가가〈假家〉,いちばん小さなのが재가〈在家〉です。
전〈廛〉というのは朝鮮時代にソウルの종로〈鍾路〉にあった店のことで,そのうちもっとも栄えていた6つの전のことを육주비전〈六注比廛〉といいます。
(1)선전〈繕廛〉:비단〈緋緞〉を売っていた店。비단というのは錦,つまり絹織物のこと。
(2)면포전〈綿布廛〉:무명(木綿)を売っていた店。
(3)면주전〈綿紬廛〉:면주(つむぎ)を売っていた店。つむぎというのは紬糸(蚕の糸)で織った絹織物のことで명주〈明紬〉とも言う。
(4)지전〈紙廛〉:読んで字のごとく紙屋。
(5)저포전〈苧布廛〉:모시(麻のようなもの)で織った布を売っていた店。
(6)내외 어물전〈内外魚物廛〉:魚屋。もともと청진동〈進洞〉にあった乾物を扱う내어물전と,서소문〈西小門〉にあった魚を扱う외어물전とが一緒になったもの。
今では節分といえば,立春の前日だけを指すようになりましたが,元来,節分とは「季節を分ける」ことから,季節の始まりを示す立春,立夏,立秋,立冬の前日のことをいいました。
昔は「立春正月」などといい,一年の始まりを立春付近に求めたのです。
立春と言えば‘가게 기둥에 입춘(店の柱に立春)’といういいまわしを知ってますか。この입춘というのは입춘 대길〈立春大吉〉の略です。
입춘 대길というのは,立春の日に吉運を祈って正門などに張り付ける文句のことです。입춘 대길のほかに건양다경〈建陽多慶〉などとも書いたりしました。
가게 기둥에 입춘というのは,そのような札が,店の柱に貼り付けてあっては似合わないという意味です。つまり,ふさわしくない,不似合いだということのたとえです。
さて가게ということばが出てきましたので,この話をしましょう。
가게というのは小さな店のことを言いますが,元来,漢字語の假家[가가]からきたことばです。
「假家」というのは仮に建てられた家という意味ですが,昔,道ばたに仮に建てた家で品物を売ったことからそう言われるようになったのです。
当時の「店」は一般の人にも品物を売っていましたが,主として官庁に物資を供給していました。中でも一番大きいのは전〈廛〉,その次が방〈房〉,そしてその次が가가〈假家〉,いちばん小さなのが재가〈在家〉です。
전〈廛〉というのは朝鮮時代にソウルの종로〈鍾路〉にあった店のことで,そのうちもっとも栄えていた6つの전のことを육주비전〈六注比廛〉といいます。
(1)선전〈繕廛〉:비단〈緋緞〉を売っていた店。비단というのは錦,つまり絹織物のこと。
(2)면포전〈綿布廛〉:무명(木綿)を売っていた店。
(3)면주전〈綿紬廛〉:면주(つむぎ)を売っていた店。つむぎというのは紬糸(蚕の糸)で織った絹織物のことで명주〈明紬〉とも言う。
(4)지전〈紙廛〉:読んで字のごとく紙屋。
(5)저포전〈苧布廛〉:모시(麻のようなもの)で織った布を売っていた店。
(6)내외 어물전〈内外魚物廛〉:魚屋。もともと청진동〈進洞〉にあった乾物を扱う내어물전と,서소문〈西小門〉にあった魚を扱う외어물전とが一緒になったもの。












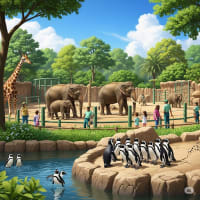

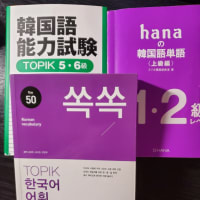
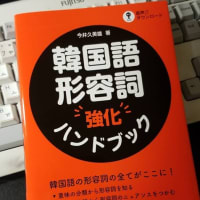





このブログを見て楽しくなりました。
韓国語中級程度ですがおもしろい記事がいっぱいで,最初からゆっくりとブログを拝見します
。