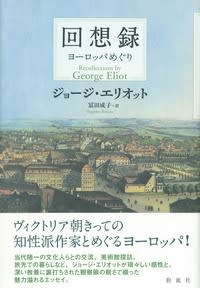画像は最近の「母なるキンツィヒ」の記念碑です。
前回の画像は2000年に撮影したものです。それと微妙に違いますが、どこかわかりますでしょうか。
下部の地面の部分にプレートが新たに設置されているのが、その違いです。
このプレートは、2015年、ケール市がモニュメントの周りに12枚のガラス板を地面に埋め込んで設置し、仏独関係の発展を人目をひくような方法でマザーキンツィヒの歴史を説明する光る碑文です。
各面三枚ずつで、合計12枚です。
その内容が独仏語で書かれているHPを発見したので、訳してみました。
前回の記事に参照している部分も多いですが、あえて全て掲載します。
現在の
ウクライナ情勢などみても、大切なメッセージだと思えるからです。
A l’origine, la statue Mère Kinzig décorait le pont de chemin de fer construit en 1861 entre Strasbourg et Kehl, par la France et la Confédération germanique.
もともと、マザー キンツィヒ像は、フランスとドイツ連邦によって
1861年に
ストラスブールとケールの間に建設された鉄道橋に飾られました。
Comme pendant
au Père Rhin, la statue de la Mère Kinzig se trouvait dans une niche du portail néogothique, sur le pilier est du pont.
ファーザーラインと対をなすものとして、マザー キンツィヒの像は、橋の東の支柱にあるネオ
ゴシック様式の正面のくぼみにありました。
Le 22 juillet 1870, les troupes allemandes ont fait sauter la partie ouest du pont, pour empêcher une invasion de Kehl par les troupes françaises.
1870年7月22日にドイツ軍は橋の西側部分を爆破し、
フランス軍によるケールへの侵攻を防ぎました。
La statue de la Mère Kinzig ainsi que celle du Père Rhin furent immergées dans le fleuve, lors de la destruction du pont,
au début de la guerre franco-allemande.
独仏戦争の開始時に橋が破壊されたとき、マザー キンツィヒの像とファーザーラインの像は川底に沈みました。
Le pont de chemin de fer a été reconstruit à la fin de la guerre et une nouvelle statue de la Mère Kinzig orne désormais sa porte d’entrée, du côté de Kehl.
鉄道橋は戦争の終わりに再建され、マザー キンツィヒの新しい像が以後、ケール側の正面を飾っています。
Vers 1900, les travaux de creusement du port du Rhin ont permis de retrouver la figure originelle de la Mère Kinzig que l’on pensait disparue.
1900年頃、ライン港の浚渫(しゅんせつ)により、行方不明になったと思われていたマザー キンツィヒのオリジナルの像が発見されました。
A l’é
poque, les élus de Kehl ont décidé d’en faire la figure principale du mémorial pour la guerre de 1870/71, érigé en 1905.
当時、ケールの議員は、1905年に建てられた 1870/71 年の戦争の記念碑の主役をその像にすることを決定しました。
Ce monument se trouvait devant la
mairie construite en 1828. Elle perdit ses fonctions en 1910, lors de l’unification de la ville et du village de Kehl et fut ensuite détruite en 1953.
このモニュメントは、
1828年に建てられた役場の前にありました。その役場は市とケールの村が合併された1910年にその機能を失い、1953年に解体されました。
Comme tous les mémoriaux allemands de cette é
poque, son but n’était pas de condamner la guerre en elle-même ou de rappeler la souffrance qu’elle procure aux hommes.
この時代のすべてのドイツの記念碑と同様に、その目的は戦争そのものを非難したり、それが人々にもたらした苦しみを思い出すことではありませんでした。
Le monument a survécu à deux guerres mondiales. En 1945, alors que Kehl était une possession française, la statue de la Mère Kinzig est restée sur la place du Marché.
記念碑は2つの世界大戦を生き延びました。ケールがフランス領だった1945年、マザー キンツィヒの像は市場広場に残っていました。
En signant le traité de l‘Elysée, en 1963, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer ont posé la première pierre à l’amitié franco-allemande.
1963年にエリゼ条約に調印することにより、
シャルル・ド・ゴールとコンラート・アデナウアーは仏独友好の礎石を築きました。
La statue de la Mère Kinzig est aujourd’hui un point de rencontre apprécié des jeunes Français et Allemands.
マザー キンツィヒの像は、今日、フランス人とドイツ人の若者の待ち合わせ場所として人気があります。
(画像および文章は、les Archives départementales du Bas-RhinのHPからです)