子供のころから,空想にふけることは得意な方だ.人間は,想像できることは,それを目標として実現できる可能性があるが,空想や想像することさえできないことは,決して実現できるようにはならないと思う.
何らかの「発想」を,人に伝えようとしたとき,それが,ビジネスの領域でも,学術的な研究でも,ただ,"生"のアイデアの形のままではうまくない.発想の内容や構造を検討,整理して,何らかの問題提起や提案の形を「構成」し,"ストーリをつくる"ことが,必要である.そして,その構成にもとづいて,提案書なり論文なりの「執筆」あるいは「プレゼンテーション」というプロセスをふむことになる.
それぞれの段階で,どうも考えがすっきりまとまらないときには,違うことをして,気分転換という手もある.しかし,私は,頭の中のある種の緊張やネタは保ったまま,別の角度から「頭の整体」をするつもりで,発想,構成,執筆,プレゼンテーション等の定番の本を読む(殆どの場合は数ページを拾い読みする)ことがある.
そうすることによって,忘れていた様々な「作法」が頭の中によみがえってきたり,第三者的に草案を「見つめなおす視点」をえられたりして,頭の中や書き出す文章等をすっきりさせることができる.
以下は,そのような場面で,私が繰り返し読み直す定番であり,どれもオススメである.
何らかの「発想」を,人に伝えようとしたとき,それが,ビジネスの領域でも,学術的な研究でも,ただ,"生"のアイデアの形のままではうまくない.発想の内容や構造を検討,整理して,何らかの問題提起や提案の形を「構成」し,"ストーリをつくる"ことが,必要である.そして,その構成にもとづいて,提案書なり論文なりの「執筆」あるいは「プレゼンテーション」というプロセスをふむことになる.
それぞれの段階で,どうも考えがすっきりまとまらないときには,違うことをして,気分転換という手もある.しかし,私は,頭の中のある種の緊張やネタは保ったまま,別の角度から「頭の整体」をするつもりで,発想,構成,執筆,プレゼンテーション等の定番の本を読む(殆どの場合は数ページを拾い読みする)ことがある.
そうすることによって,忘れていた様々な「作法」が頭の中によみがえってきたり,第三者的に草案を「見つめなおす視点」をえられたりして,頭の中や書き出す文章等をすっきりさせることができる.
以下は,そのような場面で,私が繰り返し読み直す定番であり,どれもオススメである.
 | 発想法―創造性開発のために中央公論社このアイテムの詳細を見る |
 | 創造的論文の書き方有斐閣このアイテムの詳細を見る |
 | 考える技術・書く技術講談社このアイテムの詳細を見る |
 | 考える技術・書く技術―問題解決力を伸ばすピラミッド原則ダイヤモンド社このアイテムの詳細を見る |
 | 理科系の作文技術中央公論新社このアイテムの詳細を見る |
 | どう書くか―理科系のための論文作法共立出版このアイテムの詳細を見る |
 | 常識力で書く小論文PHP研究所このアイテムの詳細を見る |
 | プレゼンテーションの極意ソフトバンクパブリッシングこのアイテムの詳細を見る |














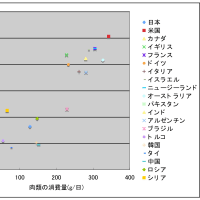
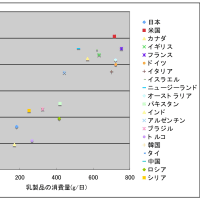
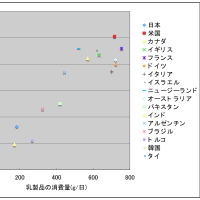






「発想法」と「理科系の作文技術」、前者は高校か大学の教養時代、後者は学部の時に読んだ本です。あの頃は若かったし、もちろん脳脊髄液減少症じゃなかったから、今でも何が書いてあったか明確に思い出せます。なので僕の場合は、読み返す必要がないようです。他にこの手の本を読む必要を感じたこともありません。
こういった名著を、できれば高校あたりで実際にテーマを与えて、並行して読ませるべきでしょうね。
しかし,世の中,毎日,なにかしらの論文等を書いているような生活をしている人は,特別な環境ですから,その点は普通の人にはあまり参考になりません.
私は,自分は書くのが不得意だと思ったことはありませんが,他の人がどうやっているか,もしくは,どう教えているか,はとても興味があります.
少しづつでも,精進して,60歳をすぎても,「以前より,さらに上手に書けるようになった」と思えるようにしたいと思います.ここでの「書ける」には,コンセプトの「デザイン」や内容の「構成」もふくまれます.
紹介している中の最後の本は,最近出た,例のデザイナーので医学博士の川崎先生の新しい本です.「プレゼンテーションをデザインする」という感じのコンセプトが背景にあります.