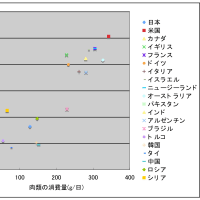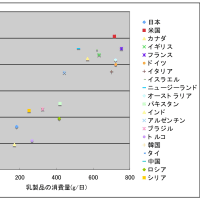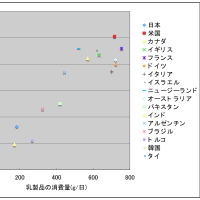自分とは異なる分野の専門家との交流はとても勉強になる.
先日,音大でピアノの講師をしながら,私の母校で情報学の博士号をとったY先生に,「色聴」(しきちょう:colored hearing) と,「共感覚」(きょうかんかく:synesthesia)という概念について教わった.
「色調」とは,「音」を聴くと「色」を感じる現象である.絶対音感を持つ人の中には,この「色調」を持つ人が多いらしい.
「共感覚」とは,視覚・聴覚・触覚・味覚・臭覚などの五感の刺激において,ある一つの系統の感覚の刺激が不随意(本人の意志とは関係なく)に他の感覚と共に感じられる現象である.例えば,味や臭いに形を感じたり,音や言葉に色を感じたりする.色調は共感覚の一種である.
私は,絶対音感はもっていないが,以前から音に色を感じていた.例えば,オーディオの試聴などをしているとき,高音(12KHz or 15KHz ~)を聴くと,なんとなく世間が「白っぽく見える」,低音では「黒っぽく見える」ように感じていた.また,高音を聴くと,背筋がぞくぞくして「寒い感じ」がすることもあった.さらに,消え入るようなピアニシモの音は,なんとなく灰色ががった色が遠ざかるように感じていた.長い間「気のせい」かとおもっていたこのような感覚は,色聴としては,ごく標準的な現象だということだ.
Y先生によると,私は「緩やかな色聴所有者」ということらしい.
Y先生に「共感覚」の入門書として本書を紹介していただいた.冒頭に,共感覚の例として,「味」に「形」を感じる人の話しが出てくる.また,共感覚との関連で,直観映像記憶:写真記憶(撮影したようにはっきりとしたイメージとして残る記憶)の話しが出ている.これらのくだりを読んで,私も似た感覚が少なからずあることをを思い出した.
全く驚きであるが,私は「緩やかな共感覚者」ということかもしれない.
先日,音大でピアノの講師をしながら,私の母校で情報学の博士号をとったY先生に,「色聴」(しきちょう:colored hearing) と,「共感覚」(きょうかんかく:synesthesia)という概念について教わった.
「色調」とは,「音」を聴くと「色」を感じる現象である.絶対音感を持つ人の中には,この「色調」を持つ人が多いらしい.
「共感覚」とは,視覚・聴覚・触覚・味覚・臭覚などの五感の刺激において,ある一つの系統の感覚の刺激が不随意(本人の意志とは関係なく)に他の感覚と共に感じられる現象である.例えば,味や臭いに形を感じたり,音や言葉に色を感じたりする.色調は共感覚の一種である.
私は,絶対音感はもっていないが,以前から音に色を感じていた.例えば,オーディオの試聴などをしているとき,高音(12KHz or 15KHz ~)を聴くと,なんとなく世間が「白っぽく見える」,低音では「黒っぽく見える」ように感じていた.また,高音を聴くと,背筋がぞくぞくして「寒い感じ」がすることもあった.さらに,消え入るようなピアニシモの音は,なんとなく灰色ががった色が遠ざかるように感じていた.長い間「気のせい」かとおもっていたこのような感覚は,色聴としては,ごく標準的な現象だということだ.
Y先生によると,私は「緩やかな色聴所有者」ということらしい.
Y先生に「共感覚」の入門書として本書を紹介していただいた.冒頭に,共感覚の例として,「味」に「形」を感じる人の話しが出てくる.また,共感覚との関連で,直観映像記憶:写真記憶(撮影したようにはっきりとしたイメージとして残る記憶)の話しが出ている.これらのくだりを読んで,私も似た感覚が少なからずあることをを思い出した.
全く驚きであるが,私は「緩やかな共感覚者」ということかもしれない.
 | 共感覚者の驚くべき日常―形を味わう人、色を聴く人 リチャード・E・シトーウィック(著),山下篤子(訳)草思社このアイテムの詳細を見る |