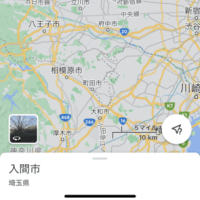2019.4.22
新緑の季節に茶臼岳にいってきました。
活火山であり、標高1,915mであり、多くの登山者で賑わっていた。
栃木県・那須町は、関東の中でも冬季の寒さが厳しく、標高も1500メートル以上ある為最高気温も冬場は0℃以下であり日によっては北海道南部の函館よりも寒い地域である。関東地方にしては珍しくタケカンバやシラカバ、ブナ、ミズナラといった亜寒帯~冷温帯に分布する樹種も分布する。自生する植物を調べるともに気候(最低気温等)も調べる為、本調査を行った。

2018.5.25
クマサザ、タケカンバ、ヤマハンノキなど時に雪崩にもあう場所でも生き残れる木が多く生えている。カラマツは、ここより少しさがった那須マウントジーンズ周辺に自生・植栽されている。

2018.5.25

2018.5.25

ウラジロタデ 2018.5.25
葉の裏の白い毛が名前の由来なようだ。岩場の隙間など、完全に開けた場所には生えていなかった。標高1800m付近から徐々に個体数が多くなった感じであった。冬季は、地上部は枯れ休眠するようだ。

ガンコウラン 2018.5.25
茶臼岳など高山帯や海岸に生える植物であり、那須山(茶臼岳)の山頂付近に多く自生していた。細かい葉が特徴で絨毯のように広がっていた。写真の株のように丸く大きく生育した物は珍しい。

5.25

火山地域なので、岩場がごろごろ。もう少し低地では、水はけが石が多くて悪くなった場所には、コゴミやヨシ、オモトヤナギなどが自生している。また、そのような場所では、ミズナラやコナラなどが生えても根腐れを起こしていずれかは枯れてしまうようだ。
2018.5.25

風雪が強い地域なので、こんな樹形の木も。樹種はミズナラで、那須の冷涼な気候にあうのか、多く自生している。ミズナラ以外にも、ブナ、イヌブナ、コナラ、カシワなどが自生している。

2019.4.22

4.22
4月も関東北部も山沿いでは、霜や積雪を観測する事がしばしば。熱帯植物を多く栽培している私は、用心深く外出すタイミングを探しているところだ。やはり、ゴールデンウイーク頃に外に出すのが無難だろう。また、2019年のGWには雪を那須高原地域で観測した程気温が冷え込んだ事に驚いた。結局、冷え込む年は寒冷地では5月下旬がいいだろう。

2019.4.22

2019.4.22

4.22
峠の茶屋駐車場から(1,462m~)タケカンバ、カラマツが点々と見え始めてやがてタケカンバの群生が多く見られるようになる。タケカンバはシラカバよりも幹が白い印象である。理由は、幹以外にも若い枝も白くなる事が挙げられる。また、タケカンバは、樹皮がよくむける事。シラカバのようにタケカンバは横縞が樹皮にはいらない事など両種に違いがあります。

2019.4.22

4.22

2019.4.22

4.22
4月にも雪が降る寒冷地。風が年中強い地域であり、自生しているヤナギ、アカマツも若い枝中心に折れてしまう。しかし、アカマツなどは折れたまま生育する事もあり乾燥・寒さに耐える生命力の強い落葉広葉樹中心の森林が広がっている。標高750~1,000mを超えるとカラマツ、タケカンバ、クマサザが生えている。

2019.4.9

2019.4.9

4.9
那須地域の気象データをより詳しく学びながら、今後の熱帯植物の耐寒性の研究に取り組んでいく予定。
また、シュロ、ソテツ、アメリカデイゴやハマユウ(浜木綿)、タイタンビスカス、宿根サルビア、ユッカ類の露地越冬に取り組んでいきたい。成功すれば、おそらく最も北の露地栽培例になるので、楽しみである。